
| Richard Coughlan | drums |
| Richard Sinclair | bass, guitar, vocals |
| Pye Hastings | guitar, bass, vocals |
| Dave Sinclair | organ, piano, vocals |
| guest: | |
|---|---|
| Jimmy Hastings | flute on 4 |
イギリスのプログレッシヴ・ロップ・グループ「CARAVAN」。 68 年 WILD FLOWERS を母体に結成。 したがって SOFT MACHINE とは兄弟関係である。 サイケデリック・ロック全盛の中から、甘美なメロディと即興を交えたユニークなインスト、そしてふんわりしたポップ感覚でぬきんでてきたカンタベリー・シーンを代表するグループだ。 メンバー交代を繰返しつつも、70 年代を通してパイ・ヘイスティングス中心に活発にアルバムを発表した。 90 年代に入って再結成、アルバム発表やライヴ活動を行なっている。

| Richard Coughlan | drums |
| Richard Sinclair | bass, guitar, vocals |
| Pye Hastings | guitar, bass, vocals |
| Dave Sinclair | organ, piano, vocals |
| guest: | |
|---|---|
| Jimmy Hastings | flute on 4 |
68 年発表の第一作「Caravan」。
ビートの名残をとどめるサウンドに、乾いたサイケデリックな幻想と深いリリシズムの陰影を加えた、初期ブリティッシュ・ロックの佳品。
ロマンティックなオルガン・ロックとしては屈指の作品だろう。
ヘイスティングスの自己主張に比べてシンクレアはまだ一歩下がっており、テナー・ヴォイスを活かすには至らない。
ハーモニーはデイヴ・シンクレアも加えて三声で決める。
また、オルガンは珍しくレスリーも用いている。
60 年代らしい冷ややかな熱気を孕むすてきな音だ。
正直にいって CARAVAN らしさはまだ十分には現れていないが、さまざまな方向へと踏み出して自らを試しているような爽やかさは感じられる。
ブリティッシュ・ロックは、DONOVAN のようなフォークおよび後期 THE BEATLES のサイケデリック・ロックから、ここを経て、KING CRIMSON のファーストへと進んでいったと思います。
ジミー・ヘイスティングスを迎えた 4 曲目は名曲。
このフルート・ソロはあらかじめ用意したものではなく、録音時に着想して一発で決めたそうです。
マジカルな 5 曲目は、「I Am The Walrus」からプログレにつながってゆく瞬間が描かれている。
最終曲は、後の大作を暗示するドラマチックな力作。
プロデュースはトニー・コックス。
リチャード・シンクレア作曲の「Policeman」、「Grandma's Lawn」では、パイ・ヘイスティングスがベースを弾き、リチャード・シンクレアがギターを弾いているそうです。
「Place Of Your Own」(4:01)個人的には DNA に刻まれている気のする作品です。
「Ride」(3:42)
「Policeman」(2:44)
「Love Song With Flute」(4:10)
「Cecil Rons」(4:07)
「Magic Man」(4:03)
「Grandma's Lawn」(3:25)
「Where But For Caravan Would I」(9:01)
本曲の作曲について、ブライアン・ホッパーへの謝辞があります。
(VLP 6011 / 2353058 / HTDCD 65)

| Richard Coughlan | drums, congas, bongos, maracus, finger cymbals |
| Richard Sinclair | bass, tambourine, hedge-clipper |
| Pye Hastings | 6 & 12 string guitars, acoustic guitar, claves |
| Dave Sinclair | organ, piano, harpsichord |
| Brother James(Jimmy Hastings) | sax, flute |
70 年発表の第二作「If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You」。
オルガンをフィーチュアした長大なインストゥルメンタルやベース・ライン、管楽器のサポートなどによって独特なソフト・サイケデリック・テイストを確立した作品。
ツイン・ヴォーカルやメランコリックなメロディ・ラインに英国本流のビートポップのイメージを残しつつも、ジャズ的な演奏によるスリルが全体を引き締めている。
変拍子や中世風のメロディもすでに登場。
一方 A 面のメドレー終盤で見られるようなフォーク・タッチの幻想的な繊細さは、本作以降では珍しくなる。
ノーブルであまやかな味わいはまさに CARAVAN。
すでにキャラがたってます。
プロデュースはテリー・キングとグループ。
「If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You」(3:05)
「And I Wish I Were Stoned / Don't Worry」(8:12)シンクレアとヘイスティングスのツイン・ヴォーカル。
「As I Feel I Die」(5:12)10 拍子のジャジーなサビ(マンザレイクばりのオルガン!)がカッコいい。
「With An Ear To The Ground You Can Make It / Martinian / Only Cox / Reprise」(9:51)ブライアン・ウィルソンばりの「うららかな」サイケデリック・テイストが心地よい佳曲。ハープシコードやピアノがクラシカルかつ幻想的な響きを生む。
「Hello Hello」(3:44)7 拍子の憂鬱なサイケデリック・ロック。 ヴォーカルはシンクレア。
「Asforteri」(1:20)
「Can't Be Long Now / Francoise / For Richard / Warlock」(14:17)
あまりにメランコリックな序盤、そして劇的な名曲「For Richard」へ。ジャジーな管楽器がいい。この作品のスタイルが本作後充実してゆく。
「Limits」(1:32)
以下、DECCA 8829682 CD のボーナス・トラック。
「A Day In The Life Of Maurice Haylett」(5:40)
「Why ? (And I Wish I Were Stoned)」(4:22)デモ音源。初出。
「Clipping The 8th (Hello Hello)」(3:13)デモ音源。初出。
「As I Feel I Die」(3:13)デモ音源。初出。
(SKL-R 5052 / 8829682)
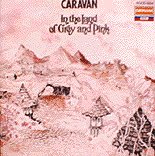
| Pye Hastings | electric & acoustinc guitar |
| Dave Sinclair | organ, piano, Mellotron, vocals |
| Richard Sinclair | bass, acoustic guitar, vocals |
| Richard Coughlan | drums, percussion |
| Jimmy Hastings | flute, tenor sax, piccolo |
| David Grinsted | cannon, bell, wind |
71 年 6 月発表の第三作「In The Land Of Gray And Pink」。
サイケデリックながらもクールに抑制したサウンドと、奇妙な品の良さが摩訶不思議な雰囲気をつくる大傑作。
変拍子やユニークな和音の響きをシュールなファンタジーで包んだ、極上のプログレッシヴ・ロックである。
リチャード・シンクレアのなまめかしきテナー・ヴォイスと、デイヴ・シンクレアのオルガンを中心としたジャジーでアンサンブルが印象的だ。
「流れるような」とライナーにも書かれているオルガンは、甘く優しくいつしかリスナーの心にしっかりと根をはってゆく。
プロデュースはデヴィッド・ヒッチコック。
ホルンによる長閑なイントロで始まる 1 曲目「Golf Girl」(5:00)はユーモラスにして切ない懐かしさでいっぱいの佳曲。
最高級の手ざわりをもつリチャード・シンクレアのヴォーカルとゆるやかなトーンのオルガンそして歌うようなメロトロン。
のんびりと暖かみある空気にあふれる演奏がときおり見せる鋭いきらめきがいい。
軽やかに舞い踊るピッコロも素敵だ。
サイケデリックでクレイジーな雰囲気とノーブルな表現がマッチした名曲である。
歌詞も洒落ている。
2001 年リマスター盤ではピッコロの存在感が強まっています。
「Winter Wine」(7:35)。
12 弦アコースティック・ギターとヴォーカルによる中世トラッド風のテーマ。
一転リズム、オルガンのスタートとともにスリリングな演奏が動き出す。
息を呑む瞬間だ。
歯切れよく刻まれるリズムとうねるベース、ソリッドなオルガンのトーン。
そして、すべての中心に、リチャード・シンクレアの切なく打ち沈むヴォーカルがいる。
伏せ目がちなのにクールな涼やかさをもつヴォーカルをリードに、一体感ある演奏はやがて憂鬱なままピアノが散りばめられ、軽やかなオルガン・ソロへと進む。
巧みに音色を変化させてはジャジーなアドリヴのコール・レスポンスを決める、エキサイティングな演奏だ。
ベースもスリリングに絡んでくる。
オルガン・ソロは歌メロの再現を経て、ドラムスとも抜群の反応を見せてゆく。
ドラム・フィルがいい感じだ。
軽やかなビート感を持ったままヴォーカルが帰ってくる。
柔らかく響き渡るヴォカリーズ、あくまでスリリングに突き進むインストゥルメンタル。
心地よい停滞からファンタジックな疾走へと鮮やかに変化する名曲。
オルガンが大きくフィーチュアされている。
しかし、一番の魅力は、シンクレアの声とさまざまな情感を切なさでまとめ上げたようなメロディ・ラインだろう。
2001 年リマスター盤ではエンディングのオルガンの余韻をたっぷり味わうことができます。
「Love To Love You」(3:03)はパイ・ヘイスティングスのヴォーカルによるカントリー・フレイヴァーある小品。
小気味よいギターのコード・ストロークとピアノが刻むビート感そして歌メロはやはり THE BEATLES 直系だろう。
パーカッションの音もユーモラスだ。
ごく当たり前のポップなラヴ・ソングだが、じつは何気ない 4 分の 7 拍子。
パイ・ヘイスティングスのヴォーカルは声量・声質ともにリチャード・シンクレアには及ばないがピュアな瑞々しい味わいがある。
この曲でもサビのコーラスのバッキング部分やエンディングのエピローグ風のフルートがとても可愛らしい。
「In The Land Of Gray And Pink」(4:58)。
フォーク、SSW 調のアコースティック・ギター・デュオによるオープニング。
再びイメージは THE BEATLES である。
一転して 3 拍目にアクセントするリズムが独特のひっかかるようなノリを生み出し、シンクレアのなめらかなヴォーカルが不思議な物語をささやき始める。
またもや世界は甘くシュールな色彩をもって浮かび上がる。
スタカートを効かせ、ほどよく抑制した演奏とヴォーカルの絶妙のバランス。
間奏はリリカルなピアノ。
ファズ・ベースのトレモロと唇をブクブクいわせるコミカルなスキャット。
続いてファズで毛羽立ったオルガン・ソロ。
デイヴ・シンクレア独特のプレイだ。
サイケなサウンドを基調に、アクセントの強い R&B 風のリズムとメロディアスなヴォーカルのコンビネーションが独特の雰囲気を生む佳曲。
シンクレアはジャジーで敏捷なメロディにおいても鮮やかな歌唱表現を見せる。
ファズを用いた音つくりやブクブクいうヴォーカルなど小技も効いている。
歌詞はひたすらシュール。
「Nine Feet Underground」(22:40)は旧 B 面を占めた超大作。
ドラマチックなオルガンを中心にスリリングなソロ、インタープレイ、センチメンタルなヴォーカル・パートを交え、夢の国の丘陵をいつまでものぼりくだり旅するようなすてきな曲である。
長いインストゥルメンタルが印象的なオルガンのリフで締めくくられ、SOFT MACHINE を思わせるオルガン・ソロを経た後に待っているのは、一種の衝撃といってもいいだろう。
静かに歌い出すリチャード・シンクレアの声はそれほど心にすっと入り込む。
初めて聴いたときにはこのヴォーカルを迎えた途端、もうとっくの昔に忘れてしまった思い出がいきなり甦ってきて涙が出そうになってしまった。
そして、エンディングに向かってひた走る「Nine Feet Underground」の旅に僕も一緒に連れていってほしいと本気で願ってしまった。
うねるようなビートに支えられたオルガンのリードで繰り広げられる、スリリングなメドレー・ナンバー。
サックス・ソロ、印象的なオルガンやギターのリフ、パイ・ヘイスティングス、リチャード・シンクレアそれぞれのヴォーカル・パートをはさみ 20 分にわたって続く一大スペクタクルである。
あなたの心の弦を弾いて甘く哀しい音をたてるにちがいない。
以下、DECCA 8829832 CD のボーナス・トラック。
「I Don't Know Its Name (The World)」(6:12)初出。
「Aristocracy」(3:42)初出。
「Its Likely To Have A Name Next Week」(3:42)初出。「Winter Wine」のインスト・ヴァージョン。
「Group Girl」(5:04)初出。「Golf Girl」の歌詞違い初期ヴァージョン。
「Dissassociation / 100% Proof」(8:35)新ミックス。
こんなにポップで切なくてけれどもしたたかでクールなサウンドは初めて。
リチャード・シンクレアのヴォーカルとデイヴ・シンクレアのオルガンはまさに絶品。
甘口なのにスリルも感じさせるまるでハッカのキャンディみたいな演奏だ。
そして最後の大作は、サイケデリック・ロックの傑作であるとともに CARAVAN がまぎれもなく SOFT MACHINE の兄弟であることを示している。
こんなにセンチメンタルになったのは THE BEATLES 以来のこと。
名作。
(Deram SDL-R1 / POCD-1834 / DERAM 8829832)

| Pye Hastings | guitar, vocals | Steve Miller | keyboards |
| Richard Sinclair | bass, vocals | Richard Coughlan | drums, percussion |
| guest: | |||
|---|---|---|---|
| Lol Coxhill | sax | Jimmy Hastings | flute, tenor sax |
| Phil Miller | guitar | Mike Cotton | trumpet |
72 年発表の第四作「Waterloo Lily」。
鍵盤奏者デイヴ・シンクレアが MATCHING MOLE 参加のため脱退し、代わりにスティーヴ・ミラーが加入。
おなじみのジミー・ヘイスティングスに加えてロル・コックスヒルやフィル・ミラーら、カンタベリーのジャズ系ミュージシャンをゲストに迎えている。
(フィル・ミラーとリチャード・シンクレアは、この後すぐに HATFIELD AND THE NORTH を結成する)
前作に比べて、インストゥルメンタル・パートが拡張されて、そこを中心にモダン・ジャズ色が強くなる。
ブルーズ・ロックの泥臭さをジャジーなフィーリングで濾して、センスよく吸い上げた感じだ。
リード・ヴォーカルは 1 曲目以外はすべてヘイスティングスによる。
プロデュースはデヴィッド・ヒッチコック。
1 曲目「Waterloo Lily」(6:47)
唯一リチャード・シンクレアがリード・ヴォーカルをとるロック・チューン。
あいかわらずの美声テナー、そしてひねりを効かすよりも力強くストレートなメロディをたどるところが印象的だ。
バッキングは R&B 調のギターとエレクトリック・ピアノのコンビであり、さりげなくも変拍子風のアクセントでオブリガートを決める。
たっぷりとスペースを取った間奏部、ギター・ソロはヘイスティングスの力演、そしてミラーによるジャジーなオルガン・ソロもたっぷり。
フレットレス・ベースらしい軽くファズのかかった丸っこい低音の動きもカッコいい。
このラフで一種だらだらっとした間奏部には、ジャズとともにサイケデリック・ロックのセンスも感じる。
気分のままにぐっと音量を落として弛緩するパートから、遠いサックスに導かれてブルース・フィーリングたっぷりのワウワウ・エレクトリック・ピアノの演奏が続いてゆく。
細かくオカズを入れて盛り上げるドラミング。
ファンキーなノリの楽曲とシンクレアのノーブルな声質の組み合わせの微妙なミスマッチ感がいい。
サックスはコックスヒル。コーラスはヘイスティングス。
2 曲目「Nothing At All / It's Coming Soon / Nothing At All」(10:25)
「Nothing At All」は、ブルーズ進行によるフリーなジャム・セッション・インストゥルメンタル。
エレクトリック・ピアノのコード・ストロークにのせて、ヘイスティングスが懸命にがんばるワウ・ギター・ソロ、ジャジーでブルージーなミラーの乱調ギターのアドリヴ、アコースティック・ピアノのアドリヴが繰り広げられる。
枠組みをしっかり支えているのは、4 ビートを刻むドラムス以上に、エフェクトに滲んだ俊敏で堅実なベースのプレイ、そしてエレクトリック・ピアノのバッキング。
フリーキーな(ヨレた)サックスも加わってセッションが繰り広げられる。
クロス・フェードから第二部「It's Coming Soon」のスタート。
まずはビル・エヴァンス風の知的なモダン・ジャズのアコースティック・ピアノ・ソロ。
おだやかに音を紡ぐギターとエレクトリック・ピアノによるカンタベリーらしい独特のテーマ(このさりげなさがすばらしい)が繰り返されて、やがてほんのりと捻れが生じてゆく。
そして一転シャープな 8 ビートのジャズロックへ。
HATFIELD AND THE NORTH ではこういう展開を進化させたかったのだろう。
追い立てるようなエレクトリック・ピアノらのバッキングに負けじとふんばるワウ・ギター・ソロ、そして奔放なエレクトリック・ピアノを従えたファズ・オルガンのプレイ。
ベースが唸りを上げるエネルギッシュな演奏の中で先のテーマが繰り返されて、クライマックスを迎える。
最後は再び「Nothing At All(Reprise)」のブルーズ進行へと戻って熱気をクール・ダウンするようにフェード・アウト。
ジャズのプレイをロックなリズム・セクションで支え、エレクトリック・ギターがワサビを効かせる、変化に富んだカンタベリー・ジャズロック。
シャープでタイトなアンサンブルがカッコいい。
「Nothing At All」はスティーヴ・ミラー作。
インストゥルメンタル。
3 曲目「Songs And Signs」(3:39)
ブリティッシュ・ロックらしいクールでファンタジックなポップロック。
ヘイスティングスの密やかなファルセット・ヴォイスとエレクトリック・ピアノの響きがジャジーなクールネスと親しみやすいポップスの味わいを同時に満たす。
このグルーヴは 60 年代からの R&B で鍛えたものだ。
間奏部はエレクトリック・ピアノがリード。
全体のムードを決めるバッキングとともにソロでもかなりのスペースを使っている。
コーラスでもリチャード・シンクレアの存在感は抜群。
クールネスと幻想性を一手に引き受けている。
ジャジーなベース・ラインもいい。
ヘイスティングスの誠実なコード・カッティングはジャズの横溢に対していい刺激になっている。
ハーモニーの雰囲気などから、ジャジーな THE BEACH BOYS といったイメージも。
スティーヴ・ミラー作。
4 曲目「Aristocracy」(3:03)
ポール・マッカトニーに迫るカントリー・フレイヴァーあふれるキャッチーなポップロック。
(ここでいうカントリー・フレイヴァーとは、THE BEATLES の「All My Loving」が基準である)
ギターの歯切れよいコード・カッティング、力強いうねりを与えてくるベース・ライン、バブルガム・ポップ風のスキャット、などなど、楽しくならないわけがない。
オルガン(ワウ・エレクトリック・ピアノか)の間奏もノリノリである。
前作の「Love To Love You」から続く、ヘイスティングスのリード・ヴォーカルによる得意のスタイルの作品だ。
ジェットマシン風のエフェクト処理されて元気いっぱいのドラムスもカッコいい。
リズミカルにしてファンタジックであり、この作風は後々のアルバムにまで続く。
5 曲目「The Love In Your Eyes」(12:31)管弦楽をフィーチュアしたオムニバス形式の劇的なジャズロック大作。
史劇の劇伴を思わせるオーケストラの降臨。
哀愁のストリングスを背景に切ないヘイスティングスのヴォーカルが流れるオープニング。
透き通るような弦楽の響きとともにギターが静かに鳴る。
タイトなドラミングが立ち上がるとストリングスが追いかけ、ビートの力を得たヴォーカルもエネルギッシュに表情を変える。
歌唱を受け取るのはオープニング・テーマを再現するオーボエ・ソロ。
透き通るように美しい。
再びドラムスの力強いリズムが打ち出されて、ヴォーカルが勇ましく主張する。
ワウ・ギターとストリングスの軽やかなせめぎあい。
8 分の 6 拍子へとリズムは変化し、フルートの華麗なソロが舞う。
「To Catch Me A Brother」だ。
ブラスによる強烈なキメ。
フルートがリードするエネルギッシュな演奏は鮮やかなベースの動きが支える。
狂おしくスケールを上下するフルートに煽られるようにアンサンブルは緊張を増す。
再びブラスが幾度となく切り込み、フルートはエネルギッシュに乱れ吹いてブラスに対峙する。
8 拍子に戻ってテンポは落ちつきを見せる。
ギターとエレクトリック・ピアノが示すマイナーのリフ。
「Subsultus」である。
エレクトリック・ピアノのストローク伴奏でジェット・マシーン風のギター・ソロ。
ヘイスティングスのプレイはフレーズよりも音色の工夫が面白い。
オルガンのような音だ。
ナチュラルに歪んだトーンのギターも重なってくると、小気味よくもややブルージーな雰囲気へと色調が変化する。
高まるギターのリフレイン。
それをなだめるようなエレクトリック・ピアノの静かなリフレイン。
トーンダウンしたアンサンブルはサイケデリックな幻想空間へと広がり始める。
ワウワウを利かせたエレクトリック・ピアノがゆるやかなアドリヴを繰り広げる。
長いディレイを用いた一人ニ重奏がおもしろい。
ピアノ・ソロは次第にジャジーに変化して、ファンキーに跳ね始める。
ゆるやかなクレシェンド。
荒々しさも強まる。
かき消すようにヴォリュームが下がるとエレクトリック・ピアノの余韻とともに「Debouchement」。
重苦しいキメの連続を聴きながらヘイスティングスが憂鬱な表情で歌い出す。
ワウ・ギターのコード・カッティングが始まると「Tilbury Kecks」。
再び一気にテンポ・アップ、エネルギッシュなアンサンブルが始まる。
ブルージーなギター・ソロはすぐにエレクトリック・ピアノとのユニゾンへとまとまってゆく
。
思わせぶりなブレイクを経てドラムスのピックアップ、そして再びワウ・ギターのリード。
ダイナミックでファンキーなアンサンブルがひた走る。
加速するようなドラムスのパターンがカッコいい。
フェード・アウト。
クラシカルなオーケストラとの共演を経て、センチメンタルなメロディを配しつつ、ジャズロック調のスリリングな演奏が続いてゆく。
ジャズ、ブルーズと微妙な表情の変化を見せる演奏が楽しい。
特に中盤以降のシャープな 8 ビートで走り続ける演奏は、難しいことをしなくてもカッコいいというロックの効率性を裏書きする名演である。
ヘイスティングスのギターとミラーのエレクトリック・ピアノに加え、前半のフルートもすばらしい。
6 曲目「The World Is Yours」(3:41)
大作のエピローグのような優しいメロディ・ラインの牧歌調歌ものロック。
軽快なテンポと甘いメロディ・コーラス。
リズミカルなアコースティック・ギターの伴奏が気持ちよい。
やさしくてちょっぴり切ないサヨナラである。
以下、DECCA 8829822 CD のボーナス・トラック。
「Pye's June Thing」(2:57)初出。
「Ferdinand」(2:57)初出。
「Looking Left, Looking Right」(5:37)初出。
「Pye's Loop」(1:21)初出。
スティーヴ・ミラーのプレイを中心にゲストの参加も手伝ってジャズ色が拡大し、ジャジーなソロとプログレッシヴなアイデアのロックが阿吽の呼吸で結びついた佳作となる。
ジャズ指向はオープニング曲や二つの大作に顕著。
CARAVAN がジャズロックなのだろうかという疑問に対する一番簡単な答えは、このアルバムだ。
そして注目は 5 曲目の大作である。
サイケデリック・ロックから出発してジャズに身を委ねつつ、遥かに高い到達点を目指す心意気が凝縮した作品である。
ドラマチックな大作だけではなく、センチメンタルなポップ・フィーリングにあふれたロック・チューンも取り揃えており、アルバムとしてのバランス確保も巧みである。
前作のようなシュールでサイケなファンタジーという趣は消えたが、アレンジによる音楽の幅の広がりを感じさせる作品となっている。
全体にやや地味なことだけが残念。
スティーヴ・ミラー氏は 98 年に逝去されました。ご冥福を祈ります。
(Deram SDL 8 / DERAM 820 919-2 / 8829822)

| Pye Hastings | guitar, vocals | Dave Sinclair | keyboards |
| John G.Perry | bass, vocals, percussion | Richard Coughlan | drums, percussion |
| Peter Geoffrey Richardson | viola | ||
| guest: | |||
|---|---|---|---|
| Tony Coe | clarinet, tenor sax | Jimmy Hastings | flute solo, conduct |
| Tommy Whittle | clarinet, tenor sax | Harry Klein | clarinet, baritone sax |
| Pete King | flute, alto sax | Barry Robinson | flute, piccolo |
| Henry Lowther | trumpet | Chris Pine | trombone |
| Rupert Hine | A.R.P synthesizer | Frank Ricotti | conga |
| Jill Pryor | larynx | Paul Buckmaster | electric cello |
73 年発表の「For Girls Who Grow Plump In The Night」。
デイヴ・シンクレアが復帰するも、今度はリチャード・シンクレアが脱退、そして新メンバーにベーシストのジョン・ペリー、ヴィオラのジェフリー・リチャードソンを迎える。
特にリチャードソンは、この後の CARAVAN を音楽的に支える重要人物となる。
ヴィオラが入った分だけデイヴ・シンクレアのキーボードの出る幕が減るのではと危惧したが、最終曲にみごとな見せ場をつくってくれている。
一方、パイ・ヘイスティングスはほぼ全作品の作曲を担当し、ハイトーン/ファルセットを活かしたリード・ヴォーカルでも活躍する。
どうやらグループの主導権は彼の手に収まったようだ。
作品は、管弦楽を含めた多彩なサウンドを駆使し、明快で親しみやすいフレージングによる器楽ソロをフィーチュアした贅沢なポップスである。
ビートポップスにジャズ的な即興ソロ・パートを盛り込んだアプローチという点で、ジャズロックの一つの潮流といってもいいだろう。
ゲストもジャズ界のミュージシャン中心に豪華。
プロデュースはデヴィッド・ヒッチコック。
前半はギターとヴィオラがカントリー・フレイヴァーあふれる演奏を見せる。
1 曲目「Memory Lain, Hugh」(5:00)。
ギターによるあっと驚くカントリー調のソリッドなリフとコード・カッティング。
クールに構えたヴォーカルがカッコいい。
リズミカルな曲調をヴィオラがなめらかに潤す。
カントリー・テイストはギター・リフに名残をとどめ、次第にデイヴ・シンクレアのオルガンとエレクトリック・ピアノ、管楽器の繰り返しが CARAVAN サウンドに染めあげてゆく。
エア・ポケットのように静かなブリッジでは、フルートが大きくフィーチュアされる。
なめらかなヴィオラの紹介を経て、グルーヴィなキーボード・ソロ、そして、その熱気を抑えるようなフルートの再現。
最後は、ドラムスを強調した熱っぽいバンド演奏とフルートの乱舞が重なり合い、ヴィオラも加わって大見得を切る。
ジャジーなカントリー・ロックの傑作。
管楽器のゲストも豪華絢爛だ。
余韻を断ち切って、軽快に「Headloss」(4:19)へメドレー。
再びカントリー・フレイヴァーたっぷりの跳ねるようにリズミカルな作品だ。
地味な声質のヘイスティングスのヴォーカルは、リズミカルな曲調でこそ活きる。
リチャード・シンクレア脱退を乗り切るための作戦はここまでは奏功している。
リラックスした歌メロと軽快な演奏にほんのりロマンティックな、心地よい空気感あり。
さりげないシンセサイザーのオブリガートは WINGS のよう。
コンガが調子よく入ってノリノリの演奏が続く。
ギターとフィドル風のヴィオラによる小気味のいいかけあい。
ヘイティングスのギターはクランチなフレーズをきっちり決めており、本人の謙遜のわりにはかなりの腕前である。
ヴィオラが口火を切り、カントリー調のギターとの軽やかなかけあいを続けつつ、なだらかな下降のようなエンディングへ。
ポップなロックンロールにぜいたくな管楽器アレンジでジャズの香りをまぶしたメドレー作品。
ギター、オルガン、ベース、ドラムス、ヴィオラまで、全メンバーのプレイがしっかりフィーチュアされている。
管絃のアレンジは、ジミー・ヘイスティングス。
2 曲目「Hoedown」(3:10)。
軽快で歯切れのいい曲調は 1 曲目に酷似するも、パーカッションも加えたリズムは軽やかな 8 分の 7 拍子である。
ヴォーカル・パートは二声のコーラス。
(一人多重録音かペリーとヘイスティングスか?)
間奏は、フィドル風のヴィオラ・ソロをたっぷり。
パーカッションとともにハンド・クラップも入って、追い立てるようなスピード感を演出している。
ヘイスティングスによるカントリー調のギター・リフがドライヴするアップテンポの変拍子ポップ・ロック。
3 曲目「Surprise, Surprise」(3:45)。
優美なメロディによるのどかで愛らしいフォークロック。
ヴィオラのゆったりしたメロディと敏捷なベースがヴォーカルを守り立てる。
さざめくようなエレクトリック・ピアノの伴奏もいい感じだ。
コーラスはここでもばっちり。
サビのファルセットはこの曲にピッタリだ。
ヴォーカルの甘さに対してリズム・セクションは非常にタイト。
後半に向かうにしたがってヴィオラがどんどん盛り上ってゆく。
やや不自然なフェード・アウト。
このリード・ヴォーカルはペリー?
ここまでの曲に共通するのは、カントリー調のメロディ楽器を支えてドラムスが一貫して手数多くパワフルなプレイを見せていること。
楽曲のドライヴ感をキープしているのはこのドラムス、パーカッションだ。
4 曲目「Cthlu Thlu」(6:10)。
珍しくヘヴィで邪悪な表情を見せる作品。
冒頭のかすれるような音はテープ処理だろうか。
スペイシーなエフェクト音が飛び交い、対話調のヴォーカル(ヘイスティングスとペリー)による不気味なムードが立ち込めるかと思えば、突如転調、明るくソウルフルなヴォーカルとクラヴィネットが飛び出して R&B 調に変化するなど、素っ頓狂な展開を見せる。
再び暗のベース・パターンそしてヴィオラがリードする明と移動するが、結局三度ヘヴィな曲調へ。
ヘヴィに刻まれるギター・リフがドライヴする場面は、CARAVAN には珍しく、攻撃的でダークなプログレ調である。
深いエコーの澱みで、さまざまな音がぐるぐる渦を巻いている。
次第に浮かび上がるは、ブルージーでジャジーなオルガン・ソロ。
ヘヴィなギターとオルガンが熱っぽく絡む。
一転テンポも上がり、再び軽快なロックンロールへ。
軽やかなサックスも聴こえる。
最後は、ダークなベース・リフを思い切りリタルダンド、不気味な余韻を引っ張って終る。
いかにもプログレらしい(「Abbey Road」の A 面風といってもいいかもしれない)凝った曲作りとひねりがあるヘヴィ・チューン。
一本調子にならないようにこういう曲が用意されているところはさすが。
5 曲目「The Dog, The Dog, He's At It Again」(5:53)。
甘く切ないメロディ、ヘイスティングスの俊敏でひそやかな歌唱とそれを支える AOR なエレクトリック・ピアノと牧歌調の温かいヴィオラの響き。
寄り添うコーラスもすてきな王道英国ポップスである。
パイプ風のシンセサイザーとヴィオラのオブリガートも表情豊か。
じつに贅沢に音が盛り込まれている。
間奏は、デイヴ・シンクレアによるメロディアスなシンセサイザー・ソロ、支えるのは粘っこくヘヴィなベースラインとギターのパワーコードの轟音。
グルーヴのあるアンサンブルだ。
60 年代風のハーモニーによるメイン・ヴォーカルを回想し、メリーゴーラウンドのように器楽とハーモニーが追いかけあう。
どこかクールな面持ちなのはヘイスティングの声質によるのだろうか。
10CC を思わせる英国風のスウィートなポップスへジャジーな器楽を持ち込んだ、CARAVAN の典型スタイルの名曲。
シンセサイザーの音がいい。
タイトルと合わないが、ジャジーで胸キュンのラヴ・ソング。器楽が充実し、さまざまな音色がふんだんに用いられている。
6 曲目「Be All Right」(6:38)。
ヘリコプターの爆音のような SE から始まり、ギターとヴィオラ、チェロのユニゾンによるリフがドライヴ感を高めるハードなオープニング。
変拍子風のアクセントが面白い。
シンプルな繰り返しのシャウトによるヴァースは、ルパート・ハイン風の王道ポップス。
ギターのワイルドなオブリガートも意外。(これはリチャードソンのプレイかもしれない)
リード・ヴォーカルはおそらくペリー。
70 年代後半から 80 年代にかけての作品のようにイージーでプラスティックなサビも印象的。
弦楽器がドライヴするハード・チューンというのも意表を突く試みである。
CURVED AIR 風のキャッチ―なパワーポップ。
「Chance Of A Life Time」で雰囲気は一転。
ヴィオラとアコースティック・ギターによる物憂い演奏と舗道を蹴る馬車の音のようなコンガの響きに支えられた、ひそやかなバラードである。
リード・ヴォーカルはヘイスティングスに交代。
エレクトリック・ピアノが加わると、西海岸の涼しげな空気が曲調を軽くする。
ヴィオラのソロによる間奏部は、ブルージーながら対応する巧みなベースラインのせいで PILOT や CAFE JACQUES のような AOR 風味もあり。
メランコリックなヴィオラ、エレクトリック・ピアノに彩られたメイン・ヴォーカルはどこまでも静かで無表情だ。
翳のあるポップスという点で CAMEL に通じる作風である。
7 曲目「L'Auberge Du Sanglier」(9:46)。
管弦楽を大きくフィーチュアしたオムニバス風の大作。
悩ましきヴィオラとアコースティック・ギターの気まぐれな爪弾きによる神秘的な序章。
エレクトリック・ヴィオラはつややかな音色で存在感をアピールする。
爆音を合図に、10+9/16 拍子のリフがドライヴするスリリングな大作「A Hunting We Shall Go」が開始。
ハードなアンサンブルでパワフルにテーマを刻み込むと、まずは切れ味鋭いオルガン・ソロ、続いて激しいギター・ソロからヴィオラのソロへ。
熱気迸る演奏だ。
ヴィオラは 6+7 拍子の第二テーマを提示、スピード感の高まりととともにアンサンブル全体を制すると、一気に静寂へと吸い込まれていく。
美しく爪弾かれるピアノの調べに導かれて、遠い潮騒のように弦楽奏が湧き上がってくる。
「Pengola(ジョン・G・ペリー作) / Backwards(SOFT MACHINE 「Slightly All The Time」より)」だ。
ゆるやかな起伏をつけながら、次第に盛り上がってくるオーケストラ。
シンセサイザーとエフェクトされたオルガンが管絃の悠然とした調べの間を浮き沈みしつつ、次第に主張を強めていってクライマックスへと近づいてゆく。
最高調で管絃とともに「A Hunting We Shall Go」がエネルギッシュに再現される。
勇壮な管弦楽に交じって響いてくるオルガンのなんとカッコいいこと!
最後は爆音ですべてが消えてゆく。
オーケストラ・アレンジは、マーティン・フォードとジョン・ベル。
以下、UICY-2392 CD のボーナス・トラック。
「Memory Lain, Hugh/ Headloss」(9:18)CD 初出。US ミックス。
「No! ("Be Alright") / Waffle ("Chance Of A Lifetime")」(5:10)初出。
「He Who Smelt It Dealt It ("Memory Lain, Hugh")」(4:43)初出。
「Surprise, Surprise」(3:15)初出。
「Derek's Long Thing」(11:00)初出。
カントリー・テイストのポップ・ロックを中心に多彩な芸域の幅を見せる佳作。
アレンジに工夫を凝らしたポップスにジャズロック的な逞しい演奏力を結びつける作風は完成の域にある。
ヘイスティングスの作曲の妙は、各プレイヤーの演奏力を活かすという点に集約されるので、リチャードソンはそういう戦略にぴったりの人選だ。(マルチプレイヤーぶりは次作以降で十分に生かされる)
前半のポップ・テイストがやや単調になりかけたところで、ミステリアスなヒネリを加え、最後の大作をぶつけて一気に幕を引く。
さて、複数の作品をつないで一つにする手法は、THE BEATLES の「A Day In The Life」や「You Never Give Me Your Money」辺りが始まりのようだが、本作品でもその方法がうまく使われている。
(Deram SDL-R 12 / DERAM 820 971-2 / UICY-2392)

| Pye Hastings | guitar, vocals |
| Geoff Richardson | electric viola |
| Richard Coughlan | drums |
| John G.Perry | bass, vocals |
| Dave Sinclair | electric piano, organ, synthesizer |
74 年発表の「Caravan & The New Symphonia」。
CARAVAN 初のライヴ・アルバムは、管絃オーケストラを率いた作品。
バック・コーラスやオーケストラとバンドの間の張り詰めた一体感は申し分なく、ライヴとしては屈指の内容といっていいだろう。
タイトな演奏に浮かび上がる独特の甘さや緩やかさなど、すべての音がいかにも CARAVAN らしく、そこへさらにライヴ独特の拡張されたダイナミクス、臨場感があって曲の良さをグレードアップしている。
オーケストラとバンドの共演は数多あれど、本作品はその試みの稀有の成功例の一つだろう。
バック・コーラスにリザ・ストライク、サックスとフルートにジミー・ヘイスティングス(彼はニュー・シンフォニアのメンバーらしい)、そしてパーカッションにモーリス・パートなど、おなじみの顔も見える。
最終曲の前に入るパイ・ヘイスティングスの英国訛りの MC に思わず頬が緩みます。
新曲が三曲。
プロデュースはデヴィッド・ヒッチコック。
1973 年 10 月 28 日英国ドルリーレーン王立劇場にて収録。
2001 年のリマスター盤はライヴ全曲(第一部はバンドのみの演奏で、第二部からがオーケストラとの共演)を収録した決定盤。
「Introduction by Alan Black」(1:01)MC によるイントロダクション。このなめらかな語り口をキングズ・イングリッシュと呼ぶのかもしれないが個人的にはセサミ・ストリートの "カエル" を思い出すばかり。
「Memory Lain, Hugh / Headloss」(9:57)CD 盤にのみ収録。前作より。前半エンディングの緊迫したアンサンブルがいい。
後半のギター・リフはリチャードソンのプレイかと思ったがヴィオラがシームレスに入るのでヘイスティングスなのだと再確認。歌いながら弾くには難しそう。ヘイスティングスのギターとリチャードソンのヴィオラによるかけあいがカッコいい。(ギターはやはりリチャードソンで弦の音はオーケストラが担当している可能性もある)
「The Dog, The Dog, He's At It Again」(6:35)CD 盤にのみ収録。前作より。サイケデリックなオルガン・ソロとクラシカルなヴィオラのミスマッチの妙。リード・ヴォーカルはペリーか?
「Hoedown」(3:55)CD 盤にのみ収録。前作より。第一部はここまで。
「Introduction」(6:55)サイモン・ジェフズによる新曲。ここから第二部。
「Mirror For The Day」(4:19)新曲。
「The Love In Your Eye」(12:02)四作目より。
「Virgin On The Ridiculous」(6:53)新曲。
「For Richard」(13:48)二作目より。
「A Hunting We Shall Go」(10:33)CD 盤にのみ収録。前作より。
(Deram SML-R 1110 / K16P-9062 / 8829692)

| Pye Hastings | guitar, vocals |
| Dave Sinclair | keyboards |
| Mike Wedgwood | bass, vocals, conga |
| Richard Coughlan | drums |
| Geoff Richardson | viola, guitar, flute |
75 年発表の「Cunning Stunts」。
ジョン・ペリー脱退後、ベースとヴォーカル担当にマイク・ウェッジウッドを迎えた DERAM 最後の作品。
前半ポップ・チューンそして後半に大曲メドレーをすえたアルバム構成は、すでに自家薬籠中の技である。
サウンド面の特徴は、オープニング 2 曲で示されるような優雅なブリティッシュ・ポップ本流の味わいだろう。
10CC や WINGS など THE BEATLES の流れを汲む一系統なのだ。
新加入のウェッジウッドは、ベース以外にもオーケストラ・アレンジやムーグをこなしている。
もちろんリチャードソンもヴィオラ、ギターで大活躍。
プロデュースはグループとデヴィッド・ヒッチコック。
ジミー・ヘイスティングス氏はクレジット以外にも(当然のように)フルートで活躍。
1 曲目「The Show Of Our Lives」(5:48)。
ストリングスの海に揺られるノスタルジックかつスペイシーなナンバー。
ゆったりと波打つようなピアノによるイントロダクション。
フレットレス・ベースのグリッサンドで完全にノック・アウトである。
なんて優美なサウンドなんだろう。
そして誰かに抱かれているようにゆったりとスウィングするメロディ。
歌詞もすてきだ。
いつのまにかストリングスに抱かれて、満点の星空を翔んでゆくのだ。
胸いっぱいになってしまう、すてきなオープニング・ナンバーである。
カントリー・フレイヴァーあふれるギター・ソロはリチャードソン。
ヴォーカルはウェッジウッド。
「I'm Not In Love」でしょうか。
2 曲目「Stuck In A Hole」(3:10)。
ギターのコード・カッティングが小気味いい、ポール・マッカートニーばりのポップ・チューン。
パーカッションも入った調子のいいアップ・テンポの作品だ。
決めの追いかけファルセット・コーラスに胸キュンである。
間奏はヴィオラとウェッジウッドの操るブラス風の愛らしいムーグ。
軽やかなポップン・ロールだ。
ちょっと伝法に叩き飛ばすリズムも洒落ている。
「Junior's Farm」でしょうか。
野卑ではない DOOBIE BROTHERS という感じもあり。
素朴なヴォーカルが不器用な男の愛の歌を思わせる 3 曲目「Lover」。
(5:07)メロディからストリングス、ピアノの使い方まで、ジョージ・マーティン直系の正統ブリット・ポップのバラードである。
ゆったりと優しげな曲だ。
ヴォーカルにそっと寄り添う控えめなピアノがいい味わいだ。
間奏の短いギターとヴィオラのユニゾンもぐっと抑え目でいい。
ストリングスをたっぷり使ったこの曲調では歌までうまいといやみだが、素朴なヴォーカルのおかげでとてもいい感じにまとまっている。
逆に最後のヴィオラ・ソロ、ストリングスは美しいが、やや大仰というかベタ過ぎてちょっといやみ。
リード・ヴォーカル、ストリングス・アレンジはウェッジウッド。
「Lover」と単数のときは実は女性からみた男の恋人というニュアンスだそうです。
4 曲目「No Backstage Pass」(4:32)
メランコリックななかにジャジーなクールさをもつ、弾き語り風のバラード。
前曲のストリングスがそのまま続いてイントロとなってゆく。
さすがにヘイスティングスのヴォーカルは甘くはなくてクール。
そして、秋風のようなメロディと伴奏のストリングスがまた英国風である。
エレクトリック・ピアノによるさりげなくもジャジーな味つけは、サビにおけるグルーヴ感をしっかり用意する。
後半のサビに続くスリリングなギター・ソロは、おそらくリチャードソンだろう。
最後は、再びストリングスに支えられた憂鬱な調子へと帰ってゆく。
5 曲目「Welcome The Day」(4:02)
R&B テイストたっぷりのファンキー・チューン。
CARAVAN としては、異色作といっていいだろう。
元来ソフトな声質らしいウェッジウッドが、無理やりパンチを効かせ、派手さのないドラムスもパーカッションをフィーチュアして細かなリズム・キープを見せる。
ヴィオラがやや浮き気味なのは、R&B にヴィオラという取り合わせが珍しすぎるせいだろうか。
うねるようなワウ・ギターとエレクトリック・ピアノのプレイなど、まさしくソウル・ミュージック、R&B だが、脂ぎらないヴォーカルとの取り合わせが、いいのか悪いのか分からない。
そんななかでシンクレアのムーグ・ソロが、SOFT MACHINE 的な知性を感じさせる。
旧 B 面は得意のメドレー大作「The Dabsong Conshirtoe」(18:02)。
ギターのアルペジオに導かれて、うっとりするほど美しいメロディの「Mad Dabsong」が始まる。
ムーグのテーマと歌メロが、なんともノスタルジックな名作だ。
伴奏はおちついたピアノのアルペジオと、木管楽器のようなムーグのオブリガート。
アコースティック・ギターはリチャードソン。
そのままノスタルジックなメイン・テーマを引き継ぎ、「Ben Karratt Rides Again」へ。
すぐに、クランチなギターがカッコいい、ハードなタッチのロックンロールへと変化する。
ここでも間奏/オブリガートにムーグ・シンセサイザーが存在をアピール。
エレクトリック・ヴィオラ、シンセサイザーらによるテンション高いインストゥルメンタルが続いてゆく。
ソウルフルな盛り上がりだ。
再び 1 曲目のノスタルジックなヴォーカル・テーマが再現、さざめくストリングスとともに「Pro's And Con's」へと進む。
ギターによるハードなリフとブラス・セクションが冴える、ハードなロックンロールだ。
早口のヴォーカルは、ポール・マッカートニー風。
独特のトーンのオルガン、エレクトリック・ヴィオラと続くコール・レスポンス風のソロ合戦もカッコいい。
「ロッキン・コンチェルト」という邦題のイメージは、ここら辺りからきたのだろうか。
ブラス・アレンジはジミー・ヘイスティングスとシンクレア。
指揮もヘイスティングスだそうだ。
ここからインストゥルメンタル・ナンバーが 2 曲。
まずは、ドラマチックなアンサンブルが一気に高まり、オルガン、シンセサイザー、フルートが印象的なメロディを散りばめる小品「Wraiks And Radders」。
ジョージ・マーティンを思わせる音作りである。
そして、モダン・ジャズ調のソロ回し大作「Sneaking Out The Bare Quare」。
ジャジーなギター伴奏に支えられたフルートによるソフトなテーマ。
ここから、エレクトリック・ピアノ、ギター(リチャードソンによる)、ムーグ、ヴィオラとソロが続いてゆく。
ヴィオラ、ムーグの絡みはブラス・セクションに乗せられて盛り上がる。
それにしても、デイヴ・シンクレアのキーボードの音に対するセンスはかなりのものだ。
最後は再びフルートによるテーマ。
思わせぶりなブレイクを経て大団円「All Sorts Of Unmentionable Things」。
「Hoedown」を思わせるカントリー調ギターのコード・ストロークが秩序をキープ、ストリングスやヴィオラらがしっかり寄り添い、力強い隊列を成してゆく。
ここでもブラス・セクションが強烈に後押し。
リフのバックでは、様々な SE がミュージック・コンクレート風に散りばめられ、交錯してゆく。
次第に第一曲「The Show Of Our Lives」が他を圧倒して感動のリプライズ、そしてフェード・アウト。
「For The Girls Who Grow Plump In The Night」の組曲や「Nine Feet Underground」にひけをとらない大作。
無窮動で一気に流れてゆくゴージャスなメドレーだ。
やっぱりマッカートニー/WINGS の影響はあるんでしょうね。
終曲「The Fear And Loathing In Tollington Park Rag」(1:12)はリチャードソンのアコースティック・ギターが軽快なシャフルを決める、ラグ・タイム風の小曲。
フルート、ヴィオラも愛らしい。
いかにも THE BEATLES 風のまとめだ。
以下、UICY-2394 CD のボーナス・トラック。
「Stuck In A Hole」(3:11)シングル・ヴァージョン。
「Keeping Back My Love」(3:15)初出。
「For Richard」(18:33)CD 初出。74 年 クロイドンのフェアフィールド・ホールにて収録。
前半をポール・マッカートニーばりのメロディ・ポップで決めて、後半はゆったり音に身を委ねられるメドレー大作と、あいかわらず全く隙なしの CARAVAN ワールド。
R&B 色やポップな曲調は後半の大作へもしっかり反映されており、スリリングなインストと対を成す魅力になっている。
1、5 曲目のリード・ヴォーカル担当、3 曲目のタイトルの意味は From USC さんからご指摘いただきました。
感謝です。
(Decca SKL-R 5210 / POCD-1838 / UICY-2394)
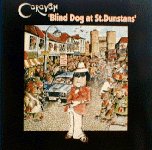
| Pye Hastings | electric & acoustic guitar, vocals |
| Jan Schelhaas | piano, electric piano, clavinet D6, ARP string ensemble, mini-moog, organ |
| Mike Wedgwood | bass, vocals, congas |
| Richard Coughlan | drums |
| Geoffrey Richardson | viola, guitar, flute, night-shift whistle |
76 年発表の「Blind Dog At St.Dunstan」。
デイヴ・シンクレアが再脱退し、ヤン・シェルハースがキーボード担当として NATIONAL HEAD BAND から加入、所属レーベルも BTM へと移籍する。
限りなくパーマネント・メンバーに近いジミー・ヘイスティングスが、今回もサックスとフルートでゲスト参加。
B 面いっぱいを使った大作は姿を消し、楽曲がややメローになったのは確かだが、ほのかにカントリー・フレイヴァーあるクールなポップ・ロックという点では、かなりの内容だろう。
サウンドでは、ピアノやシンセサイザーの音が目新しい。(シェルハースの好みか、シンセサイザーの音は格段に増えている)
また、リチャードソンがリード・ギターからフルートまでも担当して存在感が増している。
個人的には巧みなピッチベンドさばきを見せるシンセサイザーとリリカルなピアノがうれしい。
また A 面後半のメドレーで見せるジャジーな AOR 調や R&B テイストも新鮮だ。
パイ・ヘイスティングスは、ほぼ全曲でヴォーカルを担当。(1 曲のみウェッジウッドが担当)
10CC や ポール・マッカートニーの WINGS とイメージが重なるというよりも、「あの頃の音」がたっぷり入っているといった方がいいでしょう。
ちょっと大人になって小粋な振る舞いも板についてきた、そんなアルバムだ。
プロデュースはデヴィッド・ヒッチコック。
「Here I Am」(6:17)スリリングでドラマティックなポップ・ロック。
ヘイスティングスが珍しく鮮やかなリードギターを披露。
バッキングのシンセサイザーが派手。
レガートなプレイのヴィオラが楽曲のリズミカルなタッチと対比して存在感を示す。
長さに見合ったドラマ展開もあり。
「Chiefs And Indians」(5:13)
ジャジーな AOR 風の作品。
リード・ヴォーカルはマイク・ウエッジウッド。甘くまろやかな声がいい。
イントロとアウトロのピアノも新鮮。
弾き語り風に甘めに始めて、ふと気づけばジャジーでタイトなインストゥルメンタルへと展開する技もこのグループならでは。
コーラス部分からのフュージョン風のダイナミックな展開がじつにカッコいい。
洒落たオブリガートのサックスはジミー。
「A Very Smelly, Grubby Little Oik」(4:12)
英国らしいシニカルな調子が活きる一直線のポップ・ロック。ここから 4 曲は組曲風に展開する。
ジャジーなエレクトリック・ピアノはこの時代ならでは。
リードギターはリチャードソン。
達者だがヘイスティングスと比べると個性が見えない。
「Bobbing Wide」(2:31)
前曲のエンディングのヴォーカルの余韻がそのまま導く、冴え冴えとクールなインストゥルメンタル。
ここのフルートはジミーでなくリチャードソンらしい。
終盤は、さらにファンタジーが強まり初期 RETURN TO FOREVER のようになる。
「Come On Back」(3:56)
再びエレクトリック・ピアノがヴォーカルを支えてささやくシティ・ポップス風の作品。
サビだけはレイ・チャールズ風に叩きつけて変化をつける。
サックス、ヴォードヴィル調のクラリネットはジミー。
「Oik(Reprise)」(2:24)
ゴスペル風のコーラス(CHANTER SISTERS)が加わったにぎやかなリプライズ。
「Jack And Jill」(6:27)
スティーヴィー・ワンダーばりのファンキーなポップ・ロック。
メロディ・ラインはワンパターンだが、エフェクトされたベースやクラヴィネットが刻むファンキーなリズム、ユーモラスな効果音(犬も吠える)など多彩なアレンジで聴かせる。
リードギターはヘイスティングス。終盤のオルガン、ブレイク後のエピローグの舞うようなフルートもいい音だ。
「Can You Hear Me ?」(6:17)
風とともに駆け抜けるようなスピード感あふれる作品。風はオルガン。ヴィオラのオスティナートの揺らぎも独特な緊張させる効果あり。
終盤、ひとしきり走った後にテンポを落としてヴィオラが悠然と受け止め、エンディングへ導く。ドラマティック。
レーベル・メイトの RENAISSANCE にも同じ名前の曲がありました。
「All The Way (With John Wayne's Single-Handed Liberation Of Paris)」(8:52)
シンセサイザーを活かしたスペイシーでファンタジックな作品。
プログレから一歩踏み出し、AOR の半歩手前である。
10CC の名曲や WINGS を思い出すなという方が無理。
ただし、こちらの方が素朴なやさしさにあふれている。
その源の一つがジミー・ヘイスティングスのフルートの調べである。サックスもジミー。
逆に CAMEL には一歩先んじている。
(BTM 1007 / REP 4501-WY)

| Pye Hastings | guitar, vocals | Geoffrey Richardson | violin, guitar, flute, sitar, mandolin, vocals |
| Richard Coughlan | drums, percussion | Jan Schelhaas | keyboards, vocals |
| Dek Messecar | bass, vocals | ||
| guest: | |||
|---|---|---|---|
| Vicki Brown | vocals on 6 | Fiona Hibbert | harp on 7 |
| Tony Visconti | recorders on 5, electric double bass on 7 | ||
77 年発表の「Better By Far」。
ヴォーカルを中心としたメロディアスでソフィスティケートされたポップ・テイストを前面に出すと同時に、テクニカルな演奏面でも力の入った佳作。
軟弱なポップ化ではなく、冒険的にして口当たりもいいというポール・マッカトニーが本能的に行っていた手法を意識的に取り入れたような作風である。
70 年代前半にはアドリヴ主導によって音楽的な挑戦を繰り広げていたが、ここではより制御されたアンサンブル、サウンドで同様なチャレンジを試みている。
それは、多彩なドラミング表現、硬質で清潔感ある独特のキーボード・サウンド、工夫されたベース・ライン、などにまずは現れている。
また、リチャードソンがマルチプレイヤーぶりを発揮しているのにも注目。
唯一のインストゥルメンタル作品「The Last Unicorn」では、これぞ見せ場とばかりにヴィオラからマンドリン、フルート、ギターと大活躍だ。
この作品は WOLF の作品とともにフュージョン隆盛後の 70 年代後半における「プログレッシヴ・ロック」を体現した名曲の一つといっていい。
シェルハースも「Man In A Car」を提供して、ヴォーカルも披露している。
そして、ヘイスティングスが、これら 2 曲以外の全曲を作曲。
2 曲目の「Behind You」は 74 年のアルバム・セッションで収録からもれた「Keeping Back My Love」が原型。
最終曲「Nightmare」は後期を代表する名曲。 サイケデリックな CARAVAN らしさと AOR テイストの絶妙のブレンドである。
プロデュースはトニー・ヴィスコンティ。
(ARISTA SPARTY 1008 / ECLCD 1018)

| Pye Hastings | guitar, vocals |
| Richard Coughlan | drums, percussion |
| Dave Sinclair | keyboards |
| Dek Messecar | bass, vocals |
| Geoffrey Richardson | guitar, viola, flute, vocals |
80 年発表の「The Album」。
デイヴ・シンクレアが何度目かの復帰を果たし、「Better By Far」の後、セッション・ワークのためグループを離れたリチャードソンとともに録音された。
内容は、軽快ななかにもベテランらしいフックをおりまぜたポップ・アルバム。
素朴なラヴ・ソング、アメリカンな R&B 風ポップス(ブルーアイド・ソウル)、AOR からレゲエ/スカまで、多彩な楽曲を英国ロックらしいロマンティックでちょっぴりシニカルなタッチでまとめている。
もはやプログレのプの字は要所に配されたスペイシーなキーボードと叙情的なフルートになんとか残るのみである。
この 70 年代終盤のポップス・テイストは CAMEL の「Breathless」のサウンドとも共通する。
すっかりポップスになってしまったことに複雑な思いはあるが、何よりこの辺の音はどうにもこうにも懐かしくあまり客観的になれない。
多彩な楽曲を素直に楽しみたい内容だ。
シンクレアによるジャジーで雅な 3 曲目は、インストゥルメンタルの充実した CARAVAN らしい佳曲。
4 曲目「Make Yourself At Home」も「O Caroline」の作者らしいロマンチシズムたっぷりの名バラードであり、「For Girls Who Grow Plump In The Night」を思い出して正解である。
ヘイスティングスのかすれ声とメロディの甘さが絶妙のバランスを見せる。
5 曲目とともに後のシンクレアのソロ・アルバムにも収録される。
全体にリチャードソンのフルート、シンクレアのエレクトリック・ピアノ、シンセサイザーのセンスがみごと。
リチャードソンは演奏面では変わらぬ活躍を見せ、今回は多彩な楽曲も提供している。
しかしながら、本作最大の特徴は、シンクレアのメロディ・メーカーとしての存在感でしょう。
プロデュースはテリー・キング。
「Heartbreaker」(3:37)ヘイスティングス作。リード・ヴォーカルはヘイスティングス。哀愁あるジャジーなオールドウェーヴ・ロック。
改めてヘイスティングス氏のメロディ・センスは一流と感じる。バジー・フェイトンばりのギターもいい。
「Corner Of Me Eye」(3:38)リチャードソン作。リード・ヴォーカルもリチャードソン。
ボブ・ウェルチのいた FLEETWOOD MAC とノーランズが合体したようなロマンティックでダンサブルな英国ロック。
山下達郎が好きそう。ギターはすごくうまいのだがフレーズが普通すぎる。
「Watcha Gonna Tell Me」(5:48)デイヴ・シンクレア作。リード・ヴォーカルはデック・メセカー。
パワーポップ調ながらも、フルートを使ったイントロから英国色を散りばめてかつての CARAVAN らしいジャズ・タッチをアピールする好作品。
エレクトリック・ピアノがジャズを奏で、ムーグ・シンセがファンタジーを綴る。
シンプルなヴァースでもベースの動きやギターのコード・カッティングがさりげなくいい。そしてフルートでダメ押し。
2:45 くらいからの演奏がすばらしい。
エンディングに向かうギターとシンセサイザーのかけあいもよし。
「Piano Player」(5:23)デイヴ・シンクレア/J.マーフィー共作。リード・ヴォーカルはヘイスティングス。
これまたオールド CARAVAN そのもののロマンティックで愛らしい作品。
73 年くらいの曲といって違和感なし。
シンセサイザーのオブリガートの冴え、中盤の堂々としたヴィオラ・ソロなどの見所あり。
「Make Yourself At Home」(3:27)デイヴ・シンクレア作。ヴォーカルはリチャードソンか。
リズミカルなパーティ・ロック。
クラヴィネットのバッキングとシンセサイザーのソロが印象的。
「Golden Mile」(3:10)ジム・アトキンソン作。リード・ヴォーカルはリチャードソン。CAFE JAQUES あたりを思わせるトロピカルなムードのディスコ・チューン。
作曲のジム・アトキンソンはリチャードソンの旧知らしい。
「Bright Shiny Day」(6:18)ヘイスティングス作。リード・ヴォーカルはヘイスティングス。CAMEL に似た黄昏感のあるリリカルなバラード。フルートが美しい。
「Clear Blue Sky」(6:25)リチャードソン作。異色のレゲエ。
リード・ヴォーカルはリチャードソン。
シンセサイザーの打ち震えるようなオブリガートとコーラス部のジャジーな抜けのよさがいい。
「Keepin' Up De Fences」(5:18)ヘイスティングス作。
吹っ切れたようなパワー・ポップ。
ヘイスティングスは懸命に 80 年代対応を試みている印象。
(KINGDOM 74015 / CDKVL 9003)

| Pye Hastings | guitar, vocals |
| Richard Coughlan | drums, percussion, voice on 8 |
| Dave Sinclair | piano, organ, Minimoog, Prophet, vocals on 5 |
| Richard Sinclair | bass, guitars on 3, vocals |
| Mel Collins | sax |
82 年発表の「Back To Front」。
前作ツアーの好評をうけてアルバム製作の機を得、オリジナル・ラインナップが集結した。(ジェフリー・リチャードソンは別の仕事でアルバム・セッション不参加)
内容は、カンタベリーの最良部分を取り出して見せたマジカルなジャズ・ポップロック。
ヘイスティングスの作品は軽快なポール・マッカートニー路線、すなわちドラマティックなポップスを堅守(アルバム後半では冒険もしている)しているので、カンタベリー・ジャズロックのエッセンスは、リチャード・シンクレアとデイヴ・シンクレアが抽出する。
デイヴ・シンクレアのキーボード・プレイがなかなかにアグレッシヴでいい。
B 面一曲目「Sally Don't Change It」ではデイヴがリード・ヴォーカルを取り、甘い白昼夢のような世界を表現している。
B 面二曲目「All Aboard」は世界が 1974 年で止まってしまったようなティーン向けポップ・チューン。
B 面三曲目「Taken My Breath Away」はヘイスティングスがアメリカを向きつつアダルトに迫っている。なんだろう、優しい DIRE STRAITS か、デリケートな HUEY LEWIS & THE NEWS ?
この三曲目と次の四曲目ではシーンを見据えた作風の変化が感じられる。
一曲目冒頭のリチャードの声が聴こえてきただけでうっとりとできる作品です。
60 年代から続いた夢のような日々はここでいったん休止状態に入る。
(KVS 5011 / CDKVS 5011)

| Mike Wedgwood | bass |
| Richard Coughlan | drums |
| Geoffrey Richardson | violin, guitar |
| Pye Hastings | guitar, vocals |
| Dave Sinclair | keyboards |
98 年発表の「BBC Live In Concert」。
75 年 3 月 21 日 Paris Theatre で収録された BBC 音源である。
ラインナップは、「Cunning Stunts」のメンバー。
「Love In Your Eyes」,「For Richard」,「The Dab Song Concerto」など、各アルバムを代表する大作が会場を活かす。
このグループが単なるポップ・グループではないことは、ここでのソロをフィーチュアしたスリリングな演奏を聴けばすぐ分かる。
イントロの MC と 1 曲目の間が不自然に切れていることから、さらに収録された曲があると推測しているのですが。
モノラル録音。
「Intro」(0:29)アナウンサーによるイントロダクション。国営放送らしいスノッブな感じのアナウンス。
「Love In Your Eye」(15:30)前半ヘイスティングスのファズ・ギターが不調。リチャードソンはエレクトリック・ヴィオラとワウ・ギターを持ち替えて活躍。中盤のパーカッションをフィーチュアしたジャズロック・テイスト、シンセサイザー・ソロもカッコいい。13 分辺りからのギター・ソロもリチャードソンか。第四作「Waterloo Lily」より。
「For Richard」(16:55)第二作「If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You」より。潮騒のように緩やかに始まり、自然に広がってゆく演奏の妙、それだけに 6 分付近からの疾走が鮮やか。ノイズすれすれのファズ・オルガンがスリリングに走る。ウェッジウッドのベース・ラインもカッコいい。11 分付近からはエレクトリック・ピアノ、ムーグ・ソロ。名曲です。
リチャードはもういないんだけれどね(いやいやドラマーがいますってば)。
冒頭からヴィオラが巧みにフルートの役を果たしている、と思っていたら、2 分 20 秒辺りからフルートが現れる。これはリチャードソンのヴィオラからの持ち替えのような気がする。(ヘイスティングス兄はクレジットがないし、ヴィオラとフルートが同時には演奏されていないため)
それとも、メロトロン?
「The Dab Song Concerto」(18:45)第七作「Cunning Stunts」より。スムース・ジャズ調とまろやかなブリット・ポップロックの微妙なバランス。前曲の冒頭部と同じくバッキングにストリングス・シンセサイザーを使っている。「Wraiks And Radders」で一瞬フルートが聴こえたような気がするが、続く「Sneaking Out The Bare Quare」では、フルートのパートはギターが演奏しているので、幻聴かもしれない?
エンディング「All Sorts Of Unmentionable Things」は、スタジオ盤のテープ・ギミックを再現して、熱演とともにサイケデリックにドラマを仕上げてゆく。
毎度のことながら、「Sgt. Pepper's」を思わせる感動的なエンディングです。
「Hoedown」(5:20)第五作「For Girls Who Grow Plump In The Night」より。
何気なく 7 拍子のカントリー・チューン。コーラスも決まる。観客に変拍子ハンドクラップを指導。
(SFRSCD058)

| Pye Hastings | guitar, vocals(1-12) |
| Dave Sinclair | keyboards, vocals(1-12) |
| Richard Sinclair | bass, vocals(1-6) |
| John Perry | bass(7-12) |
| Richard Coughlan | drums(1-12) |
| Geoffrey Richardson | viola(7-12) |
98 年発表の「Songs For Oblivion Fishermen」。
内容は、70 年から 74 年にかけての BBC スタジオ・ライヴ。
「In The Land Of Gray And Pink」のラインナップで六曲、73 年から 74 年にかけて「For Girls Who Grow Plump In The Night」のラインナップで六曲が録音されている。
1ー8 曲目がモノラル録音。
ライヴ演奏による「For Richard」、「Caravan & The New Symphonia」収録曲のグループ演奏、またゲストなしでのアルバム収録曲の演奏など、貴重なマテリアルが揃っている。
もちろん、パフォーマンスはエキサイティングかつまとまりある優れたものだ。
曲間をスキップするような編集も、メドレー風の効果を生んでおり違和感はない。
各曲も鑑賞予定。
「Hello Hello」(2:51)二作目「If I Could Do It All Over You, I'd Do It All Over You」より。
「If I Could Do It All Over You, I'd Do It All Over You」(2:48)二作目より。
「As I Feel I Die」(4:31)二作目より。
「Love Song Without Flute」(3:20)一作目「Caravan」より。
オリジナル・タイトルは「Love Song With Flute」。
ジミー・ヘイスティングス抜きの演奏のため。
「Love To Love You」(2:25)三作目「In The Land Of Gray And Pink」より。
「In The Land Of Gray And Pink」(3:39)三作目より。
「Memory Lain, Hugh」(4:54)五作目「For Girls Who Grow Plump In The Night」より。
「A Hunting We Shall Go/Backwards」(8:25)五作目より。
オーケストラなしでの演奏。
ヴィオラとピアノ、オルガン中心の演奏で十分に美しく迫力もある。
特にテーマ部と Backwards は秀逸。
「The Love In Your Eyes」(13:52)四作目「Waterloo Lilly」より。
本曲も原曲はフルート、オーケストラ入り。
リチャードソンのヴィオラとシンクレアのオルガン、そしてヘイスティングスのギターのコンビネーションのみでも十分スリリングな演奏になっている。
リプライズ風の終曲「Tilbury Kecks」ではエレクトリック・ピアノに代わりファズ・ベースも活躍。
全体にヴィオラが強力だ。
「Mirror For The Day」(4:15)六作目「Caravan & The New Symphonia」より。
「For Richard」(15:03)二作目より。
「Virgin On The Ridiculous」(7:00)六作目より。
(HUX 002)

| Pye Hastings | guitar, vocals(1-9) |
| Dave Sinclair | keyboards, vocals(1-3) |
| Mike Wedgewood | bass, conga(1-5) |
| Geoffrey Richardson | viola(1-9) |
| Richard Coughlan | drums(1-12) |
| Dek Messecar | bass (6-9) |
| Jan Schelhaas | keyboards(4-9) |
98 年発表の「Ether Way」。
内容は、75 年から 77 年にかけての BBC スタジオ・ライヴ。
「Songs For Oblivion Fishermen」に続く HUX の発掘である。
75 年は「Cunning Stunts」のラインナップで三曲、76 年は「Blind Dog At St.Dunstan」のラインナップで二曲、
77 年は「Better By Far」のラインナップで四曲が録音されている。
この時点では「Better By Far」が CD 化されていなかったため、6-9 曲目の収録は貴重だった。
各曲も鑑賞予定。
「The Show Of Our Lives」(4:55)七作目「Cunning Stunts」より。
「Stuck In A Hole」(3:15)七作目より。
「The Dabsong Conshirtoe」(12:32)七作目より。
「All The Way」(6:33)八作目「Blind Dog At St.Dunstan」より。
「I'm Not In Love」ばりのロマンティックなスペイシー・ポップス。
「A Very Smelly Grubby Little Oik/Bobbing Wide/Come On Back/Grubby Oik Reprise」(11:45)八作目より。メドレー。
フルート演奏はおそらくリチャードソン。
「Behind You」(5:13)九作目「Better By Far」より。
「The Last Unicorn」(5:34)九作目より。ヴィオラを大きくフィーチュアした緩やかな前半から一転してギターが炸裂するジャズロックへ。そしてフルートをフィーチュアしたリリカルなエンディング。リチャードソンの独壇場である。
「Nightmare」(6:18)九作目より。
「Better By Far」(4:49)九作目より。
(HUX 002)

| Pye Hastings | guitar, vocals |
| Dave Sinclair | keyboards |
| Richard Sinclair | bass, vocals |
| Richard Coughlan | drums, percussion |
| Steve Miller | keyboards on 8 |
2002 年発表の編集盤「Green Bottles For Marjorie」。
BBC セッション音源。
68 年末のデビュー間もない頃の録音から、傑作「In The Land Of Grey And Pink」の作品までに、72 年のスティーヴ・ミラー参加の録音を加えた内容である。
最終曲以外は BOOTLEG の「BBC 1969-1973」、「Living In The Grey And Pink」と同じ音源。
録音は良質のブートレッグ程度だが、SOFT MACHINE (ケヴィン・エアーズ)のカヴァー、「Nine Feet Underground」全曲、微妙な歌詞違いなどファンにはたまらない内容だ。
2001 年からの DECCA アルバムのリマスター作業に携わった腕のいいエンジニア、パスカル・バーン氏からのプレゼントである。
「Green Bottles For Marjorie」(2:36)「If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You」の原曲。
ポップでトボケた味わいの小品。
「Place Of My Own」(4:13)デビュー作より。
ヘイスティングスの冷ややかで物悲しいヘタウマ・ヴォイスとやや大仰な音作りがいい佳品。
初期 KING CRIMSON とまったく同じ感性があるような気がします。
それは 69 年の空気の匂いなのかもしれません。
CARAVAN はこの感じをいつまでも持ち続けたと思います。
「Feelin' Reelin' Squealin'」(5:43)最初期 SOFT MACHINE のカヴァー。
テーマとコーラスはシンクレアで、メイン・ヴォーカルはヘイスティングス?
間奏部分のコワれた、迫りくるような調子は、確かに CARAVAN というよりは SOFT MACHINE 的。
「Ride」(4:20)デビュー作より。
「Nine Feet Underground」(19:20)三作目より。
「In The Land Of Grey And Pink」(4:05)三作目より。
ノーブルなヴォイスと夢語りのようなオルガンに酔う。
「Feelin' Reelin' Squealin'」(10:10)最初期 SOFT MACHINE のカヴァー。
珍しくワイルドなインプロヴィゼーション。
「The Love In Your Eye」(11:47)四作目より。
ジャジーなミラーのエレクトリック・ピアノ、ヘイスティングス最大の見せ場であるワウ・ギター・ソロなどを含む、グルーヴィかつ幻想的な名曲。
(CARAV 001)

| Pye Hastings | guitar, vocals |
| Dave Sinclair | organ, mini-moog |
| Mike Wedgwood | bass, congas, vocals |
| Richard Coughlan | drums, percussion |
| Geoffrey Richardson | electric viola, guitar, glockenspiel |
2002 年発表のライヴ盤「Caravan Live At The Fairfield Halls, 1974」。
74 年 9 月 1 日 U.K. ツアー中のクロイドン、フェアフィールド・ホールでのライヴ録音。
このツアーはジョン・ペリーと交代したウェッジウッドのデビュー・ツアーでもあるそうだ(3 曲目「Be Alright」ではリード・ヴォーカルを披露)。
セットは、「For Girls Who Grow Plump In The Night」収録の作品を中心にしたものである。
パフォーマンス、録音ともに優れており、安定した演奏が生み出す心地よいグルーヴを堪能できる。
特に、エレクトリック・ヴィオラがそのつややかな音色で演奏をリードしている。
ちなみに、本 CD の内容は、80 年に Kingdom Record から発表されたフランス廉価盤「The Best Of Caravan Live」と同じ録音源を使っているが、異なる編集がなされており、より完全なライヴのイメージに近くなっている。
「Memory Lain, Hugh/Headloss」()
「Virgin On The Ridiculous」()六作目より。
「Be Alright / Chance Of A Lifetime」()前半はウェッジウッド、後半はヘイスティングスのヴォーカル。
前半の鋭いギターのオブリガートは本当にヘイスティングスなのだろうか?
「The Love In Your Eye」()四作目より。ライヴ定番の大作。リチャードソンはギターでも活躍。サイケデリックなジャムから生まれる上品な陶酔感、これが CARAVAN の作風である。
「L'Auberge Du Sanglier/ A Hunting We Shall Go / Pengola / Backwards / A Hunting We Shall Go(reprise)」()
サイケデリックな幻想性にジャズの洗練が入り交じるインストゥルメンタルの名作。
ウェッジウッドのベースがカッコよく変拍子のリフを刻んでいる。
「The Dog, The Dog, He's At It Again」()
「For Richard」()二作目より。ライヴの定番であり、CARAVAN を代表する作品。冒頭にメランコリックなヴィオラ・ソロがある。中盤のリチャードソンのギターとシンクレアのムーグのかけあいがカッコいい。
「Hoedown」()アンコール。オーディエンスのソロがある。
(DECCA 8829022)


| Pye Hastings | guitar, vocals |
| Richard Sinclair | bass |
| Richard Coughlan | drums |
| Jan Schelhaas | keyboards |
1994 年発表の発掘盤「Cool Water」。
「Better By Far」製作後、次作用に録音されたデモ七曲(CALYX によれば収録は 1978 年 3 月、本アルバム収録作品の他にも数曲録音された模様)と GORDON GILTRAP BAND のメンバーと録音した四曲の計十一曲からなる編集盤。
楽曲は、リズムこそ鋭いが、基本は AOR 調のポップ・ソングまたはカントリー・フレイヴァーあるロックンロールである。
ファンにとってはヘイスティングスのファルセット気味のヴォーカルを耳にするだけでホッと心が休まるから問題なし。
デモ作品では、リチャード・シンクレアが復帰。
ジェフ・リチャードソンがいないせいか、音のヴァリエーションは主としてシェルハースのキーボードによる。
暖かみのあるエレクトリック・ピアノとシンセサイザーの音色がよく、プレイもピリッとしている。
後半四曲のメンバーは CD にはノンクレジットだが、ジミー・ヘイスティングス、イアン・モズレイ、ジョン・グスタフソン、ロッド・エドワーズらしい。
ジャケットは左が 1994 年版で右が 2002 年の再発盤。収録内容は同じ。
(CRP 1007)

| Richard Coughlan | drums, percussion |
| Pye Hastings | guitar, vocals |
| Geoffrey Richardson | viola, flute, guitar |
| Jan Schelhaas | keyboards, vocals |
| Mike Wedgewood | bass, vocals |
2003 年発表のアルバム「Live UK Tour 1975」。
「Cunning Stunts」プロモーション・ツアー 1975 年 12 月ノッティンガムでの録音。
ヤン・シェルハースは初のライヴではないだろうか。
オルガンのみならずシンセサイザー、エレクトリック・ピアノなど細やかな音遣いで演奏を彩っている。ソロでも出るところでは大いに主張する。
そして、リチャードソンはまたもや八面六臂の大活躍。
収録時間はライヴにしては短めだが、録音状態はいい。
ジャケットの写真を見ると、パイ・ヘイスティングスはエレクトリック 12 弦ギターも使っているようだ。
「The Show Of Our Lives」(4:42)ウェッジウッドのお披露目チューン。目立ちたがりのリード・ギターはリチャードソン。
70 年代らしさでいっぱいの佳曲である。エレクトリック・ピアノから漂うほんのりジャジーな響きもよし。
「Memory Lain, Hugh / Headloss」(9:52)ライヴでの定番メドレー。「Caravan &The New Symphonia」 より。
さすがにリチャードソン一人では管弦楽をカバーできない(もちろんヴィオラのソロは味わいあり)が、それに代わってエレクトリック・キーボードが大胆なサウンドとプレイで活躍する。
「The Dabsong Conshirtoe」(12:30)「Cunning Stunts」の核となる美しくスリリングな長編。
ファズ・ギターはヘイスティングス。
シェルハースとリチャードソンのかけあいがカッコいい。
リチャードソンはヴィオラからフルートに持ち替えてまたヴィオラに戻って大忙し。コフランのパーカッションもおもしろい。
「Virgin On The Ridiculous/Be Alright/Chance Of A Lifetime」(14:23)これもライヴでの定番メドレー。(初出は「Caravan &The New Symphonia」)2、3 曲目は「For Girls Who Grow Plump In The Night」より。2 曲目はウェッジウッドのリード・ヴォーカル。この 2 曲目のファズ・ギター・ソロはヘイスティングスか。
「Love In Your Eye」(18:22)第四作「Waterloo Lily」より。ヴィオラのピチカート・ソロ、パーカッション・ソロあり。
「For Richard」(16:50)第二作「If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You」より。
(MLP03CD)
