
| Keith Emerson | keyboards |
| Greg Lake | bass, lead vocals, guitars |
| Carl Palmer | drums, percussions |
イギリスのキーボード・トリオ「EMERSON LAKE & PALMER」。 70 年代、プログレッシヴ・ロックを一気に隆盛の頂点へと導き、スーパー・グループの称号をほしいままにしたグループ。 THE NICE、KING CRIMSON、ATOMIC ROOSTER から集まった三人の若者は、シンセサイザーというテクノロジーを携えて一躍時代の寵児となった。 クラシックとジャズ、ロックの融合を、けれんみたっぷりに、そして非常に分かりやすく成し遂げた功績は大きい。 やんちゃなキーボード・ロックの代名詞であり、結局ここへ戻ってくる人も多いはず。偉大な音を残して世界を去った二人に心からの賛辞を贈りたい。

| Keith Emerson | keyboards |
| Greg Lake | bass, lead vocals, guitars |
| Carl Palmer | drums, percussions |
次々と繰り出されるアイデアが新鮮な 70 年発表の第一作「Emerson Lake & Palmer」。
近現代クラシックとジャズ、R&B 果ては C&W など多彩な音楽性を、たくましい演奏力と強引なまでのアレンジ力でまとめあげた傑作である。
作品を見てゆこう。
冒頭「Barbarian(未開人)」(4:27)から、ファズ・ベースとハモンド・オルガンが唸りを上げてテーマを叩きつけ、爆発的手数のジャズ・ドラムスとモダン・クラシカルなピアノ・ソロというエキセントリックなアンサンブルが炸裂する。アンサンブルというよりは、「それぞれ勝手に暴れているが、奇跡的に合っている」というべき演奏である。
タイトルが示すとおり、モチーフは数あるバルトークのグロテスクで偏執的なピアノ曲から選び出した独奏曲「アレグロ・バルバロ」。
続く「Take A Pebble(石をとれ)」(12:32)は、ピアノの弦をかきならすオープニングから静と動を巧みにゆきかい、レイクのデリケートにしてオーセンティックな歌唱がやがて不思議なエキゾチズムを醸し出す、詩的な幻想大作。
クラシック、ジャズどころか、C&W にまで大胆に発展するが、その流れはきわめて自然である。
エマーソンも憂鬱なロマンティシズムを込めたピアノ演奏を見せる。
後半は、即興風のジャジーなピアノ・トリオとクラシカルなアンサンブルがなんら矛盾なく交差する、エマーソンならではの世界が広がりを見せる。
3 曲目、ヤナーチェクの「シンフォニエッタ」をモチーフとする「Knife Edge」(5:04)は、ハードな表情でもしなやかさを失わないレイクのヴォーカルと、エマーソンの凶暴なハモンド・オルガンが、際どくバランスしたヘヴィ・チューン。
挑発的でサスペンスフルなタッチを主としつつも、中間部にクラシカルな展開を持つ、完成度の高い作品だ。
かみつくようなオルガンのオブリガートも「フランス組曲」による感傷的な表現も、ともにみごとに流れにとけ込んでいる。
また、エマーソンの作曲力とプレイヤーとしての力量が如実に示されたのが、キーボード・ソロ三部作「The Three Fates」。
チャーチ・オルガンとアコースティック・ピアノを駆使し、即興的でパーカッシヴな演奏を繰り広げ、最後はバンドに雪崩れ込んで溜飲を下げる。
厳格な構成の中にも、ファンタジックともいえる陶酔の瞬間がある傑作だ。
もはや、この辺りの作品はクラシックの域に入ったのか、そちらのプレイヤーによる再現がいくつもあるようだ。
「Tank」では、バロック調とジャズ・インプロヴィゼーションを巧妙に重ねあわせるエレピのプレイから、凄まじいロールによるドラム・ソロへと突入するという破天荒な演奏まで披露する。
エンディングは、重厚かつ軽妙なムーグ・シンセサイザーのソロである。
そして、寓話的な歌詞をフォーク・タッチでまとめたアコースティック・ギター弾き語りの「Lucky Man」が、アルバムにおちつきを与えて味のある締めくくりとなっている。
もっとも、エンディングには挑戦的なムーグ・シンセサイザーのソロを放り込んで、次作へとつながる野心満々たる表情を見せているのも事実だ。
クラシック、ジャズ、ブルースからカントリーまでが奔放にまぜあわされ、美と激情の間を揺れながら、アコースティック・ピアノの音色に象徴される、モノクロで抑制されたパフォーマンスに集約されている。
ギター不在のけたたましくも重厚なサウンドは、ロックの新たな可能性を拓いたといっていい。
挑戦的にしてスタイリッシュな傑作であり、THE NICE から始まったキーボード・ロックの到達点の一つといえるだろう。
THE NICE が偶然ギタリストを失った結果生まれた、ギターレス/キーボード主体のトリオ編成という新鮮な発想が、ここで高い音楽性で実を結んだのだ。
第一作とは思えぬ完成度は、三人の音楽的バックボーンの堅固さを物語っている。
印象的なジャケットアートは当時 20 歳の美術家ニック・ダートネルの作品「Bird」。
「The Barbarian」(4:27)
「Take A Pebble」(12:32)
「Knife-Edge」(5:04)
「The Three Fates」(7:46)
「Clotho」
「Lachesis」
「Atropos」
「Tank」(6:49)
「Lucky Man」(4:36)
(ILPS 9132 / ESM CD340)

| Keith Emerson | Hammond organ, St.Marks church organ, celeste, Moog |
| Greg Lake | vocals, bass, electric & acoustic guitar |
| Carl Palmer | drums, assorted percussions |
71 年発表の第二作「Tarkus」。
卓越した運動性とエキセントリックな感性、神秘(異教)的な叙情性の合体という EL&P の特質を、早くも、完璧に体現した作品である。
タイトル組曲「Tarkus」は、不気味なエネルギーを撒き散らす変拍子のリフを導き手に、異次元の果てにあるヘヴィ・メタリックな究極の抽象世界へと誘う、巨大なる野心作。
エマーソンのハモンド・オルガンは、ハードロック・ギターのけたたましさのみを拡大したような無機的かつ攻撃的なフレーズを矢継ぎ早に繰り出し、リスナーの聴覚と感性を十字砲火のように攻めたてる。
このアグレッシヴなハモンド・オルガン、ムーグ・シンセサイザーのプレイと、レイクのメロディアスなヴォーカルが巧みに交錯して(第二章「Stones Of Years」のヴォーカルとハモンド・オルガンのインタープレイなど)、20 分あまりの大作を一気に聴かせている。
終章では、怪物を倒す敵役として、のちにレーベル名として採用する Manticore が現われる。
エマーソンのキーボードに挑発されるように、ベース、ドラムスもハイ・テンションのプレイを見せている。
「血湧き肉踊る」とは、まさにこういう曲のことをいうのでしょう。
そして、これだけエネルギッシュでありながら、どこかナンセンスで現実とは相容れない逸脱感があるところが最大の特徴である。
三人の個性によるものだと思うが、結果として、ロックというきわどい存在の危うさや書割的な薄っぺらさを象徴している作品といえるかもしれない。
組曲以外の作品も、レイクの宗教的なヴォーカルが胸を打つ「The Only Way」から重量感にあふれたピアノが強烈な「Infinite Space」、そして EL&P 流ハードロックの「A Time And A Place」など、才気の奔流の如き佳作が並ぶ。
タイトル・チューンは、東欧系国民楽派の影響色濃い圧巻のクラシカル・ヘヴィメタル・キーボード大作でありグループの代表作。
発表時点ではこんな音は誰も耳にしたことがなかったろう。
名作という位置を得た現在では想像もつかない衝撃があったと思う。
アルバムとしては、この大曲が圧倒的な存在感を示すため、後半が若干手薄に感じられてしまうところもある。
とはいえ、一気に聴かせる構成力と、ごり押しパワーに圧倒される作品であるのも間違いない。
アメリカの HR/HM 系のグループには大きな影響があったようです。
内外ジャケットを飾るきわめて漫画的でなおかつエキセントリックなキャラクターが放つオーラも凄い。
昔のチープなプラモデルのようにグロテスクにデフォルメされたこの生物は、そのまま EL&P というグループの存在感を象徴している。
(個人的に、デヴィッド・ブリンの小説に登場する E 空間はこのジャケット・アートのイメージです)
「Tarkus」(20:35)
「Eruption 」(2:43)
「Stones Of Years」(3:43)
「Iconoclast」(1:16)
「Mass」(3:09)
「Manticore」(1:49)
「Battlefield」(3:57)
「Aquatarkus」(3:54)
「Jeremy Bender」(1:46)
「Bitches Crystal」(3:55)
「The Only Way (Hymn)」(3:48)
「Infinite Space (Conclusion)」(3:18)
「A Time And A Place」(2:57)
「Are You Ready Eddy?」(2:10)
(ILPS 9155 / VICP-23103)

| Keith Emerson | keyboards |
| Greg Lake | vocals, bass, guitars |
| Carl Palmer | drums, percussions |
71 年発表の第三作「Pictures At An Exhibition」。
ムソルグスキーの怪ピアノ曲をラベルがギンギラギンのオーケストラ版へと編曲し、それをさらにギンギラギンのロックへアレンジした怪作。
元曲のエキセントリックな面を思い切り拡大し、ヘヴィで奇天烈なサウンドによるロック絵巻をつくりあげている。
桁外れのエンタテイナー、卓越したパフォーマーとしての EL&P の面目躍如たる痛快な作品だ。
「キエフの大門(The Great Gates Of Kiev)」からフィナーレへの流れは、ズービン・メータよりもこちらの方が遥かに感動的だ、という人ももはや多いはず。
一番の聴きものは、哀愁ある「古城」のテーマをシャフル・ビートとけたたましいシンセサイザーで無茶苦茶にした「The Old Castle」から「Blues Variation」への流れだろう。
ジャジーなハモンド・オルガンも冴え渡り、まさに爆発的なパワーを誇るインプロヴィゼーションである。
舞台上では下手をすればほんとうに爆発して感電死するわけだから、集中力や気合も並大抵ではないだろう。
また、「こびと(The Gnome)」や「バーバヤーガの小屋(The Hut Of Baba Yaga)」といった diminished/augumented 音を多用する作品も、ここの演奏での解釈がみごとに本質を突いていると思う。
ムソルグスキーが存命であれば、拍手喝采でテーブルを蹴飛ばしながらウォッカをラッパ呑みしたに違いない。
幾犀星隔てようとも、頭のおかしい人たち同士は強い共感で結ばれているのである。
実際ライヴでは、「プロムナード(Promenade)」とこの 2 曲、そしてフィナーレというパターンも多かったらしい。
バンドにとっても自信作だったのだろう。
そして、本作に収録されているレイクによるオリジナル名曲「賢人(The Sage)」も絶妙のアクセントとなっている。(原曲作品を聴いて「あれ、『賢人』は?」と思ったのは、わたしだけではないと思います)
アンコールはチャイコフスキーの「くるみわり人形」をロック・アレンジした B. Bumble And The Stingers の「Nutrocker」のカヴァー。
得意のホンキートンク・ピアノを駆使したノリノリのゴキゲンな演奏である。
エマーソンは演奏でのシンセサイザーのカバレージを広げ、目の覚めるような新しい音を大胆に生み出している。
グループとしての名声を獲得した上にエレクトリックなサウンドの開拓にも注力し、充実の時期だったに違いない。
原曲には当然ないレイクのヴォーカルが不思議なくらい自然に収まっているのも本作品の奇跡の一つだろう。
71 年 3 月ニューキャッスル・シティ・ホールでのライヴ録音。
音質の悪い廉価ライヴ盤にもかかわらず無茶苦茶売れたそうです。
かつて「一家に一枚」というと、本作か DEEP PURPLE の「Made In Japan」でした。
「Promenade」(1:57)
「The Gnome」(4:16)
「Promenade」(1:23)
「The Sage」(4:40)
「The Old Castle」(2:31)
「Blues Variation」(4:14)
「Promenade」(1:28)
「The Hut Of Baba Yaga」(1:12)
「The Curse Of Baba Yaga」(4:09)
「The Hut Of Baba Yaga」(1:06)
「The Great Gates Of Kiev」(6:27)
「Nutrocker」(4:33)
(ISLAND HELP 1 / ATLANTIC SD19122)
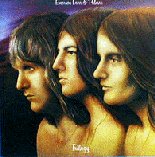
| Keith Emerson | Hammond C3, piano, Zoukra, Moog IIIC, MiniMoog Model D |
| Greg Lake | vocals, bass, electric & acoustic guitars |
| Carl Palmer | percussion |
72 年発表の第四作「Trilogy」。
ヘヴィ・ロックとヨーロピアン・クラシックに、ラグタイムやラテン、ジャズなどさまざまな音楽をミックスし、エキゾチックかつハードな世界を構築した傑作アルバム。
全作品見わたしても、本作のハモンド・オルガン、ムーグ・シンセサイザーのプレイは出色。
アクロバチックなけれん味のみが受ける EL&P において、エキセントリックな中に流れるポップの奔流が異色といえるアルバムだ。
多彩な音楽性を惜しげなく散りばめた楽曲の完成度はピカ一。
メンバーの個性が衝突しながらも、アルバムとしてまとまりを感じさせる。
個人的にはベストです。
「The Endless Enigma」は、多彩な音楽性を誇る神秘と躍動の大傑作。
エキゾチックなムードあふれるイントロから、ムーグ・シンセサイザーとピアノ、ハモンド・オルガンのプレイへと進む冒頭部は、まさに絶妙の呼吸をもつ展開というべきだろう。
荘厳なコラールを思わせるレイクのヴォーカルへハモンド・オルガンが力強く絡んでゆく。
息詰まるような、圧倒的な瞬間だ。
そして、ジャズ・ピアノからバロック・フーガへと展開する間奏曲「Fugue」(レイクのベースがポリフォニックなアンサンブルをみごとに構成する)を経て、「The Endless Enigma」が再現、激しいピアノ演奏を経て、輝かしきムーグ・シンセサイザーが降臨する。
そして、レイクのヴォーカルとともに、雄大なエンディングへと導かれてゆくのだ。
エキゾチックなメロディとクラシックのバランスという、EL&P らしいセンスが活きた壮大な組曲である。
「From The Beginning」は、レイクをフィーチュアしたラヴ・バラード。
終盤、ムーグ・シンセサイザーのメタリックな響きが、甘目のロマンティシズムに軋みを与えている。
レイクの歌ものには、ジャズ、ブルーズはもとより、カントリーやハワイアンなどさまざまな志向がうかがえて興味深い。
「The Sheriff」は、エマーソンのハモンド・オルガンとパーマーのパーカッションが冴える小噺風の作品。
西部劇仕立ての SE をユーモラスに用いており、終盤のホンキートンク・ピアノが痛快だ。
アメリカの作曲家アーロン・コープランドの作品をアレンジした「Hoedown」は、ハモンド・オルガンが小気味よく暴れ捲くるインストゥルメンタル小品。
THE NICE の「Rondo」同様、奔放な抑揚とスピード感に思わず体がゆれてしまうライヴの定番である。
そして、ロマンチックな中にもどこかミステリアスなものを感じさせるテーマから始まる「Trilogy」。
ヴォーカルが美しいメロディを静かに歌い上げ、ピアノのテーマ展開から一気にハードなアンサンブルへとなだれ込む。
この一気呵成の展開は EL&P ならではだ。
ムーグ・シンセサイザーのカデンツァは、リズムの変化とともに、ラテン風のエキゾチックな演奏へとスピーディに移ってゆく。
ムーグ・シンセサイザーのパーカッシヴな演奏を経て、エンディングは意外やブルース調。
多彩な音楽性を見せる変幻自在のアンサンブルがみごとだ。
「Living Sin」は、珍しくシアトリカルなレイクのヴォーカルと偏執的ともいうべきキーボード、ドラムスのデュオが、微妙な距離感を保って突き進む怪作。
第一作の「Tank」を思わせる音の密度の高い演奏だ。
ドラムスが珍しくロールのオカズではなくジャスト・ビートにこだわったようなハイハット、スネア打撃を見せる。
そしてアルバムの最後を締めるのは、ラベルもびっくりの本格的なボレロ「Abaddon's Bolero」。
作曲、アレンジ、録音手法、すべてにおいてエマーソンの豊かな才能を如実に語る作品であり、サウンド・メイキングは後年のポリフォニック・シンセサイザー導入を予期させる。
つまり「Fanfare For The Common Man」の前哨という位置づけかもしれない。
(ILPS 9186 / 20P2-2050)

| Keith Emerson | organs, piano, harpsichord, accordion, Moog, Moog polyphonic ensemble, computer voice |
| Greg Lake | vocals, bass, Zemaits electric & 12-string guitars |
| Carl Palmer | percussion, percussion synthesizers |
マンティコア・レーベルから満を持して発表された 73 年発表の第五作 「Brain Salad Surgery(恐怖の頭脳改革)」。
さまざまな作風の楽曲を盛り込むアルバム構成のスタイルは前作の踏襲ながら、すべての楽曲がパワー・アップし、前衛ロックとしての強烈なデフォルメが効いた超力作となる。
エマーソンのアグレッシヴな技巧とパーマーの隙間を埋め尽くすようにビジーなドラミングによる性急でメタリックなサウンドの嵐を貫いて、レイクの力強くもノーブルなヴォーカルが響きわたる。
この演奏力を生かすための素材の吟味や作曲、アレンジも充実している。
本アルバムに満ちる痛快さと絶頂感は、すべてのロック・ファンが体験すべきだろう。
特に大作「Karn Evil #9」は超絶的技巧と天性の野性味を備えたキーボード・オーケストレーションを中心にしたエンタテインメント性抜群のヘヴィ・ロック作品だ。
本アルバムは、キーボード・ロックの頂点の一つであり、緻密な技巧、高度な音楽性、奔放な娯楽性、そして巧まざるコミカルさにおいて、HM の元祖のような位置にある作品といえる。
華やかにしてスリリングなチャーチ・オルガンの響きから始まる 1 曲目は、英国では人口に膾炙した賛美歌をアレンジした「Jerusalem(聖地エルサレム)」。(ちなみに詞はプログレの父の一人、ウィリアム「怪獣大好き」ブレイク)
グレッグ・レイクの正統的な歌唱を活かしきった厳かで溌剌たる快アレンジであり、ポリフォニック・シンセサイザーのプロトタイプを導入した作品でもある。
レイクの気高き美声に酔いしれた直後には、アルゼンチンの現代音楽家ヒナステラのピアノ・コンチェルトから着想された、電気の暴力といわんばかりのヘヴィ・インストゥルメンタル「Toccata(トッカータ)」が待ち構えている。
前曲との落差のすさまじさ。
荒れ狂うシンセサイザー、パーカッシヴなオルガンとともにベース、エレクトリック・パーカッションもそれぞれフィーチュアし、三人の一体感あふれる演奏で迫る傑作である。
原作者のヒナステラが「楽曲の本質をつかんでいる」と絶賛したというから、エマーソンの解釈力が並大抵ではないことが分かる。
「Tarkus」がぶちまけた重油のように真っ暗な邪悪さがここで甦っている。
チェンバー・ロックの始祖的な位置にある作品という見方も可能だろう。
シンセサイザーはもとよりオルガンまでもパーカッション的なノイズ発生器として使うセンスがすごい。
アコースティック・ギター弾き語りにムーグがアクセントする「Lucky Man」以来の名バラード「Still...You turn me on」で、再びリリカルな世界に誘われた後は、前作の「Sheriff」を思わせるウエスタン・ソング「Benny The Bouncer」のホンキートンク・ピアノに酩酊。レイクの絶叫 St.Peter's gate ! は聖者ペテロが鍵を守る煉獄の門であり英語の「鬼籍に入る」の意。
このエンタテインメントとしての振れ幅に音楽的な余裕と鋭いバランス感覚を見る。
そして、遂に迎えるは、エマーソンのキーボード・プレイと EL&P としての音楽的エッセンスがすべて注ぎ込まれた超大作「Karn Evil #9(悪の教典)」。
三部から成る本作は、コンピュータに立ち向かう人間というチープなディストピア SF 風の主題をもつようだ。
演奏は、大見得を切るようなけれん味と暴力的なパフォーマンスに満ちあふれ、コミック・ブック的な痛快さでは他の追従を許さない。
「第一印象」では、邪悪なテーマを繰り出すハモンド・オルガンと十字砲火のように過激なフレーズを浴びせつつ暴走するシンセサイザーによって、メタリックでノイズに満ちた未来社会を描かれる。
旧 B 面へのブリッジにおいては、シーケンスのスポットを浴びたレイクによる自らパフォーマンスの進行役を買って出るコミカルな演出があまりに泥臭いが、そんな思いにとらわれる暇もなく、再び過激かつハイ・テンションの演奏に打ちのめされる。
手垢がついているはずのモダン・ジャズにクラシックをぶち込むアレンジが異常な高揚感のために新鮮に感じられるというアンサンブルのマジック。
Part.2 でも Part.1 の変奏を交えつつショーマンシップあふれる演奏が繰り広げられる。
「第二印象」では、ラテン風のエキゾチズムを演出する自由闊達なソロ・ピアノによるモダン・ジャズ変奏曲を皮切りに、スチール・ドラム風のパーカッション・シンセサイザーを導入したアフロ・テイストあふれるアンサンブルへと発展し、ミニマリズムの果てに「St. Thomas」が飛び出すような奔放なアイデアを交えて、アコースティック・メインのサウンドながらも、はち切れそうな勢いをキープしたまま突き進んでゆく。
ミステリアスにしてクラシカルな緩徐楽章を経て、再び「ジャズ + モダン・クラシック」なソロ・ピアノがリードする演奏(ドラムフィルを聞いているとほぼ即興のような気がする)が甦り、邪悪で屈折した高揚感を増大させながらメイン・テーマを再現してゆく。
このパートは、アコースティックなプログレの代表曲という見方も可能だろう。
「第三印象」は、いよいよコンピュータとの対決が待つクライマックス。
"展覧会" の「キエフの大門」に通じる堂々たる大団円である。
陳腐ともいえる設定に強引に説得力をもたせるのは、ファンファーレの如く響き渡るムーグ・シンセサイザーと厳かなオルガン、レイクの端正な美声ヴォーカル、そして止むことなくひたすらに音を生み出し続けるハイ・テンションのアンサンブル。
一歩間違えれば野暮ったくなってしまうところを不思議な魅力を放つ音楽へと仕立て上げた、いわば EL&P の電気魔術の産物だ。
ムーグ・シンセサイザーを縦横無尽に駆使した超大作である。
タイトルには意味がないそうだが、Carnival のアナグラムとするならば、本作の祝祭性、非日常性、狂気じみた開放性をみごとに象徴しているし、 また、「カーニバル文学」ならぬ "カーニバル音楽" として EL&P の音楽の特性を的確にいいあらわしていると思う。
過剰なものへの憧れを抱く若者にとってはドストエフスキー並に刺激的なのだ。
「Trilogy」で固まった音楽的結束を、さらにパワー・アップした一世一代の名盤。
「Karn Evil #9」に象徴されるように全編に力と緊張がみなぎり、破裂寸前のアンサンブルがリスナーをガッチリとらえて放さない。
これだけパワーを注いでしまうと、この作品を頂点に下降線をたどったのも仕方がないのかもしれない。
ともあれ、未聴の方へのメッセージ、「これを聴かずして何を聴く」。
(K 53501 / R2 72459)

| Keith Emerson | piano, keyboards, synthesizer | ||
| Greg Lake | vocals, bass, guitars | ||
| Carl Palmer | drums, xylophone, timpani, vibraphone | ||
| guest: | |||
|---|---|---|---|
| London Philharmonic Orchestra | |||
| Joe Walsh | guitars, voices | James Blades | marimba |
| Andy Hendriksen | tuned percussion | John Timperley | tuned percussion |
77 年発表の第七作 「Works(四部作)」。
名ライヴ盤「Ladies & Gentlemen」に続くオリジナル・アルバム、LP 二枚組。
元々三人のソロ・アルバムに用意された楽曲を持ち寄り、最終面にのみトリオでの演奏を盛り込んだ構成となっている。
ヴォリューム感はかなりのものだが、ソロ用の作品を集めただけあって当然ながら方向が散らばっており、全体通すと、最終面のみごとな充実感を合わせても、プラスマイナスややプラスくらいの印象になる。
LP 一枚目 A 面は、キース・エマーソンのオリジナル、ピアノ・コンチェルト。完全なクラシックです。
B 面は、グレグ・レイク。管絃も交えた歌もの。なんというか、声のタイプとして、いわゆるロックが似合わないことを再確認。
LP 二枚目 A 面は、カール・パーマー。打楽器をフィーチュアしたクラシカルな作品(「The Enemy God Dances With The Black Spirits」(プロコフィエフのスキタイ組曲「アラとロリー」 第二曲「邪神チュジボーグと魔界の悪鬼の踊り」より)、ファンク、ヘヴィ・ブラス・ロック、ジャズロックなど多彩な内容。
第一作の「Tank」の再演あり。予想外に面白い内容である。やたら喧しいのはこの人の持ち味と思うべき。
そして、最終面には 二曲の名大作が収められている。
「Fanfare For The Common Man(庶民のファンファーレ)」は、YAMAHA のスーパーエレクトーン(ポリシンセサイザーというべきか)GX-1 によるサウンド・メイキングが奏効した名品(イギリスではシングルチャートを上ったらしい、雪のスタジアムで演奏する雄姿はヤングミュージックショーでも放送した)。
原曲に忠実な、勇ましくも端整なテーマが快調なロック・ビートとシンクロしてゆく、EL&P の代表曲の一つである。
アメリカの作曲家アーロン・コープランドの作品をキース・エマーソンがアレンジ。(ちなみに、これより数年前に STYX も地味なファースト・アルバムで本作をサイケ・オルガン・アレンジで取り上げている)
「The Pirates(海賊)」は、管弦楽を巻き込んだ重厚なロック・シンフォニー。
勇壮なイメージを描きながらも、メロディアスで親しみやすいフレーズが幾重にも織り込まれ、非常に多面的な魅力を放っている。
エマーソンのシンセサイザー・プレイは、計算され尽くされた上に即興のきらめきが惜しみなく注ぎ込まれるという、ミュージシャンシップの究極にあり、レイクのパフォーマンスでは、オペラティックにしてロック、高潔にして野性味あふれるという卓越した表現を堪能できる。
米国のクラシック作曲家風のテイストによるオーケストレーションと、「Karn Evil」を開放的にしたような緻密なロック・インストゥルメンタルが手を結んだ稀代の名演である。
エマーソン作曲。
なお、オフィシャル・ブートレグ集で、管弦楽を使わずシンセサイザーを駆使した三人のみによる本曲の演奏を聴くことができる。
これは一聴の価値あり。
(ATLANTIC K/K4 80009 / VICP-84229-30)

| Keith Emerson | keyboards |
| Greg Lake | vocals, bass, guitars |
| Carl Palmer | drums, percussion |
92 年発表の作品 「Live At The Royal Albert Hall」。
92 年新作「Black Moon」ツアー(20 年ぶりに来日した)で収録されたライヴ・アルバム。
ベスト・アルバム的な内容であり、ブランクはさほど感じさせないパフォーマンスといえる。
カール・パーマーのドラムスのプレイが現代ロック風であること、エマーソンのキーボード・サウンドの一部がコンテンポラリーな機材らしいものになっていることなど興味深い点もある。収録時間が 70 分くらいなのでアンコールが割愛されているのかもしれない。
エマーソンのプレイにはいわゆるブルース・ロック色が希薄で、ラグタイム、ホンキートンク、ブルーグラス、ジャズ経由のブルーズ・フィーリング、ソウル、ラテンやカントリーなどがごちゃ混ぜになっていると改めて思った。ロックに出会う前に音楽個性が確立していたのでしょう。
「Karn Evil 9(1st Impression Part. 2)」(1:45)
「Tarkus(Medley)」(9:33)中間部のシンセサイザーが新鮮。
「Eruption」
「Stones Of Years」
「Iconoclast」
「Knife Edge」(5:27)エレクトリック・ピアノが使われる。
「Paper Blood」(4:10)
「Romeo & Juliet」(3:41)
「Creole Dance」(3:17)ラテンなオスカー・ピーターソンというべき圧巻のピアノ・ソロ。前曲から二曲続けてエマーソン・パート。
「Still... You Turn Me On」(3:18)ここからレイク・パート。エレアコ。中華風の和音のアルペジオが面白い。変わらぬギター名手ぶり。
「Lucky Man」(4:38)寓話調と声色のみごとな調和。ロック界のトルバドールでした。
「Black Moon」(6:33)アメリカの HM バンドの作品のよう。そう思って聴けばさほど悪くない。
「Pirates」(13:23)これが一番の聴きもの。男の子の抱く永遠の夢の一つである「海賊」を劇的に描く。多彩なシンセサイザーもみごとだが、やはりハモンド・オルガンのプレイに強烈な説得力がある。レイクの歌唱もすばらしい。
「Finale(Medley)」(14:41)
「Fanfare For The Common Man」エマーソンが楽しそうなパフォーマンス。ポリシンセ無双。
「America」THE NICE 以来の持ち歌。
「Rondo」同上。ここは映像を見ないと。
(VICP-5222)
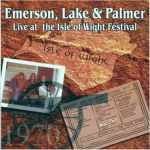
| Keith Emerson | keyboards |
| Greg Lake | vocals, bass, guitars |
| Carl Palmer | drums, percussion |
98 年発表の作品 「Live At The Isle Of Wight Festival」。
70 年、ジミ・ヘンドリクスのプレイなどで有名なワイト島ロックフェスティバルでの録音。(最後にボーナス・トラックとしてメンバーによるコメントも収録)
ファースト・アルバム発表前、実質二度目のライヴ・パフォーマンスであり、スーパーグループの離陸の瞬間である。
録音はよくないしミスタッチもあるが、荒削りの魅力とパワフルなパフォーマンスからの迫力は十分。
新グループとして少しでも目立とうと思ったか、大砲までぶっ放す。
聴きものは、ほぼ完成品の「未開人」、「展覧会の絵」。
辛口の英国音楽評論家に「電気と才能のムダヅカイ」と酷評されたのもここらから。
たしかにむやみにやかましい。
2012 年現在、別ジャケット版もある模様。
「The Barbarian」(5:09)ファズ・ベースの轟音でぶっ飛ばされる。
中間部に入ると改めて思うが、エマーソンのピアノの技量はたいへんなものだ。
それに追随してスリリングなアンサンブルを構成するレイク、パーマーもすごい。
「Take A Pebble」(11:51)一転して卓越した叙情性とドラマ構成力をアピールする名演。音楽的には後の「Trilogy」につながってゆく名曲です。中間部、終盤のピアノ・アレンジが新鮮。unfold into me やら worn-out overcoat なんて詩的な表現はこの曲の歌詞で憶えました。
「Pictures At An Exhibision」(35:47)「賢人」、「古城」も含む完全版。ムーグ・シンセサイザーをお披露目。
「Rondo」(3:59)序盤で倍速「イタリア協奏曲」。
「Nutrocker」(5:22)
(VICP 60443)

| Keith Emerson | keyboards |
| Greg Lake | vocals, bass, guitars |
| Carl Palmer | drums, percussion |
2004 年発表の作品 「Best Of The Bootlegs」。
内容は、オフィシャルブート・ボックスからのセレクションのようだ。
当然ながら音質は全体的にかなり厳しく、曲ごとの差異も大きい。
とはいえ、ファンにはいろいろと聴きどころはある。
「The Barbarian」は悪音質を逆手に取ったかと思わせるほどの迫力。
錆びたネジを耳に捻じ込まれるような気持ち悪快感です。
「Pirates」は加工前のライン録音のように奥行きのない音(若干拍手も聞こえるので確かにライヴなのでしょう)だが、バンドのみによる演奏アレンジが興味深い。
「Fanfare For The Common Man」では、「Rondo」やバッハのトッカータからの引用が入る。
などなど、EL&P のライヴは必ず「付加価値」がある。
切り売りという揶揄もあるようですが、ボックスが一気に買えない身にはたいへんありがたいです。(ただし、ボックスにはもう少し録音のいい 73 年のライヴが入っているようで... )
CD 二枚組。
(SMDDD087)

| Keith Emerson | keyboards |
| Greg Lake | vocals, bass, guitars |
| Carl Palmer | drums, percussion |
2011 年発表の作品 「Live At The Mar Y Sol Festival」。
72 年 4 月 2 日、プエルト・リコのフェスティバルでのライヴ録音。
夜にヘリコプターで到着し、そのまま演奏に突入したので何が何やら分からなかったというメンバーのコメントが、いかにも豪勢なスーパーグループらしい。
「Trilogy」の作品が入っていないが、フル・コンサートのボリュームでもないので、まだテープに残っている可能性もある。
迫力あふれる小気味のいい演奏を収録した、70 年代に発表された公式ライヴ盤に勝るとも劣らぬ好盤である。
異形の妖しさと乱調美で迫る「Tarkus」はアヴァンギャルド・ロックの金字塔。
底知れぬ凄みを感じます。
「Hoedown」(4:22)
「Tarkus」(22:56)グリーグの「山の魔王の宮殿」からの引用が入る。
「Take A Pebble」(4:45)初期 KING CRIMSON の叙情性はこの人のおかげ、と納得できるオーセンティックな歌唱とジャジーなピアノ・バッキングの配置の妙、そしてミステリアスなピアノ・インプロヴィゼーションヘ。
「Lucky Man」(3:00)冒頭は「石をとれ」のカントリー・ギター、一転して雅なストロークから本曲へ。
「Piano Improvisation」(9:56)変拍子オスティナート、ラグタイム、手癖も全開のロックなオスカー・ピーターソン。「石をとれ」へと回帰する。
「Pictures At An Exhibition」(15:27)「プロムナード」、「バーバヤーガの小屋」、「キエフの大門」から構成される。
怪力神の如く、ひたすらに荒ぶる。
「Rondo」(18:29)アンコールは THE NICE の定番曲。やりたい放題。長大なるドラムス・ソロ。
(826663-12894)

| Keith Emerson | keyboards |
| Greg Lake | vocals, bass, guitars |
| Carl Palmer | drums, percussion |
2011 年発表の作品 「Live At Nassau Coliseum '78」。
78 年 2 月 9 日、ニューヨークでのライヴ録音。
「Tarkus」では、「未知との遭遇」の交信電子音も。
ムーグよりも細い感じの音色はポリ・シンセサイザーだろうか。
ハモンド・オルガンの暴力的な存在感と比べると、対比以上にややひ弱なイメージが先立つ。
「Hoedown」をのぞくと、「Trilogy」と「Brain Salad Surgery」の作品は収録されておらず、「Works」、「Works Vol 2」の作品が入っている。
全体に録音は悪くない。ややツアーにくたびれ、ソロ色を強めた時期であることを思いながら聴くのもおもしろいと思う。
CD 二枚組。
「Hoedown」鉄板のオープニング 2 曲。
「Tarkus」
「Take A Pebble」中間部のピアノ独奏がそのまま次曲に発展する。
「Piano Concerto #1, 1st Movement 」ここの終わりで「Take A Pebble」に復帰する感じになるが、歓声が入り演奏を止めてしまう。
「Maple Leaf Rag」この曲も本来はノンストップで入って「Take A Pebble」の中間部を構成したはず。
「Take A Pebble (Reprise)」ようやく元の曲に戻ってくるが、ややとってつけた感あり。
「C'est La Vie」前曲でエマーソンがやりたい放題したので、次はレイクの番。
「Lucky Man」
「Pictures At An Exhibition」シンセサイザー多用。
「Tiger In A Spotlight」ロカビリーといえばいいのか。77 年当時もかなり微妙でした。アメリカ人には受ける模様。
「Watching Over You」そして再びアメリカンなカントリー弾き語り。しかしシャンソンよりはいいような気がする。
「Tank」ここからパーマーの番。
「Drums Solo」
「The Enemy God Dances With The Black Spirits」「邪神の舞」にしては明るく軽快。
「Nutrocker」唐突。
「Pirates」これは名演。
「Fanfare For The Common Man」
(826663-12398)
40 年前は踊りながら聴いていたほど、自分の感性とシンクロしたグループでありました。
かなり「いき過ぎ」で拍数に収まらないフレーズを弾き飛ばすキース・エマーソン、手数足数は多いものの正直リズムは危ないカール・パーマー、一人吟遊詩人のグレグ・レイク、こんなムチャクチャなトリオが生み出す音楽は、そのムチャクチャさを活かしきったユニークなものであった。
突き刺すような攻撃型ハードロックから悠然たるシンフォニー、リリカルなバラードと楽曲は多彩。
エマーソンは、THE NICE 時代に試みたクラシック、ジャズとロックの融合というテーマを追求するためにレイク、パーマーという仲間を選び、音楽のさらなる発展から完成への道のりを目指していたようだ。
同時に、卓越したヴォーカリストであるレイクは、ヘヴィな器楽と自分の歌の対比から、新たな音楽を生みだそうと考えていたようだ。
EL&P のユニークな音楽性を、このエマーソンの音楽性とレイクのセンスの化学反応に帰することも確かに可能だろう。
しかしながら、演奏面では、やはりエマーソンのキーボード・ワークにすべてにがかかっていたのである。
それを的確にプロデュースしたのがレイクであったにせよ、パフォーマンス自体はエマーソンの存在がすべてといってもいいだろう。
したがって、必然的に、エマーソンのアイデア、やる気とレイクのアレンジメントのセンスがクライマックスに達したときにこそ傑作が生まれることになるが、クラシックとロックの融合という娯楽性と芸術性のバランスの微妙なところで作品化せねばならないという状況も同時にあり、この二つの前提条件がピタッとはまった瞬間がそう簡単には出現しなかったせいか、グループとしての絶頂期は短かった。
一つ不思議なのは、これだけ大胆な音楽を生んだテクニシャンであるにもかかわらず、キース・エマーソンが 74 年以降アメリカを中心に隆盛したクロスオーヴァー/フュージョン的なアプローチを全く見せないことである。
R&B、ラテン、ジャズ、クラシック、現代音楽までもを呑み込んだ巨魁でありながら、なぜなのだろう。
こんなことは考えられないだろうか。
デイヴ・オリストが THE NICE を脱退するという事態をキーボード・トリオというアクロバティックな発想の転換で乗り切ったエマーソンという人は、どちらかというと早熟型の天才であり、技巧も音楽性も極端ないい方をすると 60 年代ですでに完成され、頂点にあった、そして 70 年代はその成果を披露するのに忙しく、同時代の新しい音楽をインプットすることにはさほど興味を示さなかったのだ、と。
70 年代中盤以降 EL&P が作品を発表しなかった原因の一つとして、意外にも偉大なるエマーソンがすでに新たな発想を生み出しえなかったということがあるのかもしれない。
さらに考えを進めると、90 年代の復活作においても、レイクのポップ・ミュージックに対するインテンションが、たとえやや時代遅れとはいえ、見えてくるのに対して、エマーソンの方はあまり明確には意志が伝わってこないことに気づく。
クラシックのロック・アレンジの腕は決して衰えていないが、その腕前は 70 年代においてすでに十分見せていた。
また、他のキーボーディストのように 70 年代中盤からフュージョンやニューエイジに流れたわけでもない。
マイルスのビッチェズ・ブリューの音楽観に否定的であったという逸話もあるが、彼自身は一体何を目指していたのだろうか。
唯一見せていた管弦楽との共演へのこだわりから考えて、常に革新を求めるクリエイターというよりは、抜群の解釈力/演奏力をもつ「プレイヤー」としての姿が、彼にとっての自然体なのかもしれない。
音楽的に果敢な姿勢を見せるよりも、エンタテインメントとして果敢なプレイを繰り広げる方が、好きだったのかもしれない。
個人的には、アヴァンギャルド・ミュージックやフリー・ジャズへ挑戦するエマーソンをぜひ見てみたいのだが。
92 年には正式に再結成するが、その前、86 年と 87 年にそれぞれ Emerson Lake & Powell、THREE としてアルバムを発表している。
