
| Eduardo A.Niebla | guitar |
| Paco Ortega | organ |
| Juan Punet | drums |
スペインのプログレッシヴ・ロック・グループ「ATILA」。 73 年結成、78 年解散。作品は三枚。 カタロニアのグループらしい。 ギタリストは、セッション・ミュージシャンとして MOTHER GONG のアルバムにも参加。

| Eduardo A.Niebla | guitar |
| Paco Ortega | organ |
| Juan Punet | drums |
75 年発表の第一作「The Beginning of the end(El Principio del fin)」。
タイトル曲一曲のみを収録したライヴ盤である。
バッハの「トッカータとフーガ」をモチーフにした、サイケでエネルギッシュなインプロヴィゼーションが繰り広げられる。
収録時間が 29 分と LP にしては短い。
元々ライヴの観客向けのプロモーション・コピーとして配られたアルバムらしい。
意図的なのかどうか分からないがスペイン色は出していない。これは後の他のグループと比べると大きな違いである。
チャーチ・オルガンによる壮麗なバッハ演奏で幕を開ける。
重厚にして典雅。
悠然たるリタルダンド、そして激しい問いかけのリフレインは憂鬱に沈み込み、次第に加速する。
豊かに響く和音とざわめくシンバル。
華麗なカデンツァは、バスドラのキックとヘヴィなギター・リフを呼び覚ます。
DEEP PURPLE を思わせる展開だ。
オルガンとベースによる挑発的なビートとけたたましいギター。
そのまま、ギターとオルガンのリフでリードする、ブルージーなジャムへと突き進む。
軽快なリズムによる 12 小節進行だ。
シングル・ノートを打つベース、オルガンの伴奏で、ギターのフリーなアドリヴ大会が始まる。
ATOMIC ROOSTER にも似る。
いったん 3 連のトゥッティでアクセントを決め、再びギターのアドリヴへ。
これはエンドレスになりがちな展開だ。
オルガン、ギター、ベースが一つにまとまると、オルガンがしなやかな経過句風のテーマを奏でる。
リズムが消え、トーン・ジェネレータによるノイジーなメロディが流れる。
追いかけるオルガン、そしてシンバルのざわめき。
ノイズは吹きすさぶ風の音へと変わり、ドラムスとともに不安な空気をつくりだす。
やがてタイトなリズムが復活、ノイズはそのままにギター・リフがきっちりとした演奏をリードする。
再びややブルージーな演奏へと落ちつく。
沸き立つように激しいドラミング。
ノイズはヴォリュームを上げて吹き荒れる。
ざわめくシンバル。
再び、バスドラのキックからギター・リフが復活、寒風のようなノイズが吹き荒れるままブルーズ・ジャムへと戻ってゆく。
混沌を貫いて一本筋が通った感じだ。
ノイズが高まるとともに、抗うようにドラムスは激しく暴れだし、そのままドラム・ソロへと突入する。
強引な展開だ。
ソロはとにかく手数勝負のパワフルなもの。
モダン・ジャズのドラムスのようなソロであり、カール・パーマーがうまくなったような感じだ。
スネアをマーチ風にロールし、フロア・タムを連打する。
やがて、ソロはスネアのロールへとまとまり、再びノイズが飛来する。
オルガンが湧き上がり、不気味な音を響かせる。
タム回しからギター・リフ、そしてオルガンによる「トッカータとフーガ」が復活する。
今度はドラム入りの演奏だ。
8 ビートによるバッハはやや安っぽいが、音の悪さが奇妙な説得力を生む。
激しいタム回しからギターも飛び込み、オルガンは一気にジャズへと変貌。
ギター・リフが推進力を生み、オルガンが演奏をひっぱる。
オルガンとギターによるコール・レスポンスへとまとまってゆく。
そしてリズムがまたも消えてゆく。
オルガンは静かにメロディを響かせ、ベースがオブリガートする。
そして悩ましげなギター・ソロがスタート。
ブルージーな「泣き」のギターである。
律儀な 8 ビートとベース・ランニング。
ギターは、ひたすらブルーに歌を吐き出し続ける。
リズムが復活、アップテンポでギターのソロは続き、ベース、オルガンがバックアップする。
ロールから決め。
チャーチ・オルガンの荘厳な和音。
そしてパワフルなドラムスが応える。
オルガンのテーマはややエキゾチックに表情を変化させる。
激しいドラムス、ベースの連打から一気にヘヴィな演奏が高まる。
スタッカートの応酬のようなテーマ。
打ち鳴らされるドラムス。
ようやくオープニングのギター/オルガン・リフが復活。
ブルージーなジャムへと戻る。
たたみかけるような演奏。
いったん静かになって、再びベース・リフのリードで動き出すアンサンブル。
ヘヴィなオルガンのコードが轟くと、ギターも粘りつくようなプレイで、ノイジーに迫ってくる。
さすがに疲れてきました。
フリー・フォームのギター・ソロが続き、オルガンはエコーを効かせてバッキング。
最後はトーン・ジェネレータのノイズが満ち、爆音のようなギターが炸裂してフィナーレ。
大喝采。
CREAM の「Wheel Of Fire」というアルバムのライヴ面に、延々続くブルースのインプロヴィゼーションがあったが、ここでは 10 年遅れで同じことをやっている。
オルガンとギターの絡みはなかなかスリリングだが、それでもちょっと我慢が必要である。
正直辛いところもある。
ノイジーな展開の果てにバッハへ回帰するまではともかく、その後のインプロヴィゼーションがちょっと長過ぎる。
メリハリもない。
せめてテーマに戻ってほしかったが、それもないとなると単なる開放端のアドリヴ大会である。
このライヴ感を味わえ!というメッセージなのだろう。
29 分の大熱演。
ところで後半現れるベースはどなた?
( )

| Eduardo A.Niebla | guitar | Miguel A.Blasco | bass |
| Juan Punet | drums | Benet Nogue | organ, mellotron, piano, moog, voice |
| Juan Vidal | sound effect | Carmen Ros | chorus |
| Montserrat Ros | chorus | Nieves Del Miguel | chorus |
| Gloria Del Miguel | chorus |
76 年の第二作「Intencion」。
キーボーディストは新メンバーに交代、ベーシストと音響担当も加入して、五人編成となる。
内容は、ヘヴィ・ディストーション・ギターとオルガン、シンセサイザーを主とするキーボードが引っ張る 70 年代初期型ハードロックである。
クラシカルな味わいはキーボードが一手に引き受け、ギターとリズム・セクションはとにかく走り回る、もしくはむせび泣く。
荒々しくもひたすらにセンチメンタルな表現である。
休みなくハイ・テンションのプレイで進行をリードするドラムス、高音を多用して目立ちたがるベース、大泣きのギター、挑戦的なハモンド・オルガンなど役者の揃ったコテコテのプレイのなかで、さらにびっくりさせられるのが、特撮映画のレーザー・ビームのようなムーグ・シンセサイザーの電子音である。
おそらく音響担当者によるものだろう。
70 年代終盤に盛り上がるスペイン・プログレの礎となったプレ・プログレ・サイケデリック・ロックの佳作といえる。
B 面は第一作のスタジオ再録版。
また、上掲のジャケットの CD は盤起こし。
2003 年現在、第三作の再録を含んだリマスター CD もあり。
1 曲目「Intencion」(8:44)
ノイジーにしてクラシカルなハード・シンフォニック・ロック。
ブルージーなファズ・ギターとバロック調かつジャジーなハモンド・オルガンがぶつありあう、70 年代初期らしいニューロック・サウンドである。
例えるならば、FOCUS、初期 CAMEL 路線で、かなり DEEP PURPLE 寄りといった感じだろうか。
シンフォニックなメロトロン、ムーグの電子音、ギターとキーボードによるたたみかけるような攻撃性など、典型的な要素を取り揃え、破天荒な音にもかかわらず、場面展開は徹底して泥臭い。
そして、歌メロはどうしようもない「泣きメロ」。
ジャジーなオルガンに導かれてけだるいヴォーカルが始まり、悩ましげなギター・アドリヴへと進む。
この進行、すでに立派な様式美の世界である。
もっとも、コテコテな分だけ、演奏そのものには安定感がある。
キーボードはもとより、ギターのプレイや音数任せのドラムスも、かなりの使い手ではないだろうか。
ただし、後半現れるエレクトリックな効果音だけは、さすがに時の流れを感じさせるのだが。
2 曲目「Cucutila」(4:43)
クラシカルで愛らしい作品。
リムスキー・コルサコフ、もしくはムソルグスキー辺りのせわしない調子と、テレマンかヘンデル(FOCUS なら「Sylvia」ですな)のようなメロディアスな調子を組み合わせている。
演奏は、ユーモラスで表情豊かなキーボードがフィーチュアされている。
ドラムスも効果音的なプレイをしている。
スケールの大きなオープニングからリズミカルに進み、「呼び出しジングル」のテーマ(マイルスの「If I Were A Bell」か?)を得てからは、キュートな演奏が続く。
後半のポップなスキャットもいい感じだ。
テーマは可愛いが、演奏そのものはなかなかタイトだ。
インストゥルメンタル。
3 曲目「Dia Perfecto」(6:30)
クラシカルなムーグ・シンセサイザー、オルガンをフィーチュアした、EL&P の「Toccata」風のエネルギッシュなインストゥルメンタル・チューン。
クラシカルな勇ましさと叙情性とともに、ロックらしい不良っぽさ、いい加減さがしっかり出ている。
この爪の垢を、最近の生真面目一本槍なクラシカル・ロック・バンドに煎じて飲ませたい。
クラシカルなフレーズとせわしないビートを強引に結びつけ、当然だろといわんばかりにファズ・ギターが轟き、気がつけば神々しいスキャットがわななく。
「落差」を隔てた運動性こそがキーである。
乱暴なのだが痛快であり、果てしなくエモーショナル。
4 曲目「El Principio Del Fin」(終末の原理?)(15:51)
オープニングとエンディングのテーマとしてバッハの「トッカータとフーガ」を使った 15 分あまりのインストゥルメンタル大作。
おそらく前作の再編曲版だろう。
他の曲と同じく、基本はキーボードを前面に出すも、本作ではギターもかなり活躍する。
そして曲調は、かなりなハードロック寄りから、ジャズ風のアドリヴまで多彩。
アドリヴの応酬でありながら曲全体にドラマがあるのは、リズムレスのスペイシーなパートと、パワフルなドラミングによる強烈なアクセントをもつパートをバランスよく配分し、効果的に対比させているからだろう。
サウンド的にも、ファズ・ギターの荒々しくザラついた音色とハモンド、ムーグのなめらかな音色がみごとなコントラストを成す。
ギターは、音色こそ古めかしいが、フレージングは非常にナチュラルであり、しなやかさのある演奏である。
中盤のドラム・ソロもリズムに切れがあるため、楽しめる。
かなりジャズっぽいソロだ。
ラフさはあるが、最後までひっぱってくれる娯楽作。
時代劇や西部劇、戦争映画(怪獣映画?)と同じようなニュアンスである。
DEEP PURLE がややプログレ寄りになったような作品。
精緻さや構成美といったプログレッシヴ・ロックの要素とは無縁であり、どこまでも荒っぽい。
しかしなぜか憎めない。
この時代にようやく実験段階から定型へと落ちつき始めたキーボード・ロックであるが、当時はこのくらいの出来でも十分通用したようだ。
キース・エマーソンと比べてしまうと一歩も二歩も落ちるが、エネルギッシュなプレイやコテコテとはいえクラシックの換骨奪胎など、チャレンジャー精神は旺盛である。
本作はオルガン、ムーグを使ったハードロックと思うべきだろう。
理屈よりもカタルシスなのだ。
注目すべきはドラムスとギター。
この作品に重みを与えているのは、ひとえにこのアグレッシヴなドラムスだろう。
ギターも、音こそ古臭いがフレージングはみごと。
ハードにしてしなやかなプレイは、音色さえよければ今でも十分通用するだろう。
とはいえ 76 年にしては音が古臭いのは、イギリスから音が届くのに 3、4 年かかるということなのだろう。
(EMI 10C 054-021 462)

| Eduardo A.Niebla | guitar |
| Jean P.Gomez | bass |
| Juan Punet | drums |
| Benet Nogur | keyboards |
77 年の第三作「Reviure(Revivir)」。
内容は、ブルージーなギターとオルガン、シンセサイザーを駆使した技巧的かつスペイシーなシンフォニック・ロック。
キーボードはオルガンと比べて圧倒的にシンセサイザーを多用するようになり、このシンセサイザーによるサイケデリック、コズミック調が特徴である。
ギタリストは、わりと古典的なブルーズ・ロック、ハードロック的なプレイが多いが、ジャジーな演奏にも十分対応はできるようだ。
そして、ドラムスは、相変わらずの手数によるロック・ドラムスの名手。
サイケデリックな酩酊状態を生み出し、それと同時に演奏を引き締めてもいる。
ブルージーなギターとメカニカルなシンセサイザーと手数の多いリズム・セクションといった特徴から、RETURN TO FOREVER や MAHAVISHNU ORCHESTRA 影響下の SBB、FERMATA といったユーロ・ジャズロック系グループと音楽性が共通性する。
原初的なロック・スピリットを持ったままテクニックを磨いていくとこういう境地に到達するのかもしれない。
大作四曲で構成されるアルバム。
構成云々というよりは、ライヴ風の奔放な演奏で押し切る感じである。
奇怪なジャケットは、ダリの作風(「内乱の予感」?)を模したものでしょうか。
1 曲目「Reviure "Revivir"」(9:53)
シンセサイザーをフィーチュアしたクラシカルかつハードな作品。
衝撃的な序章は、MAHAVISHNU ORCHESTRA の第一作のオープニングと共通する。
アカペラ、モノローグ調の劇的なヴォーカルもあり。
変拍子でごり押しするメカニカルなパターン、スペイシーなシンセサイザー・サウンドなど SF 映画っぽい演出である。マイク・オールドフィールドも若干意識か?
終盤、シャフル・ビートによるシンセサイザーの疾走が痛快。
DEEP PURPLE がオルガンからシンセサイザーに乗り換えたような、またはイタリアン・ロックのサウンドを洗練したような印象だ。
2 曲目「Somni "Sueno"」(9:32)
タイトル通り、幻想的でややとりとめのないイメージながら、快調に飛び走る作品。
ALPHATAURUS の名曲にも共通する波打つような反復/シーケンスの美学がある。
主役はリズム・セクション、そして奔放なシンセサイザーの電子音。
サイケデリック・ロック調であり、アコースティック・ギターが刻むコードの響きに暖かみがある。
6:15 を境にテンポアップ、ギターが走り出す。
3 曲目「Atila」(11:53)
オルガン、ピアノとギターが熱気をはらんで走り、クラシック、R&B テイストもある、前作までの路線の延長にある作風である。
4 曲目「Al Mati "En La Manana"」(7:14)
バラード風の哀愁ある作品。怪しいスペイン語のヴォーカルが切々と訴え、ギターもフラメンコ調の速弾きを見せる。
終盤、驚くほど高密度のアンサンブルを披露する。
(EMI 10C 054-021 462)
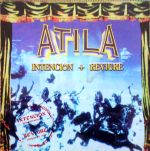
| Eduardo A.Niebla | guitar on 1-4 |
| Miguel A.Blasco | bass on 1-4 |
| Benet Nogur | keyboards |
| Juan Punet | drums |
| Joan Cardoner | guitar on 5-8 |
| Ignasi Bosch | guitar on 5-8 |
| Pere Martinez | bass on 5-8 |
2002 年の作品「Intencion + Reviure」。
第二作のリマスター・ヴァージョンと第三作の 1999 年ライヴ録音から構成される編集盤。
第二作の CD がノイズだらけの盤起こしで、第三作が EMI の許可が下りずに未 CD 化状態だったので、この内容はありがたかった。
第二作は音の輪郭がはっきりとしたのでバッタもん臭い安っぽさは払底し、壮大な書割風の大風呂敷クラシカル・ハードロックとしての魅力が際立つ。
第三作は、現代のキーボード・サウンドのせいでイメージが変わるかと思ったがそうでもなく、深みのある音がいい感じだ。
ライヴ録音の編成は、ドラマーがオリジナル・メンバー、キーボーディストが第二作からのメンバーで他は新メンバーのようだ。
(PYM1)
