
| Holger Czukay | bass |
| Michael Karoli | guitar |
| Jaki Liebezeit | drums |
| Irmin Schmidt | keyboards |
| Malcolm Mooney | vocals |
ドイツのプログレッシヴ・ロック・グループ「CAN」。 68 年結成。 78 年解散。 確固たる音楽的バック・グラウンドのあるミュージシャンが集まり、いかにしてロックたるべきかを模索して活動。 かなりのインテリ集団である。 サウンドは流れるようなビートとアンビエントな音を組み合わせた独特のもの。

| Holger Czukay | bass |
| Michael Karoli | guitar |
| Jaki Liebezeit | drums |
| Irmin Schmidt | keyboards |
| Malcolm Mooney | vocals |
69 年発表の一作目「Monster Movie」。
本作の特徴は、反復ビートとノイジーなギター、キーボード、独り言をわめいているようなヴォーカルらが乱立するガレージ風のサウンドである。
最初は VELVET UNDERGROUND 風にも聴こえたが、それはおそらく、チープなギターの音やシンプルなロックンロールであることと、当時の機材や録音手法からくる音質の類似によるのだろう。
何度かのリスニングを経て感じるのは、ここにあるのは、クールなリリシズムではなくあくまで無機質でアッケラカンとした音の連続であるということ。
しかし、凝ったプレイなぞどこにもないにもかかわらず、呼吸のよさは抜群であり、グルーヴがある。
どこを切っても同じ音が出てくるようなスタイルは、いわばロックの骨格だけを取り出して写真に撮り、それを何枚も重ねてアニメーションにしたような感じといえばいいだろうか。
1 曲目で底なしの転落を味わうと、2 曲目のセンチメンタリズムにもやや疑心暗鬼になるものの、結局ねじ伏せられて涙もろくもほろ酔い状態となり(初期 KING CRIMSON 的名曲です)、3 曲目では虚脱したルー・リードかカッコ悪いジム・モリソンのような世界に戸惑うばかり。
大作「Yoo Doo Right」では、ヴォーカル・パートにおけるブレイクからのドラムス、ベースの入りの絶妙のタイミングで痺れ、シンプルな繰り返しによる浮遊感に酔う。
後半は、ほとんどドラムスとベース、ヴォーカルのみだが、力強くも土人風のドンドコ・ドラムスが生み出す軽妙で脱力したグルーヴがたまらない。
全体には音を抑えておき、決めどころで切れ味いい技を決めるなど、きわめて計画的である。
それでいて曲調はルーズだからまたおもしろい。
心を弛緩させる薬品(まさにクラウト・ロック!)のような音であり、古びることのない音の一つといえるだろう。
69 年の時点で、すでにここまで行ってしまっていた人たちがいたということが驚きです。
「Father Cannot Yell」(7:01)つんのめるような律動とともに突き進む、十代のセックスのようにパンキッシュな作品。
ヴォーカルとギター、壊れてます。
「Mary, Mary So Contrary」(6:16)切ないラヴ・ソング。
ファズ・ギターの悲鳴のようなフィードバックが印象的。ヴァイオリンがユニゾンしているようにも思う。
「Outside My Door」(4:06)しなやかなカッコよさとそれを超える危うさ。
「Yoo Doo Right」(20:14)呪術的な大作。ノイズを使った音響処理のセンスのよさ、卓越したドラミング。
(SPOON CD 004 / 9057-2)

| Holger Czukay | bass |
| Michael Karoli | guitar |
| Jaki Liebezeit | drums |
| Irmin Schmidt | keyboards |
| Damo Suzuki | vocals |
71 年発表の三作目「Tago Mago」。
ハードなブギーやらデタラメな歌やら、ガレージっぽい脈絡のなさに浮かび上がるセンチメンタルな翳りと書割宇宙を漂うような異形のスケールの大きさがカッコいい名作。
前半三曲は、チンピラ風のダモ鈴木が軽やかに舞う煙たいロケンロー。
そして、三つの大作はジャーマン・ロック、プログレを代表する秀作、というか似非ロケンロー。
リーベツァイトのハンマー・ビートが拡散する粒子を集めてなんだかわからない巨大な塊にしてゆく「Halleluhwah」、ノイズやシーケンス風のフレーズがディープなエフェクトとともに収拾がつかなくなり、やがて真っ暗な穴だらけになってゆくかと思ったら最後はリーベツァイトが世界を救う「Aumgn」、きらめく狂気の奔流とともに宇宙へと旅立つ「Peking O」。
改めてロックにおけるドラムスの存在の重要性に気づかされます。
独特の音響処理、効果にも注目すべき。現在のテクニックの基本はすべてここにあるような気がします。
アナログ二枚組。
「Paperhouse」(7:29)感傷と虚脱とヤケッバチがかげろうのように揺らぐ序盤から、メカニカルなビートが駆動する疾走へと進むサイケの傑作。
絡み合う二つの古臭いギターには、AMON DUUL、POPOL VUH(同じ人か)と共通する種類の味わいが。
それにしても中盤のドラムス、カッコよ過ぎる。
低音がやや弱い(ベースがない?)のは元々なのか CD の出来(の悪さ)なのか。
「Mushroom」(4:08) DOORS ばりの堂の入った退廃感を醸し出す。
まあタイトルからモロなわけですが。
「Oh Yeah」(7:22)ダモの日本語ヴォーカルが冴える。
そして世界を切り開き、波打たせるような、鮮やかなるハンマー・ビート。
「Halleluhwah」(18:32)ビートの制する世界。
「Aumgn」(17:22)ノイズの制する世界。
「Peking O」(11:35)珍しく正統的アヴァンギャルドな展開も。
「Bring Me Coffee Or Tea」(6:47)
(SPOON CD 006/7)
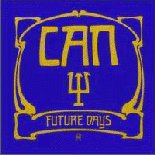
| Holger Czukay | bass |
| Michael Karoli | guitar |
| Jaki Liebezeit | drums |
| Irmin Schmidt | keyboards |
| Damo Suzuki | vocals |
73 年発表の六作目「Future Days」。
ヴォーカリスト・ダモ鈴木参加最後の作品。
サウンドは、薄霧のようにすべてをおおいつくすキーボードとサーフ・ロック風のチープなギター、あまりに歯切れのいいリズム・セクションによる摩訶不思議な浮遊感と疾走感を兼ね備えたもの。
シーケンサーもかくやと思われるドラムス、細かなパーカッション、シングル・ノート、オクターヴ連打を繰り返すベースが搬送波となり、ギターや遠くに離れて歌っているようなダモ鈴木の歌唱などさまざまな音響が、収縮しつつ、いつまでも流れ続ける。
あたかも、長いすべり台をするするとどこまでもすべってゆくようなフィジカルな快感を伴う音であり、反復と残響を活かした軽妙なグルーヴのうちにやがて心地よい酩酊感が生まれてくる。
BGM やヒーリング・ミュージックとしても機能するかもしれない。
衝撃的な音はどこにもない。
その代わりに中毒性がある。
さて、なにごとにつけまとまることを拒否して脱退したダモ鈴木だが、そのヴォーカル・スタイルは皮肉にも日本人が英語でうまく歌ってやろうとすると必ずこうなってしまう一つの典型に陥っていると思う。
意外なことに最も「まとめ」に入っているという印象を与えるのは、このヴォーカルなのだ。
タイトル・ナンバーは、響きと流れが一体となったメランコリックでポップそしてうっすらラテンな傑作。
スクラッチやパーカッションによる軽やかなビートがすばらしく気持ちいい。
2 曲目は断片的なオルガンの響きと密教風パーカッションが印象的なサイケお経ジャズロック。
3 連のダンサブルなグルーヴとライド・シンバルの連打が巻き起こす緊張感、そしてクールな 8 ビートへのシフト。
ギターのささやきとカッティングにしびれる。
プログレらしいカッコよさは一番でしょう。
3 曲目はしなやかなビートで走るブギー。
きわめてシンプルな繰り返しに、さまざまな効果音が絡むだけなのにこんなにカッコいい。
後年流行するテクノ・ポップの源流の一つかもしれない。
アンビエントなオープニングが美しい超大作「Bel Air」は、疾走の挙句ポップなヴォーカル・パートを経た終盤では、KING CRIMSON すら連想させるプログレど真ん中な演奏が続き、息を呑む。
ラウンジ系 BGM かと思っているうちに、宇宙の果てへと連れて行かれて帰ってこられない。
Fripp & Eno との干渉はあったのでしょうか。
ストリングス・シンセサイザーが美しい。
喧しさや難解な部分はなく、ジャーマン・ロックが苦手な方には一番のお薦め。
アンビエント・ミュージックの魁ともいえる、美しいアルバムです。
あまり知らないのですが、シカゴの音響派やある種のポスト・ロック系のグループは、おそらく、この音を聴いていると思います。
ホルガー・チューカイの録音技巧に負うところもあるだろう。
「Future Days」(9:34)
「Spray」(8:28)
「Moonshake」(3:02)
「Bel Air」(20:00)
(SPOON CD 009 / 9055-2)
