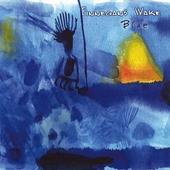FINNEGANS WAKE
ベルギーのプログレッシヴ・ロック・グループ「FINNEGANS WAKE」。
93 年結成。2011 年現在、作品は七枚。
プログレッシヴ・ロックの影響大の、キーボード、管楽器を使用したチェンバー・ミュージック。
グループ名はおそらくジェイムス・ジョイスの奇妙な作品から。
Yellow
| Jean-Louis Aucremanne | keyboards |
| Henry Krutzen | vocals, keyboards, percussion, sax, reita, recorder |
| Alain Lemaitre | bass, keyboards, drums & percussion programming |
| Michael Ouchinsky | guitar |
| Richard Redcrossed | lylics |
| guest |
|---|
| Wendy Ruymen | violin |
| Jean-Luc Clercx | solo guitar |
| Anel Bhasin | guitar weeping |
| Christian Lauwers | guitar |
94 年発表の第一作「Yellow」。
内容は、怪しい室内楽風ロックを基調にするも、あまりに奇妙な振幅で揺れ動き、評価に予断を許さぬ音楽である。
ヴァイオリン、ピアノを中心にした耽美な室内楽風味、ヴァイブを使用したモダン・ジャズ調といった雰囲気を、それぞれキーボードが管絃など適切な音でデフォルメし、その醸成された雰囲気をひずんだギターによるハードロックが凶暴で自信満々に切り裂いてゆく。
けたたましいギターが暴れるが金属的な重苦しさはなく、音の印象は全体に軽め。
そして、そのユーモア交じりの軽さのままにさまざまな世界をふらふらと揺れ動いてゆく。
しかし、軽いからといって明るいわけではなく、どちらかといえばメランコリックであり、顔色悪く薄笑みを浮かべている感じである。
ヴォイスは、ジャズ・スタンダードのパロディ風に軽妙であり、主として英国ポップス的なデカダンス、怪しさの源となっている。(デヴィッド・ボウイの芸風に近くないだろうか)
同時に、小気味のいいハモンド・オルガンのプレイ、ザッパ風としか表現できないリズムと一体化した早口ハーモニー、メロディアスなソロ・ギター、クラシカルなヴァイオリン、キーボードによる高低ストリングス系の音が厳かにスペイシーにたゆとうなど、プログレ・プロパー的な技もある。
また、ほんのりとインド、アジアンな、エスニックな演出もあるようだ。
そうなると、後期 KING CRIMSON との音楽的な接点を求めたくなるが、それほど音の密度や強い圧はない。
似非っぽさと洒脱さが表裏一体となったところは、80 年代以降のフェイク・ジャズあるいは黒塗り白人の擬似ヴォーカル・ジャズのイメージである。
室内楽風に聴こえるのは、ドラム・ビートがあまり強力ではないからだろう。
このミクスチャー感覚あふれる作風は、英国ロックらしさの一つの特徴である批判的なパロディ精神に通じるし、それもまた往年のプログレの特質でもあったはずだ。
英国ロックをひきずった個性的でスタイリッシュな作風であり、独特のペラペラ感に慣れた後にいろいろと見えてきそうな音だ。
そこまで我慢できるか、が問題である。
専任の作詞担当がいるところはユニーク。
「Chamber Music」(6:06)
「Wooden Horse」(5:56)
「King Wenceslas」(3:52)
「El Cid(Chimene's Song)」(11:18)史劇の映画音楽風の重厚なオープニングが印象的な快調歌ものプログレ。後半以降ではハモンド・オルガン、ギター・ソロをフィーチュア。
「For Joelle」(1:57)サティを鬱にしたようなピアノ・ソロ。テーマはあの有名な「The Godfather」にも似る。
「Last Poem」(4:06) 一転して、凶暴なギターが唸りを上げるバラード。
「Standard To You」(5:13)憂鬱な弾き語りから英国ポップス調へ。カッコ悪いヴォーカルにからむギターは、手癖全開ではあるが、それなりにカッコいい。
(MMP 256)
Green
| Jean-Louis Aucremanne | keyboards, piano |
| Henry Krutzen | vocals, keyboards, piano, tenor sax, recorder, percussion |
| Alain Lemaitre | bass, keyboards, drums & percussion programming |
| Pierre Quinet | guitar |
| Richard Redcrossed | lylics |
| Celine T'hooft | vocals |
| guest |
|---|
| Philippe Collington | vocals on 4 |
| Benoit Gillet | clarinet on 2 |
| Anne Monjoie | flute on 6 |
| Wendy Ruymen | violin on 3, 6 |
96 年発表の第二作「Green」。
若干のメンバー交代を経て、音楽はキーボードによる高級感のあるサウンドを中心とした室内楽調プログレとなる。
製作面の充実か、前作よりも音に手がかかっている感じだ。
演奏は、明快なパーカッション系キーボード、ストリングス系キーボード、ハモンド・オルガン、ピアノ、ギター、管絃楽器、ヴァイブによるアンサンブルが中心であり、穏かでクラシカルなパートから、怪しい歌ものパート、プログレ直系の器楽パート、シリアスに迫るパートなどがさまざまに盛り込まれている。
ただし、盛り込むといっても余裕があり、演奏には常に飄々とした面差しがある。
クラシカルなパートでは、ヴァイオリンや木管楽器の音がアンサンブルにオーセンティックな響きを与えている。
一方、コミカルな男性ヴォーカルやサックスなどストレートなジャズに変貌することもある。
また、ドラムスのアフロっぽさやアラビア風の音階などエキゾティックな演出もある。
一貫するのは、独特の拙さとクールネス、そして乾いたユーモアである。
したがって「奇妙な音楽」という第一印象は変わらない。
室内楽、ジャズ、フュージョン、ニューエイジ、プログレ、ポップスといった要素をより合わせているのだから、ミクスチャーによる「フェイクっぽさ」や「外し」のセンスはあるはずだが、それを強く主張することなく、あくまで薄味の洒落っ気にとどめている。
また、ヴォーカルに顕著なユーモラスな表現とバランスの取れた器楽をじつにキレ味よく切り換えている。
本格的にクラシカルなアンサンブルにアカデミックなスタンスを感じていると、突如 VdGG のカヴァーが始まったりする、この意外性のおもしろさも特徴だ。
カンタベリーというほどには演奏に運動性はないが、センスはかなり近いと思う。
さらりとしたタッチのくせに、木で鼻をくくるようなところもあるユニークな音楽です。
「Boleral」(3:05) 序曲風の優美なエレクトリック弦楽奏。
「Italics」(8:21) 前作の「El Cid」と通じる怪しいプログレ。クラシックとフュージョンが交じり合い、コミカルな味付けもある。
「Poly's Gone」(5:56) ややシリアスな表情を見せるチェンバー・ロック作品。
「Queen' Wenceslas」(7:16) タイトルからして前作の曲と対を成す? 後半現れるギターがカッコいい。
「Torquemada's Dream」(7:16) ヘタウマなギターが朗々と歌い、パイプ・オルガンが高鳴り、奇妙なヴォイスが歌う。
「The Dragon And The Fish Suite」(7:00)フルート、ヴァイオリンをフィーチュアしたチェンバー作品。マイク・オールドフィールドも若干入っている。
「Squid One(Remix)」(6:20) VdGG のカヴァー。他の曲のフレーズも盛り込まれている。
このグループの散らかり具合と VdGG のコワレ方には確かに共通するものがある。
「Mountains And Clouds」(6:19) おそらくアフリカのどこかの言葉で歌われている。
(MMP 321)
Pictures
| Jean-Louis Aucremanne | keyboards, piano |
| Henry Krutzen | keyboards, tenor sax |
| Alain Lemaitre | bass, keyboards, sound engineering |
| Richard Redcrossed | lylics, vocals |
2001 年発表の第三作「Pictures」。
内容は、多彩な弦楽器と管楽器を大幅に導入したエレクトリック・チェンバー・ミュージック。
エレクトリック・ギターとリズム・セクションにもステージを大きく取り、「チェンバー」側も「ロック」側も充実した演奏になっている。
楽曲はアブストラクトで精緻な現代音楽であり、インダストリアルで無機的な手触りがあって、暗さや威圧感、恐怖感よりも明快さと活発さが先立つ。
したがって難解なイメージもさほどでなく、小気味のいいグルーヴに身を任せたり、美しく気品のある叙情性に陶然となることができる。
これは、一つには録音含めサウンド面の充実によると思うし、端的に編曲が優れているともいえる。
そして、管弦楽を退かせてバンドに近い演奏形態になると、前作、前々作と同じく独特の「軽さ」と飄々としたユーモア、ロマンチシズムが浮かび上がってくる。
重量感あるハードロックでカッコよく攻めるところもあるし、ロングトーンのギターとヴァイオリンのユニゾンやジャジーなドラムスなど、KING CRIMSON を思い出してしまうところもある。
また、管楽器セクションがリズム・セクションと渡り合うところでは、マイク・ウェストブルックやキース・ティペットによる往年の英国ビッグ・バンド・ジャズロックのようなニュアンスも出てくる。
オークレマンヌとクルッツェンは演奏にも参加している(オークレマンヌによる優れたピアノ演奏やメロトロン風の音もあり)が、作曲者としてもかなりの大役を果たしていると思う。
ゲストには、UNIVERS ZERO のディルク・デスへーメケル(クラリネット、バス・クラリネット)の名前もあり。
傑作。
「Downtown」(10:55)
「Pictures」(16:47)奇天烈なヴォイス・パフォーマンスも含めた、わりとシリアスなチェンバー・ロック。
中盤の幻想悪夢的なピアノ・ソロ、そして終盤 2 分あたりの無調テーマを巡るアンサンブルがカッコいい。
「First Blow」(7:28)
「God Meets The Devil Drink Of Wenceslas (Part 1)」(7:01)
「Lllimited」(6:55)メカニカルでポリリズミックな現代音楽アンサンブル。こういう演奏で音色に温かみがあるところが個性的である。
「God Meets The Devil Drink Of Wenceslas (Part 2)」(4:01)
「Finale」(1:21)
(GA-8649 AR)
4th
| Henry Krutzen | keyboards, tenor sax, ken |
| Alain Lemaitre | bass |
| Alexandre Moura-Barros | acoustic guitars, electric guitars |
| Richard Redcrossed | lylics, vocals |
2004 年発表の第四作「4th」。
内容は、正統的に整ったイメージのチェンバー・ロック。
管絃数多くのゲストを動員し、クラシカルな整合感をもったアンサンブルにロックらしいモーメンタムをブレンドすることに成功している。
室内楽側の主役は、ピアノ、ヴァイオリン、オーボエ辺りだろうか。
適度な運動性とアクセスしやすいメロディ、和声に重きがあり、いわゆるチェンバーのシリアスさとは異なる、時にロマンティックですらある作風である。
ダイナミズムや迫力という点で、ヘヴィなエレクトリック・サウンドを一手に担うギタリストの貢献が大きい。
「明快にしてアヴァンギャルド」というタッチが、フランス 80 年代の雄 TIEMKO の傑作にかなり近い。
本格的なチェンバー・ロックとしてグレードが上がったことで、英国プログレの影響は初期作品と比べると見えにくくなっているが、ハモンド・オルガンのフレーズや何気ないアコースティック・ギターのアルペジオに、GENESIS や KING CRIMSON の影がちらついているような気もする。
チェンバー・ロックというと超絶的な技巧の連発とこんがらがったアンサンブル、気難しい曲調といったイメージを抱かれやすいが、本作品は、クラシカルな美感と豊かな音色、ロックとしての勢いが分かりやすく結び付けられており、難解さはない。
1 曲目からすばらしくカッコいいです。
リーダー格のヘンリー・クルッツェンは 2001 年にブラジルに移住、本作品もベーシストのトラック以外はブラジル録音である。前三作まで活動をともにしたジャンルイ・オークレマンヌとは袂を分かったのだろうか。
CD 二枚組。
(C7-071/072)
Blue
| Henry Krutzen | piano, keyboards, tenor sax, percussion |
| Alexandre Johnson | flutes |
| Alain Lemaitre | bass |
| Marcitio Onofre | piano, keyboards |
| Xochit Schutz | lylics |
2008 年発表の第五作「Blue」。
内容は、現代音楽調室内楽ロック。
演奏は、ドラムスやエレクトリック・ベースによるビートと管弦アンサンブルを合体させて、その中でピアノとエレキギターを際立たせるスタイルである。
つまり、クラシックとロックをまぜこぜにする、というプログレの古典的なアプローチであり、系列としては UNIVER ZERO 系で 80' KING CRIMSON の影響下だろう。
ただし、一部楽曲は完全なクラシック作品になっている。
パフォーマンスは、おそらく即興は抑えられていて、管弦セクションを中心に作曲ものが主だろう。
リズム・セクション、キーボード、管弦、エレキギターをフルに活かした演奏である。
サウンドの選択とアンサンブルの表情の組み合わせがかなり特徴的であり、明朗な音を選んだ挙句のアンサンブルが怪奇な色に染まっているとでもいえばいいのか、いわば、「怒りながら笑っている」ような奇妙に矛盾した味がある。
シリアスなのに緩い感じがある、いいかえるとコワいのにファンタジックなのだ。
これが意図的なものなのかそうでないのかは、よく分からない。
結果として、歪みのある怪しげな音全体に、緊張感を超えた独特の和みテイストが感じられる。
オオッと耳を惹きつけるのは、オペラ風の歌唱とピアノや管弦との組み合わせが生み出す屈曲したシリアスなタッチやプログレ・マインド全開で攻め立てるオルガンなど。
ヒラヒラと舞うヴァイオリンやクラリネットと HM/HR 風の轟音ギター・リフの同時進行というのもかなり珍しい。
大胆にエレクトリックなダンス・ビートを使うのも特徴的だ。
70 年代のプログレッシヴ・ロックが目指したのと同じ方向を現代らしい明晰なサウンドで目指している、という見方は正しいと思う。
そして、メロディアスでグルーヴィであることと前衛的であることは必ずしも矛盾しないとも思う。
「The Battle Of Novgorod」は、4 分弱の作品ながら、UNIVERS ZERO 直系の圧迫感あるチェンバー・ロック。
特筆すべきは、ボーナス・トラック「Agakuk」。
ラヴクラフト的な怪奇暴走チェンバー節が炸裂するが、それもそのはず、ギ・セガーズ、レジナルド・トリゴーなどベルギー・アヴァンギャルド系の雄らと北欧個性派ドラマー、モルガン・アグレンがゲスト参加している。
ユニゾンでねじくれながら激走するアンサンブルがとにかくカッコいい。
「Honfleur La Jolie」(6:47)ヘビメタ室内楽。
「Die Geste von Kreuzlingen」(4:36)
「Mida」(6:06)
「Luftspiel」(4:07)
「Blue」(5:48)目まぐるしく変化するエレクトリック・クラシカル・ロックの傑作。木管の響きが美しい。
「Ents And Things」(5:40)
「Magical Cave」(4:50)
「The Battle Of Novgorod」(3:52)
「Vulnavia」(4:07)
「Agakuk」(7:12) ボーナス・トラック。
(ALT 006)
 close
close