
| Hugh Banton | keyboards |
| Guy Evans | drums, percussion, keyboards |
| Peter Hammill | keyboards, guitars |
イギリスの超個性派プログレッシヴ・ロック・グループ「VAN DER GRAAF GENERATOR」。 67 年結成。 哲学的な歌詞をアジテートするヴォーカリストをオルガンとサックスによる暗くヘヴィなサウンドが守り立てるスタイル。 活動前期は、エレクトリック・ギターを使わないというユニークな編成。 78 年解散。 2005 年再始動。 初めて聴いたときに強くデジャヴを覚えた唯一のアーティストです。
2012 年発表の作品「Alt」。
トリオ編成の第三作は、仮住まいの簡易スタジオ設備(前作もここで収録されたようだ)をフル回転させた即興主体の完全なインストゥルメンタル・アルバムである。
2006 年から 2012 年までの録音をまとめたもののようだ。
音楽的にもすでに簡にして妙を得る境地にあると思いますが、ファンであれば、何より、彼らがすぐそばで遮二無二楽器をぶっ叩いているような臨場感に心震えます。
大胆極まる製作姿勢含め、心底プログレな人たちです。
本作には 「歌は一切ありません」 のでご注意を。
(EVDGCD 1003)

| Hugh Banton | organ, bass guitar, harpsichord, piano, glockenspiel, 10 string bass guitar on 11 |
| Guy Evans | drums, percussion, guitar on 12 |
| Peter Hammill | vox, pianos, guitars, bass on 7 |
2011 年発表の作品「A Grounding In Numbers」。
トリオ編成の第二作。
歌物については、バラード調にしてもパンキッシュなアジテーションにしても、ハミルのソロ作の芸風に沿うものである。(前作のような大作がないせいでもある)
ただし、ドラムスのラウドな音やバックを染め上げるオルガンの響きといった、つまり、バンドらしさを決定づけるパフォーマンスが図抜けてパワフルであり、そこがソロとの違いになっている。
おかげでアグレッシヴに攻め立てる歌唱の腰がすわり、このグループに自然に備わっている崇高さ、慈愛に満ちた厳かさを補完する重量感が出ている。
スタイルという点では、どちらかといえば、70 年代中盤以降のパンキッシュで突き刺さるような表現が主になっている。
変則的なリズムと不協和音や非旋律的なフレーズ、リフによる独特の逸脱感、緊張感は本作でも堅持されているが、往年と異なるのは、フリー・ジャズ的な展開を大きくは広げないこと。
これには、デヴィッド・ジャクソンが不在なこともかかわるだろう。
(ささやくようなオルガンがフルートに聴こえてしまうのも、ファンとしてはいた仕方なし)
2 曲目は、数学に思いを託しつつオイラーの公式をささやくシリアスなバラード。ユニーク。
3 曲目は、調子外れのリフで攻めたてるニューウェーヴ風ロックンロール。こういう曲が実にいい。
5 曲目「Bunsho」は、ストレートで力強い佳作。ライヴでも取り上げられている。
6 曲目「Snake Oil」は、アヴァンギャルドな名品。ただし、往年よりも作りはコンパクトである。
8 曲目は、変則リズムのパンク。
それにしてもこの楽曲、演奏がすべて六十代後半の人間によるものだとはとても思えず、ただただ驚くばかりである。
才気、反骨心、噛みつくような攻撃性には年齢は関係ないようだ、いや年齢はまったく関係ないという特別な人たちなのだ。LP も発表された。
「Your Time Starts Now 」(4:13)
「Mathematics」(3:37)
「Highly Strung」(3:37)
「Red Baron」(2:24)
「Bunsho」(5:03)
「Snake Oil」(5:20)
「Splink」(2:37)
「Embarrassing Kid」(3:07)
「Medusa」(2:12)
「Mr. Sands」(5:23)
「Smoke」(2:30)
「5533」(2:42)
「All Over The Place」(6:01)
(EVDGCD 1001)

| Hugh Banton | organ, bass guitar |
| Guy Evans | drums, percussion |
| Peter Hammill | vox, guitars, pianos |
2008 年発表の作品「Trisector」。
ヒュー・バントンの厳かなるオルガンが完全復活、ナルシスティックなヴォーカルとともに、VDGG が永遠の個性派ブリティッシュ・ロッカーとして毅然たる姿を現した。
オールド・スクールであるのは間違いない。それも並外れた。
あえていうと、ヘタなのかもしれない。
しかしそれは前から変わらないし、そもこのグループのようにロックすることは、うまいヘタとはほとんど関係ない。
頑ななまでにスタイリッシュなところと、それが完全に音になりきっているところなどは、デヴィッド・ボウイや JETHRO TULL と同じしたたかさと心底からのアーティスト魂を感じてしまう。
元々、唯一無二の個性派だったので、それがそのまま年月を経ただけである。
むしろ、変わったのは「こちら」の方である。
デヴィッド・ジャクソンの管楽器がないため、サウンドのバリエーションは少なくなっているが、強固な芯のある、モノクロームなイメージを作り上げるという点では奏効していると思う。
3 曲目に「さよなら」と歌っているところがあるようです。
「The HurlyBurly」(4:35)サーフロック風のギターが印象的なインストゥルメンタル。
「Interference Patterns」(3:50)発信音のような変拍子パターンでたたみかける、息もつけぬ性急さ。
「The Final Reel」(5:47)オルガンがオブリガートする懐の深いバラード。バントンはベースも演奏する。ハミルはピアノとギター。いつ風を巻いて走り出すかというワクワク感がいい。
「Lifetime」(4:45)厳かながらもオプティミスティックな肯定感のある作品。オルガンは教会風。
「新しさ」がスティーヴ・ハケットの作風に似るような。
「Drop Dead」(4:47)ハードでパンクなロケンロー。
「Only In A Whisper」(6:44)エレクトリック・ピアノが入るイントロで一気にマイルス・デイヴィス風になる。
「All That Before」(6:26)後期 VdGG らしいアジテーション。
「Over The Hill」(12:26)傑作。ファンなら納得。
「(We Are) Not Here」(4:06)変拍子のリフが強烈なヘヴィ・チューン。マンネリといわれようと名曲であることにかわりなし。
(50999 5 21030 0 1)

| Hugh Banton | organ |
| Guy Evans | drums |
| Peter Hammill | vox, guitars, pianos |
| David Jackson | saxes, flutes |
2007 年発表の作品「Real Time」。
2005 年 5 月 6 日金曜日、午後 7 時 43 分から 10 時 8 分まで行われた、北緯 51 度 30.4 分、西経 0 度 7 分に位置するロイヤル・フェスティバル・ホールでのライヴの録音。
圧巻の名曲目白押し。
CD 二枚組。
スリーヴにはこのライヴに臨むハミルの緊張に震えるような決意表明がある。
「Undercover Man」(8:29)「Godbluff」より。
フルートのシングル・ノートの連続とともに一気に湧き上がる歓声。ブチ切れるってジジイになっても大切ですね。
「Scorched Earth」(10:05)「Godbluff」より。前曲より切れ目なしでこのスタイリッシュなイントロが始まる。アルバムの興奮をそのままに。アヴァンギャルドと雄々しく凛としたたたずまいが矛盾なく両立している。なんと力強い肯定感。
「Refugees」(6:01)「The Least We Can Do Is Wave To Each Other」より。
慈愛と恩寵、そして永遠の逃亡。
「Every Bloody Emperor」(7:36)新作「Present」より。70 年代の作品といっても通る。
「Lemmings」(13:20)「Pawn Hearts」より。
ギター・リフのイントロがアジテートするヴォーカルを導く。歪なフォルムが粛然たる乱調美に至り、厳粛なるロマンを湛え始める。
サックスはひしめき合うレミングの群れを巧みに表現している。
破綻寸前の一線に賭けることを辞さない潔さ。
「(In The) Black Room」(11:16)ハミルのソロ作品「Cameleon In The Shadow Of The Night」より。ほぼバンドの作風そのままの凶暴な作品。ハミルはエレクトリック・ピアノも弾いているようだ。しいていえばヴォーカルがすべてを引きずって突き進む度合いがバンドのときよりも強い。
「Nutter Alert」(6:05)新作「Present」より。新作の中でも特に往年の芸風に寄った作品である。
これだけシンプルな構成でも説得力があるからすごい。
「Darkness (11/11)」(7:20)「The Least We Can Do Is Wave To Each Other」より。魔界のプリンスのテーマ・ソング。
「Masks」(6:47)「World Record」より。
「Childlike Faith In Childhood's End」(12:34)「Still Life」より。
「The Sleepwalkers」(10:44)「Godbluff」より。
「Man-Erg」(11:36)「Pawn Hearts」より。
「Killer」(9:55)「H To He Who Am The Only One」より。
「Wondering」(7:01)「World Record」より。
(FIXD 01)

| Guy Evans | drums |
| Hugh Banton | organ, bass |
| Peter Hammill | vox, electric piano, guitar |
| David Jackson | saxes, flutes, soundbeam |
2005 年発表の最新作「Present」。
黄金期のメンバーによる奇跡の復活作。
スタジオ新作 6 曲とライヴ・インプロヴィゼーション 10 曲による CD 二枚組。
不思議なほど、音楽が変わらない。
古びてもいないし、今風でもない。
「孤高」とは、こういうことをいうのでしょう。
表情豊かな管楽器、厳かなオルガンの響き、激情を燃やし続けるドラムス。
混沌から立ち上るアジテーションの炎と慈愛の調べ、ナルシスティックな感傷と暴力的なカタルシス、英知の言霊と透徹なまなざし。
すべてを携えて、VAN DER GRAAF GENERATOR が帰ってきた。
「Every Bloody Emperor」(6:58)ハミルのソロ・アルバム? いや、やっぱりバンドだ!と気づかされるオープニング・チューン。
「Boleas Panic」(6:48)インストゥルメンタル。
「Nutter Alert」(6:07)いろいろな意味で濃い作品。昭和プログレ。
「Abandon Ship!」(5:03)ギターが吠えるグラム/モダーンポップ系作品。演劇調など、ルー・リードやデヴィッド・ボウィとも共通するテイストがある。
「In Babelsberg」(5:28)いらつき牙を剥く凶暴性の向こうから詩的な美が浮かび上がる。攻撃面を強調したプログレ力作。
「On The Beach」(6:48)正統的歌ものプログレ。というかこちらが元祖。潮騒がいい。
「Vulcan Meld」(7:15)
「Double Bass」(6:27)
「Slo Moves」(6:19)
「Architectural Hair」(8:50)
「Spanner」(4:57)
「Crux」(5:49)
「Manuelle」(7:49)
「'Eavy Mate」(3:47)
「Homage To Teo」(4:39)
「The Price Of Admission」(8:49)
(7243 8 73676 2 3)

| Guy Evans | drums, percussion |
| Hugh Banton | piano, organ, backing vocals |
| Nick Potter | bass, guitar |
| Peter Hammill | lead vocals, acoustic guitar, piano on 2 |
| David Jackson | alto & tenor saxes, flute, backing vocals |
| guest: | |
|---|---|
| Gerry Salisbury | cornet |
| Mike Hurwitz | cello |
69 年発表の第二作「The Least We Can Do Is Wave To Each Other」。
本作にて、70 年代を通して活動する不動のラインアップが整う。
サイケデリックなムードを残しつつも、ハミルのヴォーカルを中心にした独特の器楽構成によるフリーキーにして荘厳な演奏スタイルが芽を吹いた作品といえるだろう。
音楽は、バロック音楽的な厳粛さとヘヴィなエレクトリック・サウンドによる凶暴性が一つになり、あくまで若々しく大胆である。
プロデュースはジョン・アンソニー。
「Darkness(11/11)」(7:27)。
オルガン、サックス、そしてうねるようなリフを操るベースが生み出す暗黒の空間を、ハミルのヴォーカルが切り裂いてゆくアグレッシヴなニューロック。
吹き荒れる風から生まれるハイハットのリズムと、ガラスを叩くようなピアノ、蠢くベースによって描かれるミステリアスなイントロから、この暗闇の物語は始まる。
密やかな呟きから、演奏とともに感情をクレシェンドさせてゆくハミルのヴォーカルが強烈だ。
そして、ヴォーカルに絡みつきながら、クライマックスではともに爆発するサックスとオルガン。
ピアノの音は、時おりさし込む光のように、暗黒に突き刺さる。
終盤の圧倒的なツイン・サックス(スタジオではオーヴァー・ダヴだろうが、ジャクソンは、ライヴでは二管吹きも見せているようだ)の演奏は、後の作品でも見られる得意技。
暴力的な昂揚と狂乱が、ピークに達してゆく。
執拗なベース・リフとオルガン、サックスが繰り広げる激しいソロは、ハードにしてすさまじい粘り気がある。
それでいて、演奏全体のイメージは、不思議なくらい硬質でアコースティックなのだ。
ニュー・ロック的な質感を引きずりながらも、さまざまな情動を叩き込み、たぎる坩堝のようなへヴィ・ロックへと進んだ傑作。
ヴォーカルが生むドラマに酔いしれるべし。
(11/11) とは何を意味するのでしょう。
「Refugees」(6:22)。
フルート、オルガンとチェロによる典雅なバロック・トリオと、切々と訴えかけるヴォーカル・コーラスがあいまって、宗教的な感動を呼び覚ますバラード作品。
まっすぐ切り立つようなオルガンの響きとともに歌い上げるアンサンブルは、静々と、そして時おりたたみかけるようなリズムも用いて、表情を変化させてゆき、やがて高みへと昇りつめてゆく。
一貫してヴォーカルに寄り添うチェロ、サックスの癒しの響きは、あたかも心の傷一つ一つに染み込んでゆくようだ。
前曲から本曲への落差は、あっけにとられるほどみごと。
ハミルの詠唱には、慈愛に満ちた神々しさが宿る。
時のほむらに焼かれるものへの鎮魂歌。
ここでのピアノはハミル。
「White Hammer」(8:15)。
荘厳なチャーチ・オルガン、天上へと誘うコルネットの響きが織りなすバロック調のサウンドと、燃えたぎるサイケデリック・ロックが交互に現れるドラマを貫いて、ヴォーカルが駆け抜けてゆくヘヴィ・シンフォニック・ロック。
彼岸の響きで癒すコルネット。
そして、あくまでヘヴィで現世的なサックス、オルガン。
ヴォーカルは、気高く両方の世界を物語る。
硬軟を巧みに行きつ戻りつする演奏において、やがてハードな部分が、あたかも貪欲な炎のように拡大し始める。
ここでも中盤再び、ツイン・サックスのプレイがある。
ここまで、オルガンとサックスの演奏だけ取り上げると、R&B っぽいノリなど、いかにもニュー・ロック調である。
最後は、静寂を突き破って現れる重戦車のようなディストーション・オルガンとサックスの狂喜乱舞が演奏を締めくくる。
二重人格のように表情を変えるヴォーカルには改めて感嘆。
「Darkness」とはまた違った攻撃性を孕んだ曲であり、後々まで続いてゆくアヴァンギャルドで大胆な構成をもつ作風の始まりである。
コルネットの響きとエピローグの異常なまでのヘヴィネスは、どうしても KING CRIMSON を思わせる。
いわば「裏 21 世紀」であり、これ以外ではメッセージを語れないという形式である英国ロックらしさという観点でも満点。
。
ここまで旧 A 面の流れは、ただただ圧巻。
音楽を聴いて涙を流すことはほとんどないのですが、これだけは例外です。
「Whatever Would Robert Have Said?」(6:07)。
スリリングなオルガンのリフイレンにギターのロング・トーンとサックスのつぶやき、躍動するタム連打が重なり、やがて一つにまとまってゆく劇的なオープニング。
アコースティック・ギターのストロークを交えてテーマを歌うメイン・ヴォーカルはなぜか地味だが、ヴォカリーズを経て B メロに渡るあたりから得意のぶっ飛んだ威勢を見せる。
そうなればヴォーカルは存在感抜群であり、伴奏部を置き去りにする勢いがある。
サビでは、力強いリフに刺激され、線の細い吟遊詩人から狂気のアジテーターまで表情の変化を見せる。
訥弁型ながらギターのオブリガートの音がなかなか新鮮だ。
8 ビートを破断する 8 分の 6 拍子による激しい突き上げ、トゥッティとユニゾンするアグレッシヴなヴォイス。
イタリアのグループが緊張感を煽るために好んで用いた常套手段である。
中盤は、サックス、オルガン、ギターによるフリー・フォームの演奏へと、あたかもエアポケットに落ちるように、進む。
音はふらつき気味でスカスカだ。
さすがにそのままでは終わらず、ギターをきっかけにフリージャズ調の激しい混沌へと突入する。
無論こちらのアグレッシヴなアンサンブルの方がこのグループらしい。
ブレイクから再びヴォーカルは穏やかに歌をささやくも、激しい 8 分の 6 拍子のトゥッティの突き上げと交互に現れて、ギターのテーマを再現して終る。
初期の GENESIS を真似たようなギターは、ヘタだが素朴な味がある。
(タイトルは朋友ロバート・フリップを指すようだが、実際の演奏はニック・ポッターか)
ヘヴィだが芯のない感じがするのはコンスタントな進行をせずに、立ち止まったり走ったりを繰り返すせいだろう。
このまとまり切らなさは、後々までの顕著な作風である。
「Out Of My Book」(4:07)。
優しげなフルートとアコースティック・ギターの伴奏で、慈しむように歌われる弾き語りフォーク。
オーヴァー・ダブされたメロディアスなフルートは小鳥のさえずりのように舞い、オルガンとともに雅でクラシカルな響きで曲を満たしている。
ヴォーカル・メロディは、シャンソンに近い都会的な洒脱さと田園牧歌調がブレンドしたもの。
オーヴァー・ダブされた一人コーラスもあり、ファルセットも美しい。
フルートによるバロック管弦楽調のオブリガート、重厚さと軽やかさをともに演出する巧みのオルガン。
こういう歌をすてきに聴かせるハミルのヴォーカル・スタイルの幅広さに敬服。
安らぎを覚える曲である。
初期 GENESIS と共通する魅力である。
「After the Flood」(11:28)。
アコースティック・ギターによるのたくるような変拍子テーマを狂言回しにさまざまなストーリーを力強いヴォーカルと器楽ユニゾンで強引にまとめたオムニバス大作。
せわしなくたたみかけるリズムでオルガン、サックスがノイジーに暴れる演奏や、ストレートなヴォーカルを前面に押し出した力強くメロディアスな演奏、悠然としたシンフォニックな演奏などが変拍子テーマをはさんで次々と姿を現す。
フルートとサックスによるきわめて英国ロック的なフリー・ジャズ・アンサンブルや、サックス、オルガンのユニゾンによる荒々しい変拍子パターンが強烈だ。
中盤は濃密かつ凶暴なる混沌世界、サックスが金切り声を上げオルガンが発狂する。
その百鬼夜行が吸い込まれるようにフェードアウトすると、抑制の効いたアコースティック・ギターに導かれて混沌を統べる若き魔王の如きハミルが出現する。
電気処理された絶叫とオルガンが轟音が爆発すると、その灰燼からはうち沈むアコースティック・ギターのテーマの余韻が立ち昇る。
そして一気に力強いアジテーションが再現、オルガンの轟きとギターのうねりとともに堂々たるエンディングへ。
電気処理やノイズ、フリー・フォームでの大暴れ、大胆奇天烈な展開など、本アルバム中最もストレートなサイケデリック色が強い作品である。
何曲分かのアイデアを詰め込んだ贅沢な作品なのでリスナーには一気呵成の勢いについていく元気が必要だ。
散漫と揶揄するよりも八方破れを楽しもう。
つなぎのテーマには一歩間違えると珍妙になるのを辛くも逃れている際どい面白さがあり、このグループの器楽スタイルの象徴といえそうだ。
若くしなやかな感性が生み出したドラマティックでアヴァンギャルドな問題作。
個人的には好きな作品です。
個性的なヴォーカルと重苦しい演奏をフィーチュアした、ドラマチックな作品。
サックス、オルガンを中心にした救いのないヘヴィな演奏から、チャーチ・オルガンやアコースティック楽器による魂を浄化するような気高い演奏まで、若いエネルギーの奔流のようなパフォーマンスが次々と現われる。
アグレッシヴな作品と文学性を感じさせる詩的な作品が、交互に配置されているのも、豊かな音楽性を印象づける。
基調はサイケデリックな要素もあるヘヴィで暗いサウンドだが、つややかなヴォーカルとサックスやピアノのせいか、なぜかアコースティックでモノトーンのイメージを強く感じる。
この辺が、いずれ彼らの特徴になってゆくのであろう。
ただのオルガン・ロック、サイケデリック・ロックとは一線を画し、オリジナリティのある前衛サウンドへ第一歩を踏み出した作品、といえる。
とにかく、はちきれそうなくらい瑞々しい感性がある。
60'、サイケデリック・ファンにもお薦めできる作品だ。
歌詞内容も、かなり奇矯なようだ。
傑作。
(CAS 1007 / CASCD 1007)

| Guy Evans | drums, percussion, tympani |
| Hugh Banton | organs, piano, bass on 2,5, vocals |
| Peter Hammill | lead vocals, guitar, piano on 2 |
| David Jackson | saxes, flute, vocals |
| guest: | |
|---|---|
| Robert Fripp | guitar on 3 |
| Nick Potter | bass on 1,3,4 |
70 年発表の第三作「H To He Who Am The Only One」。
ベーシストのニック・ポッターが脱退し、本作にはゲスト参加。
ポッター不在の曲では、ベースはヒュー・バントンがペダル演奏でカヴァーしているようだ。
KING CRIMSON のロバート・フリップのゲスト参加も特筆すべきだろう。
ハミルの歌詞の世界は、きわめて SF 的なタイトルが示すように、内省的なものから空想物語、ゴシック趣味とさまざまな広がりを見せ始める。
センチメンタリズムを堂々押し出すヴォーカル表現に深みが増すとともに、演奏面では破格な前衛性が強まる。
何とも喩えようのないサウンドだが、青年期特有の、高揚と沈潜が乱高下する混沌とした精神状態をそのまま映した音というものがあるとすれば、これこそまさにそれだろう。
ジャケットの記述によれば、アルバム・タイトルは、水素からヘリウムへの熱核融合が宇宙のエネルギーの唯一の源泉であるということらしい。
また、ジャケットの奇妙な絵は、大気圏を出て無重力になったため用を成さなくなった天秤のようだ。
プロデュースはジョン・アンソニー。
アシスタント・エンジニアとしてデヴィッド・ヘンチェルの名前もある。
「Killer」(8:07)煮えたぎる熱いテーマと扇動的なメッセンジャーたるヴォーカル、そしてすべてを押し流す怒涛の如きアコースティック・ギターのストロークやピアノの打鍵など力強くダイナミックな面が強調された傑作。
荒々しいタッチながら緻密な構成をもち、緊迫感が途切れない。
絶望的な孤独を象徴する寓話的な歌詞も魅力。
オルガンは野獣のように咆哮し、ピアノは鋼鉄の弾のような和音を雨霰と降り注がせる。
サックスは狂おしくも肉感的であり、ドラミングは緊張で張り詰めた世界を揺るがせる。
中間部は得意のフリージャズ的な混沌だが、このグループの作品にしては全体的に派手なイメージであり整理された調和感のあるハード・チューンである。
「歌舞伎町の女王」にも同じエピグラフを冠したい。
ベースは、ニック・ポッターが担当。
「House With No Door」(6:03)
詩情あるピアノ伴奏をバックにハミルのデリケートな歌唱が映える内省的なバラード。
ハミルは自らに問いかけて自ら応えようとしてもがいている。
間奏ではフルートは救済を暗示するように静かにハミングする。
柔らかくも引き締ったドラミングがすばらしい。
からだに突き刺さるような孤独感と絶望を語るハミルの言葉と表情が胸を打つ。
哀しみとポジティヴに花開こうとする気持ちが交錯する。
陶酔できる曲だ。
誰も出てこれない誰も入れない扉のない家というのは心を閉ざした人を意味するようだ。
「The Emperor In His War-Room」(8:04)本作は、二部構成の物語であり、テーマは「戦いに明け暮れる王の孤独」である。
第一部「The Emperor」は、フルートが奏でる哀しげな旋律で幕を開ける。
哀しみのあまり足場を失ったような密やかなアンサンブルと、オルガン、フルートが押し出すヒステリックなテーマが交錯する中を、独善的な主張のあるヴォーカルが突き進む。
ハミルによるアコースティック・ギターも聴こえる。
このまま、内省的な静けさと凶暴な激情の噴出を狂おしく繰り返してゆく。
クライマックスは、無慈悲に時を刻みとるタム連打とともに渦を巻くパワフルなユニゾン。
そして、一転して厳かな響きの中へ暗い諦念のメッセージをそっと置き去りにしてゆく。
調子、テンポの変化は自在であり、歌唱と演奏が一体となっている。
そして一つになったまま乱れる心のように躁鬱をめまぐるしく切り換え、轆轤のように不気味に回転するユニゾンすら、コーラスとともに記憶のかなたに消えてゆく。
フルートの暗くもつれるような響きが初期の KING CRIMSON を思い出させる。
第二部「The Room」は、ドラムスのピックアップからベースの刻むテーマ・リフの主導のもと、ロバート・フリップの神経症的ロングトーン・ギターからスタートする。
フルートも遮二無二乱れ吹きで荒れ狂うギターにしがみつき、第一部とは異なるガレージ風のロックっぽさ、やんちゃさが現れる。
左右のチャネルにオーヴァー・ダビングされたヒステリックなギターは、手数多く叩きまくるドラムスとともに、狂人の脳を刺激する電磁波のように渦を巻いて暴れる。
ヴォーカルは荒々しく歌を叩きつけ、ギターはどこまでも狂おしく叫ぶ。
混沌としたギター・ソロが静まると、演奏は「Emperor」の沈痛なテーマに回帰、前半のフルートをサックスへともちかえ、オルガン、サックスが高らかに雄叫びを上げてノイジーなギターとともに狂熱的なユニゾンを決める。
そして、最後は、祈りの如き厳粛な余韻を残して去ってゆく。
幻想的なフォークソングとへヴィで狂的に集中した器楽を結合したアヴァンギャルド・ロック。
前曲のようなリリシズムを湛えつつも、歌唱と器楽の結合は歪であり、その歪さ、不健康さのままに走り出すところが不気味である。
悪夢的といえばいいのだろうか。
そして、重苦しさを振り払うようなナチュラルでメロディアスな流れがあるところがいい。
リフや決めのテーマも印象的だ。
きめ細かい管楽器のアレンジも効果的。
ベースは、ニック・ポッターが担当。
本曲は、ハミルの BBC ライヴでの独演はあるが、バンドの公式のライヴ録音はない様子。
「Lost」(11:13)二部構成の組曲。
「Part 1. Dance In Sand And Sea」は、フルート、サックスとオルガンによる錯乱気味のイントロダクション。
3 連リフレインによる眩暈を起こさせるほどにストレンジな軽さは酩酊感を超越し、狂気を暗示する。
意味深なブレイクを経てオルガン、サックスの 3 連リフレインを伴奏に、ハミルがテンション高く歌いだす。
伸びやかな美声で主張するヴォーカルをきっかけに、サビではリズムがシュアーな 8 ビートへと変化。
ヴォーカルは演奏に合わせてふわりと着地するようにメロディアスに変化する。
いつもながら、ヴォーカルにしっかりとつきしたがう伴奏がみごとだ。
ヴォーカルはまさしく正調ハミル節、気高くも情熱を秘めている。
メイン・ヴォーカル・パートの繰り返しを経て、間奏部は、オルガンによるノイジーな変拍子リフレインが渦を巻き始める。
緊迫感をあおるようなタムタム連打。
ついにはサックスによる扇情的変態リフレイン(懐かしの「生活向上委員会」のようだ!)が噴出し、追い立てられた世界の位相はねじれ、歪み始める。
ゆがみの中で我を忘れたように虚ろに歌い始めるハミル、そして身悶えるように叫ぶ。
一転、沈痛な面持ちのヴォーカルとともに、薄暗い「Part 2. Dance In Frost」が始まる。
ヴォーカルは圧倒的な力強さで切実な思いを歌い上げる。
伴奏は、ほとんどサックスのみであり、その不気味な輝きのほかは抑制された演奏といっていいだろう。
ボレロ風のスネア連打とともに、オルガンのヴォリュームも次第に上がってくるが、それを凌駕するのは切実な表情で迫るヴォーカルである。
哀しげだが、どこまでも雄々しい。
ヴォーカルを追うようにサックスが哀しげに歌い上げ静かに消えてゆくと、今度は、よりスインギーなビートでジャジーにリラックスしたサックス・ソロが始まる。
そして、オルガンの 3 連リフレインがゆっくりとフェード・イン。
第一部の雄たけびヴォーカルが復活し、再び熱気は強まるが、オルガン、サックスはともに熱せられないかのように着実な歩みを続ける。
メロディアスなサビに燃え盛り、吹き上げるのは濃密な情念である。
沈み込むような表情を見せることもあるが、すでに抑制は困難である。
苦悩するヴォーカルとともに演奏も高まってゆく、ゆっくりと。
再び現れるフリー・ジャズ調の乱調リフレイン、しかし音符が譜面から外れて落ちてゆくようにリズムは一拍づつ削れてゆく。
陰鬱なヴォーカルはまだ去らない、訴えたいことがまだ胸に渦巻くのだ。
最後は、バリトン・サックス、テナー・サックスが迸る重厚なアンサンブルに、ハミルの絶唱が吸い込まれてゆく。
そして、未来永劫続くかと思わせるサックスのプレイを、狂ったようなピアノの和音の連続が引きちぎり、轟々迸るサックスとドラムス、ピアノが呼応しつつ消えてゆく。
切実かつ悲劇的な重みのあるヴォーカル・パートと乱調気味のフリー・ジャズ・パートを大きく揺れ動くアヴァンギャルドな大作。
常にオーセンティックなイメージを与える声質と歌唱を十分活かして重心としながら、楽曲を破壊する限界ギリギリまで器楽演奏のデフォルメを試みた、といってもいいだろう。
リフレインが繰り返しごとに一拍づつ縮まってゆく辺りは、真剣さと思いつきのいい加減さがきわどくバランスしている。
器楽の中心となっているサックスはフリー・ジャズ的な暴力性と下劣な肉体性を誇示する。
一方、オルガン、ドラムス、ヴォーカルによるパフォーマンスはクラシカルに整っている。
終盤は、序盤のテーマへと回帰し、初期 KING CRIMSON を思わせる力強い演奏を繰り広げる。
錯乱の果て「I Love You...」と絶叫するハミルの声が、耳に突き刺さる。「Pawn Hearts」への序章と見ることは可能だろう。
ベースは、ニック・ポッターが担当。
本曲もライヴ録音が見当たらない。
「Pioneers Over C」(12:25)オシレータの電子音がうねるイントロダクション。
オルガンののっそりとしたリフレインは、既に救いのない暗さに満ちている。
ドラムスとともに静かに立ち上がり、ささやきもつかの間、みるみる高まってゆくヴォーカル。
オルガンも炎を吹き上げる。
厳かな詠唱、そして、ベース・ペダルとサックスのユニゾンによるテーマは、不気味だが力強い前進力にあふれる。
ヴォーカルも演奏をなぞってストレートに歌い上げるかと思えば、突然調性を無視したようなシャウトを見せるなど大胆極まりない。
深い空間を意識した演奏は、虚空に放り出された主人公たちの状況を示すのだろう。
ノイジーなオルガン、遠くざわめくサックス、唐突に噴出すジャズ風のアンサンブル、そして開き直ったように叫ぶヴォーカル。
頓狂な歌唱で一区切りつけると、再びサビから詠唱へ。
恐るべきベース・ペダルとサックスのユニゾンをヴォーカルが追いかけ、テンポ・ダウンとともに内省的な表現に変化する。オルガンも管楽器のようだ。
しかし、ここでも歌唱の末尾を管楽器とともに捻じ曲げてしまって素直になれない。
アコースティック・ギターが静かに奏でられているのに気づく。
いつしか、謎めいたバラードへ。
バスドラが響き、サックスが訥々とささやく。
再び、いや三度か、今度はピアノによる変拍子リフレインが始まり、さまざまなノイズや即興的な音響、ドラミングが散らばされる。
メインパートへと回帰し、訴えかけるヴォーカル、厳かな詠唱、しかし末尾は不安定である。
パワフルなユニゾン、追いかけるヴォーカル、ミステリアスな伴奏とともにヴォーカルは歌い続ける。
フリージャズの洗礼再び、偽者っぽい高揚とアジテーション風のファルセット、壊れたジャズ・コンボががらがらと崩れてゆく。
ノイズだけが残される。
1983 年という"未来"に地球を飛びたった宇宙飛行士達が遭難し、救助を求めているというレイ・ブラドベリィの短編小説を思わせるシチュエーションを描く作品。
歌詞だけ読むとやや唐突で妙な感じだが、深刻さと哀愁をにじませるハミルの本格的なヴォーカルと前衛的なバックの演奏がうまく練り込まれており、狂気の弾き語りというニュアンスのもと、ドラマチックかつエキセントリックな名曲になっている。
吟遊詩人の弾き語り風の叙情性、変拍子のフレーズでたたみかける攻撃性、急激な調子や和声の変化、不安に満ちたコラージュ風の演奏などを次々と叩きつけて、リスナーの予想をことごとくはずしてゆく。
一貫するのは闇に漂う不安感。
強烈な演奏には、成否はともかくとして、フリー・ジャズを呑み込まんとする勢いがある。
明解な流れがないようでいて、暗澹たる雰囲気がしっかりと全体を貫いている。
前曲とともに、イタリアン・ロックへの影響ははかり知れない。
特異な歌詞と熱狂的な歌唱表現、そしてフリー・ジャズの影響を消化した前衛的なインストゥルメンタルに、いよいよミュージシャンシップの真髄が発揮された傑作。
演奏には、独特のハードネス、ダイナミズム、そしてダークネスがある。
前作で見せたクラシカルな雰囲気は、この暗く熱っぽい演奏へと、とかし込まれているようだ。
比較的ナチュラルで直線的な展開をもつ 1、2 曲目と比べて、後半の 3 曲では、凝った構成と実験性を存分に見せつける。
ヴォーカルと管楽器に明らかなように、演奏は、暗さと同時にジャズ的なしなやかさ/力強さも持っている。
しかし、それ以上に、エキセントリックでアヴァンギャルドな面が強調されている。
バンドは、あと一歩で緊張から失笑へと破綻してしまいそうなポイントで、アクロバチックな反転を繰り返し、ハミルはピエロになる寸前で、青ざめた死神のような凄まじい微笑みを見せ、
不可思議な物語を囁きかける。
おそらく、好悪のはっきり分かれるアルバムである。
しかし 4、5 曲目を聴いてのめり込めれば、もう逃げられないはずだ。
また、まったく根拠はないが 1 曲目、2 曲目の展開、配置は KING CRIMSON の第一作の「二十一世紀の精神異常者」と「風に語りて」に、よく似たムードを持っていると思う。
フルートが入っているせいだけとも思えない。
現在入手できる CD は音がややこもっている。
こういう作風だけに、雰囲気としては悪くないが、明晰な音で聴いてみたい気もする。
結論、1 曲目「Killer」だけでも十分元は取れる作品。
ハミルのカリスマ性は、デヴィッド・ボウイを凌ぐ。
(CAS 1027 / CASCD 1027)

| Guy Evans | drums, percussion |
| Hugh Banton | organs, piano, Mellotron, bass pedal/guitar, synthesizer, vocals |
| Peter Hammill | lead vocals, guitars, piano |
| David Jackson | saxophone, flute, vocals |
| guest: | |
|---|---|
| Robert Fripp | guitar |
71 年発表の第四作「Pawn Hearts」 。
アヴァンギャルドながらも崇高な悲劇性というロマンティックな焦点の感じられた作風を突き詰めて抽象的かつ魔術的な方向を極めてしまった大傑作。
精神の深淵の「向こう側」へ突き抜けた感が強い。
立派な現代音楽であり前期を総括する作品といっていいだろう。
火を噴く激情と手折れそうなデリカシーを行き交う衝動的ともいえるパフォーマンスが矛盾なく一つの色調にまとめられて綴れ織りを成し、重厚な手応えのある大作三つに集約された。
オルガンや管楽器によるアンサンブルは混沌のうちに神秘を極め、ハミルのヴォーカルは魂を病む人のように無限の神々しさを放つ。
そのつややかな狂気の質感、アナーキーな重量感は KING CRIMSON の第一作に共通し、絶望の彼方に救済の輝きを見出すような音の響きは PINK FLOYD の傑作群に共通する。
ナンセンスへの逸脱すれすれの綱渡り的な展開にも知性と意気込みが感じられ、他では味わえないスリルとカタルシスが生まれている。
プロデュースはジョン・アンソニー。
「Lemmings(Including Cog)」(11:39)
焦燥に身悶えしながらもポジティヴな主張を狂気すれすれのアジテーションで撒き散らす、きわめて攻撃的な作品。
燃え盛る炎のような錯乱の嵐の向こうに空ろな暗闇がぽっかりと口を開く。
崇高なるオルガンと肉感的なサックスは毒々しい表情を貫いてヴォーカルにまとわりつき、静かで気品あるピアノ、フルートと鮮やかなコントラストをなす。
ヴォーカルは、聖人の如き清らかさと犯罪者の如き邪悪さまで、多重人格者のように表情を操る。
中間部「Cog」では狂気の頂点に達し、軋みながら躁鬱の連鎖を手繰る歯車のイメージそのもののインダストリアルで密度の高い即興演奏が繰り広げられる。
ピアノとエレクトリック・サックスのパワフルなパフォーマンスが際立つ。
終盤には完全燃焼の後の虚脱の灰塵が舞い散る。
「Man-Erg」(10:21)
暗闇に差し込む一筋の慈愛の光を思わせる、厳かにして胸に迫るシンフォニック・ロック。
厳粛なオルガンとモノクロのピアノに彩られたハミルのバラードは、苦悩する精神に差し伸べられた天の恩寵のように清らかで力強い。
対して、複合拍子がドライヴするぶち切れ気味の中間部は、自らのナイーブさを強引に振りほどき、叩き潰すためのものだろうか。
文脈や意味を失う寸前のアヴァンギャルドな展開だ。
心の暗闇にある邪悪な病魔をふり切れ、動け、そして立ち向かえ。
再び、静かに始まり高まってゆくハミルの歌声に、暗黒を貫く曙光のようなサックスが朗々と応え、遥か眼下ではオルガンが緩やかに渦を巻く。
フリーなピアノとパワフルなトゥッティ。
ハミルは虚空へと遠ざかりつつ、歌を残してゆく。
漆黒の大伽藍に壮大な演奏が響き渡り、恐るべき狂気の複合拍子アンサンブルがクロス・フェードする。
しかし、今度は、その強引な響きが礼賛の歌へと変化し、すべてを押し流してゆく。
前作までのサイケデリックなカオスから噴き出す感情的なメッセージとは一味違う、大人としての確固とした自信に裏づけされた懐の深いメッセージ(フリージャズ風のアジテーションですら風格あり)を感じる名作であり、この作風は後期に引き継がれてゆく。傑作。
「A Plague Of Lighthouse Keepers」(23:04)
10 のパートから成る超大作。
孤独感を灯台守になぞらえた懊悩と慈愛、解脱の寓話であり、大著を思わせる巨大なドラマであり、永遠の代表作である。
このグループの作品をもし一曲だけ聴くとしたらと問われれば、激辛の強烈な体験にはなるだろうが、この曲を薦める。
「a.Eyewitness」
抑制されたイントロダクションは、地声とファルセット・ヴォイスによるシリアスなダイアローグへ。
ドラムス、サックス、オルガンはヴォーカルへと巧みに寄り添い、知らず知らずのうちに独特のモノクロームのアジテーションの世界へと誘われている。
「b.Pictures Lighthouse」
スペイシーなインストゥルメンタル。
海鳥の鳴き声を思わせるサックスの残響、汽笛のようなオルガンのほとばしり、鋼鉄の車輪の緩やかな回転を思わせる轟音。
「c.Eyewitness」
厳かなチャーチ・オルガンの高まりとともに諦念に満ちたヴォーカリストが再訪する。
「d.S.H.M.」
グラマラスなブギー調の作品。
「e.Presence Of The Night」
天上の響き、宗教的高揚。
「f.Kosmos Tours」
ハイテンションの歌唱と挑発的な変拍子トゥッティ。
そして破断。
「g.(Custard's)Last Stand」
穏やかな慈愛の響き。
「h.The Clot Thickens」
凶暴なる訴え、絶叫、モノローグ、狂乱する演奏。KING CRIMSON 直系。
メロトロンが珍しい。
「i.Land's End(Sineline)」
一瞬の断絶、厳かなピアノそして崇高なる感得の境地。
「j.We Go Now」
広がる視界と意識。世界を見渡すような大団円。
このアルバム発表後、メンバーはツアーに疲れ、グループ活動を停止する。
同年ハミルは、ソロ活動に専念し始める。
ただし、このソロ作品には、バントン、エヴァンス、ジャクソンらメンバーが参加しており、音楽的にもグループ活動の延長上にあることがわかる。
(CAS 1051 / CASCD 1051)
お薦めは、以上の前期の三枚。
出発点であったサイケデリック・ロックから一歩レベルアップし、夢と現実の狭間にある暗い世界を重厚な音響で構築している。
大音量で聴くと新しい世界が啓ける稀有なアルバムの一つだ。
再始動後、後期の四枚は、グループ存続のための苦肉のアルバム「Quiet Zone」以外は、すでにピーター・ハミルのソロ・アルバム的色合いが濃いが、その中でも「Still Life」、「World Record」は、名盤といえるだろう。
歌詞を眺めると、ピーター・ハミルの作品が、世界と人生に関する真摯な態度がにじむものばかりではなく、SF /怪奇趣味をも横溢していることも分かり興味深い。

| Guy Evans | drums, percussion |
| Hugh Banton | keyboards, vocals |
| Peter Hammill | lead vocals, guitars, piano |
| David Jackson | saxes, flute |
75 年発表の「Godbluff」。
再結成後、前作から四年ぶりの作品。
内容は、熱気で滾る器楽と荒々しい扇動と挑発で魂を揺さぶるヴォーカリストによるアグレッシヴでケイオティック、なおかつセンシティヴなロック。
フリージャズやクラシックを吸収して独自の世界へと昇華した空前絶後の作風であり、KING CRIMSON や GENTLE GIANT 同様グループ名そのものがジャンル名になるタイプの音楽である。
楽曲はすべて高密度の大作。
明快かつ独特の癖のあるテーマをふんだんに盛り込んだアンサンブルはロックというよりも異形の室内楽というべきものだろう。
曲調の変化は唐突にして強烈、そして二重人格的であり、あらゆるプレイに地の果てまでも突進するヤケクソ気味のモーメントがある。
噛みつくようなヴォーカル表現含めて「パンキッシュ」といって差し支えないと思う。
そう、本作品ではパンクにしてシンフォニックという独創性が極められている。
新鮮なのはハミルのギター・プレイ。
作風についてはハミルのソロ作品との区別が難しいが、やはりグループとして作品の方が運動力が勝っていると思う。
これだけのテンションがあってこそ、再結成が可能になったのだろう。
衝撃的名作。
プロデュースはグループ。
1 曲目「The Undercover Man」(7:25)断続する信号のように眩惑的なフルートとヴォーカルのつぶやきが忍び寄る波乱含みのインントロダクション。
ミステリアスにして背筋が痺れるほどスリリングだ。
ゆったりとしたクレシェンドで音が満ち渡り、崇高なメロディへとまとまってゆくさまは、「Refugee」などの名品につながる。
がっちりと受け止められるような安心感。
伴奏はピアノ、フルート、そしてオブリガートにはクラシカルなオルガンが翻る。
心地よい緊張をキープするのは丹念なドラミング。
このドラムスが気高く主張に満ち満ちた朗唱に忠実に付き随う。
ささくれ立ったクラヴィネット(ギター?)とサックスがオーヴァーラップする間奏は、生きながらすでに彼岸にいる精神といまだ現世に迷う肉体が互いに呼び合うような不思議なイメージだ。
変幻自在のアジテーションを見せるヴォーカルのリードでフルートとピアノ、オルガンによる控えめながらも的確な演奏が背景を塗り込めてゆく。
このグループらしい巧みなストーリー・テリングと凍るような厳かさとあふれ落ちんばかりのロマン。
一人讃美歌ロックの名曲。
クロス・フェードで立ち上がる「Scorched Earth」(9:48)。
エレクトリック・ピアノが提示するリフにギター、オルガン、サックス、ドラムスが同調してゆく、リズミカルにして緊張感が心地よいオープニングだ。
呪いの言葉を吐きかけるハミルのアジテーションに、サックス、ギター、オルガンによるアンサンブルが強力なリフで対抗し、その拮抗とシンクロの絶妙の呼吸で曲が展開してゆく。
派手なプレイはないが、演奏は荒ぶるヴォーカルをなぞるバッキングにとどまらず鋭くダイナミックであり、時に突出する。
ジャジーな間奏もあくまで攻撃的である。
不恰好に角ばった邪悪な第二のリフが示され、第一のリフと刺激しあい、やがてサックスがリードする勇ましい第三のテーマ(第一リフの発展形か)が輝かしく降臨する。
このサックスがリードするシンフォニックな全体演奏は分厚い雲海を天上から貫くヤコブの梯子のように神々しい力にあふれている。
そして、うねるような変拍子テーマのトゥッティには歪みや波乱をそのまま強引に束ねるような力がある。
混沌をオルガンが治め、サックスが絶叫するとともに力強いメイン・テーマへと戻る。
荒々しいヴォーカルとサックスのバトルが続き、中盤のサックス・リードの輝かしく力強いリフも再現される。
終盤は、テーマが激しく拮抗しながら、雄々しく逞しいアンサンブルがそのテーマのぶつかり合いとともに飛散しそうな勢いでぐんぐんと高まってゆく。
大胆な変拍子とシンコペーションを駆使したテーマがせめぎ合う力強いロック・シンフォニック。
迎合を嫌う奔馬のようなアンサンブルを何とか束ねて走り続けるテンションの高さが魅力だ。
孤高のグループらしい、荒ぶり続けて自らを破壊することも厭わないスタンスがよく分かる。
器楽の充実した名曲。
3 曲目「Arrow」(9:45)珍しくジャズロック調のジャム・セッションがフェード・インするイントロ。
フリージャズ風の気まぐれなサックス、小刻みなドラミングの主張を経て、オルガンが一閃し演奏を制してエフェクトの響きを残して静まると、エレクトリック・ピアノが物悲しい和音をゆったりと奏で始める。
深いエコーで遠景に広がるサックス、フルートも寂しげな音だ。
クラシカルなエレクトリック・ピアノのオブリガート、そしてヒステリックに歌い出すヴォーカルは、身を削り血を吐くような悲愴感であふれている。
バラードかと思えば、みるみるうちにアジテーションへと変貌し、悪鬼のように怒りを撒き散らすのだ。
狂気を感じさせて「怖い」。
ヴォーカルを支えるサックスのオブリガートもミステリアスだ。
唐突なロールなどアドホックなプレイを続けていたドラムスが、パワフルなリズムを刻み始めると、すべてが大きなうねりを成す。
不吉なエレクトリック・ピアノの響きが力を増す。
ぶちキレたヴォーカルがくり返し叫びを上げ、その強烈なシャウトを引き継ぐように、サックスのリードによるパワフルな間奏へと突進する。
再び現われたヴォーカルを支えるのは、どこまでも肉感的なサックスのオブリガートである。
あまりにも凶暴で危険な叫びにエレクトリック・ピアノの和音が叩きつけられると、ヴォーカルは最高潮に達し身を捩るように呪詛の言葉を吐き散らす。
圧巻。
再び演奏はサックスのリードで強引に進み、エレクトリック・ピアノとギターがつきまとう。
込み入ったリズムの上で呪いの言葉を撒き散らすようなインストゥルメンタルが続いてゆく。
重々しいリタルダンド、そして渦を巻くようなエンディングの後には謎めいた余韻が残る。
スペイシーなジャズロック調の演奏と、もはやパンクを越えた激烈な調子で叩きつけるヴォーカル・パフォーマンスのコンビネーションによる、煮えたぎる嵐のような傑作。
ヴォーカル主導の即興風のパートがクライマックスの絶叫とともに全体演奏へと収束する瞬間のカタルシス。
せせら笑うように絶え間なく刻まれるエレクトリック・ピアノ(クラヴィネット?)の音が新鮮だ。
ベース・ペダルも用いられている。
構成されすぎない「緩さ」が凶暴さにとって代わるところが特徴である。
4 曲目「The Sleepwalkers」(10:31)
サックスとオルガンによる宗教劇的なスペクタクルを予感させる独特のテーマ。
8 分の 6 拍子をベースに微妙に変化し、あえて不安定さを刻み込むようなところがある。
奇怪なダンスのような波乱含みのオープニングである。
妙な起伏はあるがなめらかでリズミカルなテーマと対照的に、ヴォーカルの声にはシリアスな響きがある。
テーマは微妙に形を変えて渦を巻く。
沈み込むようなオルガンと透明感あるサックスと軽妙なパーカッションなど、音色の対比が巧みに使われる。
サビではサックスがテーマを変奏し、ドラムスも鋭くたたみかける。
ファルセットを使ったハーモニーも現われて、ヴォーカルは一人芝居のように役柄をすばやく入れ代える。
そして、テーマの変奏はいつしかチャチャチャのようなラテン調の軽やかな調子へと変化し、サックス、パーカッションもユーモラスに飛び込んでくる。
この TV ジングル風のラテンのテーマを用いたプレイがしばらく続く。
一転して、シリアスなユニゾンに戻り、オルガンのアルペジオとシンバルを打ち鳴らす音がスペイシーに響く。
タイトなリズムにのったヘヴィなアンサンブルが復活し、演奏は安定した 8 ビートへと移ってゆく。
力強いサックスのリフとオルガンが重厚に響く。
再び激しく歌い上げるヴォーカル。
細やかなオルガンのパッセージがぐるぐると回る。
肉感的なテナー・サックスのテーマが主導権を握り、演奏に安定感と力強さが戻ってくる。
地に足がついた感じのミニマルな展開だ。
SOFT MACHINE 風ですらある。
二つのサックスのブロウがオルガンの和音の轟きと交錯し、またもヴォーカルのアジテーションが始まる。
変則テーマも復活、サックスのオブリガートにまとわりつかれながらヴォーカルは突き進む。
ついにはラテン調もひそかに回顧しつつ、めまぐるしくメロディ/拍子が変化する。
ヴォーカルばかりが注目されるが、各パートの演奏技術もべらぼうだ。
エンディング、全体演奏はシンフォニックな調子を取り戻し、ヴォーカルは泣き叫ぶように訴える。
そして、すべてが泡沫の夢であったかのように、オルガンを中心としたサイケデリックなノイズの渦にすべてが吸い込まれてゆく。
誰も何も覚えていない。
タイトル通り悪夢のように予測不能の展開を繰り広げつつも基本は勇壮でシンフォニックな大作。
独特の変拍子テーマの奇妙な調子が生む不安定感が全編を貫く。
明暗、陰陽、軽重、善悪の変化の相が入り乱れるところに魅力がある。
軽妙なラテン調への大胆不敵な変化もあり。
10 分あまりを一気に駆け抜ける。
ハミルの強烈なアジテーションを、変拍子を駆使した怪奇なテーマと複雑かつパワフルなインストゥルメンタルで支える傑作。
暗く力強く類まれな一体感のある、このグループらしいロックであり、まさに完全復活といえるでき映えである。
4 曲すべてが、それぞれに独特の光を放つ名曲だ。
苦悩に満ちながらも猪突猛進な 1 曲目、シンフォニックな 2 曲目、血を吐くようなアジテーションに絶句の 3 曲目、そして 4 曲目は、狂気のヘヴィネスと軽妙さを激しく往復する野心作である。
唯一残念なのは、CD スリーヴに歌詞が印刷されていないこと。
(CAS 1109 / CASCD 1109)

| Guy Evans | drums, percussion |
| Hugh Banton | organs, bass pedals, bass guitar, Mellotron, piano |
| Peter Hammill | lead vocals, guitars, pianos |
| David Jackson | saxes, flute |
76 年発表の作品「Still Life」。
内省的な歌詞とともに、力強く肯定的なシンフォニック・サウンドが特徴の再結成二作目。
剥き出しの感性とハードなサウンドの調和はかつてない高みを極め、聴きやすさも含めて本当に傑作といえる作品となった。
「Pawn Hearts」と並び最高傑作にあげる人も多いはず。
プロデュースはグループ。
オープニングは、「僕らは皆旅人だ」というメッセージを、清々しくも力強く訴える傑作「Pilgrims」(7:12)。
味わい深い歌詞に加え、繰り返されるファルセット・ヴォイスによるメッセージとともに力を得て翼を広げてゆく誇り高きアンサンブルにも胸を打たれる。
ヴォーカルとオルガンとのやりとりが非常に美しい。
シンフォニックな響きが素直に心に流れ込む。
「Refugee」とともに、道に迷ったときに涙を受け止め、力強く背中を押してくれる作品だ。
あまりに陰鬱なヴォーカルが切々と語りかける「Still Life」(7:24)は、グループの代表作の一つ。
オルガンを背景に密やかに囁きかけるヴォーカルが、伴奏とともにいつしか攻撃的な表情へと変化し、呪いのように言葉を吐き散らしてパワフルなサックスと激しくせめぎあう。
パンク・ロック的な荒々しさをふり撒きながらも、曲調は崇高かつメロディアスである。
その姿はまさに圧巻。
終盤にて凶暴なアジテーションは、再びピアノの調べとともに悩ましく沈み込み、嵐の余韻のような演奏とともに静かに去ってゆく。
明快なクライマックスをもつシンプルな展開にも関わらず、深いドラマを感じさせ感動を呼ぶ。
演奏はヴォーカルにしっかり寄り添い、挑発を繰り返す。
そして、独特のうねりを生んでゆく。
ヴォーカリストとして完成されたイメージを与える傑作。
オルガンが印象的な「La Rossa」(9:52)は、攻撃的で荒んだ曲調にもかかわらずラブ・ソングらしい。
遠回しのほのめかしが余計にエロティックな内容を想像させる。
しかし、つやのあるサックスとオルガンに扇動されるようにハミルは強烈にアジテートする。
荒々しい表情のヴォーカルがリードする演奏は非常に攻撃的だ。
パンキッシュに叫ぶヴォーカルと肉感的でリアルな響きをもつサックスが激しく挑発しあう演奏は、いつのまにかスピードを落として淡々としたビートへとシンクロする。
そして演奏も疲弊したように落ち込んでゆくが、すぐに熱気を取り戻し始める。
オルガンによる 8 分の 6 拍子のリフレインをきっかけに、サックスが暴れ、ユニゾン・リフから荒々しいヴォーカルが復活する。
一体感あるラウドな演奏だ。
アップ・テンポの快調な演奏と渦を巻くようなオルガンのリフレインをリズム/テンポ・チェンジとともに繰り返しながら、演奏は次第に鋭さと速度を上げ、収束へと向かう。
そしてシンフォニックな高まりとともに大団円へ。
躁鬱を駆け巡るヴォーカルとともに緩急自在で前進し続け、長大だが最後までテンションの落ちないハードロックである。
ブギー風のノリのよさもある。
ソプラノ・サックスとピアノによるテーマが美しい「My Room」(8:02)。
抑えた表情で呟くように語りかけるヴォーカル。
ヴォーカルを取り巻いてたおやかに歌うサックスは、痛々しいまでに優美であり、懐かしさにあふれる。
サックスと密やかな歌唱が、あたかも救いの手を差し伸べるように優しく重なりあう。
切々とした調べが次第に胸にしみてくるタイプのバラードだ。
過去の栄華に思いを馳せるときにもれる微笑のように、安らかながらもどこか空疎で現実感のないテーマがいい。
ベース・ペダルとピアノが重いユニゾンを刻み、サックスのアドリヴが次第に空ろな響きを帯びてゆく長いエンディングは、不安感をかき立て、暗く終わりのない旅の道行を示すかのようだ。
過去を振り返れば切なさが胸をかきむしり、未来を見通せば不安に心の行き場がなくなるという暗示のような、美しくも不気味な作品。
初期 GENESIS の諸作と通じる雰囲気がある。
「Childlike Faith In Childhood's End」(12:24)は、フルートの調べと密やかな語りから始まって、サックスとオルガンのバックアップで次第にヴォーカルが力を得て突き進んでゆく大作。
絶望的な状況を力強く打開しようとする歌詞は、PINK FLOYD にも似た深刻さを持ち、演奏はヴォーカルとオルガン、サックス、ドラミングが一本の流れとなり、しなやかに、ドラマチックに展開する。
演奏がヴォーカルにエネルギーを注ぎ、ヴォーカルが演奏を扇動する。
そのスパイラルに胸が躍る。
テーマをエレキギターが引き継ぐと、最初のクライマックスだ。
たゆとうような緩徐楽章、崇高な静けさのブリッジを経て、サックスのファンファーレとともに再びドラマは上昇するベクトルを得る。
しかし、ストレートに高潮には向かわず、混沌とした足踏みのような演奏を繰り返しながら、次第に勢いを取り戻してゆく。
ふと気づけば、メイン・ヴォーカルが復活し、乾ききった声がアジテーションを繰りかえしている。
喉も裂けよと叫ぶハミルに引き金を引かれ、気高くエネルギッシュな演奏は作品世界の緊張をみごとにキープしつつ、アナーキーなヴォーカルに導かれて宇宙へとしみ出すようにシンフォニックに広がってゆく。
エンディングのアンサンブルの力強さ、そして救済を迎えるエンディングの感動。
今までハミルの歌に現れたいくつかのキーワードがこの作品ではすべて現れ、彼の精神世界の総決算的な作品となっている。
初期を思わせる暗黒のシンフォニック・ロック、そしてリアルな魂の物語である。
畢生の大作。
頑固なまでに前衛を貫く姿勢と楽曲に込められたエモーションがバランスし、自然な流れをもちながらも崇高なまでの力に満ちた音楽となった大傑作。
奇を衒うような不自然さは霧消し、撚り合わされたすべての音が必然、一貫した流れが感じられる。
そして、結果的に、初期のシンフォニックなサウンドに近づいている。
興味深いことだ。
ハミルのヴォーカルの表現力は、囁くようなバラードから烈しくアジるハードロックまで、すべてにわたってほぼ円熟に達し、モノクロームの鈍い輝きをもった曲に生命を吹き込んでいる。
そしてインストゥルメンタルも、パワフルに前進する演奏からメロディアスにヴォーカルと絡む演奏まで、必要十分の音を配置している。
贅肉を落とし研ぎ澄まされたトゥッティのなんとすばらしいことか。
ダークでシンフォニックかつ手折れそうなデリカシーを感じさせる名作。
音が明晰である。
(CAS 1116 / CASCD 1116)
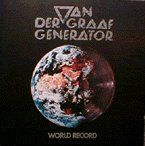
| Hugh Banton | manuals & pedals |
| Guy Evans | drums, cymbals, percussion, fingerpop |
| Peter Hammill | vox, Meurglys III, Wassisttderpunktenbacker |
| David Jackson | alto & tenor & soprano sax, accountrements, flute |
76 年発表の作品「World Record」。
苛立つように猛るヴォーカルを中心に凶暴で攻撃的な演奏が冴えわたり、新たな方向を指し示す好作品。
内省的な部分や切実なメッセージ性が感じられた前作と対照するのは、もう一度怒りを自らかきたてるような、エスタブリッシュされたものへと遮二無二反発するような荒々しさ、そしてその挙句の虚脱寸前の表情である。
この荒々しさをパンクといってしまっていいかどうかは分からないが、自らの心をかきたてて出てきたロックの根元にある衝動のようなものだと思う。
ハミルのエレキギターとともに、神々しくきらめくシンセサイザーも導入されて、インストゥルメンタルにはあたかも黒光りするかのような過激な味わいが備わっている。
歌唱表現の比重を高めた前二作から、改めて器楽の充実へと揺り戻した感もあり。
ヴォーカルの表情には、さまざまなスタイルの実験を経て辿りついた、一種独特の虚無感すら感じられる。
それだけに最終曲の慈愛の響きがいっそう美しい。
プロデュースはグループ。
1 曲目「When She Comes」(7:59)
ジャズ調のスウィンギーなリズムとともに、サックス、フルート、ハーモニウムらによるフリーなジャム・セッションから始まる。
次第にサックスのリフへと収束し、荒々しくもファンキーなヴォーカルが入ってくる。
アグレッシヴな歌唱を、ジャズ風のテーマを中心に、その発展型であるサックスの力強いブロウと、オルガンによるシンフォニックなオブリガート/伴奏が取り巻き、全体演奏のリフが強烈に攻めたてる。
ギターのコード・ストロークも聞える。
ドラムスの 2、3 拍目のアクセントもユニークだ。
間奏部分では、ワイルドなサックスのソロとともに、控えめながらも、泡立つような金管楽器風のシンセサイザーが奏でられている。
冒頭と同じくサックスのリフの周辺に音が集まり始め、後半が始まる。
ここをぐっと引き締めるのは、意外にもジャジーなピアノのストロークである。
歯をむき出すようなヴォーカル、オルガン/管楽器によるまろやかにしてパワフルな演奏が、一体となって高まり、去ってゆく。
パンキッシュなブギー調が貫くアグレッシヴな作品。
歌詞の主題は、幽霊のような女性に魅入られた男という、象徴的かつユーモラスなもの。
この歌詞のせいか、ジャズ風のリズムを用いたエネルギッシュにしてシンフォニックな演奏という得意技のミクスチャー・スタイルに、どこか逸脱した奇妙なタガの緩みが感じられる。
ヴォーカルは、一貫してクレイジーで噛みつくようにアグレッシヴ。
要所でたたきつけるようなギターが入る。
2 曲目「A Place To Survive」(10:02)
淡々と刻まれるリズムに、焼けつくようなオルガンとサックスによるテーマが重なってゆくオープニング。
サム・テイラー風の下品なサックスが印象的だ。
ダルでロウキー、無表情な演奏が、かえって波乱を予感させる。
オブリガートで気まぐれに奇声をあげるオルガン、そして、ノリ切らない演奏への怒りを噛み殺すようなヴォーカル。
サビでは、我慢の限界のように荒々しく吠え立てる。
間奏は、サックスがヘヴィで垢抜けない第二テーマを打ち出し、ひずんだオルガンが煮えたぎるように絡みつく。
デュオにもかかわらず、ハーモニーは破綻しかけている。
サックスは、スタッカートのテーマを、荒々しく官能的になぞる。
すべてに、ブルージーというのとも違う、けだるくやるせない感じがあり、そこから、きわめて不機嫌で凶悪な空気が立ち昇っている。
激しく挑発するヴォーカルとオブリガートによる猛々しい一人かけあいを経るうちに、演奏は力をため込み、サックスによる力強い演奏が始まる。
サックスに対抗して湧き上がるのは、刃物のようなきらめきを一閃させるシンセサイザー。
再び、ぶつぶつと煮えたぎるオルガンとサックスがリードするヘヴィな演奏でバランスを取ろうとするが、一気に激しいドラムス連打が巻き起こって、サックスとオルガンが身悶えしながら金切り声を上げる。
どう見ても破裂寸前、破綻寸前である。
そして、とどめを刺すのは、究極の「ドレミファソラシド」ギター。
狂乱し、呼吸困難で失神寸前のサックス、唐突な 3 連フレーズで渦を巻くオルガン、修羅の巷をえぐり取るようにぐいぐいと突き進むドラムス。
エンディングでは、脱力したかのようにヴォリュームを落とし、ベースだけが唸りを上げ、そして、すべてが崩れ落ちてゆく。
逞しくいななくサックス、煮えたぎるオルガンがリードするヘヴィなブギー調の演奏と凶悪なヴォーカルによる、殺伐たる雰囲気が特徴のハードロック。
ジャジーなヘヴィ・ロックという稀有の作風であり、70 年代初頭から英国の数々のグループが試みたジャズ、ブルーズ、R&B の融合を、きわめて個性的な形で完成させたといっていいだろう。
FREE にジャズの要素を加えたら、こういう感じになったかもしれない。
あるいは、70 年代後半ヴァージョンの「21世紀の精神異常者」。
エンディングへ向け、ナンセンスにして狂乱するインストゥルメンタルが圧倒的な破壊力で突き進む。
まさに、乱調美の極致である。
3 曲目「Masks」(6:56)
メロディアスに歌うサックスをほてるように熱いオルガンが支える、おだやかなイントロダクション。
ここまでの展開からして、ここでこういう優しげな音に出会えるとは思っていなかった。
狂気の果ての慈愛の響き、PINK FLOYD 的ともいえそうだ。
ヴォーカルは、歌い疲れた後のザラついた声ながら、前曲までのアジるような調子が嘘のように淡々とした表情を見せる。
おだやかというよりは気だるげであり、一暴れしたあとの虚脱状態のようだ。
それでも、歌い込む力はまったく失われていない。
さわったら火傷しそうな、危険な感じが残っている。
表現の懐が深い。
オルガンはそんなヴォーカルにしっかりと付き随っている。
珍しくギターのパワー・コードが口火を切るサビでは、ヴォーカルにアジテーション調が復活する。
シンセサイザーのメタリックなアタックがグラマラスなアクセントになっている。
間奏はサックスでスタート。
やがて、バッキングのトゥッティとサックス・ソロが乖離し始めて気まぐれなプレイが渦を巻きだす。
混沌を回収するかのように、シンセサイザーがシンフォニックな金管調の響きでムードを一転させ、メイン・パートへの回帰をうながしてゆく。
間奏を経て、再び、荒々しさの中に空しさを漂わせるメイン・ヴォーカルへ。
ひずんだギターとオルガンが、ヴォーカルとともに、高く力強く駆け上がる。
ヴォーカルもパワーを取り戻し、豪快に主張を強める。
荒々しくも繊細な表情も見えるバラード。
序盤と終盤のメイン・パートは、エリック・クラプトンのバラードのようだ。
ギターとシンセサイザーという新たな音の新鮮な質感、そしてヴォーカルの微妙な表情の変化が、興味深い。
力強く一体となったアンサンブルは今まで通り、ただし、新たな境地へと進む可能性を示しているようだ。
個性派ポップスといっていい内容である。
ジョン・レノンを思わせる瞬間もある。
4 曲目「Meurglys Ⅲ」(20:47)
キーボードとフルートが気まぐれにフラフラと揺れ動くオープニング。
ほのかに耽美、そしてミステリアス。
サックスのリードによって、演奏は変拍子によるギターとオルガンのしなやかなメイン・テーマへとまとまってゆく。
気高さを取り戻したリード・ヴォーカルはテーマをなぞる朗誦。
反復のたびに、さまざまな音が飛び出したり引っ込んだりと、テーマに微妙な変化をつけながら、刻み込むような演奏が続いてゆく。
全体の雰囲気を支える、ドラムスのリズムの取り方がみごとだ。
イラつくようなギターのテーマ、ピアノの乱れ打ち、渦を巻くオルガン。
4 分付近で、演奏はいったん勢いを失い、浮遊するような、呆然と立ち尽くすような様相を見せる。
虚脱するヴォーカル、深い空隙を意識させるオルガンの響き、鼓動のようなタム、ベース。
シュアーなドラム・ビート、静かにしかし朗々と歌うサックス、訥々としたギターらによって、演奏は次第にベクトルを取り戻し、スローながらもアドリヴ調の展開が続いてゆく。
哀しげにささやくサックス、そして時おり、気まぐれに、素っ頓狂といっていいほどの勢いで牙をむくギターとオルガン。
ギターとオルガンが刺激しあい、ユニゾンで暴れる。
そして、一気にギターとサックスによるシャープなインタープレイが産み落とされ、演奏はタイトな調子を取り戻して走り始める。
変則的なリズムでも難なくみごとに一体感を見せる。
ハミルは声色と表情を凶暴に変化させ、狂おしく絶叫する。
しだいに高まるテンション、そして刺々しくキナ臭い空気。
ギターが叩きつけ、オルガン、サックス、ドラムスが応じる変拍子テーマのトゥッティは狂おしく、渦を巻くように続く。
一瞬のブレイク。
そして激しいキメの一閃、サイレンを思わせるオルガン、ギター、サックスによる新たな荒々しいトゥッティが燃え上がる。
今度はサックスの勢いが強く、フリー・ジャズ的な破壊力が中心だ。
シンセサイザーのメタリックな残響を最後にすべては弾け飛ぶように消える。
初期の KING CRIMSON を思わせるダイナミックで生々しいアンサンブルだ。
暗転、そして虚脱したギターの弾き語り、モノローグ。
オルガンとドラムスが静かにレゲエのリズムを刻み始め、ギターとサックスが官能的な表情でリードを取る。
あまりに意外なレゲエへの発展だが、不思議なことに脈絡が感じられる。
変化の相に一貫した何かがある。
軽妙なサックスときまぐれなギターによる饒舌なやりとり、キレのあるクランチなオルガンの和音。
ジャジーな安定感のあるサックスに対し、ギターは素人臭さ故のパンク・テイストの魅力で迫る。
何ともいえぬミスマッチの妙あり。
最後まで、軽妙にして腰にくるグルーヴもある演奏が延々と。
変拍子による危ういテーマを巡って即興風の展開がこれでもかと繰り広げられる、全力にして脱力した超大作にして問題作。
自発的な展開を力尽きるまで繰り返した結果の作品と思われる。
ギターを中心にした、フリージャズではない、ロックなドシャメシャであり、ヘタウマの極北であり、VdGG による即興演奏の試みである。
終盤のバントンのオルガンによるレゲエ・ビートが、あまりにナチュラルでびっくりする。
最後は、これ以上発展できず、力尽きてゆくような印象である。
短期間で習得したといわれるハミルのギターが大きくフィーチュアされている。
歌詞にも人と話すのが不得手になったとあり、それほどギターに打ち込んだということなのだろう。
下手は下手だが、凄みのある下手さ加減である。
最終曲「Wondering」(6:35)
シンガーとしてのオーセンティックな力量を正面から見せつけるハミルを、キーボード、管楽器と丹念なドラムスらが支えるドラマチックな大感動作。
暗黒世界にほのかな反射光を放つシンセサイザーとオルガン、フルートらによるアンサンブルは、GENESIS にも匹敵するクラシカルで幻想的な美しさをもつ。
そこへ、ヒューマンな暖かさと厳格さを併せもつハミルのヴォーカルが加わり、さらに重厚かつ荘厳なイメージを付与している。
「祈り」や「神」といった、人知を超えたものも感じられる。
巧みに盛り上げるドラムスは特筆もの。
リヴァイアサンを打ち滅ぼさんと、水平線からめくるめく光とともに立ち上ってくる天上の進軍ラッパの響きのように、歓喜と祝福に満ちた演奏であり、曲調は賛美歌といって差し支えないだろう。
未来への希望を象徴するような輝きを孕むシンフォニックな響きが、いつまでも余韻を残す名曲だ。
弦楽系の音や冒頭のフルートのような音など、メロトロンも使われているようだ。
シンセサイザーに象徴される神々しさ、気高さの演出もみごと。
完成から破壊/再構築へと止むことなく前進を続けようとしたバンドの姿を活写した作品。
すでに完成されていたヴォーカル中心の楽曲に、ギターやシンセサイザー、ヴォーカルの表情など新たな要素を放り込み、既存と新規が軋みをあげながらも突き進む。
その姿は感動的だ。
手持ちをさらに洗練し、新たなものを積極的に取り込むのも、無限の荒野へと踏み出すためである。
また、最終曲は、このアルバムで頂点を極めることを予見した上での、リスナーへの最後のメッセージとも取れるような胸を打つ名曲である。
(CAS 1120 / CASCD 1120)

| Graham Smith | violin, viola |
| Nic Potter | bass |
| Peter Hammill | vocals, guitars, keyboards |
| Guy Evans | drums, percussion |
| guest: | |
|---|---|
| David Jackson | saxes inserts |
77 年発表の作品「The Quiet Zone/The Pleasure Dome」。
さまざまな事情で脱退したヒュー・バントン、デヴィッド・ジャクソン(一部ゲスト参加)に代わる器楽担当として、レーベル・メイトである元 STRING DRIVEN THING のヴァイオリニスト、グラハム・スミスを招き、グループ名も「VAN DER GRAAF」に変更する。
新布陣による起死回生を図ったアルバムである。
(グラハム・スミスとは、ハミルのソロ作「Over」で共演済み)
また、ニック・ポッターも久々に復帰。
ヴォーカルを中心にした引き締まった演奏による作品が主であり、オルガンによる奥深い音空間がないことで、バンドの作品というよりも、ハミルのソロ作というべきイメージが強い。
前作、前々作よりもエレキギターを抑え、アコースティック・ギター、アコースティック・ピアノによる弾き語りも多い。
常にヴォーカルを取り巻くエレクトリック・ヴァイオリンは、オルガンとは異なる独特の奇妙な(一種コミカルな)味わいをもっており、シリアスなヴォーカルとの微妙な対比、緊張感があるようだ。
それにしても、本作を前にして改めて感じられるのは、彼らの音楽が、プログレだ、パンクだといったレッテルとはほとんど本質的に無関係であることだ。
デヴィッド・ボウイほどスタイリッシュではないが、ナルシスティックな現代の象徴詩人としての存在感は、勝るとも劣らない。
ハミルの歌声に魅せられたファンにとっては、何の問題もなく聴くことのできる内容である。
本作が最後のオリジナル・スタジオ・アルバムとなり、グループは 78 年に解散。
プロデュースはピーター・ハミル。
各曲も鑑賞予定。
「Lizard Play」(4:29)
「The Habit Of The Broken Heart」(4:40)
「The Siren Song」(6:04) バラードの名品。
「Last Frame」(6:13)
「The Wave」(3:14)
「Cat's Eye / Yellow Fever(Running)」(5:20)
「The Sphinx In The Face」(5:58) ハミルらしいアコースティック・パンク。軽妙なノリもある怪作。リズムも乱れ捲くり。クライマックス。
「Chemical World」(6:10)
「The Sphinx Returns」(1:12)前々曲のリプライズ。
(CAS 1131 / CASCD 1131)

| Graham Smith | violin |
| Nic Poter | bass |
| Peter Hammill | vocals, guitars, keyboards |
| Guy Evans | drums |
| Charles Dickie | cello, keyboards |
| David Jackson | saxes, flute |
78 年発表の作品「Vital / Van Der Graaf Live」。
解散後発表されたライヴ・アルバム。
怒りとともに絶唱を振り絞るヴォーカルを筆頭に、エレキギター、ヴァイオリン、チェロ、ベース、すべての音がぎざぎざの表面を剥き出しにしてささくれ立っており、傷を負わずには近寄れない。
ハードロックの直線的な運動性やブルージーな泣きは皆無であり、いわゆるノリ、グルーヴとも程遠い。
どちらかといえばサイケデリック時代を思い出させるダウナーで崩壊しかけた演奏であり、ノイジーでとげとげしい音の向こうに SSW 風のデリカシーが見えなくもない。
(ファンとしてはこの「綱渡り」的な演奏がたまらない)
また、知性はあるのに極端に自己陶酔型だったり自己滅却型だったり、とにかくモラルの箍が怪しい。
つまり、パンクである。
ヴァイオリンが前面に出る即興パートでは、中後期 KING CRIMSON と共通した味わいがある。
オリジナル LP は、二枚組。
VIRGIN 盤 CD は、旧 C 面「Sci-Finance」と旧 D 面「Nadir's Big Chance」の二曲が収録されていない。
日本盤 CD は、オリジナル LP と同じ曲編成です。
「Ship Of Fools」(6:43)シングル「Cat's Eye」B 面曲。
神秘的な東洋風味、ヘヴィなファズ・ベースなどヴァイオリンがあった 72 年くらいの KING CRIMSON に通じる。
「Still Life」(9:42)同名アルバムより。バッキングはあるがアカペラのイメージ。
それだけ歌唱が輝いている。
前半のチェロとヴァイオリンの二声によるヨレた伴奏も奇妙な味があり悪くない。
「Last Frame」(9:02)アルバム「The Quiet Zone/The Pleasure Dome」より。
クラシカルなヴァイオリンのプレイをフィーチュアした重厚なるバラード。
狂気の発露を表現するのにヴァイオリンがうってつけであることを再確認できる。もはやりズムはあってなきが如し。
「Mirror Images」(5:50)ハミルのソロ作「PH7」より。
フォーク風の繊細で切実なバラード。ファルセット、だみ声中低音、絶叫など完全なハミル節。
ジャクソンのか細いフルートが現れる。
「Medley」(13:41)
「Plague Of Lighthouse Keeper's」アルバム「Pawn Hearts」より。
ピアノとヴァイオリンによるオープニングが美しい。
「The Sleepwakers」アルバム「Godbluff」より。
曲名の綴りが元曲とやや異なるのは意図的か、単なる間違い(L が抜けた)か。
何にせよ、軽妙さすら感じさせる大胆な展開の名曲である。
「Pioneers Over 'C'」(17:00)アルバム「H To He Who Am The Only One」より。
ヴァイオリンのピチカートを交えたイントロダクション含め、オリジナルよりも雅楽風。
ただし、轟音ファズ・ベースがリフをリードし始めるところからは一気にガレージ・ロックへ。凶暴でヨレヨレで、カッコいいです。
リズムレスの即興風のパートでは、エレクトリック・ヴァイオリンの存在感が強い。
11:20 からの爆発は完全にパンク。
「Door」(6:00)新曲。MC あり。
「Urban part 1.- Killer (section)- Urban part 2.」(8:20)新曲。
中間部はアルバム「H To He Who Am The Only One」より。
(CVLD 101 / CVLCD101)

| Peter Hammill | vocals, guitars on 2, organ on 8, piano on 1,3,7,9,10, bass on 4 |
| Guy Evans | drums on 1-4,6-10 |
| Hugh Banton | organ on 6,7,9, bass pedals on 1,3 |
| David Jackson | saxes on 1-4,6-10, flute, piano on 4 |
85 年発表の作品「Time Vaults (Unreleased tracks 1971-75)」。
解散期の録音も含まれる、VdGG 時代の未発表曲集。(81 年発表当初はカセット・オンリーのリリースだった)
音質はブートレッグ並みであり、ヴォーカルとサックスの一部がオーヴァー・ダビングされている。
後半の迫力が音質を補ってあまりある作品だが、カタログ志向のヘッドフォン・フリークには、あまりお薦めできない。
イマジネーションとユーモアに富んだ中毒リスナーにのみ、贈られたプレゼントである。
「Roncevaux」は、オリジナル・アルバム収録曲と遜色ない濃密な作品。
深みのあるハミルのヴォーカルとサックスが迸る、VdGG らしい茨の心を抱いた熱きバラードである。
「It All Went Up」は、ホルストの火星を思わせる狂乱のインストゥルメンタル。
インストゥルメンタル「Faint And Forsaken」も、オリジナル・アルバム収録曲のモチーフとなっていると思う。
小曲だが圧倒的な迫力である。
ハミルのソロ作品「Black Room」も傑作。
CD ジャケットは二種類ある。
各楽曲のクレジット、録音日時などはあまりあてにならなそうだ。
近年のインストゥルメンタル・アルバムなどからも想像できるように、こういった未完成品、デモ音源は死ぬほどあるのではないだろうか。
欠片でもいいから GENTLE GIANT のようにかき集めてアーカイヴ作としてまとめてほしい。
「The Liquidator」(5:24)ヴォーカル・ダビング。73 年録音。超力作。なぜ発表されなかったのかハミル本人も首をひねっている。
「Rift Valley」(4:40)ヴォーカル・ダビング。75 年録音。すでにパンク、いやパンキッシュな呪詛。
「Tarzan」(2:09)74 年録音。コミカルなインストゥルメンタル。ベース・ペダルとサックスのお下劣なリフが強烈。
「Coilnight」(4:12)サックス・ダビング。即興。75 年録音。前曲の発展形か、凶暴なインストゥルメンタル。後期の作品で使われていると思う。
「Time Vault(Miscellaneous)」(3:33)カットアップ録音のコラージュ。断片の連続だが、不思議なことに、心地よい。
「Drift(I Hope It Won't)」(2:40)72 年録音。バントン作のオルガン中心のインストゥルメンタル。
「Roncevaux」(6:55)ヴォーカル・ダビング。72 年録音。フルートも聴こえる。
「It All Went Up」(4:07)71 年録音。ハミルがキーボードを弾いているとのこと。メロトロンのような音もする。サックス、ドラムスとのトリオ。弩サイケな混沌、だがカッコいい。
「Faint And Forsaken」(2:45)即興。75 年録音。カッコいい。フリージャズ、サイケ、パンク・ロックを貫く。
「Black Room」(8:52)72 年録音。もう一つの力作。詩人のアジテート。
(SS 3 / PHRL014CD、CDTB 106)

| Peter Hammill | vocals, guitars, keyboards |
| Guy Evans | drums |
| Hugh Banton | organ, bass pedals, guitar, Mellotron, piano |
| David Jackson | saxes, flute |
| Nick Potter | bass |
86 年発表の作品「First Generation」。
セカンド・アルバムから三枚の、いわゆる前期の作品からのベスト・コンピレーション・アルバム。
シングルのみだった「Theme One」が聴けるのがうれしい。
傑作を次々と生んだ初期の作風を見渡すにはお薦め。
「Darkness (11/11)」安定の苦悩する歌ものシンフォニック・ロック。代表曲。
「Killer」血の匂いのする歪な愛の物語。
「Man Erg」青春の苦悩が沸き立つ自己探求の物語。バラードだが演奏はデフォルメの効きが半端ない。
「Theme One」インストゥルメンタル。ジョージ・マーティン作。暗黒を貫くシンセサイザーのきらめきが印象的。Cozy Powell もやってましたね。BBC RADIO 1 の開局テーマ。
「Pioneers Over C」歌詞内容に感情移入できるかどうかは分からないが、強引すぎる器楽の展開に独特の説得力があるのも確か。エンディングの到達点がまったく予想できないこのグループの大作のスタイルを決定付けた作品だ。
「A Plauge Of Lighthouse Keepers」演劇風の巨大な組曲。大海を彷徨うオランダ人を導くのが灯火ならば、灯台守は誰が導くのか。傑作。
「Refugees」天上遥か響き渡る慈愛の賛歌。
(COMCD 2)

| Peter Hammill | vocals, guitars, keyboards |
| Guy Evans | drums, percussion |
| Hugh Banton | organ, bass pedals, guitar, Mellotron, piano |
| David Jackson | saxes, flute |
| Nic Potter | bass |
| Graham Smith | violin, viola |
86 年発表の作品「Second Generation」。
再結成後から四枚の、いわゆる後期の作品からのベスト・コンピレーション・アルバム。
常に音楽的なチャレンジを希求する姿勢に感動。
「過渡」や「不安定」や「未完成」はこのグループの音楽への賞賛の言葉である。
「The Undercover Man」ストーリー・テラーであるヴォーカルを中心にすえた作風の出発点。
「Scorched Earth」クライマックスに一気に駆け上がる疾走感満点の傑作。
「Sleepwalkers」夢魔の跳梁か、さえずるような管楽器が妖しさを演出する。ラテンへの逸脱が大胆。
「Pilgrims」感動のバラード。
「Still Life」生と死を巡る懊悩のドラマ。傑作。
「When She Comes」パンク・ジャズ的ガレージ・プログレの傑作。
「Siren Song」王道バラード。ドラマの作り方がみごと。
「Cat's Eye - Yellow Fever (Running)」弦楽を生かしたスリリングな ESPERANTO 風の作品。
「Wondering」感動のバラード #2。
(COMCD 3)

| Peter Hammill | vocals, guitars, keyboards |
| Guy Evans | drums |
| Hugh Banton | organ, bass pedals, guitar (tracks 1-8) |
| David Jackson | saxes, flutes (tracks 1-8, 10) |
| Keith Ellis | bass (tracks 1, 2) |
| Nic Potter | bass |
| Graham Smith | violin (tracks 9, 10) |
| Charles Dickie | cello, keyboards (track 10) |
93 年発表の作品「I Prophesy Disaster」。
二つの時代をカヴァーする、前出二枚のベスト・アルバムの補遺プラスシングル曲集。
Virgin Universal シリーズ中の一作である。
「Afterwards」アルバム「The Aerozol Grey Machine」より。
「Necromancer」アルバム「The Aerosol Grey Machine」より。
「Refugees」シングル・ヴァージョン。
フェード・インや華麗なストリングス、チェンバロの参加などアレンジが異なる。
アルバム・ヴァージョンは「The Least We Can Do Is Wave To Each Other」に収録。ポッターのベースラインになかなか味があることを再発見。
「The Boat Of Millions Of Years」シングル「Refugees」の B 面。
初 CD 化。
(LP ではベスト盤「68-19」(Charisma CS2)に収録)第二作以降の素材になっていそうな作品だ。
「Lemmings(including Cog)」アルバム「Pawn Hearts」より。本アルバムではその圧倒的な密度で他曲を凌ぐ存在感を示している。
「W」シングル「Theme One」の B 面。ソロ作品風の異形美弾き語りバラード。エキセントリックな表情と捻れた演奏で迫る。係り結びや鑑定を徹底して拒否する。
「Arrow」アルバム「Godbluff」より。ジャズロックとパンクを捻じ伏せた傑作。サックスのエフェクトが強烈。
「La Rossa」アルバム「Still Life」より。エキセントリックな変拍子ブギー。邪悪で耽美でグルーヴィ。高密度でなおかつ柔軟性に富む演奏が GENESIS と共通する。
「Ship Of Fools」シングル「Cat's Eye」の B 面。
スタジオ・ヴァージョン。
吐き捨てるようなヴォーカルとエレキギターが強烈なグラム系ハードロック。
「Medley(parts of "A Plague Of Lighthouse Keepers" and "Sleepwalkers")」アルバム「Vital /Van Der Graaf Live」より。
(CDVM 9026)

| Peter Hammill | vocals, guitars, keyboards |
| Guy Evans | drums |
| Hugh Banton | organ, bass pedals, guitar |
| David Jackson | saxes, flutes |
94 年発表の作品「Maida Vale (The BBC Radio One Sessions)」。
71 年から 76 年にかけての BBC スタジオ・ライヴ音源集。
曲目はすべてオリジナル・アルバム収録。
「Darkness」(7:17)寂寥感のあまり重苦しいエモーションを爆発させる名曲。
「Man-Erg」(11:00)崇高。
「Scorched Earth」(9:40)アジテートするテーマに大胆なリズム・チェンジをシンクロさせた 70 年代中盤の新感覚プログレの傑作。
「Sleepwalkers」(9:58)脈動するスタッカートのテーマを無理矢理なぞる怒りにまみれたモノローグ風のヴォイス、軽妙なるラテン・タッチとのコントラスト、忙しない陰陽の反転と幻想性、やがて一つのベクトルが生じて終盤に向けて力強い歩みが続く。
「Still Life」(7:20)
「La Rossa」(10:00)
「When She Comes」(8:08)
「Masks」(7:22)
(SFRSCD 064)

| Peter Hammill | vocals, guitars, keyboards |
| Guy Evans | drums |
| Hugh Banton | organ, piano, bass pedals, bass |
| David Jackson | saxes, flutes |
| Keith Ellis | bass |
| Nic Potter | bass |
| Graham Smith | violin |
| Charles Dickie | cello |
2015 年発表の作品「After The Flood VAN DER GRAAF GENERATOR At The BBC 1968-1977」。
「Maida Vale (The BBC Radio One Sessions)」以来の BBC 音源。
1968 年から 1977 年までの「Top Gear Sessions」、「Sound Of The 70s Session」、「BBC Radio One John Peel Concert」などの番組から。
ハミルのソロ作からの「Vision」、および「ManErg」、「W」、「Killer」、「A Plague Of Lighthouse Keepers / Sleepwalkers"」らの未発表音源あり。
曲ごとの音質の差が大きい。CD 二枚組。
「People You Were Going To」(3:29)グループ初録音となったシングル盤。後にソロ作「Nadir's Big Chance」にも収録。68 年「Top Gear Sessions」より。
「Afterwards」(4:41)第一作収録。68 年「Top Gear Sessions」より。
「Necromancer」(4:08)ここまでベースはキース・イーリス。サックスはなし。第一作収録。68 年「Top Gear Sessions」より。
「Darkness」(6:49) ここからジャクソン参加。第二作収録。70 年「Top Gear Sessions」より。
「After The Flood 」(10:56)芸風を固めた最初のアヴァンギャルド大作。ここまでベースはニック・ポッター。第二作収録。70 年「Top Gear Sessions」より。
「ManErg」(11:08)ここからはベースはバントンのペダル、不動の 4 人体制。第四作収録。71 年「Sound Of The 70s Session」より。
「Theme One」(2:56)シングル盤。インストゥルメンタル。フェード・アウトがカッコいい。71 年「Sound Of The 70s Session」より。
「Vision」(3:13)「Fools Mate」収録。71 年「Sound Of The 70s Session」より。
「Darkness」(7:15)第二作収録。71 年「Sound Of The 70s Session」より。
「ManErg」(10:37)第四作収録。71 年「BBC Radio One John Peel Concert」より。
「W」(5:08)シングル盤。「Theme One」の B 面。71 年「BBC Radio One John Peel Concert」より。
「Killer」(8:09)ブチキレ気味のハミルがカッコいい。第三作収録。71 年「BBC Radio One John Peel Concert」より。
「Refugees」(6:17)第二作収録。71 年「John Peel Session」より。
「Scorched Earth」(9:40)第五作収録。75 年「John Peel Session」より。
「Sleepwalkers」(9:59)第五作収録。75 年「John Peel Session」より。
「Still Life」(7:19)第六作収録。76 年「John Peel Session」より。
「La Rossa」(9:56)第六作収録。76 年「John Peel Session」より。
「When She Comes」(8:09)第七作収録。76 年「John Peel Session」より。
「Masks」(7:23)第七作収録。76 年「John Peel Session」より。
「Cat's Eye / Yellow Fever」(4:44) ここからは、ベースはニック・ポッター、チェロはチャールズ・ディッキー、ヴァイオリンはグラハム・スミス、バントン、ジャクソンは不在。第八作収録。77 年「John Peel Session」より。
「The Sphinx In The Face」(5:32)第八作収録。77 年「John Peel Session」より。
「(Fragments Of) A Plague Of Lighthouse Keepers / Sleepwalkers」(9:28)第四/五作収録。77 年「John Peel Session」より。
(472 210-3)
雑談。
僕は、まず初期のベスト盤から入って、「World Record」、「Pawn Hearts」の順で聴いていった。
第一印象では、普通ならギターが出るような場面で代りにサックスがふんばり、初期 KING CRIMSON にも似た、渦を巻くような曲調になるところがおもしろいと感じた。
独特の暗い雰囲気といわゆる即興とも異なるグループの一体感から成るひきずるようにヘヴィーな演奏、そして暗いが艶のあるヴォーカルは、いかにもブリティッシュ・ロックらしいとも思った。
ただ、彼らの音楽をロックと既定してしまっていいのだろうか、という思いもある。
彼らの音楽は、ユニークなテーマをもつ詩歌を強力な器楽が取り巻くスタイルであり、その器楽も主題を怪奇に彩る以外は自己主張というにはあまりに衝動的で過激なものだ。
曲構成はシンプルなようで複雑であり、総体としては前衛音楽といって間違いないものである。
ロバート・フリップが参加しているアルバムがあるせいか、KING CRIMSON と並べて演奏のヘヴィさを語られることが多いような気がする。
しかし、両グループには大きな違いがある。
このグループは、KING CRIMSON ほど作品毎にさまざまな顔を見せてはくれないし、演奏技術そのものをさほど重視してもいないようだ。
とにもかくにも、ハミルの思いと物語をどうやったら効果的に伝えられるか、が作曲と演奏の力点のようである。
詠唱に耳を傾けないリスナーがいたならば無理矢理にでも耳に捻じ込むためにエネルギッシュな演奏を繰り広げる、いわば過激な詩人のパフォーマンスなのだ。
PINK FLOYD には、詩人にして意識家のロジャー・ウォーターズがいて、パーソナルな思い入れを延々と作品のテーマにしていたが、デイヴ・ギルモア以下のメンバーのプロ根性が娯楽としての音楽というスタンスでそれとバランスを取り、結果としてセールス的にはとてつもない成功を収めた。
VDGG に、このギルモアにあたる人物がいたのかどうかは知らないが、こちらはコマーシャルな成功を収められずにいったん解散してしまう。
しかし、リーダーであるハミルは、コマーシャルな成功とは無縁なままに創作意欲のままに次々とソロ・アルバムを製作し、自分の思いを延々と歌い続けている。
成功するか否かに係わらず、このグループの音楽の成り立ちからいって、解散は必然だったのかもしれない。
しかし、それでもなおグループとしてもっと活動していたらどうなっていたのだろうという思いを捨て得ない。
ハミルのセンスからして、さらなる傑作が生まれたのではないだろうか。
ハミルの唱法は、ささやくように語りかけるかと思えば、激しくアジり倒す、ファルセットを使うなどきわめて多彩なものだ。
役柄に徹した演劇的な表情も見せる。
ただし、あくまで優れた声質を活かした本格的なイメージを与えているところが、この人の特徴だ。
ピーター・ゲイブリエルが、声量と声質をカヴァーするためもあって演劇的なスタイルを取り入れたのとは、少し事情が異なる。
ゲイブリエルのフォロワーがたくさんいるのに対して、ハミルのスタイルがさほど明らかには受け継がれていないのは、そのオーセンティックな歌唱を真似ることが難しいためだろう。
もっとも、激しくアジるスタイルが、初期のパンク・ロッカーに影響を与えてはいるようだ。
ファンの願いが届き、2005 年遂に復活。来日。
