
| Fred Frith | guitars, violin, viola, piano, voice |
| Tim Hodgkinson | organ, piano, alto sax, clarinet, voice |
| John Greaves | bass, piano, whitsle, voice |
| Chris Cutler | drums, toys, piano, whitsle, voice |
| Geoff Leigh | saxes, flute, clarinet, recorder, voice |
イギリスのアヴァンギャルド・ロック・グループ「HENRY COW」。 68 年結成。「SLAPP HAPPY」との融合/分裂を経て 78 年まで活動。 作品は五枚。 解散後も、各メンバーが旺盛な活動を世界規模で続ける。 複雑な作曲と即興の交差、室内楽的アンサンブル、現代音楽的アプローチを特徴とする真の前衛ロック。 RIO 運動の原点。 Henry Cowell という作曲家がいましたが、何か関係はあるのでしょうか。

| Fred Frith | guitars, violin, viola, piano, voice |
| Tim Hodgkinson | organ, piano, alto sax, clarinet, voice |
| John Greaves | bass, piano, whitsle, voice |
| Chris Cutler | drums, toys, piano, whitsle, voice |
| Geoff Leigh | saxes, flute, clarinet, recorder, voice |
73 年発表の第一作「Legend」。
内容は、カンタベリー・ジャズロックの即興性とアヴァンギャルドな面をクローズアップした快作。
「チェンバー・ロック」というと厳しく難解なイメージを与える恐れがあるが、カンタベリーという冠通り、冴えたポップ・センスがあることを強調したい。
また、フランク・ザッパからの流れをたどりなおして、「Uncle Meat」あたりに立ち返ったといってもいい音楽性である。
演奏は、俊敏なリズムの上で、クラシックやジャズ風味を交えた管弦/鍵盤楽器とロック・ギターが、挑戦的に荒々しく、ときにユーモラスに交流するもの。
おそらくは、即興とスコアが交錯する内容なのだろうが、推進力をもつ鋭いビート、歪んだ音色のギター・プレイ、そして、精度を求めつつも、呼吸のよさを優先してしまう若さや緩やかさを考えると、やはり、フリー・ジャズでも現代音楽でもないロックである。
リリカルなメロディと突発的で狂気じみたプレイが同居する不可思議な演奏は、ロック・ファンには、とても新鮮ではないだろうか。
難解なイメージは、少し聴き込めばなくなると思います。
East Side Digital 版 CD は、ホジキンソン、フリスによって 90 年にリミックスが施されており、オリジナルよりもリバーブ処理が多く、後に加入するクーバーのプレイなどのオーヴァーダブもある。
また、98 年には、ReR よりオリジナル・ミックスの CD も出ている。
「Nirvana for Mice」(4:56)
昭和歌謡調のメロディアスな全体演奏は、奇妙な圧迫感をもつギターで破断され、狂おしいサックスのリードでフリー色を強め、パワフルで挑発的な即興演奏へと高まってゆく。
さまざまなノイズやきまぐれなリフレインが平然と放り込まれ、まろやかな演奏のイメージがどんどん歪曲してゆく。
演奏には自信に満ちた推進力があり、うねるようなドライヴ感がある。
管楽器はフリージャズ風の肉感的でダイナミックなブローで全体を貫き、ギターは内向的かつ偏執的でほぼ騒音のよう、ドラムスはジャズにしてはパワフル(フィルとフロア・タム連打がカッコいい)であり、ベースは細かなフレーズを操りひたすらテクニカル。
シュアーなビートとサックスのリードで邁進しつつも、奇妙な音がどんどん放り込まれては遠ざかる。
けたたましいリフレインをたたみかけ、アジテーションのような声が飛び込む唐突なエンディングには独特のユーモアも感じられる。
エンジニアとしてマイク・オールドフィールドのクレジットあり。
ESD 盤では、オープニング付近のピアノのオブリガートや最後の声に、リバーヴ処理が施されている。
耳に馴染むオープニングを変容させてサックスを軸としたインパクトのある演奏へとなだれ込み、リスナーを新しい世界へといざなう。出色のオープニング・チューンである。
「Amygdala」(6:58)
美しく躍動的なアンサンブルに、即興風のプレイというスパイスで変化をつけて織り上げた、摩訶不思議なジャズロック。
メロディアスにして精緻であり、デリケートなハーモニーが無限の渦巻きになっているようなイメージである。
HATFIELDS よりは、キーボードに生ピアノのみを使った NATIONAL HEALTH というべきだが、何にせよそれらのグループと近しい関係にあることが分かる内容である。
序盤は、ハーモニウムを思わせるオルガンと丹念なギターによる、内向きの静かなアンサンブル。
小刻みなドラミングも表情は穏やかである。
フルートによってやや華やいだ調子が加わり、管楽器の参入辺りから躍動感が生まれ、新たな展開への準備が整う。
各パートが絡みあう挑戦的な変拍子アンサンブルは、互いに追い越し追いつきあう競争のように緩急自在に進む。
ファズ・ギターやエフェクタッド・ギターのアクセントも効いている。
フルートをきっかけにスペイシーな叙情パートへと入り、幻想的なアンサンブルが繰り広げられる。
ピアノとフルートのリードする演奏に管楽器やギターが次々と重なり、ユーモラスでにして目まぐるしい動きのある世界となる。
時おり踊り場に達したようにゆったりとした調子を取り戻すが、すぐに次の展開へと飛び込み、再び慌しくも愛らしい演奏を繰り広げてゆく。
ややラウドに高まるクライマックスを経て、終盤は再びゆったりとした、今にも Northerttes のスキャットが聴こえてきそうなアンサンブルになる。
心の表層のようにフラフラクルクルと変化するわりには、流れは自然であり、聴き終わると濃い後味が残る。
これは、ゆったりとしたパートとせわしなく走り回るパートを丹念に紡いだシナリオのおかげだろう。
何にせよ緻密で巧妙な演奏である。
フリー・ジャズや現代音楽よりは、若々しさと耽美な甘さがあり、そこが魅力なのかもしれない。
カンタベリーらしいジャズロックの逸品。
ESD 盤では、リンゼイ・クーパーのバスーンがオーヴァーダブされている。
インストゥルメンタル。
「Teenbeat Introduction」(4:32)
おそらく完全即興による次曲へのプロローグ。
典型的なフリーのスタイルで、アルト・サックス、ソプラノ・サックス、プリペアド・ギター、ドラムス、ベースがアドホックなやり取りを繰り広げる。
希薄で不安定な空間が透明なまま次第に密度を上げてゆくようなイメージである。
互いに出方をうかがい、ミスコミュニケーションを繰り返し、ギターによる不思議な音が次々と現れ、やがて、散らばっていたしずくが集まって一つの流れとなるように、一体となったなめらかな動きが生まれ出る。
サックスのプレイは「いななき」(フラジオ)スタイルも多用。
終盤一つの集中した動きが発生し、そのまま次曲へ。
インストゥルメンタル。
「Teenbeat」(6:48)
スピーディなリズムチェンジの嵐による幾何学的なアンサンブルにどことなくナンセンスなユーモアが浮かび上がる作品。
珍妙なフレーズを凝り捲くった変拍子(16 分の 23 拍子 !)、ポリリズムで支える。
トレモロ、連打、ヴォカリーズによる波打つ様なオープニングを経て、技巧的なギターのブリッジ、そして、管楽器のリードするユーモラスなアンサンブルが現れるも、演奏はくるくると変転する。
展開のキーとなるのは、ワウワウも使って細かなパッセージを次々繰り出すギター、そして奇妙に田舎じみたクラリネット。
2:50 辺りで管楽器によって提示されるコミカルな主題が最後まで見え隠れする。
中盤はとぼけたようなクラリネット・ソロをこのコミカルなテーマによるポリリズミックなアンサンブルが支える。
きめ細かい文様のような演奏だが、不思議と緊張感がないのは、バックの変拍子リフのせいだろう。
終盤、エアポケットのように大胆なブレイクで雰囲気を転換、プリペアドギターのノイズとともにメロディアスなアルト・サックス(ティム・ホジキンソンか)が受け止めて終局へと導く。
インストゥルメンタル。
「Nirvana Reprise」(1:14)
ESD CD のみの収録曲。
「Extract from "With The Yellow Half-Moon and Blue Star"」(3:38)
ポリフォニックな室内楽風のクラシカルな構築性とその構築性から外れようとする勢いがせめぎあう、ユニークな作品。
序盤、ギターの多重録音による思いのほか暖かく穏やかな演奏が地均しし、そこにヴァイオリンやフルートも登場して珍妙なるカノンが始まる。
ふつうの室内楽よりも遥かに逸脱調だが、ベース・ラインを交えたみごとなポリフォニーだ。
「Teenbeat」のコミカルな主題も一瞬回想される。
ドラムスも加わって、やや重くシリアスな調子の主張が押し出されるが、リコーダーのオブリガートからメロディアスな管楽器の響きとともに次曲へ。
中盤のフルートとサックス、最後のサックスなどキラリと光るメロディがある。
ユーモアも生真面目さもある充実した内容だ。
前半にドラムレスの演奏があるので、より室内楽的なイメージになっている。
「Teenbeat Reprize」(5:04)
4 曲目のリプライズ。
うねるようにサスティンするファズ・ギターのリードによるスピード感あふれるジャズロック。
忙しないベース・ラインと煽るようなドラム・ビート、和音のストロークはエレクトリック・ピアノか。
アコースティック・ピアノによる鋭いオブリガートもきらっと突き刺さる。
息詰まるようなテンポアップで押し捲り、一直線に走り抜ける。
中盤で一度奥に引っ込むが、強力なリズム・セクションが管弦楽器を呼覚まし、あざやかなエンディングになだれ込む。
「The Tenth Chaffinch」(6:04)
ノイズ+ミュージック・コンクレート+即興。
キーボードの和音が鳴り響き、鳥のさえずりのようなギターがざわめく幻想的な序盤から、一定したビートやリズムのないまま、ベース、フルート、キーボードらによる間歇的な演奏が即興的に繰り広げられる。
さまざまなノイズに加えて、人声も音響として積極的に使われている。
ドラムスの乱打音が強まるとともにギターも緩やかな自己主張を始める。
しかし、なんとも尻切れトンボのまま終わり。
この脈絡のなさに強い脈絡を感じねばならぬ。
「Nine Funerals Of The Citizen King」(5:30)
おそらくグリーヴスの歌唱によるメロディアスなドイツ歌曲風の作品。
初期 SOFT MACHINE を思わせる佳曲であり、ヴォーカル表現は、ロバート・ワイアットの影響下にあるようだ。
ヴァイオリンによるクラシカルな伴奏とオブリガート、ヴィオラ、管楽器、ベース、オルガンによる室内楽的な表現が新鮮だ。
「Bellycan」(3:19)
ESD CD のみの収録曲。
日常生活ですっかり鈍った精神に鉄槌を下すようにぶつかってくる前衛ジャズロック。
初めはとっつきにくかったが、聴き込むほどに、小気味いいプレイが魅力を放ち、挑戦的な姿勢がカッコよく思えてくる。
不協和音のベールを剥げば、そこにあるのは、スピード感あるタイトなロックなのだ。
HATFIELD AND THE NORTH が、初期クロスオーヴァーに反応したグループとするならば、こちらは、フリー・ジャズの即興性と現代音楽の挑戦に応じたグループといえるだろう。
もっとも、ジャズという共通項があるせいか、遊びの感覚や自由度は似通っている。
クラリネットやヴァイオリンなど室内楽的なイメージをもたせるファクターもある。
フリスのギター・プレイは、訥々と語ったり、美しく歌ったり、やおらアグレッシヴに迫ったりと、さまざまな表情を見せるが、どれもみごとに決まっている。
やはり名手の一人だ。
一方、カトラーのドラミングは、乾いた音と安定した手数で、きっちり演奏を仕切っている。
全体的な音の感触が、どことなくロバート・ワイアットの作品を思わせる辺りも興味深い。
アヴァンギャルド/チェンバー・ロックの出発点として、永遠の一枚。
(V2005 / ESD 80482 / ReR HC1)

| Fred Frith | stereo guitar, violin, xylophon, piano |
| Tim Hodgkinson | organ, alto sax, clarinet, piano |
| John Greaves | bass, piano, voice |
| Chris Cutler | drums |
| Lindsay Cooper | bassoon, oboe, recorder, voice |
74 年発表の第二作「Unrest」。
ジェフ・ライが脱退、女性管楽器奏者のリンゼイ・クーパーが加入する。
美人が入れば、当然バンドは盛り上がる(か、崩壊する)。
ともあれ、ここで、バスーンとオーボエというロックの世界では珍しい楽器が、導入されることになった。
チェンバー・ロックというネーミングは、当然こういう楽器の使用とも関係しているのだろう。
1 曲目から 4 曲目までが作曲ものであり、5 曲目から 8 曲目がスタジオ・インプロヴィゼーションに編集作業で手を加えたもの、そして ESD 盤のみ収録の 9、10 曲目は、ほぼ手つかずのインプロヴィゼーションだそうだ。
ロバート・ワイアットとウリ・トレプテ(GURUGURU のベーシスト)に対する謝辞がある。
さて内容は、奇天烈な即興のテンションとともにメロディアスな主張もあり、全体に余裕の感じられる作品となっている。
つかず離れず絶妙の均衡を見せるアンサンブルに、ソロのアクセントも巧みにちりばめた演奏が生み出す高度な音楽性は、後続グループに多大な影響を与えたに違いない。
緩衝域のような空間に、静かにさまざまな音が散りばめられる場面や、ヒリヒリした緊張感に満ちたアンサンブル、暴力的ともいえる激しいインプロまで、数々のフリー・ミュージックを味わうことができる名作だ。
「Ruins」はチェンバー・ロックの金字塔。
「Bitten Storm over Ulm」(2:18)。
ギターのコード一発そして妙に律儀なベース・パターンが動き出す。
7+3 もしくは 7+4 拍子だろうか、妙におちつかないリズムだ。
ざらつき乾いた音のドラムスがマメに仕切るも、ギターがヘヴィ・ディストーションによるウネウネとしたヴィブラートとチョーキングを用いるプレイで脱力させる。
ギターをかき鳴らすようなさまざまなノイズが気まぐれに散りばめられる。
何か特殊なギター奏法なのだろう。
ドラムス、ベース、ギターのトリオにエレピと管楽器がアクセントをつける、ユーモラスなオープニングである。
ギターと並行に動き続ける管楽器アンサンブルは、ヒョウキンな 8 分の 10 拍子(繰り返しでは 2 拍くらいずれるが)のテーマを提示。
ギターは我関せずといった趣で、わざとらしくロック・ギターのパロディのような盛り上がりを見せる。
さまざまなノイズはキーボードとギターの特殊奏法のオーバーダブだろうか。
もつれるような管楽器によるクリアーなユニゾンが、混迷する演奏を鮮やかにまとめて去ってゆく。
ギターと管楽器をフィーチュアしたコミカルな変拍子チェンバー・アンサンブル。
わざとらしい力みのあるギターとチンドンな管楽器による、まるで笑いを必死にこらえているようなユーモアある演奏だが、
イメージとして近いのは、クラシックの室内楽である。
人懐こいメロディ・ラインなどは前作の 1 曲目にも通じており、意外にこういう調子も基本の一つなのかもしれない。
ニュー・ミュージックだからといって、なにも堅苦しくしゃちこばる必要はないのさ、といいたげだ。
THE YARDBIRDS の「Got To Hurry」(アルバム「For Your Love」収録)を元ネタにしているそうだが、不勉強なのでよく分かりません。
ETRON FOU に伝わったのはこういう部分だったのだろう。
フランク・ザッパの作風に通じる人を食ったようなリラックスしたオープニングである。
「Half asleep; Half awake」(7:59)。
序盤は、残響を活かした、タイトル通りまどろむように美しいソロ・ピアノ。
ピアノの余韻が絶えるとともに、ベースが怪しげなリフを提示して一気にアンサンブルは動き出す。
リードはオーボエ。
ノイジーなギター、オルガン、ピアノがオーボエを支え、ベースも積極的に動いてゆく。
続いてギターがリードを交代し、オーボエのつかずはなれずのデュオを繰り広げる。
メロディアスなアンサンブルに手数の多いドラムスがアクセントをつけてゆく。
3 拍子系のせいか、込み入った音のわりにはゆったりとしたイメージのある演奏である。
続いてサックスがリード。
バスーンがおっとりと追いかける。
サックスの示す小刻みなテーマは、SOFT MACHINE や、HF&N を思わせる知的で粋な感じである。
管楽器は、柔らかな音にもかかわらず、堅固に進行するベクトルを提示する。
どうしても SOFT MACHINE を思わせる展開だ。
ワウ・ギター、バスーンらによる、ややモヤッとした即興風のアンサンブルが続く。
次第に、バスーンはアドリヴの存在感を強めてゆき、周囲も緊迫したムードに対応してゆく。
全パートが一斉に暴れだすも、ドラムスがハイハット連打に切りかえた辺りから、演奏はゆっくりと解きほぐされてゆく。
トリル、気まぐれなストロークを放ってきたギターによるアルペジオは、あたかも新たな秩序を促すようだ。
バスーンはいまだうねるようなトリルを続ける。
そして、神秘的にして独特の美意識を保つソロ・ピアノがクロス・フェード・イン、名残を惜しむかのように静かにフェード・アウト。
美しいピアノ・ソロをプロローグとエピローグに配した、緻密ながらもメロディアスなジャズロック。
ソロの一歩手前のような印象的なフレーズをそれぞれの楽器が持ち寄っており、木管の響きこそクラシカルだが「チェンバー」というよりは「ジャズロック」という表現が似合う演奏になっている。
前半は、さまざまな音がそれぞれの流れに乗って関連しつつも澱みなく動いてゆく明快かつ精密なアンサンブルであり、後半はフリー/即興風の心地よい乱れと緊張が生じてゆく。
こういう作品では、手数多くアンサンブルの時間軸を仕切るドラムスが、いよいよワイアットに聴こえてしまう。
夢見るようなピアノにいざなわれて眠りにつくも、悪夢に悩まされ、目覚めの前に再び美しい幻想を見る、そんなイメージだ。
「Ruins」(12:10)。
ヴァイオリンかキーボードか、アタックのない甲高いドローン(?)がフェード・イン、キリキリと聴覚を刺激する。
オーボエ、オルガンによる気まぐれなつぶやきは、強いエコーのかかった金属音(ピアノの打鍵だろうか)に追いかけられ、断ち切られる。
空間的な広がりを感じさせるとともに緊張感もあふれるオープニングだ。
マリンバ、ギター、ベースらによるもつれるようなアンサンブルがクロス・フェード・イン、
一転して、オルガン、ベースがリードするメロディアスなアンサンブルが始まる。
ベース、オルガンをピアノとマリンバが追いかけ、ピアノ、マリンバがユーモラスだが無機的という印象的なテーマを提示し、反復する。
8 分の 15 拍子。
安定感ある HF&N 調の展開である。
ファズ・ベースが唸り、スネア・ロールをきっかけに、ギターのインプロへ。
ノイジーなギターが思うさま暴れ続け、ドラムスが勝負を挑む。
ピアノ、ベースは大胆なシンコペーションによる奇妙なアクセントを刻む。
そこへドラムスの連打と独走状態のギターが折り重なり、奇妙なノイズもおおいかぶさる。
挑戦的な演奏だ。
管楽器が加わったかと思う間もなくポリリズミックな演奏は突如断ち切られ、ヴァイオリンが不気味に宙にさまよいだす。
ヴァイオリンを受けるのは、バスーンとベースによる小刻みなユニゾン。
新生 KING CRIMSON を思わせる、シリアスにして逸脱調、なおかつ神秘的な展開だ。
オープニングと同じく、バスーンがヴァイオリンにからむようにようにつぶやき、ヴァイオリンは苛つくように追い立てる。
管楽器、ヴァイオリンらによる伸びやかな反論が高まるも、バスーンがゆったりととぼけたように応じ、今度はヴァイオリンとベースがそれに反応する。
再び、管楽器、ヴァイオリンらによる伸びやかな主張、そして、今度はマリンバとドラムスがコミカルに反応する。
均衡を失った不安定な世界が描かれてゆく。
バスーンはヴァイオリンを追いかけ、やがて陰鬱なハーモニーを成してゆく。
バスーンとヴァイオリンの深刻なデュオに、ベースとマリンバが突っ込みを入れる展開が幾度か繰り返される。
リズムは失われ、管弦楽器が不安定な世界をただただ漂ってゆく。チェンバー・ロックという呼称にふさわしい展開だ。(7:15)
オルガン、管弦らによるユニゾン、ハーモニーが力強く一つにまとまり、分厚く声高の主張が始まる。
プリペアド・ギターによる珍妙かつバラエティ豊かなノイズとともに、管弦楽器とオルガンらが一歩一歩、踏みしめるように堅実な歩みを続けてゆく。
ここの管弦楽器のパターンは、ピアノとベースが以前刻んでいたシンコペーションのパターンである。
さまざまな音が断続的に重なりあい、あたかも室内楽の録音テープを細切れにしてつなぎ直したような演奏が続く。
普通の音楽ファンはこのあたりでウンザリするかもしれない。
ようやくヴァイオリンがリードをつかみ(9:00)、バスーン、ベースそしてオーボエらが合流してポリフォニーを成す辺りから秩序が復活、ドラム・ビートも刻まれる。
一気にロックらしいハードなビート(ただし変拍子)が復活し、暴力的なギターをきっかけにして大胆なベースの搬送とともに演奏が動き出す。
管楽器、オルガン。ギターらによるハーモニーはメロディアスに一本筋を通すように流れてゆく。
前曲のリズムに室内楽を加えたようなスリリングな演奏が盛り上がるが、それもつかの間、幻のように消え去って、余韻はロバート・フリップばりのギター・ヴィヴラートによるロングトーンのうねり。
そうか、これがオープニングの音なのだ。
管楽器も寄り添いギターに重なってゆく。
奇妙なキャラバンは余韻ならぬ余韻を残して何処ともなく去ってゆく。
現代音楽の無機的脱構築性とジャズの数学的肉体的呼吸、ロックの強引なドライヴ感をより合わせた異形の構築美を誇る挑戦的大作。
変拍子ジャズロックによる序盤、リズムレスでアヴァンギャルドな室内楽風の中盤(即興のようだが、鋭いユニゾンやコール・レスポンスもある)はやがてノイズのカオスと化し、いつしか一体となったアンサンブルが力強い変則リズムとともに去ってゆく終章。
ギターの特殊奏法によるものを主に、さまざまなノイズが現れるが、宙に音を撒き散らしながらも前進する堅実なベクトルがある。
弛緩はない。
さまざまな楽器の奇妙な調べとノイズは交錯し、反応し、新しい流れとなる。
不安なまま秩序を維持するアンサンブルが息を呑む緊張を生み、素っ頓狂ともいえるプレイがふと息をつかせる、この配合の妙。
中盤では、次々に楽器が役割を変えてゆく凝ったインタープレイもある。
フリスのヴァイオリンやギターなど、KING CRIMSON の即興を思わせる場面もある。
クラシカルな構築性と衝動的な表現のインパクトを兼ね備える、真にプログレッシヴな音楽といえるだろう。
ドラマも感じます。
名作。
「Solemn Music」(1:11)。
シングル・ノートを響かせるベースをきっかけに、オーボエがゆったりと、哀しげに歌い出す。
クラシカルな演奏である。
ギターはユニゾンやアルペジオ風の伴奏などでオーボエの調べに静かに寄り添ってゆく。
オーボエとギター、ベースによる典雅でクラシカルなトリオ。
憂いをもつオーボエの音色がいい。
ドラムレス。
「Starless And Bible Black」中の小曲を連想させます。
「Linguaphonie」(5:31)。
バスーンと思われる低音が渦巻き、毛羽立ったノイズがからみつく。
あまりに不気味なオープニングをさらにおぞましくするのが、混声による奇妙なシュプレヒコール(英語ではないようだ)である。
おそらくギターの特殊奏法なのだろうが、機械のような轟音や雑音の断片が降り注ぐ。
ドラムス、管楽器も少しづつ加わって、突発的に吐き出されるヴォイスとともに、無秩序な空間が広がってゆく。
バスーンの即興、そしてかすれた女声ジャズ・スキャット。
突如湧き上がるギター、打ち鳴らされるドラムス、ねじくれるノイズ。
何もかもが壊れるようなドラムス、ギターの騒音。
メタリックなノイズに覆われた、インダストリアルな即興演奏。
断片的な音と意味不明のヴォイスが無秩序に湧き上がり、こっけいな感じもあるが、全体としては緊迫していて、その緊張感の狭間に浮かび上がる美もある。
ほとんどのノイズはフリスによるギターの特殊奏法によるようだ。
ロバート・フリップ、デレク・ベイリーを思わせるギター即興もある。
余談だが、ギターがプレイヤーの狂気によってノイズを生むのに対して、管楽器は楽器そのものが狂気を噴出していると感じることが多い。
管楽器奏者は他の器楽奏者以上に魂を楽器に明け渡しているに違いない。
何度もいうが、初期 KING CRIMSON の即興演奏と類似した音が確かにある。
「Upon Entering The Hotel Adon」(3:04)。
回転する電子音がいらつくノイズに変化するやいなや、突然の大絶叫とドラムス乱れ打ちによる大狂乱。
乱れ打ちはいつしかビートへと変化、ベースを主にした堅実な演奏へと収斂する。
管楽器ユニゾンによるテーマの提示をきっかけに、演奏はさらに秩序立ち、爆発力はそのままに演奏が続いてゆく。
サックスら管楽器も絶叫し始める。
一瞬落ちつきを取り戻しそうになるが、再びもつれあうような全体演奏へと突っ込んでゆき、挑発し合い、発展してゆく。
音数の多いベースだけが冷静に自分の道を進んでいるようだ。
ギターのコード・ストローク、そして荒々しいアドリヴを経て、またも爆発的なドラムスとともに、今度はサックス主導でフリー・ジャズ的な展開へと突っ込んでゆく。
打楽器的な音を駆使し、ハイテンションで突き進むエネルギッシュな作品。
全員で全力投球が最後まで続く。
ベースがかろうじて理性的な動きをするが、それ以外は完全な乱打、乱撃、ドシャメシャ状態。
バラバラの音が一気にまとまって走り出す瞬間の壮絶さ。
「Arcades」(1:57)。
静寂の中、緩やかにバスーンが流れ出すも、危険な予兆がある。
室内楽風の演奏ながらも高まる緊張。
ピアノの弦をかき鳴らす音が衝撃的に切り込む。
サックスが断片的な音を散りばめる。
バスーンがややシリアスな表情を見せるも、サックスはあくまで気まぐれな音を吹き散らす。
オルガンかギターか分からぬが、さまざまな音が浮かび上がっては消える。
サックスの音が支配的になって終わり。
余韻と残響が異様な迫力を生むチェンバー・ロック。
緩やかな干渉はあるものの、明確な形、方向を成さぬまま消えてゆく。
叙景的。
ドラムレス。
「Deluge」(5:24)。
ベースに反応するように、ハイハットをこねくり回すドラムスと金属的なギターが食いつくように追いかける。
サックスは一瞬顔をのぞかせては消える。
断続音が次々現れるだけで、音の定位もよく分からない。
自然発生的だが、それでも次第にまとまりをみせてゆく演奏。
掴み合いのような断続音の連なりを、いつのまにかクラリネット、オーボエ、ヴァイオリン、オルガンがクロス・フェードで湧き上がり塗りつぶしてゆく。
レクイエム風の美しくも暗いユニゾンが響く。
そして、ピアノの静かな和音の響きとともに、グリーヴスのヴォーカルが始まる。
ふともぎとられたように音は消え、余韻すら残らない。
終末感漂う美しいエンディング。
前半の行き場のない即興が、次第にまとまりを見せるかと思えば、一気にドラマチックな終焉へと流れ込む。
すばらしい演出だ。
ヴォーカルはロバート・ワイアットを思わせ胸に迫る。
フリー・ジャズの影響を強く受けた演奏スタイルから個性的な即興音楽へと進化を遂げた名作。
これだけぶっ飛んだ演奏ながらも、作曲ものについては「キャッチー」な聴き心地すらある。
しかしながら、やはり圧巻は後半の多彩な即興演奏である。
これを聴いた後では、前半の作曲ものがこじんまりとまとまって感じられる。
そして、このグループについては、スタジオ盤というのは可能性の一断面に過ぎないという思いも強くなる。
後半、カオスの只中に放り出されたような心細さがあるだけに、最終曲のロマンティックな余韻がより一層すばらしい。
(V 2011 / ESD 80492 / ReR HC2)
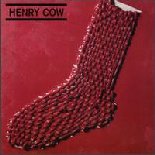
| Tim Hodgkinson | organ, clarinet, piano on 2 | Fred Frith | guitar, violin, xylophon, piano on 4 |
| John Greaves | bass, piano | Chris Cutler | drums, radio |
| Dagmar Krause | voice | Peter Blegvad | guitar on 2,3, voice on 1, clarinet on 1 |
| Anthony Moore | piano on 1,2, electronics, tapework | Lindsay Cooper | bassoon, oboe, recorder, voice |
| guest: | |||
|---|---|---|---|
| Geoff Leigh | soprano sax on 1 | Mongezi Feza | trumpet on 1 |
| Phil Becque | oscillator on 4 |
75 年発表の「In Praise Of Learning」。
74 年「Desperate Straights」にて SLAPP HAPPY と共演後、SLAPP HAPPY のメンバーが HENRY COW に合流する。
本作は、スタジオ盤として三作目であり、その合流後の初作品である。
(本作品録音後、ダグマー・クラウゼを残して SLAPP HAPPY とは決別するため、結果として HENRY COW が個性的な女性ヴォーカリストを獲得したことになった)
ダグマー・クラウゼの歌唱はギター、サックスらとともに調性を外れて突き進み、透き通るような音色を吐き出しつつ、次第に深刻な器楽アンサンブルへととけ込んでゆく。
そして、物語の文脈をたどるのではなく、無明の闇への発散を示唆する。
この、秩序からはずれる怖さが特徴だ。
もちろんロリータ・ヴォイスの娼婦のような歌唱が物語性を付け加えるところもあるにはあるが、強く印象に残るのは決然とした主張の強さであり、時にグロテスクなほどのアジテーションである。
そうなると、むしろ器楽の方に、即興が主体ながらもシリアス一辺倒ではなく、夢見るように美しいピアノや穏やかなオルガンの響きなどに象徴されるポップなタッチがあり、より自然なドラマがあることに気がつく。
ヴァイオリンやマリンバも険しさとは正反対に世界を賛美するように健やかになる瞬間がある。
美しくもシュールで凶暴な世界に設けられたヴォーカルという定点は、実はアクセスしやすさのためではなく、より過激な展開への突破口として機能しているようだ。
全体として室内楽色は後退し、無調性や不協和音を強調しノイジーな即興を多用した、アタックの強い荒々しい演奏である。
カンタベリーな遊び心はごく一部で感じられるのみ。
ESD 盤のボーナス・トラックは、騒音蠢き、殺気漂うインスダストリアルなアヴァンギャルド・ロック。
また、ジャケットには「芸術とは鏡ではなくハンマーである」という言辞が記されている。
ちなみに、東京事変の元ネタのゲルニカはこの辺りからの影響が大きいと思います。
「傾向賛美」という奇妙な邦題も懐かしいです。
「War」(2:24)ムーア/ブレグヴァド組によるナンセンスな感じの相聞歌。底意地の悪い老婆のようなクラウゼのヴォイスが強烈。
モンゲジ・フェザを筆頭とする管楽器のアレンジがカッコいい。
「Living In The Heart Of The Beast」(15:18)冴え冴えとしたヴォーカルを緊張感ある器楽の中で活かした演劇的なオムニバス作品。
ポリフォニックなアンサンブルもあるが、器楽というよりも楽器同士の芝居を見るようなイメージである。
反応がよく主張が強いということだろうか。
ヘヴィ・プログレといっていいような険しく凶暴な音もあり。(10 分過ぎのギター主導のけたたましい展開は非常にカッコいい)
「Beginning:The Long March」(6:20)騒音渦巻くインダストリアルなノイズ・ミュージック。
未知の惑星の工業地帯を描くように叙景的。
管楽器などアコースティックな音も多いが、バックグラウンドの電気的なノイズがステージやホールやスタジオではない、日常に近い「外」の世界をイメージさせる。
深読みするならば、音楽による現実逃避を許さないということだろうか。
「Beautifull As The Moon - Terrible As An Army With Banners」(6:55)独特の乾いたハードボイルド感のある歌もの。
耽美にしてストイックな歌唱と重厚な演奏のコンビネーションがすばらしい。フリスとグリーヴスのピアノ・デュオもあり。
「Morning Star」(6:02)集団即興。俊敏なドラムスのプレイがカッコいい。
「Lovers Of Gold」ESD 盤のみの収録曲。(6:28)
(V 2027 / ESD 80502 / ReR HC3)
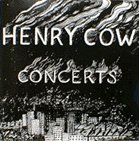
| Lindsay Cooper | bassoon, flute, oboe, piano on 8 |
| Chris Cutler | drums |
| Dagmar Krause | voice |
| Fred Frith | guitar, piano |
| John Greaves | bass, voice, celeste |
| Tim Hodgkinson | organ, clarinet, alto sax, piano on 7 |
| guest: | |
|---|---|
| Robert Wyatt | vocals on 2 |
| Geoff Leigh | tenor & soprano sax, flute, clarinet, recorder on 7,8,9 |
76 年発表のライヴ・アルバムの名作「Concerts」。
LP、CD ともに二枚組。
ライヴならではのメドレーや、20 分にわたるインプロヴィゼーションが収録されている。
「Ruins」に象徴されるように、スリルとパワーとデリカシーが一つになった屈指のライヴ作品といえるだろう。
ESD / ReR 盤(2006 年リマスター) CD には「Greasy Truckers Compilation」からの抜粋が、ボーナス・トラックとして収録されている。
メディアとしての容量が異なる上に、LP 二枚組から CD 二枚組への移行のため、曲順がアナログ LP から大きく変更されている。
「Groningen」と「Udine」を切り離したのが、やや不自然に感じられるかもしれない。
現行 CD にはヴァージンからサポートを打ち切られそうになった状況での本作品発表について興味深い話が載っている。
「Beautiful as the Moon;Terrible As An Army With Banners」(22:46)アナログ A 面収録のメドレー。75 年 BBC ピール・セッションより。
「Nirvana For Mice」
「The Ottawa Song」
「Gloria Gloom」
「Moon Reprise」
「Bad Alchemy / Little Red Riding Hood Hits the Road 」(8:16)アナログ B 面 1 曲目。ワイアットの歌声が聴ける。75 年ニュー・ロンドン・シアターでのライヴ録音。ピアノはジョン・グリーヴス。
「Ruins」(16:14)アナログ B 面 2 曲目。75 年イタリアでのライヴより。ピアノはダグマー・クラウゼ。
「Groningen」(8:49)アナログ D 面 1 曲目。74 年オランダでのライヴより。
「Groningen Again」(7:12)アナログ D 面 3 曲目。KING CRIMSON のインプロに酷似。74 年オランダでのライヴより。この二曲はリンゼイ・クーパーは不参加。
「Oslo」(25:59)アナログ C 面収録。ノルウェーでのライヴ録音。リコーダーはリンゼイ・クーパー、ピアノはクリス・カトラー、ヴァイオリンとシロホンはフレッド・フリス。
「Off The Map」(8:30)「Greasy Truckers Compilation」より。以下の四曲は 73 年オクスフォードでの録音。管楽器はジェフ・ライ(クーパーは加入前)。ピアノはティム・ホジキンソン。
「Cafe Royal」(3:22)「Greasy Truckers Compilation」より。
「Keeping Warm In Winter」(1:00)「Greasy Truckers Compilation」より。
「Sweet Heart Of Mine 」(9:06)「Greasy Truckers Compilation」より。
「Udine」(9:29)アナログ D 面 2 曲目。75 年ニュー・ロンドン・シアターでのライヴ録音。ピアノはリンゼイ・クーパー。
(CAD 3002 / ESD 80822/832 / ReR HC5 & 6)

| Tim Hodgkinson | organ, alto sax, clarinet, hawaiian guitar on 1,2, piano on 3 |
| Lindsay Cooper | bassoon, oboe, soprano sax, soprano recorder |
| Fred Frith | electric & acoustic guitars, bass, soprano sax on 3 |
| Chris Cutler | drums, electric drums, noise, piano on 4, trumpet on 3 |
| guest: | |
|---|---|
| Anne-Marie Roelofs | trombone, violin |
| Irene Schweizer | piano on 5 |
| Georgie Born | bass on 7 |
78 年発表の「Western Culture」。
グループとしての最終作。
ジョン・グリーヴスはすでに脱退、ブレグヴァドとの活動を経て NATIONAL HEALTH に参加している。
アナログ A 面はホジキンソン、B 面はクーパーによる作品が並ぶ。
つまり、全体即興は限定されている、と考えていいだろう。
「History & Prospect」の副題をもつ A 面は、ギター、キーボードと管楽器によるアンサンブルを中心とする均整の取れたモダン・クラシック風のチェンバー・ロックである。
UNIVERS ZERO のような強圧的な変拍子パターンによる「押し」の勢いやジャズ的な爆発力ではなく、表情豊なドラムス、パーカッションもフルに活かした、物語の流れを感じさせる丹念なタッチがメインである。
二管の応酬も特徴的だ。
フリスのギターは、ディストーションを効かせたヒステリックなロングトーンとプリペアドによる特殊奏法(2 曲目のエンディング)が特徴的だが、2 曲目「The Decay Of Cities」冒頭のクラシカルなタッチでも存在感を現す。
ホジキンソンにクレジットされている「ハワイアン・ギター」というのは、ラップ・スチール・ギター(スライド・ギター)のことだと思う。まさに「都市の崩壊」らしいカタストロフィックな終盤もカッコいい。ヴァイオリンが加わったアンサンブルには緊張感とともに独特の逸脱感(キチガイじみた感じ)あり。
3 曲目は、カンタベリーの向こう側でフランク「Wazoo」ザッパが微笑んでいるような世界。
不安げにゆれつつも二管、ヴァイオリンらが成す暖かく緩やかな流れに身を任せられる。
こういった作風も、アメリカのレコメン第二世代へと引き継がれているはずだ。
1 曲目を代表に、基本的には険しく抽象的なイメージの演奏だが、後のホジキンソンの超厳格な作風とはかけ離れたアクセスしやすさもあり、ロックとしての力点が確保されていることが分かる。
B 面には「Day By day」の副題がつく。
管楽器奏者の作品らしく、二管や管/ギターの連携と呼応が強調されているようだ。また、緩急含むスピード感ある演出も効いている。
二管のユニゾン、ハーモニーを軸にたたみかけるように走るところもある。
ロックらしいモーメンタムやグルーヴは A 面以上だろう。
もっというと、クラシカルなタッチを強調することでいわゆるプログレらしさも出ている。5 曲目「Falling Away」ではゲストのセシル・テイラーばりのフリーなピアノがフィーチュアされるが、キース・ティペットのいる CRIMSON に聞こえなくもない。一転して 3 曲目「Look Back」は緩徐楽章のような小品。最終曲「1/2 The Sky」はヘヴィなギターとオルガンによる厳かな世界を管楽器の痙攣が揺るがせる、カンタベリーらしさ満点作品。運動性のアップはジョジー・ボーンのベースが加わったためだろう。
全体に、フリージャズ的な力でねじ伏せるタイプではなく、構築と緩やかな逸脱が均衡した佳作である。
聴きやすい、というと真に受けてもらえない可能性もあるが、最も聴きやすい作品ではないだろうか。
「History & Prospect」
「Industry」(6:58)
「The Decay Of Cities」(6:55)
「On The Raft」(4:01)
「Day By day」
「Falling Away」(7:38)
「Gretel's Tale」(3:58)
「Look Back」(1:19)
「1/2 The Sky」(5:14)
(BC1 / ESD 80852 / ReR HC4)

| Georgie Born | fretless bass, cello on 1-7,12-14 |
| Lindsay Cooper | bassoon, flute, recorder, soprano sax, piano on 1-6, tapes on 13 |
| Chris Cutler | drums, electrification on 13, piano on 10 |
| Fred Frith | guitars, xylophone, piano on 14 |
| John Greaves | bass on 8-11, voice on 8 |
| Tim Hodgkinson | organ, alto sax, tapes on 13 |
| Dagmar Krause | singing |
2008 年発表の「Stockholm & Göteborg」。
40周年記念ボックス・セットの 6 枚目の単品もの。
1975 年、77 年にスウェーデンの放送局で録音された音源に若干の手を加えたようだ(Non invasively とあるが)。
室内楽ロックというニュアンスを裏切らない、挑戦的にして創造性にあふれ、自信に満ちた安定感あるパフォーマンスである。
主義主張に基づく厳格さ、俗界に伍するを潔しとしない険しさと音楽的な繊細な美感の均衡が絶妙。
神懸り的なクラウゼのヴォイス、独特の金属音を響かせるオルガン、変わったベース・ライン、管楽器群の衝動的なプレイなどが綾なす、間隙を活かした不思議なアンサンブルである。
KING CRIMSON の即興に豊かな色彩と女性的なデリカシーを加味したような表現ともいえそうだ。
「Stockholm 1」(6:38)
「Erk Gah」(3:28+2:55+2:27+6:17+1:59)
「A Bridge To Ruins」(5:08)
「Ottawa Song」(3:27)
「Goteborg 1」(6:06+8:20+2:27)
「No More Songs」(3:35)
「Stockholm 2」(6:13)
「The March」(4:15)
(ReR HC12)
