
| Phil Miller | guitar | ||
| Dave Stewart | organ, electric piano, piano | ||
| Neil Murray | bass | ||
| Pip Pyle | drums, percussion | ||
| guest: | |||
|---|---|---|---|
| Alan Gowen | electric piano, synthesizer, piano | Amanda Parsons | vocals |
| Jimmy Hastings | flute, clarinet | John Mitchell | percussion |
イギリスのジャズロック・グループ「NATIONAL HEALTH」。 75 年結成。 HATFIELD AND THE NORTH、GILGAMESH から主要メンバーが結集したカンタベリー・オールスターズ。 そのサウンドは、両グループの音楽性を推し進めた、遊び心もスリルもある華麗なジャズロック。 しかしながら、時代の潮流と衝突し、恵まれぬ環境の中で二枚しか作品しか残さなかった。 メンバー・チェンジの果てに 80 年解散。 82 年、ガウエン追悼のために一時再結成、アルバムを発表。

| Phil Miller | guitar | ||
| Dave Stewart | organ, electric piano, piano | ||
| Neil Murray | bass | ||
| Pip Pyle | drums, percussion | ||
| guest: | |||
|---|---|---|---|
| Alan Gowen | electric piano, synthesizer, piano | Amanda Parsons | vocals |
| Jimmy Hastings | flute, clarinet | John Mitchell | percussion |
78 年発表の第一作「National Health」。
4 曲のジャズロック大作から成る作品。
一部スキャット風の女性ヴォーカルが入る以外は、インストゥルメンタルである。
ギターはフィル・ミラー、べースは元 GILGAMESH のニール・マーレイが担当。
アラン・ガウエンはすでに脱退しており、ゲスト扱いである(とはいうものの、脱退前の彼の曲を演っているのだが。ああややこしい)。
さらに、CARAVAN、SOFT MACHINE への参加で知られるジミー・ヘイスティングスが、ここでもゲストとしてフルートを演奏している。
内容は、精密な技巧と夢見ごこちのグルーヴはアメリカ産フュージョンと共通ながらも、ピリッとしたユーモアと独特のメランコリーが特徴的なジャズロック。
流暢にしてシニシズムあふれる語り口に不器用なイノセンス、純朴さも感じられるという、きわめてチャーミングなパフォーマンスであり、ヴォリュームからいっても、カンタベリー・ジャズロックの総決算的内容の大傑作である。
「Tenemos Roads」(14:32)フェード・インで始まるのは、軽やかなムーグとオルガンの和音が、フーガのように追いかけあう、思わせぶりなイントロダクション。
こういった、ペダンチックでシニシズムあるセンスがなんともイカす。
そして、ファズ・オルガンのリードで演奏は走り出す。
オルガンは、高音がハモンド・オルガンのナチュラル・トーンであり、低音にのみファズをかけているようだ。
そして現われるテーマは、ムーグとギターのユニゾン。
オルガンのプレイに比べると、格段にのどかだ。
心地よい 4 分の 3 拍子。
オルガンとテーマが追いかけあうようなハーモニーを見せる。
転調から、やや曲調は緊迫し、ノイジーなオルガン・ソロへ。
ハードロック・ギターのソロのようにブルージー。
続いて、オルガンは、ワウでやや丸みを帯びた音色へと変化し、ソロが続く。
これは EGG、HATFIELDS でおなじみの音だ。
噛みつくような突っ込み気味の演奏が続いてゆく。
続いてギター・ソロ。
一気にジャジーな空気へと移り、ギターに合わせて、ベースもマイルドな音へと変化する。
オルガンが背後でテーマを変奏するのをきっかけに、再びテーマへ。
さわやかさとユーモアのあるいいテーマだ。
そしてパーソンズのヴォーカル。
オブリガートのエレクトリック・ピアノが美しい。
伴奏は饒舌なオルガンだ。
リズムが不規則に変化し、ヴォーカルに合わせて、緩やかな伴奏が浮き沈みするように続く。
ヴォーカルは、メジャーともマイナーともつかぬ不思議なメロディだ。
幻想的。
エレクトリックな効果音が交錯しオルガン、ギターがヴォカリーズとかけあう。
ヴォカリーズが静かに去ると、ピアノとエレクトリック・ピアノのおだやかなかけあいをきっかけに、フリーな演奏がスタートする。
まず、ドラムレスでエレクトリック・ピアノが一人静かにつぶやきはじめる。
ベースがひっそりとしたパターンで反応。
ファンタジックでミステリアスな瞬間。
フルートがさえずる。
カモメが鳴くような音は、ディレイを効かせたギター? さびしい口笛のようなムーグ。
ファンタジックな緩徐楽章だ。
ギターのアルペジオに導かれ、再び、透明感あふれるヴォカリーズが、夜明けの森に響き渡るニンフのささやきのように、湧き上がる。
名残惜しげな星のささやきのようなムーグ、浮かび上がるベース。
次第にリズムが復活、ムーグをきっかけに、一気にテーマが再現。
最後はヴォーカルつきだ。
後ろ 2 拍をアクセントするスネアが、心地よいビートを生む。
フィナーレは、ドラムスがスリリングなストロークを見せ、ヘヴィなギター、ベースのユニゾンから豪快に決めが炸裂。
明快なテーマ、ドライヴ感あるリフ、挑発的でひねくれたソロ、幾何学模様をなすアンサンブル、ファンタジックなサウンド、遊園地のように目まぐるしい変転など、カンタベリーらしさを思い切り引き伸ばした傑作。
現代音楽的な先鋭性や鋭角的な演奏を、ポップでおしゃれな音で和らげ、ファンタジーにまで昇華した作品である。
エレガントなサウンドだけではなく、レガートとスタッカートの巧みな対比、バランス、緊張と弛緩、攻めと引き、など係り結びという点でも、きわめて明快でアクセスしやすい。
緊張感あふれるロック・オルガンとジャジーなギターがシームレスに一つの曲を構成するような、その音楽的間口の広さも個性である。
おそらく、カンタベリーらしいファズ・オルガン、ファズ・ギターは、フュージョンとの間に打ち込まれた楔であり、明確な境界線なのだ。
アマンダ・パーソンズのクリスタル・ヴォイスは、フローラ・ピュリムのように優美で官能的でありながら、クールネスではやや勝っている。
一方、ヴォーカル・パート後半からのフリーフォームの伴奏は、いわば、カンタベリーのサイケデリック面を提示している。
ガウエンのエレクトリック・ピアノは、控えめながらも、チック・コリア/ゲイリー・バートンを思わせる世界を示している。
また、パイルのドラムスのプレイは、堅実なタイム・キープと弾けるような奔放なビート感がともにしっかり充たされている。
個人的には、とても好きなドラムだ。
変化に富んだ、どちらかといえば、とっ散らかった作品なのかもしれないが、テーマの明快さとふんだんに配されたサウンドの彩りのおかげで、実際の演奏時間ほどには長さは感じられない。
ヘヴィさとライトさを併せ呑むところも、カンタベリーの真髄なのだろう。
スチュアートの作品。
「Brujo」(10:13)
前曲の余韻の中から湧き上がるのは、ユーモラスなムーグとピアノ、ベース、ギターが追いかけあうおだやかなアンサンブル。
夢見るようなヴォカリーズが重なる。
すべての旋律が、追いかけ、絡みあい、室内楽風のハーモニーを見せる。
ヴァイブも加わっている。
ヴォカリーズに導かれた流れるような演奏だ。
そして、ヴォカリーズのフェード・アウトとともにブレイク。
今度はエレクトリック・ピアノからスタート。
ドラムレス。
エレクトリック・ピアノが軽やかなフレーズを決め、フルートを呼び覚ます。
フルートは波間にわたるそよ風。
シンバルは潮騒のようだ。
ベースがハーモニクスやグリッサンドでアクセントをつける。
静かな 8 分の 4+5 拍子のリフレインは、オルガンだろうか。
パーカッション類が夢の欠片をちりばめる。
フルートが美しい。
そして、東洋風のエキゾチックなメロディを歌うヴォカリーズ。
フルートが透き通るような音で応じる。
ハイハットが静かに刻まれてリズムが作られ、ヴォカリーズが続いてゆく。
ギターがロングトーンでヴォカリーズに重なる。
オルガンも和音を静かに響かせ、エレクトリック・ピアノが散りばめられる。
次第にこのグループらしい音になってくる。
エレクトリック・ピアノのきっかけで、一気に演奏が動き出す。
ベースがユーモラスなリフで鮮やかにリード。
ムーグとギターによるスピーディなユニゾン。
きらめくようなエレクトリック・ピアノ、そして鋭い決めを連発。
瞬間ブレイク。
ライド・シンバルが打ち鳴らされ、ムーグ、オルガン、ギターがシャープなユニゾンでたたみかける。
緊張感が高まる。
細かなリズムを刻むアンサンブルから抜け出るのは、軽やかなムーグ。
ファンタジックな音だが、リズムは細かく刻まれ緊張が高まる。
ムーグはベンディングを駆使したすさまじい速弾き。
RETURN TO FOREVER の「Romantic Warrior」調である。
フレットレス・ベース特有のグリッサンドを用いたパターン。
伴奏はエレクトリック・ピアノ、ギターは和音のみでベースの役割が大きい。
クラシカルなピアノの和音弾きがスケールを駆け下りると、ファズを効かせたオルガン・ソロ。
ここでも、ベースが反応よく低音を効かせて、演奏を支える。
オルガンもムーグに負けない挑戦的な速弾き。
粋な感じの弾き飛ばしである。
この辺は、テクニカルなクロスオーヴァー調。
伴奏は、コード中心のエレクトリック・ピアノ。
スチュアートのオルガンが聴こえると、一気に「世界」ができあがる気がする。
これこそ個性なのだろう。
けれんみたっぷりの決め。
続いてギター・ソロ。
テンポは速いが、あいかわらずのファズを効かせた朴訥な味わいのジャズ・ギターだ。
テンポが緩やかにダウン、ピアノの重々しい和音をきっかけに、ヴォカリーズが復活。
弛緩。
再び RETURN TO FOREVER 風である。
ヴォカリーズのリードで一気に再びテンポ・アップ。
エレクトリック・ピアノのメカニカルなリフレインがドライヴする。
緊張。
そしてヴォカリーズ。
再び弛緩。
そして、丸っこい音色のムーグ・ソロ。
今度は、やや低めのおちついた音で走る。
ライド・シンバルがあおる。
アップテンポの演奏にヴォカリーズも加わって、さらに走る。
ややシリアスな変拍子パターンへとアンサンブルはまとまり、繰り返し。
最後も緊張感を高めるようなピアノのコード打ちの連発。
ジャズ室内楽風の典雅なイントロでぐっと惹きつけ、ファンタジックな序盤を経ると一気に技巧的な演奏へと突入してゆく作品。
語法は、スチュアートの作品に比べると、格段にフュージョン的である。
そして、そのフュージョン・サウンドに類まれな個性の注入と稠密な(気まぐれなのかも知れないが)工夫を凝らして成功している。
まず、序盤では、幻想的なフルートとオリエンタルなヴォカリーズそしてパーカッション。
ひたすら美しい。
初期 WEATHER REPORT か。
中盤以降は、息を呑むようなソロだ。
ガウエンは、絶品といえるムーグ・ソロとエレクトリック・ピアノ、ピアノで展開をリードし、スチュアートはもっぱらオルガン・ソロ。
各自のソロをフィーチュアし終わると、終盤に向けガウエン中心にテンションが上がってゆく。
そして、ガウエンをしっかり支えるのが、マーレイのベースである。
全編でベースは大活躍だ。
後半は、透明感のあるデリケートな音を、テンポの変化をまじえつつ、スピーディに積み重ねており、きらびやかさと同時にヒリヒリするような神経質なイメージもある。
パイルのプレイはシンバル・ワーク中心。
ガウエンの作品。
「Borogoves」(4:12+6:29)ムーグ、オルガン、フルートによるクラシカルなアンサンブル。
管楽器を思わせる美しいムーグ。
追いかけあい重なり合う主題(1)。
こういうセンスは、フュージョン界ではなくブリティッシュ・ロックのものなのだろう。
一瞬の静寂に続き、オルゴールのように可憐に歌うエレクトリック・ピアノ、そしてベースのハーモニクスと柔らかなグリッサンド。
夢見るような世界である。
やはり RETURN TO FOREVER を思わせる。
ベースがワウと深いコンプレスを効かせて切なく歌う。
二つのベースが録音されており、なかなかブルージーな絡みを見せる。
ふと気づけば、エレクトリック・ピアノ、ベースにハイハットが加わり、次第にリズムが形作られている。
やがて、アンサンブルとして静かに動き出す。
このひそやかな立ち上がりがすばらしい。
夢から醒めたように鮮やかに飛び出すギター。
伴奏はリズミカルなクラヴィネットとベース・リフ。
8 分の 10 拍子。
ワウ、ナチュラル・ディストーションを効かせた、ややヘヴィなジャズ・ギター・ソロが続く。
乱れ打つドラムス、ベースとクラヴィネットの跳ねるようなリフが、ギターを支えて続いてゆく。
スタカートにリズミカルなボトムとレガートにうねるリードのコンビネーションだ。
最後はドラムスがビシッと決める。
(Excerpt From Part 2)
荒々しいオルガンのロングトーンにミドルテンポのドラムスとベースがアクセントする、重厚なオープニング。
メランコリックなファンファーレのようなテーマ(2)が、スチュアートのオルガンからガウエンのムーグへと交互に渡りながら、次第に音程を上げてゆく。
ファズ・オルガンとムーグは、追いかけあいから二声のハーモニーへと進む。
珍しくシンフォニックな広がりのある演奏だ。
このテーマ(2)は主題(1)の変奏のように聴こえる。
そしてギターが主題(1)を明解に再現。
ムーグは、引き続きバロック・トランペットを思わせるシンフォニックなオブリガートを見せる。
テーマのリフレイン、そしてスネア・ロールから透明なヴォカリーズへ。
前曲に似て、ややオリエンタルなヴォカリーズでムードは一気にメローなジャズ・タッチに。
主題(1)を回想しつつも、リズミカルでリラックスした演奏へと移ってゆく。
ムーグのリードによる軽やかなテーマ演奏。
クラリネットのようなムーグ。
すそを払うようなハモンド・オルガンの控えめなオブリガートがいい。
行進曲風の勇ましくもかわいらしい演奏だ。
ムーグのテーマは、フェード・アウトしてゆく。
再びギターが主題(1)を提示。
続いて 4 拍子と 3 拍子の交じった GENTLE GIANT 風のユーモラスなアンサンブルが始まる。
ピアノ、エレクトリック・ピアノに続き、ベースとギターが、ひそひそ話のような演奏を繰り広げる。
クラシックならハイドンのようなおどけた曲調だ。
そして、ワウ・ギターに続くおどけたようなオルガンの下降音形をきっかけにして、ファズ・オルガンがテーマを提示。
伴奏はピアノの和音弾き。
ギター、ベースも次々加わり、音は厚みを増し演奏は加熱してゆく。
ユーモアとスリルのバランス。
クライマックスでドラムスが激しく一撃し、演奏は追い立てるように迫る。
決めを一発。
宝石が散らばるように華麗なエレクトリック・ピアノの下降、そしてピアノ、エレクトリック・ピアノが反応しあい、ギターのリードで演奏は一気に走り出す。
ピアノは激しくコードを連打。
荒々しいドラミングによるつむじ風のような演奏が始まる。
ギターのリードとピアノのコード・ストローク。
ブレイク。
再び、エレクトリック・ピアノが華麗に舞い踊り、テインカー・ベルの杖の一振りのように魔法の粉をふりかけると、すべてが静まり可憐に消えてゆく。
(Part 1)
クラシカルな愛らしいテーマを用いた、小さなオーケストラのようなジャズロック作品。
ファンファーレ調のムーグが印象的だ。
ファンタジックな空気が静かに渦を巻きながら一つの流れへとまとまってゆく、前半の美しさ。
一方、クラヴィネットでリズムを刻み、ギターが走るパート 2 終盤は、典型的なジャズロック。
さらに、オルガンとムーグがシンフォニックなアンサンブルを見せ、悠然とした雰囲気のままパート 2 のテーマが再現するパート 1 前半からムーグによるマーチに至る辺りは、まるで EGG のようだ。
リズミカルでユーモラスな後半は、GENTLE GIANT なみの複雑な演奏である。
浮遊感と疾走感を山あり谷ありといった感じで乗り切ってゆく演奏は、テーマを大事にしたアンサンブル指向であり、ソロはほとんどない。
この緻密な構築性は、クラシックの影響だろう。
パート 2 抜粋がパート 1 の前にあるという構成は、単なる洒落なのだろうか、それとも?。
スチュアートの作品。
「Elephant」(14:32)
象の鳴き声の如きギターとムーグによる効果音風のノイジーなオープニング。
荒々しい音響処理が HENRY COW 風である。
そして、互いに様子を見るような雰囲気を保ちながら、ムーグとエレクトリック・ピアノによるフリー・フォームの演奏が始まる。
電気処理されたドラムスが挑発的に駆け抜ける。
秩序はまだない。
ゆらゆらと湧き上がっては沈み込むノイズと電子音。
エレクトリック・ピアノによるきらめくような和音が繰り返される。
渦を巻くような曲調だ。
2 拍子のエレクトリック・ピアノと 3 拍子のファズ・ギターが重なり合う。
ドラムスは、力強い 8 分の 6 拍子を叩き出し、ベースも猛々しく吼えるようにリフを刻む。
即興風のソロ・ギターが続くも、周囲はまるで意にそぐわないように勝手に進んで、ぶつかり合う。
序盤はアグレッシヴなフリー系ジャズロックである。
ピアノが 8 分の 5 拍子のパターンを提示。
ファズ・ギターがうねる。
エレクトリック・ピアノ、ドラムスによる 8 分の 25 拍子のパターンへ。
そして、ムーグ・ソロ。
小粋にベンディングを決めまくる、メインストリーム・フュージョン風の達者なソロだ。
テンポは軽やかにアップ、シャープで弾力あるリズム・セクションとともに、疾走感が強まってゆく。
ボトムはファンキーなリフへと変化し、ソロはムーグからオルガンへ渡る。
後拍を強調するブルージーなリズムとともに、ごわごわとしたオルガンが唸りを上げる。
ネジを巻くようなオルガンが一閃すると、なんと 1 曲目「Tenemos Roads」のテーマが鮮やかに甦る。
これは驚いた。
透明感あふれるヴォカリーズと対照的にアンサンブルの音色は荒々しい。
華麗に機敏に動きながら、アルバム全体を回顧する演奏が続く。
まろやかな音と変拍子という得意のコンビネーションが、他では得られない独特の緊張ある調和感を生む。
静かなギターに導かれて、フルートとピアノらによる幻想的なアンサンブルヘ。
ヴァイブやオルガン、ヴォカリーズの切れ端が風に緩やかに舞う。
美しくもメカニカルなところは、複雑な教会の旋法による賛美歌のようだ。
オープニングと同じ形なき世界が帰ってくる。
ヴォカリーズとエレクトリック・ピアノ、ヴァイブの 5 拍子の歩みが一筋の光明に思えるも、世界は揺らいだままである。
やがて、オルガン、エレクトリック・ピアノ、フルートの響きが重なり合い、すべてをぼやけさせ、うっすらと光る霧の向こうへと消えてゆく。
長い長いデクレシェンド。
おいてきぼりを食らったような、寂しく、それでもどこか慰撫されたような気持ちのまま、僕らは取り残される。
即興パートをつなぎ合わせて一つのドラマに仕立てた大作。
うっすらと色のついた混沌が渦を巻くうちに、大胆な変拍子アンサンブルへとまとまり、再び、形を解きほどいて消えてゆく。
エフェクトや電気処理などサウンドにも凝った作品である。
1 曲目のテーマへの回帰がみごとにドラマを締めくくっていると思う。
スチュアート・ガウエン共作。
作曲者の特徴がよく現れたインストゥルメンタル主体のジャズロック大作が並ぶ。
個性的プレイヤーの集結した大所帯なだけに、大作における各メンバーの音楽趣味総覧的な面は避けられないが、そこは、一人一人のプレイをじっくり楽しむということで問題ないだろう。
コンパクトな楽曲指向としてではなく、アドリヴ込みのライヴを見るような感覚で聴くと、今度は、その綿密な構成にかえって驚くくらいだ。
エレクトリックなサウンドに込められたソフトなグルーヴと知的な構成、品のあるユーモアは、いかにも英国風であり、この幻想的なサウンドと、いわゆるフュージョンの健康的な躍動感が結びついた理想的な音楽が、「これ」なのだ。
おもしろいのは(予想通りというか)、ガウエンのエレクトリック・ピアノとムーグのプレイに彼のエレガントでひたむきな美音志向がにじむ一方で、スチュアートの作品には、オルガンを用いたテーマが提示されるせいもあって、ストレートなロック・スピリットが色濃く出ていること。
この二人の拮抗も、このサウンドを生み出した原動力の一つだろう。
全体に、明快でユーモラスなテーマを軸に躍動的なソロと精緻なアンサンブルがてんこもりであり、カンタベリー・ジャズロックの総決算といえる内容だ。
好きな人にはため息ものでしょう。
そして、当たり前かもしれないが HATFIELDS と GILGAMESH のいいところ取りです。
ここでリチャード・シンクレアのヴォーカルがはいるはず、と力んで外されちょっとズッコケますが。
メイン・ストリームから注目されなかったのは、世間でよくいわれるパンクの隆盛よりもアメリカ偏重他国珍重のジャズ・シーンの硬直が原因ではないでしょうか。
どこかにありそうな音を使ってどこにもない音楽ができている、といってもいかもしれない。
(AFF 6 / ESD 80402/412)

| Phil Miller | guitar | Dave Stewart | organ, electric piano, piano, synthesizer |
| John Greaves | bass, vocals | Pip Pyle | drums |
| guest: | |||
|---|---|---|---|
| Georgie Born | cello | Paul Nieman | trombone |
| Phil Minton | trumpet | Selwyn Baptiste | steel drum |
| Keith Thompson | oboe | Jimmy Hastings | flute, clarinet, bass clarinet |
| Peter Blegvad | voice | Rick Biddulph | bass |
78 年発表の第二作「Of Queues And Cures」。
第一作の発表を待たずして、ベーシストが元 HENRY COW のジョン・グリーヴスに交代、通常の 4 ピース編成に管弦楽器奏者など多彩なゲストを迎えている。
(後の「Playtime」のライナーでは、女性チェロ奏者ジョジー・ボーンの加入が大きな刺激になったとある)
アラン・ガウエン、アマンダ・パーソンズらがグループを離れて、グループ本体はスリム・ダウン、まるで HATFIELDS の時代に戻ってしまったようだと、スチュアートが回想している。
ただしグリーヴスの存在感は大きく、プレイ/作曲ともにスチュアートと対等な位置に迫っていると思う。
内容は、前作よりも多彩である。
めまぐるしいリズム・チェンジと緻密なアンサンブルが不思議なユーモアと透明なファンタジーを生み出す、マジカルなジャズロックを基本に、「分かりやすいポップ」さとストレートな表現も盛り込まれている。
そして、ジョジー・ボーンやジミー・ヘイスティングスら、ゲストの管弦の音を的確に用いて、さまざまな効果を上げている。
全体に、前作と比べてリラックスしたイメージのある内容だ。
本作録音後のヨーロッパ・ツアー中に、「即興性の高まり」を不服としたデイヴ・スチュアートが脱退する。(即興集団 HENRY COW 出身のグリーヴスの音楽性との相性もあったのかもしれない。実際「Playtime」のコメントにそれらしいことを匂わせている)
スチュアートの後任探しは難航するが、結局アラン・ガウエンが再加入し、ライヴ活動が続く。
「The Bryden 2-step(Part.1)」(8:52)
一直線に走るような、スピード感ある演奏が特徴の作品。
「Tenemos Roads」を思い出させるセンチメンタルなギターのテーマを軸に、スピーディでパーカッシヴなタッチの演奏が続く。流れるような展開の中では、丹念さが売りのファズ・ギターが演奏をやや重苦しくしてしまっている、という意見もあるやもしれない。
キーボードやブラス、リズム隊(ジョン・グリーヴスのベースは予想以上にテクニカルであり、アピール度も高い)によるメローな表現の切れがいいだけに、余計に目立つ。
もっとも、それを特長、個性と受け取れればいいのだが。
一方、後半のギターを中心としたアグレッシヴなプレイは新鮮だ。
また、オープニングをはじめ、シンセサイザーを大きくフィーチュア。
華やいでもハードになっても、品性とユーモアあり。
スチュアート作。
「The Collapso」(6:16)
ギターによるノリノリのラテン風テーマが印象的な明朗ジャズロック。
テーマの変奏をメインに展開してゆくが、スティール・ドラムスも用いた明るく元気な調子から、現代音楽調(オルガンのせいか EGG に酷似)のこんがらがったアンサンブルまで、演奏は変幻自在。
気がつけば、ラテンからはずいぶんと離れ、込み入った演奏になっているところが、このグループらしい。
4 分 20 秒辺りからの変拍子トゥッティが強力だ。
それでいて、軽やかさは一貫する。
ドラムスも目のさめるようなプレイを連発。
ベースは、ファズを使うなど、ここでも目立ちたがり。
キャッチーなテーマ、緻密で迫力あるアンサンブルなど、代表作の一つといえるでしょう。
スチュアート作。
「Square For Maud」(11:30)
硬質かつ厳しい空気に満ちたジャズロック。
リズム・チェンジと圧迫感ある変拍子アンサンブルが特徴。
冒頭から、ボーンのチェロらによる低音反復が厳粛なイメージを強める。
一方、オリジナル NATIONAL HEALTH らしさ(HATFIELDS らしさというべきか)は、ここではミラーのギターの存在感にかかっている。
変則リズム、謎めいた反復、ノイズや管弦楽器を用いたアヴァンギャルドな展開など、全体に緊迫感あり。
中盤、緊張感が強まり、管弦器主導のヘヴィなトゥッティが爆発するところは、KING CRIMSON を思わせる迫力である。
管楽器を追い立てる、嵐のようなハモンド・オルガンのオスティナートに注目。
管楽器のアドリヴが始まるポリリズミックな演奏を、ナレーション(ピーター・プレグヴァドによる)で破断させて緊張を解き放つアレンジはみごと。
後半もギターがリードするがダークな雰囲気は変わらず。
8 分 30 秒くらいからのシンセサイザーによるテーマからは、ヘヴィなニュアンスはあるが、スチュアートらしいプレイで疾走が始まる。
エンディングはやっぱり HENRY COW だ。
前曲とのギャップは、そのまま、HENRY COW と HATFIELDS の志向の違いを浮き上がらせる。
(かように主義のある演奏志向極まれりというイメージのある二人が、後にともにセンスあるポップ・ミュージック路線で成功を収めるところがおもしろい。天才は変わり身も鋭いのだ)
チェロのアクセントがみごと。
名作。
グリーヴス作。
「Dreams Wide Awake」(8:48)ハードなロックンロールとメローなカンタベリー・タッチが切り替わるキャッチーな作品。
ロカビリー風の活きのいいオープニング。
8+4 拍子のリフでワウ・オルガンが走る。
サイケデリックで荒っぽいソロだ。
意外にも爽やかなギターのストロークから、オルガン、ギターのトリッキーなユニゾンでしばらくひきづり回して、メロディアスなオルガンへと軟着陸。
EGG や HATFIELDS でおなじみのスチュアート・トーンのすてきなオルガンだ。
ベース・ラインも、リチャード・シンクレアと同じく、なめらかな歌心を感じさせるプレイでオルガンと積極的に絡んでゆく。
16 分の 10 拍子上のおなじみのギター・ソロあたりからバッキングのキーボードはエレクトリック・ピアノに変化。
絡まるようなトゥッティが、くるくると拍子を変えながら、舞台をひっくり返してゆく。
最後は、シンセサイザーとギターのユニゾンから、エレクトリック・ピアノ、ベースらによるリズミカルなトゥッティ、そしてメローなキーボードがまとめる。
やや軽めだが、時代の音を把握したカンタベリー・ジャズロックの佳品である。
ベースはたしかにカッコいいのですが、出ずっぱりで食傷する。
ミラー作。
「Binoculars」(11:43)
HATFIELDS の第二作を思わせるメロディアスで小粋な歌ものジャズロック。
多彩な音による味つけがとてもうまい。
オープニングは、オルガンの和音によるおだやかな調べ。
ベースに導かれて軽快に始まるのは、なんとメロディアスな歌である。
グリーヴスは美声であり歌唱にも味わいはあるが、ここはぜひリチャード・シンクレアに登場していただきたかった、と思ってはいけないことを思ってしまう。
オブリガートは独特の生硬さが魅力のギター、そして間奏では、ヘイスティングスのフルートをフィーチュア。
こうなると、完全に甦る HATFIELDS である。
流れるようなアンサンブルとともにフルートが舞い踊る。
受けとめるオルガン・ソロもスチュアートらしいファズの効いた音による軽快なものだ。
5:15 辺りの和音進行によるテンポ・ダウンも きわめて HATFIELDS 的だ。
テンポが落ち切った 6:40 付近からは、クラシカルな金管楽器を静かに沸き立たせ、管弦楽による即興のようなアンサンブルを経て、再びフルートやオルガンが演奏を包み込む。
そして、回想されるメイン・ヴォーカル。
クラシカルなタッチとジャズ、AOR の絶妙なブレンド。
エンディングも、ファズ・ギター、芯のあるベース、オルゴールのようなエレクトリック・ピアノのアンサンブルの上を、フルートが静かに、すべるように流れてゆき、ギター・ソロがまとめる。
ゴージャスなラウンジ・ミュージックである。
パイル作。
「Phlakaton」(00:08)
混声アカペラによる早口言葉のようなもの。
パイルの作品。
「The Bryden 2-step(Part.2)」(5:31)
EGG 風のオルガン主体のアンサンブルに導かれる終曲。
Part.1 のテーマも思い出を振り返るように再現。
スリリングに高まる変拍子アンサンブル。
スチュアートの作品。
(CRL 5010 / ESD 80402/412)
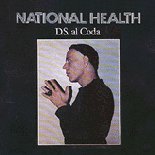
| Phil Miller | guitars | Dave Stewart | keyboards |
| John Greaves | bass | Pip Pyle | drums, electric drum |
| guest: | |||
|---|---|---|---|
| Elton Dean | saxello | Amanda Parsons | vocals |
| Barbara Gaskin | vocals | Jimmy Hastings | flute |
| Richard Sinclair | vocals | Annie Whitehead | trombone |
| Ted Emmett | trumpet |
82 年発表の作品「DS al Coda」。
アラン・ガウエン追悼のためにグループを再結成し、発表された。
全曲ガウエンの作曲であり、内容は GILGAMESH の作品から、リハーサルのみで公式には演奏されなかった作品まで、多岐にわたる。
ここ以降しばらくの間作品があまり発表されないことを考えると、カンタベリー・ジャズロック最後の傑作という見方もできる。
オープニング、管楽器セクションとエレクトリック・ドラムスをフィーチュアした 80' サウンドに驚かされるものの、フィル・ミラーのギターがリードを取り始めると、やや新しめのカンタベリー・サウンドという感じになり、一安心。
パット・メセニーはここの音を聴いていただろうか。
ミラーはあまり他の作品では見られないアグレッシヴなプレイを随所で披露している。
1 曲目は、エルトン・ディーンのサックスが見せ場を作る。デジタル・シンセサイザーの薄っぺらな音に慣れられるかどうかがキー。80 年ごろのわたしはダメでした。
3 曲目は、リチャード・シンクレアのノーブルなスキャットも交えた、軽妙で繊細でエレガントな傑作。70 年代カンタベリー・シーンを次代へと橋渡しするような作風である。結局はフルート、フレットレス・ベースなど記名性の高さが核なのだろうか。
4 曲目はアグレッシヴな良作。
6 曲目は明快なアンサンブルによるドリーミーなファンタジー。硬めのシンプルな 8 ビートとこんがらがりすぎないところが 80 年代である。
名小品「Arriving Twice」もあり。
スチュアートのプレイ・スタイルはややハード・ドライヴィンであり、ガウエンのデリカシーあふれる文学書生スタイルとはニュアンスが大きく異なる。
「Portrait Of A Shrinking Man」(5:35)デジタル・シンセサイザー・サウンドをフィーチュアしたビッグ・バンド風のゴージャスなジャズロック。
ディーンもナベサダばりにメロディアスに迫る。あまりに派手で唖然とするが、終盤のアンサンブルは「らしさ」が現れる。
「TNTFX」(3:11)GILGAMESH の第二作より。クライマックスの連続のようにハイ・テンションでスリリングな佳作。小品だが密度が高い。フィル・ミラーが大見得をきる。
「Black Hat」(4:52)リチャード・シンクレアのスキャットで一気に視界が開けるカンタベリー・ジャズロック。大人になった HATFIELDS。キーボードとフルートの呼吸も抜群。心なしかギターもうまい。スチュアートがガウエン風のムーグのプレイを披露する。ベースもシンクレアのようだが。
「I Feel A Night Coming On」(6:38)ノイジーなサウンドでアグレッシヴに迫るキーボードがカッコいいハード・ジャズロック。
ポイントは、スチュアートのシンセサイザー・ソロとグリーヴスによるベース・ライン、そしてサックスとエレクトリック・ピアノの応酬の妙。。
BRUFORD、U.K. と並び、現代までファンが途切れないテクニカルでプログレッシヴなスタイル。
フュージョンとの違いは、やはり諧謔味とサイケ感覚(カオスでも平然という気合)。
サックスはフリーの素養を見せつつもしっかりフュージョンしている。
「Arriving Twice」(2:20)GILGAMESH の第一作より。アコースティック・ギターとキーボードのデュオによるドリーミーな小品。
「Shining Water」(8:50)オープニングは派手だが、後は、HAPPY THE MAN にも通じる密やかでファンタジックな世界像。
フルート、キーボードによる管楽器アンサンブルの手ざわりは、未知の惑星で未知の生物たちが戯れる静かなダンスのようだ。
アナログ・シンセサイザーの名手として、ガウエンのデリケートな感覚は、キット・ワトキンスと相通じるのかもしれない。
「Tales Of A Damson Knight」(1:55)これはいかにも。長尺で完成させていただきたかった。
「Flanagans People」(5:20)デジタル・シンセサイザーがオルガンだったら EGG の曲といってもいいかもしれない。ダイナミックでカッコよし。出入りの多い展開はいかにもカンタベリー。
「Toad Of Toad Hall」(7:26)ガウエンらしいデリケートな世界からスチュアート風のダイナミックな展開へ。
序盤は、RETURN TO FOREVER の第一作を吸収し、練り上げ、醸造した作品である。
バッキングを張るブラス系のシンセサイザーのサウンドがいまひとつなのがここでも悔やまれる。
(LA 02 / ESD 80402/412)

以上の鑑賞・解説は、三枚のオリジナル LP を全収録した ESD の CD 二枚組「National Health Complete」を用いて行った。
本作には、オリジナル・アルバム以外にも追加トラックが収録されている。
特に、初期の豪華ラインナップによる「Paracelsus」(抄)は、ツイン・ギター、ツイン・キーボードによる絶妙なアンサンブルを洒脱さとユーモアで包んだ幻の大傑作。
さらに 1990 年録音の「The Apocalypso」は、第二作の「The Collapso」を打ち込みで翻案した、キーボードの魅力満載の迫真のプログレッシヴ・ジャズロック。
打ち込みにも関わらず、光り輝くような演奏になっている。
今のスチュアートさんにはこういうのを期待します。
(ESD 80402/412)

| Phil Miller | guitar in 2,3,4,5,6,7,8,10,12 | Phil Lee | guitar in 5,6,8,10 |
| Steve Hillage | guitar in 2,3,4,7 | Dave Stewart | keyboards in 2,3,4,5,6,7,8,10,11 |
| Alan Gowen | keyboards in 2,3,4,5,6,7,8,10,12 | Mont Campbell | bass in 2,4,5,6,7,8,10 French horn in 1 |
| Neil Murray | bass in 3 | John Greaves | bass in 12 |
| Bill Bruford | drums in 2,3,4,5,6,7,10 | Pip Pyle | drums in 8,12 |
| Amanda Parsons | vocals in 3,6 | Barbara Gaskin | vocals in 11 |
| Peter Blegvad | vocals in 12 |
96 年発表の「Missing Pieces」。
ビル・ブルフォード在籍時の録音やアルバムに名を残すことなく途中脱退したモント・キャンベルによる作品など、オクラ入り音源を集めた編集盤である。
「Complete」では抜粋でしか聴けなかった「Paracelsus」が、完全版で入っているなど、度肝を抜く内容の発掘ものである。
EGG 以来モント・キャンベルの作曲センスには定評があったが、それも本作によって改めて証明されたことになる。
サウンドはもちろん、とんでもなく複雑な構成やリズムにも関わらずソフトで洒脱に響くカンタベリー・ジャズロック。
電化マイルスに端を発した潮流は現代音楽と合流し、英国で一つの完成形を見た。
1 曲目「Bouree」キャンベル作曲のフレンチ・ホルンの多重録音による小品。
クラシックの素養が活かされたというか、クラシックそのもの。
2 曲目「Paracelsus」小粋で愛らしいテーマにしたがって、多彩なキーボードとギターがクラシカルにして華麗なるアンサンブルを繰り広げる傑作。
「Bouree」のオルガン版を挿入したり、エンディングがライヴ録音にリミックスされていたりと、遊び心たっぷりの編集である。
とろけるような美感と裏腹に複雑な演奏になっており、特にリズムへのこだわりは怪奇というべきものである。
キャンベルの作品。
個人的に、不思議に思うほど好きな曲です。午前の TBS のラジオ番組のジングルだったと思うのですが。
原点はマイルス・ディヴィスの「Filles De Kilimanjaro」か。
3 曲目「Clocks And Cloud」やや哀しげで切ないエレクトリック・ピアノ(おそらくガウエンだろう)のイントロがアマンダ・パーソンズのヘヴンリーなヴォーカルで美しく昇華してゆく作品。
フィル・ミラー独特のギター、エレクトリック・ピアノ、ピアノによる瑞々しいアンサンブルが、品のある落ちつきを感じさせる。
しみわたるような音の響きの美しさを堪能できる作品だ。
終盤のオルガン・ソロの歪んだ音は、まさしくデイヴ・スチュアート。
AOR 調の音使いながらアメリカ風の汗臭いファンキーさがないところは、ある意味衝撃的。
スチュアートの作品。
傑作。
4 曲目「Agrippa」では、重々しいリズムでゆったりと進む演奏がリラックスしながら緊張するという矛盾した気分を醸し出す。
計算を積み重ねた結果、最後には即興に近くなりましたという作品なのかもしれない。
アンサンブルが、まるで顕微鏡でのぞいたアメーバのように、伸び縮みをゆったりと繰り返している。
ふわふわと浮遊するような曲調なだけに、スッとはまった時には息を呑むようなカタルシスがある。
HENRY COW 的な面もある。
キャンベルの作品。
史上の人物名を題にするのは、その人物をイメージしているということなのだろうか。
5 曲目「The Lethargy Shuffle & The Mind-Your-Backs Tango」ビッグ・バンドを模した軽妙な 8 分の 9 拍子のアンサンブルで始まるダンス・ナンバー。
オルガン・ソロ、ギター・ソロなどを交えつつ、スピーディな演奏からメローな演奏まで目まぐるしく曲調が変化する。
オルガン、エレクトリック・ピアノ、二つのギター、エフェクトあり/なしの組み合わせから任意の数だけ取り出して、自由に並べたような曲である。
スチュアートの作品。
6 曲目「Zabaglione」解説不能のジャズロック。
ベースのリフが多少目立つが、後はもう目まぐるしく変化する生き物のようなアンサンブルであり、相性が悪いと悪酔いするかもしれない。
ヴォカリーズもあればキーボード・バトルもあり、エンディング付近では珍妙なユニゾンの決めもある。
ユーモラスだがどこか恐ろしい。
7 曲目「Lethargy Shuffle Part 2」パート 1 同様ビッグ・バンド風のオープニングからエレクトリック・ピアノ、ギターとフィーチュアされ、4 ビートに変わると二本のギターでインタープレイが始まる。
強烈な決めを連発してオルガンが踊りドラムスがオルガンとシンクロすると再び 4 ビートに戻ってギターが苛立っているがそれ以外は割と穏やかな演奏が続く。
しかし、リズムが 8 ビートに変わると、すべての楽器がそれぞれにはりきり始め、収拾はつかなくなる。
それでも強引にユニゾンに持ち込み、最後はジャジーにカッコよく決める。
シンプルなビートの効いたジャズロック。
60 年代のジャズ・ミュージシャンによるロック解釈のパロディのような感じ。
スチュアートの作品。
8 曲目「Croquette For Electronic Beating Group」キャンベルの最初期の作品。
ファズの効いたオルガンとギターによるオープニングから、全体にシリアスなトーンが感じられる。
二台のエレクトリック・ピアノ、オルガンと二本のギターそしてベースが次々と組み合わせを変えながら、さまざまなハーモニーやユニゾンを繰り広げる。
クラシカルなフレーズやフーガ風の展開もある。
しっかりと計算され整ったアンサンブルがキャンベルの作風らしい。
小曲ながら充実した内容だ。
ドラムスはピップ・パイル。
9 曲目「Phlakaton」ライヴの嬌声と科白だけ。
パイルの曲となっているからパイルの声なのかもしれない。
10 曲目「The Towplane & The Glider」唯一ガウエンの作品。
ガウエンらしい耽美な演奏とハードな調子をうまく組み合わせ、全体に躍動感のある作品だ。
典型的な NATIONAL HEALTH の音であり明快な佳作だ。
11 曲目「Starlight On Seaweed」キャンベルの作品。
演奏はスチュアート/ガスキンによる。
幻惑的なシンセ、ファズ・オルガンの重々しい響きとエレクトリック・ピアノのきらびやかな響きに包まれ、情感を破棄したように抑制されたメロディ・ラインが歌い上げられる。
12 曲目「Walking The Dog(extract)」ライヴでけたたましく奏でられる R&B。
一瞬で終わり。
やっぱり真面目には終われません。
タイトル通り、最初期のアルバム未収作品を集めた驚愕の発掘作品。
エネルギッシュでありながらスタイリッシュな、カンタベリー・ジャズロックの貴重な一ページである。
初期のイニシアチブを、EGG 出身のモント・キャンベルが取っていたことも分かった。
奔放なプレイがいびつな形を成しつつ、次第に一つのうねりにかわってゆく面白さ。
緻密な計算と豊かなポップ・センスによる、ユーモラスで知的な音楽の法悦。
やはり NATHONAL HEALTH は、このカンタベリー・ジャズロックをきわめた頂点にあるグループなのだ、と実感させる内容だ。
特に取り上げるならば、最初期のメンバーであったモント・キャンベルの作品だろう。
大胆なリズムとポリフォニーの実験は現代音楽に迫るものである。
このアカデミズムが、スチュアートのロッカーらしい骨っぽさやガウエンのデリカシーあふれる審美センス、パイルの海千山千なジャズ感覚と結びついたところに、音楽としての幸福があったといえるだろう。
発掘作にも数々あれど、本アルバムこそは真の必聴盤といえる。
(VP-113-CD)

| Phil Miller | guitar |
| Alan Gowen | keyboards |
| John Greaves | bass, vocals |
| Pip Pyle | drums |
| Alan Eckert | guitar on 1,3,4 |
2001 年発表の発掘ライヴ盤「Playtime」。
音源は、79 年 4 月のフランス公演(前半 4 曲)、および同年 12 月のアメリカ公演(後半 5 曲)より。
スチュアート脱退後の最終ラインナップによる演奏である。
メンバー交代の過酷な状況を乗り越え、ガウエンを再びキーボーディストに迎えてグループを復活させた勢いが感じられる。
音楽的な内容は、アメリカのクロスオーヴァー/フュージョン・シーンへの、英国からの決定的な回答といえるもの。
ミラーのギター・プレイに HATFIELDS の名残を見るも、残りのメンバーの演奏は、きわめて技巧的かつメインストリームのエレクトリック・ジャズを意識したハードなものだ。
耽美にして繊細そしてユーモラスという英国カンタベリー・ジャズロックとしての魅力を越え、パワフルなインプロヴィゼーションも取り込んだ、アメリカのフュージョン・ミュージックへの挑戦という熱気が感じられる。
テンションの高さは、MAHAVISHNU ORCHESTRA や RETURN TO FOREVER や BRAND X の全盛期にひけをとらない。
特に、フランス公演にて ART ZOYD から迎えた アラン・エッカルのギターは、ほとんどジョン・マクラフリンかジョン・グッドソール。
目立ちたがりのグリーヴスのテクニカルなベースも機を見ては前面に出る、というか出ずっぱり。(もちろんヴォーカルも披露)
しかし、全体を通して輝くのは、やはり、アラン・ガウエンの卓越したキーボード・プレイだろう。
楽曲は、第二作のものとツアー中に作曲された新曲から。
「Flanagan's People」(15:57)電化マイルスか初期 KING CRIMSON か、熱っぽいインプロヴィゼーションを交えた力演。
前半の BRAND X ばりのハード・ドライヴィンな演奏もカッコいい。
即興か作曲かに悩んだグループが、その悩みのままに思いの丈を吐き出したような演奏である。
CRIMSON のイメージはディストーションを思い切り効かせたベースのせいでもある。
第三作より。
「Nowadays A Silhouette'」(6:32)ジャジーなバッキングを受けてガウエンのドリーミーなムーグ・シンセサイザーが冴える。
HAPPY THE MAN のキット・ワトキンスとともに、この楽器の第一人者であることは間違いない。
独特のピッチ・ベンドが心地よい。
自由なテンポのゆれでスポンテニアスに動くアンサンブルもみごと。ガウエンのライヴ・アルバム「Before A Word Is Said」でも演奏されている。
「Dreams Wide Awake」(8:18)再びガウエンのシンセサイザーさばきが冴える名品。ミラーのギターが入った途端に一気に HATFIELDS 化する。
中盤、エッカルの暴走ギターが率いる火の出るような演奏も聴きもの。第二作より。
「Pleaides」(10:26)
「Rhubarb Jam」(1:17)
「Rose Sob」(1:46)
「Play Time」(9:38)前半は鬼気迫る熱演。やはり KING CRIMSON。 (まったくの私見だが、フィル・ミラーはロバート・フリップをアイドルの一人としていると思う)後半でようやくお馴染みのカンタベリー節が現われる。いつになくミラーのギターが過激に度を越す。GILGAMESH の第二作より。
「Square For Maud part 1」(5:11)第二作より。冒頭のチェロはグリーヴスがベースで再現。文字通り角張った感じの演奏が続く。
「Square For Maud part 2」(7:51)オルガン(メロトロンか)とエレクトリック・ピアノによる胸にしみいるブリッジを経て、再び熱いアンサンブルへ。とはいえ殺気はなく、どちらかといえばリラックスした、演奏を楽しんでいるような雰囲気である。
(RUNE 145)
キーボード奏者の一人アラン・ガウエンは若くして亡くなったが、ソロ作として「Before A Word Is Said」や元 SOFT MACHINE のヒュー・ホッパーとのコラボレーションを残している。 (GILGAMESH の項参照)
