
| Derek Shulman | lead vocals, bass |
| Ray Shulman | bass, violin, guitar, percussion, vocals |
| Phil Shulman | sax, trumpet, recorder, lead vocals |
| Kerry Minnear | keyboard, bass, cello, lead vocals, percussion |
| Gary Green | guitars |
| Martin Smith | drums, percussion |
イギリスの技巧派プログレッシヴ・ロック・グループ「GENTLE GIANT」。 60 年代に R&B バンドで活動していたシャルマン三兄弟が新しい音楽の模索やコマーシャリズムへの反発を掲げて結成した。 70 年 VERTIGO からアルバム・デビュー。 ほぼ不動のメンバーでいくつもの名作を発表し、70 年代を駆け抜ける。 81 年解散。 初期の作品は、ヘヴィなサウンドとリリカルな語り口を対比させながら、眩惑的なリズム、マドリガル風のハーモニー、室内楽風のアンサンブルなどの技巧を凝らしたもの。 クラシカルな叙情性とビートを主眼としたファンキーな作風が拮抗するが、一貫するのは R&B 的なグルーヴ。 ポップスから決して離れていないところがすごいのだ。 彼らの野望は、今世紀のポップ・ミュージックの集大成と、その新たな進化のヴィジョンの提示である。

| Derek Shulman | lead vocals, bass |
| Ray Shulman | bass, violin, guitar, percussion, vocals |
| Phil Shulman | sax, trumpet, recorder, lead vocals |
| Kerry Minnear | keyboard, bass, cello, lead vocals, percussion |
| Gary Green | guitars |
| Martin Smith | drums, percussion |
70 年発表の第一作「Gentle Giant」。
THE BEATLES に端を発するアート・ロックやブルーズ・ロックの経験を活かして、流行のヘヴィなサウンドにさまざまなアイデアを盛り込んだ作品である。
後年、にわかに表現し難い個性派として名を馳せる本グループだが、本作では、巨人伝説のような幻想文学的な主題の採用やクラシックのカットアップなど、典型的なプログレのアプローチを取っており、比較的「分かりやすい」作風となっている。
演奏面では、自然に感じられる変拍子やアクセントずらし、立体的なヴォーカル処理、トリッキーなアンサンブルといった特徴もある。
ハードでファンキーなサウンドと感傷的で叙情的な表現が一つになった、ブリティッシュ・ロックらしい作品ともいえる。
往時主流であったブルーズ・ロックやハードロック、サイケデリック・ロックを消化して独自のやり方で再構築している。
プロデュースはトニー・ヴィスコンティ。
VERTIGO レーベル。
「Giant」(6:26)
チャーチ・オルガンが厳かに湧き上がり、そこへベース音の連打が重なってシンバルが打ち鳴らされる、スリリングなイントロダクションだ。
デレク・シャルマンはソウルフルなヴォーカルを叩きつけ、受けとめるギター、ホーン、オルガン、ベースらのアンサンブルは、ダイナミックでしなやかながらも、あたかも呼吸をさえぎるように不規則で奇妙なリズムでうねる。
この一人かけ合い風のアンサンブルは、繰り返しごとに少しずつ音色やパターンを変化させてゆく。
ドラムスも普通のタイム・キープはしない。
パワフルでエネルギッシュだが、ハードロックになり得ない、どこかいなすようなテクニカルな演奏である。
一糸乱れぬユニゾン、ぶわっと湧き上がるオルガンの響きなどから、叩きつけるような決めを経てブレイク、一転してアカペラが始まる。
ベース連打、ビッグバンド風のホーンの高まり、波打つオルガンに反応して高まるヴォーカル・リフレイン。
そして、湧きあがるオルガンとともにリズムが復活、三度エネルギッシュなメイン・ヴォーカル・パートへ突進する。
ギター、ベース、オルガンがしなやかに、敏捷に絡み合いながら、演奏の舵を切ってゆく。
ユーモラスなユニゾンから再び音量が落ち、テンポが変わって、二度目の緩徐パートへ。
ベースが静かに堅調にリフを刻み、オルガンとメロトロンがゆったりと、神妙に澱みながら流れてゆく。
ここの演奏には SOFT MACHINE に通じるアブストラクトにしてミステリアスな効果がある。
ビートは失われ、雄大なメロトロン・クワイアとブラス(シンセサイザーもあるようだ)、コーラスが鳴り響き、演奏は交響楽的なクライマックスへと向かう。
一山越えると再びベースのビートによる密やかなアンサンブル、そして二度目の壮大なクライマックスもホーン、メロトロン、コーラスが泰然と轟きわたる。
ベースのシングル・ノート連打をきっかけに、むさ苦しい熱気あふれるメイン・ヴォーカル・パートが四度再現。
キレのあるユニゾンでぷっつりと途切れる。
リズムやアクセントに工夫を凝らした、ファンキーでクラシカルな変わり種ハードロック。
ワイルドなメイン・ヴォーカルをハードにうねるアンサンブルで支える変拍子テーマを狂言回しに、吹奏楽やミニマリズムやモード、無調演奏や教会音楽風など、一風変わった展開を見せる。
エネルギッシュなようでいてそのトーンはあくまで悪夢的、幻想的である。
ロックっぽいだけで何か別の音楽なのかもしれない。
全編を支えるホーン・セクション、安定感あるギター、音数多いベース、俊敏なオルガンなど、各役者は絶妙の呼吸でプレイする。
「騒」と「沈」を組み合わせた比較的単純な構成ではあるが、大胆なリズムの変化と多彩な音色と解き明かせないアンサンブルに魅力がある。
ヘヴィでアグレッシヴなテーマを支えるのは、豊富な音楽知識とシュールレアリスティックな感覚だと思う。
一筋縄ではいかないことを早々と開陳する、格好のオープニング・チューンだ。
「Funny Ways」(4:24)
室内楽調のヴァイオリン、チェロのアンサンブルにかき鳴らされるアコースティック・ギターのストロークが重なる哀愁あるイントロダクション。
イメージは「エリナー・リグビー」だ。
たおやかなリード・ヴォーカル(ミネア)とハーモニー(フィル・シャルマン)は、あたかも寒空に肩を寄せ合うような歌唱である。
繰り返しの伴奏はエレガントなピチカート。
展開部では、憂鬱なチェロがざわめき、三人目のヴォーカリスト、デレク・シャルマンが決然と問いかけ、ヴァイオリンとともにハーモニーが密やかに応える。
哀しげな弦楽の響きが尾を引き、メランコリックなメイン・ヴォーカル・ハーモニーへと回帰する。
ギターのストロークの堅実な響き、弦楽の伴奏の細やかな変化。
再び、力強い低音弦の響きと厳しい問いかけ、そして典雅なストリングス、コーラスによる応え。
一転、ピアノ、パーカッションらによる快調な 7 拍子のリフが飛び出して、快調なブギーへ。
低音部を強調したラグタイム風のリズミカルなリフレインが、ここまでのうち沈んだ様子とあまりに対照的だ。
タムタムを打ち鳴らしヴォーカル(フィル、ミネア)がノリノリのお囃子調で軽やかに歌うと、一気にムードはリラックス、演奏もジャジーに変化して、オルガンはファンキーに跳ねる。
バロック風のトランペットがきらめくように響きわたり、一瞬の空隙を経て、パンチのあるドラミングとともにブルージーなギター・ソロが飛び込んでくる。
シンセサイザーによるバロック・トランペットのオブリガートが鮮やかだ。
またも、弦楽の余韻を引っ張って、アコースティック・アンサンブルの伴奏するメイン・パートのバラードへと戻る。
セピア色をした、消え入るようなヴォーカル・ハーモニー。
最後は、タムタムが空ろに鳴り響き、つぶやくように「Funny Ways...」が繰り返される。
弦楽をフィーチュアした、センチメンタルで英国ロックらしいバラード。
弦楽の優美だが哀しげな音色とアコースティック・ギターの枯れた寂しげな音色が、深い哀愁と気品を交じりあったような雰囲気を作る。
感傷的だが甘さはない。
もう一人のリード・ヴォーカリスト、ケリー・ミネアはか細い美声とそれに似合ったデリケートな歌唱表現が特徴である。
無常感の演出にはぴったりだ。
中間部は苦渋に満ちた現実から悩みのない夢の世界へと足を踏み入れたようなイメージだが、最後に再び現実に帰るところにビターな味わいがある。
中間部のインスト・パートの展開は、初期の KING CRIMSON に通じるスリルと知性が感じられる。
ピチカートや重音の旋律など、弦楽器のプレイにいろいろと工夫がある。
センチメンタルでクラシカルな静けさの中に中世をイメージさせる本源的な暗さがにじむところもこのグループの特徴であり、それは英国産のロックに流れる血のなせる業だと思う。
1 曲目とのコントラストも効果的。
「Alucard」(6:05)
遠くでシンセサイザーが早口の独り言。
サックス、ギター、オルガンが追いかけあう序奏から、ドラムスのピック・アップとともにシンセイサイザーとファズ・ベースのリードする力強いリフが立ちあがる。
サイケデリックなサウンドによるファンキーな R&B 調の演奏だ。
ファズでギトギトに加工されたベース、ギターとサックス、オルガンが奇妙な応酬を繰り広げる。
ノイズ風に処理された音は初期のシンセサイザーだろうか、すさまじい音を吐き出しながらも、演奏にはしっかりとユニゾン、ハーモニーと係り結びをこなす安定感がある。
下降ユニゾンとともに走るドラムスのフィルがカッコいい。
にじむようなノイズとともに消えてゆくアンサンブル。
実音より反響が先立ってクレシェンドする「お化け屋敷」風の不気味なハーモニー(テープ操作なのだろう)が始まる。
フロア・タムが静かに刻まれる。
オブリガートはびっくりした声のような、というか元祖オーケストラヒットのようなブラスの一撃。
ギターはうねうねとした舌足らずのフレーズを繰り返し、オルガンは狂おしくまとわりついて、ファズ・ベースとともに怪しくもどこか滑稽な雰囲気を盛り上げる。
オープニングのパワフルなアンサンブルが復活。
サックスのリードでオルガン、ファズ・ベース、ギターがエネルギッシュに攻め立てる。
一瞬の破断、ヴォリュームが一気に落ち、同じリフを繰り返しつつもオルガンのアドリヴを交えたひそひそ話のような演奏となる。
オルガンが奔放に呪文を奏でるうちに次第にジャジーなアドリヴへと発展、ホーンを中心としたアンサンブルの演奏のヴォリュームが次第に上がってくる。
ギターが奇妙な舌足らずのフレーズを再び繰り返すも、尻切れトンボ気味に演奏はリタルダンド、各パートが呼応しつつフェード・アウトしてゆく。
ブレイク。
フロア・タムの連打とともに、幽霊屋敷風のおどろおどろしいヴォーカル・ハーモニーが復活。
ガイコツの踊りを思わせる舌足らずギター・リフレインを経て、今度はギター、オルガン、ベースが短いフレーズを数珠繋ぎにした追いかけっこ風の演奏を見せる。
これは傑作だ。
力強いリフでリードする全体演奏が復活、エンディングはキメを経て全員乱れ弾き。
そして、オープニングと同じように、遠くでシンセサイザーが早口の独り言。
効果音的なアレンジを駆使しシンセサイザーのエレクトリックなサウンドをアクセントに配したファンキー・チューン。
ラウドでファンキー、なおかつサイケデリックなセンスもある作品であり、全体にデフォルメの効きが強烈だ。
メイン・パートでは、管楽器、ギター、シンセサイザーらが緊密に連携しあうジャジーかつパワフルなアンサンブルが圧倒的。
オフビートな休符を強調した奇妙なギターのフレーズが印象的だ。
ハーモニーの音響処理やアンサンブルの音量を大きく変化させる展開などドラマティックな演出も取り入れている。
サイケデリックなギトギト感もあり、毛色の変わったブラス・ロックと見ることもできる。
有名な「ドラキュラ」のアナグラムであるタイトル通りに内容は怪奇ものらしく、さまざまな妙な音は幽霊屋敷風の効果を出すためのようだ。
「Isn't It Quiet And Cold ?」(3:43)
ジプシー風のヴァイオリンとチェロのロマンチックなデュオが導くのは、センチメンタルなフォーク・ソング。
巧みなピチカートとアコースティック・ギターの伴奏によるワルツ。
ヴォーカルはあくまでソフトでデリケートである。
弦楽の小さな間奏を経た展開部では、いつのまにかアクセントの位置が変わって 4 拍子になっている。
ピアノの爪弾き、枯れ葉散るカルチェラタンを想い出させるフレンチ・ジャズ風のヴァイオリンによる間奏。
切ない歌を支えるヴォカリーズが美しい。
寂しさを紛らすように音を転がすマリンバ・ソロと巧みだが嫌味のないベース・ラインは、ジョン・レノンの名作「Girl」や「In My Life」を髣髴させる。
曲の終わりに、前曲と同じシンセサイザーの一くさりが挿入されている。
アコースティックなサウンドがすてきなシャンソン風フォーク・ソング。
伴奏をつとめる弦楽奏、ちょろちょろと駆け回るピチカート、もの悲しくも愛らしいマリンバのソロ、バックのヴォカリーズなどなど、THE BEATLES の流れのブリティッシュ・ロックの伝統を感じる。
3 拍子と 4 拍子の切りかえはあまりに鮮やかであり、初めはなかなか気がつかない。
こういうラヴソング的な叙情性のある曲が配されているところが、ふつうのプログレッシヴ・ロックのグループとは大きく異なるところである。
胸キュンの歌詞もいい。
2 曲目と同じく、前曲とのコントラストによって、アルバムの流れを巧みに作っている。
「Nothing At All」(9:12)
12 弦アコースティック・ギターによるベース下降のアルペジオは時を彫琢して美しい波紋を織り成す。
幻想へといざなう可憐なる序奏は、見えざる天使の呟きのようなフォーク風の美しいハーモニーを呼び覚ます。
受け答えるオブリガートのベース、ギター、オルガンもひそやかであり、夢のようなアンサンブルである。
アコースティック・ギターが静かにコードをかき鳴らすサビの歌メロには深い切なさが刻み込まれている。
2 コーラス目からは丹念なギターのアルペジオをキーボードが気まぐれに、しかし静かに支えている。
むなしきコーラスそして哀感の強いサビを経て展開部へと進むが、まずはエレキギターがブルージーなリフで挑発を繰り返し始める。
何かが始まるのかと思わせておいて、返答するのは風に吹きすさぶか細いオルガンの調べだけ。
再びギターの挑発、そして今度はデレク・シャルマンのパワフルなヴォーカル・パフォーマンスが飛び出す。
へヴィなリフ、ヴォーカルにギターが執拗に絡みつく。
すべてを忘れたかのようなブレイクを経て、シンバルが響き渡り、電気処理されたドラム・ソロが始まる。
渦を巻くような連打の嵐の果てに唐突に挿入されるのは、クラシカルなピアノ独奏(リストの「愛の夢」)である。
ピアノの音はあたかもラウンジ B.G.M のように流れるが、執拗に挑発するエレクトリック・ドラムスによってフリー・ジャズに変貌し、ドラムスとアグレッシヴな呼応を繰り広げる。
このピアノ、ドラムスのインタープレイは、やや取ってつけたようではあるが実験精神旺盛、大胆でいい。
シンバルの響きが収まると、あたかも夢から覚めたかのように、アコースティック・ギターの調べが静々とつむぎだされ、美しいヴォーカル・ハーモニーが再現される。
諦観というかニヒリズムというか伴奏のオルガンが湧き立ち、アコースティック・ギターが響く。
幻想的な哀愁バラードを軸に白昼夢のように融通無碍の変転を見せる奇想曲風の傑作。
メイン・パートは、透明感あるきわめてデリケートなフォーク・バラードであり、ブルージーなハードロックを経て、ドラム・ソロ、クラシック・ピアノ・ソロ、現代音楽にまで発展する。
そして、二人のヴォーカリストの表現特性の違いを大いに活かしている。
硬軟/強弱の変化による音楽的なストーリー・テリングというよりは、一見脈絡がないようで螺旋階段を上がり下がりしながら巧妙に流れてゆく、いわば、逃れようにも足が動かない悪夢によく似た展開といえる。
ドラムス・ソロを盛り込むための作品という見方もできるが、ピアノを交えたそのドラムス・ソロのアレンジも大胆奇抜である。
メイン・テーマを奏でるハーモニーのたおやかな美しさ、センチメンタリズムは、間違いなく英国ポップスの主流、王道にある作風といえる。
こういった王道ポップス的な主要素を活かしつつ誰も演奏できないロック・アンサンブルを作り上げるのがこのグループの得意技だ。
「Why Not」(5:34)
密やかにリフを提示するオルガンをきっかけに、ギターとともに一気に跳ねるようなハードロックの幕開けである。
パワフルなメイン・ヴォーカルと鮮やかに対比する、変化の予兆の如きクラシカルなオルガンのオブリガート。
メイン・パートではギター・リフとパンチのあるヴォーカルをブラスがオブリガートしながら、ハードなファンクのグルーヴで突き進む。
再びバロック風のオルガンのオブリガートを経て、予想とおり、リコーダーのハーモニーがミネアによる繊細な賛美歌ヴォーカルを呼び覚ます。
教会音楽への一気呵成の変転である。
この動と静のコントラストはお見事。
哀愁をはらむベース・ライン、無調風ながらもほのかにロマンティックな響きのある旋律を刻むギターのリードは次第に力を増し、メイン・リフの再現とともに、ゲイリー・グリーンらしい技巧的なブルーズ・ギター・ソロが始まる。
ギターは歌メロをなぞりながらも、あくまで自由奔放な動きを見せる。
バッキングはダイナミックだ。
フィル、デレクによるツイン・ヴォーカルのメイン・パートをパワフルな演奏が支えて走る。
繰り返しからは、ファンキーなリフをギターによる 5 拍子が押さえつけるブリッジを経てテンポ・アップ、軽快なブルーズ・ジャムが始まる。
ブルーズ・ギターとソウル・ジャズ調のオルガンが調子よく反応しあうイケイケなロックンロールである。
ギターが大きく見得を切っておしまい。
そして、エピローグだろうか、またも遠くでシンセサイザーが早口の独り言。
クラシカルなアクセントを大胆に効かせた、変化に富む船歌調のハードロック。
野卑なブルーズ・ロックと教会音楽というかなりの落差を自然な流れでまとめている。
リズムの変化も巧みだが、曲調の豹変もまた圧巻である。
間奏のオルガンで何かあるぞと匂わせて、間奏部の始まりで一気にクラシカルで優美なアンサンブルへと持ち込むのだ。
後半では、本格的なブルーズ・ジャムへと突っ込み、テクニカルなギターを全開にし、「堅苦しいのはやめにしようよ」といわんばかりにアルバムを締めくくる。
前曲ではケリー・ミネアの繊細なヴォーカル・パートでデレク・シャルマンの豪快な歌唱をはさんだが、本曲では逆のサンドイッチになっている。
この二人の声質の違いを生かしたツイン・ヴォーカルのアレンジは、後々まで続いてゆく。
ちなみにオーディションでグループに参加したギタリスト、ゲイリー・グリーン(オーディションに際して、自分の出番で、唯一この人だけがバンド全体のチューニングのし直しを要求したという逸話がある)はこのとき二十歳の若者。
ギタリストは才気を制御できない天才型の早熟プレイヤーが多いが、グリーン氏は終盤になってのようやくの出番でも冷静にこなしている様子である。
天性のスタジオ・ミュージシャン気質か。もっとも、そういう気質でないとこんなバンドに自ら入らないだろう。
「The Queen」
英国歌のワン・コーラスから、しなやかなギター演奏、そしてエンディングのキメを繰り返して、おしまい。
THE BEATLES の「Her Majesty」にも似たおフザケか。
ブルージーでパワフルなヘヴィ・ロックにクラシックやジャズを放り込んで、なお聴きやすさも損なわないという構成力に驚かされる傑作。
多彩極まる曲調をまとめあげるアンサンブルの妙から変拍子やアクセントずらしなどリズム面の技巧まで、充実した演奏力を見せつけるが、そういう技巧だけを無駄に浮き上がらせない、センチメンタルなメロディとファンキーなグルーヴがある。
これは、ポップスの基本ができているということだろう。
サウンド面でも、ハードなオルガンやギターのプレイが切れのあるロックらしさをしっかり強調し、その上でヴァイオリン、チェロ、サックス、さらにはトランペットまでにわたる多彩な音色が味付けとしてぜいたくに盛り込まれている。
かように多様なファクターを楽曲に映えさせるセンスもいい。
さらに言及すべきは、ツインからトリプル、コーラスまであるヴォーカル・ハーモニーのみごとさである。
主としてフィル・シャルマン、デレク・シャルマンとケリー・ミネアがリード・ヴォーカル担当のようだが、特に、デレクとケリーの声質/唱法のコントラストが、雰囲気作りに大きく貢献している。
ケリーのヴォーカルには教会旋法の影響が見られるので、ひょっとするとこのバンドのコーラス・ワークの巧みさは教会で培われたのかもしれないといった想像も湧いてくる。
とにもかくにも、まず、ポップス、ロックとしての基本がしっかりできており、そこへさらなる挑戦と実験を試行した内容である。
さまざなま音楽の要素を大胆にまぜ合わせて、ポップスの限界点を大きくクリアしようというグループの意図は明白である。
ただし、あえていえば、音の印象が VERTIGO らしいというか、やや重く渋すぎるという気もするが、それもたいした瑕疵ではないだろう。
普通のロック・ファンにはどう聴こえるのか、たいへん興味があります。
(VERTIGO 6360020 / LICD 9.00722 O)
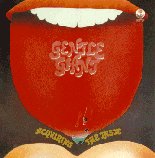
| Derek Shulman | alto sax, clavichord, cowbell, lead vocals |
| Ray Shulman | bass, violin, viola, electric violin, Spanish guitar, tambourine, 12 string guitar, organ bass pedals, skulls, vocals |
| Phil Shulman | alto & tenor sax, clarinet, trumpet, piano, claves, maracas, lead vocals |
| Kerry Minnear | electric piano, organ, mellotron, vibraphone, Moog, piano, celeste, clavichord, harpsichord, tympani, maracas, lead vocals |
| Gary Green | 6 & 12 string guitar, 12 string wah-wah guitar, bass, donkey's jawbone, cat calls, voice |
| Martin Smith | drums, tambourine, gongs, side drum |
| guest: | |
|---|---|
| Paul Cosh | trumpet, organ |
| Tony Visconti | recorder, bass drum, triangle |
71 年発表の第二作「Acquring The Taste」。
大胆なアイデアあふれるサウンドと卓越したテクニックが織りなす奇天烈な楽曲が詰め込まれた傑作アルバム。
中世風の旋律が醸し出す暗鬱な幻想のトーンが貫く地味でくすんだ色合いの作品集だが、淡々と進む演奏の中には複雑な趣向がこれでもかと盛り込まれている。
アンサンブルは普通のロックを大きく離れ、ガウディの建築のように怪奇な整合性とフリー・ジャズやアヴァンギャルド・ミュージックに迫る逸脱性を兼ね備えた現代音楽風のものになっている。
楽曲は、クラシックのエチュードのようにシンプルなモチーフやいわゆるロック的な語法をパーツとして用いて組み上げてサウンドに対する並外れた配慮をゆき届かせた、精密な手工芸品である。
(ペンタトニック・スケールをブルーズではなく民謡風に使うのが特徴的)
楽器のクレジットを一見するともう笑うしかない。
明らかにやり過ぎである。
卓越したヴォーカル・ハーモニーも特徴。
はち切れそうなまでに膨れ上がった幻想をシャープなギターのキメが切り裂いて溜飲を下げるオープニング曲が本アルバムを通した作風を象徴している。
静かなる挑戦というイメージの内容であり、本作がベストというリスナーはシアワセだが根治不能。
プロデュースはトニー・ヴィスコンティ。
ムーグ・シンセサイザーのプログラミング担当はクリス・トーマス。
VERTIGO レーベル。
「Pantagruel's Nativity」(6:54)
奇妙な管楽器を思わせるムーグ・シンセサイザーによるユーモラスにしてどこか妖しい序奏。
切れのいいアコースティック・ギターのコード・ストロークと太いベース音に支えられて、賛美歌調のヴォーカルがおだやかに歌い出す。
宙ぶらりんのような不思議な旋律の繰り返しに連れて湧きあがるメロトロン・ストリングス、次第に高まる緊張。
ケリをつけるのは、ギターが放つ鋭いのキメのフレーズである。
2 コーラス目には、ぴよぴよとさえずるリコーダーと勇ましいバロック・トランペットも伴奏に加わる。
高まる演奏、そしてクライマックスを経てギターによるシャープなキメ、湧き上がるストリングス。
それを切り返すようにもう一つのギターがけたたましい和音を轟かせて、テーマを再確認する。
ムーグのテーマと繰り返しとともに沈みゆくアンサンブル。
一転して荒々しいギターによって第一テーマを変奏した強烈な第二テーマが提示される。
ぐいぐいと何かを突きつけるようにうねるテーマ、そしてデレク・シャルマン主導で幻惑的な多声コーラスが始まる。
複雑にエコーする祈祷のようなハーモニー。
ベースのリフがリードする演奏に重なるように、サックスとワウギターがテーマを繰り返すも、演奏は次第に無表情になってゆく。
そのまま、ジャジーなヴィブラフォン・ソロ。
幻惑的なヴァイヴの音、そしてタイム・キープのドラミングが心地よい。
そして、ギター・ソロ。
ディストーション・サウンドとペンタトニック・スケールによるシャープなハードロック調のプレイだ。
次々と音の加わったけたたましいアンサンブルは、ヘヴィなギターによる第二テーマの再現で断ち切られ、丹念なドラミングに支えられて、再び渦を巻くような三声コーラスが湧き上がる。
謎めいた演奏だ。
ドラムスがふと止まってブレイク、メロトロン・ストリングスのうっすらと響く中、トランペットとベースが空ろな表情で、それでもせい一杯、テーマを再現し、繰り返す。
リズムも復活、トランペット、ベースのテーマ演奏に深くぼんやりと澱むメロトロンが交差し、薄墨色の幽玄の世界が広がる。
そして、さえずるリコーダーとともに神秘的なメイン・ヴォーカル・パートへと回帰。
穏やかながらどこか不気味な詠唱にトランペット、オルガンらの活気ある演奏がからみつき、矛盾孕みの不思議なムードにあふれる。
シュールな展開で脈絡をぶっ飛ばすところは KING CRIMSON 風の野心的なスタンスだ。
最後も、吹き上げるメロトロンをバックにシャープなギターがまとめる。
サイケデリックなけたたましさと半音進行がえもいわれぬ宙ぶらりんな不気味さを醸し出す幻想作品。
特異な音階とシンコペーションも用いた変則リズムの主題を軸に、モーダルなヴォーカル・ハーモニーと多彩な音色のソロとを配した内容である。
クラシカルな味わいも充実し、主題やトランペットの音がバッハの晩年の作品を思わせるところもある。
間奏の始まりでギターによって提示されるヘヴィな第二テーマも、リズムのアクセントとのズレが奇妙な印象を与える。
これは第一作の 1 曲目でも用いられていた手法だろう。
また、他に特徴があり過ぎるために目立たないが、ブラス・ロックなどと呼ばれることは決してないのに、これだけ管楽器が充実している(テナー/アルト両サックス、トランペット)ロックバンドも珍しい。
KING CRIMSON の「Lizard」あたりを思わせる中世暗黒時代的な雰囲気もある。
メイン・ヴォーカリストはケリー・ミネア。
俊敏なリコーダーはトニー・ヴィスコンティだろうか。
題名から、内容は中世巨人伝説に材を取ったフランソワ・ラブレーの風刺小説に関わるものと思われる。
傑作。
「Edge Of Twilight」(3:51)
クラリネット、ヴァイオリン、チェロらの夢見るようにゆったりとしたドローンとともに、呪文のように謎めいたヴォーカルが歌いだす。
歌唱は繊細に音程を追うも深いエコーにおおわれて陰鬱である。
間奏は、深いエコーに浸ったヴァイブとムーグによる愛らしくも消え入りそうなデュオ、それを受ける足音のようなベースのリフレイン。
ヴァースの繰り返しの伴奏は、アコースティック・ギターの自由な爪弾きとテープ逆回転処理を施したノイジーなスネア・ドラムスである。
迷宮に誘い込まれたようなイメージだ。
再びヴァイブの間奏からベースの足音リフレインに導かれて、チェロ、クラリネットの薄暗いデュオによるテーマ演奏と不気味なコーラスによるかけ合いが繰り返される。
高いところから深い海の底を覗き込むような音の定位だ。
いつしかティンパニの連打も始まり、ハモンド・オルガンが静かにそれに応じてゆく。
切り返すチェンバロ、アコースティック・ギター、ヴァイオリンのピチカートらが交錯するアンサンブルは、漣のように寄せては返し、人力ディレイのような独特の効果を上げる。
泡が水底からゆっくりと水面へと浮かび上がってゆくイメージだ。
勇ましいティンパニ連打を皮切りに、スネア・ドラムス、木琴らが加わってフリー・フォームの打楽器アンサンブルが始まる。
ロックの打楽器ソロといえば退屈なドラムス・ソロが定番だったが、ここでは大胆かつ技巧的な打楽器アンサンブルが繰り広げられる。
再び木管、アコースティック・ギター、ヴァイオリンらの伴奏によるによるメイン・ヴォーカル・パートへ。
消えてゆくヴォーカルを追うように、エレクトリック・ピアノが一くさりささやく。
多彩な楽器群と凝った音響処理によるバロック風ポリフォニーの現代音楽ロック。
いわゆるチェンバー・ロックに迫るきわめて現代音楽な内容であり、じつはロックというよりはアレンジに凝り捲くったポップスというべき内容である。
管絃楽器によるメロディアスにしてモーダルなテーマ、打楽器をフィーチュアしたフリー・パートなどは、ひたすらに幻想、妄想的であり、現代人特有の不安な気分を巧みに表現している。
興味深いのは、古典的で安定感のあるクラシックのサウンド要素をまとめていながら、伝統的な情趣を静かに拒絶するような挑戦的な姿勢が感じられるところだ。
音響処理によるクラシックのアップデート版と見てもいいだろう。
メイン・ヴォーカリストはケリー・ミネア。
パーカッション・パート(ティンパニ)のアレンジと演奏、そしてチェロ、木琴の演奏もケリー・ミネア。
ゲイリー・グリーンは演奏に加わっていない模様。
歌詞の冒頭は 6 曲目の曲名と同じなので何か関連があるのだろう。
「The House, The Street, The Room」(6:05)
ピアノをリードに、ベース、ファズ・ギターのユニゾンによる暗く重みのあるテーマが提示される。
8 ビートだがアクセントを半拍ずらしてリフが完結するため、変拍子に聴こえるところが面白い。
特に繰り返しでは、同じ音形ながら微妙にシンコペーションの位置をずらしており、拍子を数えていると心拍がおかしくなりそうだ。
そして、テーマをバックにデレク・シャルマンのソウルフルかつ無遠慮なシャウトが叩きつけられる。
スキャットのハーモニーも薄暗くミステリアスである。
一転、アコースティック 12 弦ギターがかき鳴らされるとヴォーカルがケリー・ミネアに交代、伴奏もバロック風の愛らしいものへ変化する。
ただし、その結末はエレキ・ギターが加わってややおちゃらけ気味に崩れてゆくのだが。
再び、パワフルなメイン・ヴォーカル・パート、そしてアコースティックなバロック・アンサンブル、ミネアのヴォーカル・パートが繰り返される。
アコースティック・ギターのトレモロ風のフレーズがエレキギターと合流して崩れてしまうと、ドラムスの連打とともに秩序は消え失せる。
ここから即興演奏開始、ピアノ、アコースティック・ギター、マリンバ、トランペット、チェンバロ、ヴァイオリンのピチカートらが落ちつきなく無闇やたらと転がりまわる。
よく聴くと、テーマを遁走曲のように繰り返すクラシカルなアンサンブルになっているようだ。
混乱し始めたアンサンブルに突如飛び込んで世界をひっくり返すのは、けたたましいブルーズ・ギターのアドリヴ。
ヘヴィなハモンド・オルガンもテーマを 8 分の 6 拍子で切り取って再現しながら飛び込んでくる。
ギターはメタリックなオルガンの轟きとともに独走状態に入ってぶち切れた気味のアドリヴを繰り広げ、スクラッチのような低音ノイズ(これ、何の音ですか)がざわめいて、過激な一触即発ムードが高まる。
ギターとオルガンはけたたましくポリリズミックに交錯し、そのクライマックスを切り裂くように、変則リズムのテーマとともに再びパワフルなメイン・ヴォーカル・パートが雪崩れ込む。
受け止めるのは、やはりささやくアコースティック・ギターと密やかな詠唱である。
エンディングは再び秩序を失って、さまざまな楽器が次々とテーマを打ち出して気まぐれな演奏を繰り広げる。
得意のブルージーな労働歌調を基本としながらも、変則アクセントのテーマやノイズ、フリーフォームの演奏などによる振れ幅が大きい怪へヴィ・チューン。
野太く、それでいて傾いだように不安定なテーマを巡り、重く硬いシャルマンのパート、それを軽くいなして受け止める感じのクラシカルなミネアのパートが対立しつつ、やがてオモチャ箱が破裂したようなカノンへと発展するかと思えば、爆発的なへヴィ・ロックへと転げ落ちる。
どことなくすわりの悪い演奏をきりきり舞いするようなプレイで破断して、ギターとハモンド・オルガンが轟くへヴィ・ロックによる荒々しくも安定したクライマックスへと導く。
カタルシスはそこにある。
コワれる寸前というか、コワれて破片が飛び散った後の祭りというか、このグループ以外では味わえない作風である。
トランペットはポール・コッシュ。
リコーダーはトニー・ヴィスコンティ。
「Acquiring The Taste」(1:39)
ヴァイオリン、フルート、バスーン、リコーダーといったさまざまな音をムーグ・シンセサイザーで模し、ポリフォニックなアンサンブルを構成する、モダンなメヌエット。
奇妙に揺らいだオープニングから、優美な多声の流れを経て、愛らしい呼びかけと返答を繰り返すうちに溌剌としたユニゾンへと収束し、みごとなアンサンブルとなる。
アナログ・シンセサイザーの多重録音によるバロック風ソナタ小品。
ムーグ・シンセサイザーの旋律が対位的に構成されている。
テーマそのものはクラシカルだが、そのアンサンブルには一口で何風といえない不思議な味わいがある。
演奏はすべてケリー・ミネアによる。
ピッチの狂ったようなオープニングは、意図的なのかそれとも製作上の事故なのか。
「Wreck」(4:40)
冒頭、怪しげなベース、ギター、電気発動機のノイズのようなシンセサイザーによる得意の「終わりのよく分からない」テーマ(3 曲目同様アクセントずらしの 4 拍子)が力強く示される。
パワフルなデレク・シャルマンのヴォーカルはテーマをそのままに、労働歌のような節回しのコーラスがヴォーカルを囃す。
1 コーラスはベースが支え、一瞬のヴァイオリン間奏から 2 コーラス目はギターが加わる。
野暮ったくも力強い。
突如、ヴァイオリン、チェンバロ伴奏によるバロック・アンサンブルが出現、ヴォーカルも旋律はそのままにミネアによるソフト・タッチに変貌する。
リスナー置いてきぼりのただならぬアレンジの妙である。
典雅なチェンバロのオブリガート。
悠然と高まる弦楽奏をバックにギターが華やかに飛翔する。
ただし、テーマの旋律は貫かれている。
再び、ピアノが導く舟歌コーラスのクロス・フェード、ヴォーカルもハーモニーもパワフルにがなりたてるが、それもつかの間、フェード・アウトともに、今度はトニー・ヴィスコンティの加わったリコーダー・アンサンブルによる美しいバロック・ソナタへと豹変する。
おそらく P.F.M. が憧れたに違いないジョージ・マーティン風の弦楽奏の優雅な響きと切なく泣きそぼるギターの高まりを経て、最後は、またもヴォーカルとコーラスのかけ合いによる野卑な労働歌である。
舟歌調のへヴィ・ロックと雅な宮廷風クラシックを一つの変則アクセント・テーマでつないだプログレッシヴなロック。
転調後、砂糖菓子のようにカラフルでデリケートなバロック・アンサンブルに変化するあたりが本領発揮である。
ライナー・ノーツにある通り、野卑なコーラスの繰り返しが耳に残る。
一つのテーマを巡り、デレク、フィルのシャルマン兄弟、ミネアによるマルチ・ヴォーカルを駆使して、いくつもの曲想をぜいたくに配した作品だ。
ちなみに、リコーダーのアンサンブルは GG のライヴにおける必殺技の一つである。
「The Moon Is Down」(4:48)
チューニングかテープ逆回転処理か、ふらふらと揺れ動くブラス・アンサンブルがフェードイン、次第に明確なテーマへと収斂してゆく。
テーマを受けて、チェンバロ、ベースの伴奏で多声のハーモニーによる歌唱が始まる。
余韻は深くこだまし、旋律もモーダルなので幻惑的なムードが強い。
サビはアコースティック・ギターのコード・ストロークが決然と響き、コーラスにエコーがかかる。
エレクトリック・ピアノのオブリガートも鮮やかだ。
2 コーラス目からドラムスが加わる。
ビートは軽めのロックだが、チェンバロ中心のアンサンブルとヴォーカル・ハーモニーはきわめて教会音楽的である。
すっと消えゆくハーモニー、そして、ピアノ、ベースが刻むビートとアコースティック・ギターのアルペジオを経て、流れるようにスピード感ある 5 拍子に変化(なぜか最初の 2 小節だけパターンが違う)、次第に演奏のテンポも上がり、心なしか緊張も高まる。
一瞬で軽やかにダンサブルな 8 分の 6 拍子のアンサンブルに変化し、重みのあるピアノの和音とともにやや緊張を解いて安定を取り戻すと、そこで溜め込んだエネルギーを吐き出すように、息を呑むほどにクリアーなブラスのテーマが高鳴る。
屈折した展開が多いだけに、こういうジャジーな突き抜け感は新鮮だ。
遅れなく動き回るベース・ラインにも注目。
弦をミュートしたピチカートがスピーディにかき鳴らされると、トーンを操作してコンプレッサをかけたようなオルガンが幾重にも交錯する、せわしなくも愛らしいアンサンブルがコロコロと転がり始める。
イタリアン・ロックの味わいである。(というかこちらが本家)
饒舌に走るのはエレクトリック・ピアノだろうか。
テンポはみるみる落ち、ピアノとストリングスがゆったりと流れを受けとめて高らかに美しく響き、奥深いファンタジーとなる。
再び、冒頭のテーマによる神秘的なアンサンブル、ヴォーカル・ハーモニーが戻り、ピアノとともにメロトロンが深くどこまでも鳴り響く。
劇的で重厚なエンディング、そしてその後にドビュッシー調の湧き立つようなピアノが夢の余韻を残して消えてゆく。
ジャジーで軽やかなインストゥルメンタル・パートを間奏にはさむ、幻想的なバラード。
その幻想性にはサイケデリックなバッド・トリップの翳りがあり、繊細な美感と耽美な湿り気が微妙に交じりあう。
逸脱しそうで基本はメロディアスな流れがあり、オブリガートなどにおいてはじつに細やかな音遣いを見せる。
間奏部のクライマックスで飛び出すブラスのテーマで目を覚まし、その後は目まぐるしいメリーゴラウンドのようなアンサンブルに引きずられてゆく。
エンディングのまとめもいい。
サイケデリック、プログレ的な幻想性、重さとジャジーなしなやかさ、運動性がブレンドした、独特の美感を誇る名曲である。
「Black Cat」(3:54)
ミュートしたギター、ヴァイオリンとストリングスが、小洒落た 7 拍子のリフをかけ合うイントロダクション。
コケットでやや挑戦的なタッチのリフとは対照的に、メイン・ヴォーカル(フィル・シャルマン)は落ちついて密やかにささやきかけ、追いかけるコーラス(ケリー・ミネア、デレク・シャルマン)とともに妖しく謎めいたハーモニーを成す。
テーマはわりとポップだが、バッキングは薄暗く、コーラスが入るとマドリガル風という得意技である。
散りばめられるエレクトリック・ピアノ。
ミュート・ギター、ヴァイオリンとストリングスのかけあいによる間奏は、一転してビートを失い、生真面目なストリングス・カルテットによるカノンに変化する。
しかし、ピチカートやパーカッションを用いた調子外れのユーモラスな脱力演奏も加わって、弦楽アンサンブルも変調をきたす。
ピチカートした弦の響きは、弾け飛びそうな危うさを演出する。
いつのまにかピチカート連弾がオープニング・テーマを奏で始め、リズムが戻ってくる。
密やかなヴォーカル、そしてハーモニー、そして猫の声がからみつくテーマ演奏の繰り返し。
ストリングスをフィーチュアしたジャジーで官能的な変拍子ラヴ・ソング。
クラシカルな素材を、ストリングスのボウイングとピチカートの音質の違いを効果的に使って配置し、コミカルで描写的な演奏になっている。
テーマは不幸を導く美しくも妖しい黒猫である。
ストリングスとマドリガルによるこわく的で妖艶なるタッチが、妙に堅苦しく行儀のいいカノン風のアンサンブルになって、すぐに乱調気味に崩壊するのは、したたかなキャパ嬢に手玉に取られた良家のお坊ちゃまを描いているに違いない。(妄想です)
いうまでもないが、終盤のストリングスのリフレインにまとわりつくスライド・ギターのグリッサンドのような妙な音は、猫の鳴き声を模したものだろう。
密やかなリード・ヴォーカリストはフィル・シャルマン。
デレク・シャルマンのかすれ声をコーラスで耳にするというのも珍しい体験である。
こんな小品でも、サウンドやアレンジ面で大胆な冒険が行われている。大好きです。
「Plain Truth」(7:37)
オープニングは、ワウをかけたヘニャヘニャなエレクトリック・ヴァイオリンによるブルージーなアドリヴである。
MC のような奇妙なモノローグ(ゲイリー・グリーンらしい。ポール・マッカートニーかと思ったが、そんなわけないか)に反発するように、一気に、ハードな演奏が炸裂する。
テーマ・リフの凡庸さは、飛車を落としてここからどれだけ聴かせることができるかを示すための勇気あるハンデではないだろうか。(別に誰も挑戦していないと思うけど)
孤高のバンドらしい『一人相撲』である。
さて、メイン・ヴォーカリストは、またもや汗臭い労働歌調である。(デレク・シャルマンが歌うと、みなそうなるのかもしれないが)
力強く押すメインのリフは 8 分の 10 + 8 分の 8 で呼応する変拍子パターン。
ファンキーにして下品、そして折れ曲がった、得意のスタイルである。
ギターは、シャフル気味のリフを奏で、大胆にオブリガートを決めるなど渋く活躍する。
間奏は、ヴォリュームをぐっと落としてベース、ギターがテーマを穏やかに繰り返すなかを、エレクトリック・ヴァイオリンが追いかけ、ギターとバトルを繰り広げる。
ここはダイナミックかつ細やかな表情を出すべき演奏なだけに、ドラムスのキレがかなり微妙に感じられる。
交代劇というよりは解雇に近いと想像できる。(大きなお世話)
ヴァイオリンとギターのインタープレイから珍妙なヴァイオリンのオブリガート、そして再び、ハードなメイン・ヴォーカル・パートで強烈にダメを押す。
ここ(3:18 あたり)からが長いインストゥルメンタル・パート。
ギターのリズミカルなアルペジオのリフレイン(何気ないがカッコいい!)から音量を抑えて始まり、そのギター、エレクトリック・ヴァイオリン、ベースによるストイックなアドリヴ応酬(レイ・シャルマンによる一人多重録音だろうか)を経て、やがて我慢し切れなくなったようにギターのパワー・コードが加わってくる。
ワウワウを決めるヴァイオリン、次第にたまってゆくエネルギー。
最高潮から三度メイン・ヴォーカル・パートへとなだれ込む。
エンディングのクールな決めの後も、エレクトリック・ヴァイオリンはフリーキーなワウワウ・ソロをエピローグのようにひっぱり、ヘヴィなトゥッティに止めをさされる。
レイ・シャルマンのエレクトリック・ヴァイオリンをフィーチュアした、ブルージーな変拍子ハードロック。
垢抜けないが力強く、説得力あるリフにもかかわらずリズムはひねくれており、ステップを踏んだら確実に床よりも他人の足を踏む。
一貫してワウ・エレクトリック・ヴァイオリンが、自由なプレイで狂言回しに徹している。
リズムの変化に加えて音量や速度の変化も巧みだが、間奏のアドリヴ・パートはちょっと長過ぎるかもしれない。
エレクトリック・ヴァイオリンの可能性を追求してみたかったのかもしれない。
テーマを聴いていると、イタリアの BANCO への影響が相当強かったことが分かる。
また、全体にカッコいいギターがフィーチュアされている。
なぜか最後のキメの後にもギターをかき鳴らす音が聴こえる。
凝りに凝りまくったという印象を与える傑作アルバム。
古楽調のアンサンブルとヘヴィ・ロックの混合だけでも凄いところへ、変則リズム、複雑なコーラス、フリー・ジャズのような破壊力も持ち込んで、丹念につくり上げた傑作である。
どの作品にも、深い谷のように真っ暗で底無しのイメージがある。
さらりと聴くことも可能だとは思うが、細部に分け入るとさらにさまざまに堪能できる。
そして、楽器のクレジットを見ていただきたい。
通常のバンドで使う楽器に加えて、弦楽器から管楽器まで、もう何でもあり状態である。
特に、ケリー・ミネアとレイ・シャルマンは、恐るべきマルチプレイヤーである。
また、硬軟をうまく使い分けたツイン(トリプル?)・ヴォーカルも、なかなか他では見当たらない特徴だ。
アコースティック・ギターの音がよく聴こえるのも本作品の特徴だと思う。
とにかく 3 曲目までをじっくり聴いてみましょう。
二作目にしてピークを迎えた雰囲気すらある。
個人的には、前期のベストです。
現行の日本盤 CD よりも 15 年ほど前に出た西独 LINE レーベルの CD の方が音が明快です(経年変化が心配ですが)。
本作収録の作品はライヴ録音が少ないそうです。
(VERTIGO 6360 041 / PHCR-4202)

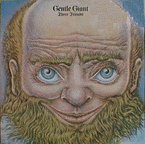
| Derek Shulman | vocals |
| Ray Shulman | bass, violin, 12 string guitar, vocals |
| Phil Shulman | sax, vocals |
| Kerry Minnear | keyboards, vibraphone, percussion, Moog, vocals |
| Gary Green | guitars, percussion |
| Malcolm Mortimore | drums |
72 年発表の第三作「Three Friends」。
ドラマーがマルコム・マルティモアに交代。
作品は、三人の同級生が学校時代の回想と現在の境遇をオーヴァーラップさせる初のトータル・アルバムである。
今回も、オープニングからエンディングまで、流れるような技巧を誇る演奏が幻想的なサウンドで繰り広げられる。
前作できわめた悪夢テイストのアレンジは冴え渡り、ノスタルジーの演出においても独特の奇妙でいびつなイメージを前面に出してくる。
精緻な反復パターンは、次第に不可思議な文様を成して渦を巻きながら異次元へと誘うようだ。
バラードも荒々しいへヴィ・ロックも座標軸の捻れとともにその姿を尋常ならざるものへと変化させてゆく。
トーン調節によるハモンド・オルガンの多彩な音色の延長上にムーグ・シンセサイザーを配置するなど、サウンド・メイキングのセンスにも感服。
35 分程度に抑えたのは、それ以上だと眩暈がしてくるからだろう。
アメリカ・デビュー作。(米盤ジャケットを英国盤第一作と同じにしたのはそのためだろう)
プロデュースはグループ。
VERTIGO レーベル。
「Prologue」(6:14)
スネア・ロールを引き金にハモンド・オルガンとギターによるミステリアスな 3 拍子のリフレインがエネルギーをため込み、ピアノが刻む重いビートとともにスリリングなテーマが提示される。
主導はうねりの効いたギター。
8 ビートだがフレーズを 7 小節と 9 小節に分けているために奇妙に舌足らずな感じがする。
このウネウネとしたテーマを、繰り返し毎にムーグ・シンセサイザーを加えたり、サックスを加えたり、ファズ・ベースを加えたりと、細かく変化をつけながら曲を通して繰り返してゆく。
イントロのオルガンとギターの 3 拍子リフレインと 8 ビートのテーマが交錯しあって緊張が一気に高まると、低音のムーグ・シンセサイザーが一閃、その緊張を解くようにフィル・シャルマンによる密やかなヴォーカルが始まる。
調性の感じられない平板な旋律のヴォーカルだ。
オブリガートのコーラスは得意の三声マドリガルであり、三人の友人を象徴しているのだと思われる。
間奏は、叩きつけるようなオルガンとギターの 3 拍子リフレイン。
2 コーラス目は、伴奏にアコースティック・ギターが加わる。
深いエコーやマドリガルが、動きのままならない、悪夢的な展開に追い込む。
今度の間奏は、ベースとオルガンの奇妙なやり取りに端を発し、執拗な反復のうちにいつの間にか 4 分の 3 拍子に変化、オルガンのフレーズ反復がさらに重なり合い、ムーグ・シンセサイザーも加わって、目もくらむばかりに渦を巻く反復とともに、次第に演奏の緊張が高まってゆく。
一瞬のポーズともに演奏は解体するが、ムーグ・シンセサイザーが機敏に演奏をまとめ、再び序盤のギターのリードによるへヴィなテーマ演奏へと回帰する。
よく聴くとバリトン・サックスが加わっているようだ。
ムーグ・シンセサイザーによるケバい残響も独特である。
斧を叩き込むように、ずっしりと重い演奏だ。
アルバム全体の曲調を予感させるスリリングでサイケデリックなヘヴィ・ロック。
ハードロック調ながらも、深酒の果ての悪夢を思わせる作風である。
オープニングからダイナミックで淀みないが、目くらましのような変則アクセントよるテーマを巡って重厚な演奏が続くうちに、次第に体が傾く
ような気分になる。
巧みなコーラスや 3 拍子と 4 拍子の交錯など、あいかわらずの技巧的な内容だ。
何か妙なしかけをしないと演奏できないらしい。
が、そこが好き。
リード・ヴォーカリストはフィル・シャルマン。
多彩なハモンド・オルガン、ムーグ・シンセサイザーなどキーボード・プレイも大活躍。
「Schooldays」(7:37)ヴィブラフォンとエレクトリック・ピアノ、ギターの愛らしいユニゾンによる、早口で舌足らずのささやきのようなオープニング。
得意の対位的マドリガル(追いかけコーラス)が忍び寄るようにスタート、すべるようになめらかなテンポ・アップとともに鍵盤打楽器とキーボードの主導する伴奏とコーラスがスピーディに交錯しながら進んでゆく。
序奏と同じギター、キーボードらが交錯しながら展開をリード、オブリガートでリズムやテンポは目まぐるしく変化する。
コーラスはひたすら幻惑的であり、演奏はスタートとストップを繰り返すように落ちつきがない。
走りながら去ってゆくコーラス、クロス・フェードするのは、まったくリズムの異なる不気味なピアノの和音の連打、そして厳かなリフレイン。
(5 拍子のコーラス・リフレインに重厚なピアノの和音が 2 拍でクロス・フェードする辺りが、さりげなくすごい)
厳かなピアノ和音の打鍵とともに湧きあがる神秘的なメロトロン・ストリングス。
そして、深いエコーとともにピアノも幻想的にさざめき、ベースと重々しく呼応しながら、深く薄暗い広がりを生み出してゆく。
その空間を遊泳するように、ゆったりと広がってゆくヴォーカル。
メロトロン・ストリングスは、ピアノとともに映画音楽風のややジャジーなバラードのニュアンスを醸し出し、スロー・テンポで演奏は続いてゆく。
ようやく現れたドラム・ビート、あどけない子供の声とミネアの声が重なり、呪文のようなダイアローグを織り成す。
心の内側へと語りかけるような不思議な雰囲気は、映画の回想シーンのように現実からの遊離を表現しているのだろう。
劇的にひらめくクラシカルなピアノとともハーモニーは歩み去ってゆく。
フェード・インするのは軽妙なピアノのリフレイン、そして一転スピーディなリズムとともに、ヴィブラフォンがリードするジャズロック調の軽快な演奏が始まる。
軽やかな 7 拍子の演奏は細切れのようになって、エコーの効いた追いかけコーラスとつぶやきのようなアンサンブルへと変化し、まるで辻褄が合わなくなったのを恥じるように、フッと消えてしまう。
内省的にして悪夢を思わせる不可思議ロック・バラードの傑作。
思い出を語るにしてはウェットでなく、愛らしくも乾いたユーモアが表情に感じられるのは、夢の世界で奔放に遊んでいるからだろう。
前半は、ヴァイブとギターのクラシカルなデュオと追いかけコーラスによる軽やかでリズミカルな展開(8 分の 5-6-7 拍子が交錯するというリズム・チェンジの嵐)であり、大胆なクロスリズムによるブリッジを経て、回想場面らしいあまりに幻想的なヴォーカル・パートへと進む。
ヴァイブを用いたジャズロックにクラシカルなピアノ・コンチェルトをぶつけるなど、チャレンジングな編曲姿勢が感じられる。
曲調の大きな変化は、おそらく現実と回顧を意図しているのだろう。
ミネアのリード・ヴォーカル。
最初のコーラスはミネアとフィルだろうか。
「Working All Day」(5:12)
いくつものギター(クラヴィネット?)がオーヴァーダブされてクシャクシャなフーガのように絡まるイントロダクション。
ピッチが下がって尻切れとんぼに消えてしまうと、いきなりヘヴィな 8 ビートとともにデレク・シャルマンのパワフルな歌唱が始まる。
オブリガート、間奏は、けだるくもリズムの込み入ったバリトン・サックス、ギター、オルガンのアンサンブル。
セカンド・ヴァースに入るタイミングがまったくつかめない。
ヘヴィな音なのだがアンサンブルそのものはなかなかクラシカル、そしてヴォーカル・ハーモニーを交えると民謡、舟歌風である。
ギターとサックスが、即興風に音を散りばめつつも決めはきっちりとまとめる。
8 ビートと 3 拍子を交錯させながら、醒め切ったアンサンブルが淡々と進む。
リフを繰り返しながら、次第に主導権はワイルドなハモンド・オルガンへと移ってゆき、いつしか猛烈な速弾きソロへ。
クールにして眠気も誘う独特の反復(もしくは延々と続く助走)による伴奏と、奔放でアグレッシヴなオルガン・ソロの奇妙なコントラスト。
忍び寄るヴァイオリンのピチカート乱れ弾きをきっかけに、「どっこいしょ」なリズムと舟歌調のヴォーカルが戻ってくる。
バリトン・サックスはのっそりとヴォーカルに寄り添い、間奏ではサックスとオルガン、ギターらがこんがらがる。
この主張があるような、ないような感じ、「醒めたアジテーション」といえばいいだろうか。
独特の野卑な調子が特徴的な舟歌、民謡調ブラス・ロック。
歌詞によれば、働く辛さを歌う歌らしい。
ヴォーカル・パートにはパワフルなグルーヴがある一方、間奏パートでは、野太い音ながらもバリトン・サックスやギターが反復のたびに汗臭さを払底するかのように、アブストラクトでクールな演奏を続けている。
インスト・パートにおける精緻なのに安定感を拒否するようなアンサンブルはこのグループにしかあり得ない
よく聴けばメイン・ヴォーカルも力みかえるわりには、平べったいメロディであり、まるでお経を唱えているみたいだ。
4 拍子と 3 拍子の交錯のようなリズム・チェンジはもはや当たり前である。
デレク・シャルマンのリード・ヴォーカル。
子供時代を懐かしむ気持ちとともに、「勉強(労働)ばかりするジャックはダメな子になる」という戒めも入ってるのでは。
間奏部分のオルガンのアドリヴが強烈。
この辺りまで聴くと、ドラムスにもう少し華があるといいなあという気持ちになってきます。
「Peel The Paint」(7:31)
密やかなささやきヴォイスはフィル・シャルマンだろうか。
静かな伴奏はゴボゴボと沸き立つハモンド・オルガンとヴァイオリンのピチカート。
間奏では、抽象的なオルガンと美しく華やぐ弦楽奏が徹底的に噛み合わない呼応を繰り返す。
美しいはずの弦楽の響きも、やがてドライで無慈悲なタッチになってくる。
2 コーラス目もひそひそと謎めいている。
再びオルガンと弦楽の無益なる応酬。
ボソボソいうベースとオルガンのリフレインにギターが鋭くケリをつけると、やおら、ギター、サックス、オルガンによるけたたましくヘヴィな演奏が爆発する。
ブルース色さえなければ、初期の KING CRIMSON とよく似た音である。
ヴォーカリストはデレク・シャルマンに交代、パンチの効いたシャウトのハードロックへと豹変する。
パワフルなリフとギター、サックスの唸りで世界は一変し、荒々しいオルガンとともに 4 拍子と 3 拍子のリフを交互にたたみかけながら、ついには怒涛のギター・ソロへ。
呆気に取られるほど鮮やかな変わり身。
ギターは迸るように激しいブルーズ・ロック・ソロを繰り広げる。
ドラムスの乱れ打ちにも注目。
ウェザースばかりが噂に上るが、本作のマルコム・マルティモアも相当なテクニシャンである。
けれん味がない分地味なだけだ。
しかし、ギターは途中で我に帰ったかのように周囲を気にし始め、ノイジーなディレイとともに 3 拍子によるフォーカスのぼやけたような不思議なアンサンブルへと溶解してゆく。
ギトギトした二日酔いのサイケデリック世界にもかかわらず、奇妙な静けさ、覚醒感もある。
ブルーズ・ロック調のアドリヴが遠く、すぐにでも消えそうな音で続いてゆく。
ギター・アドリヴの絶叫もドラムスの乱打と重なり合い打ち消しあい、かすれたように電子音に吸い込まれる。
混沌に秩序をもたらすドラムス、そして後片付けのようなデレク・シャルマンのシャウト、パワフルなアンサンブルがリタルダンド、大いにタメで大団円。
クラシカルな弦楽奏と無機質なオルガンによるアンバランスなアンサンブルがサイケデリックなハードロックへと花開いてゆく怪作。
展開は不可逆であり、きわめて大胆である。
弦楽とオルガンをフィーチュアしたちまちましたアンサンブルを聴かせる前半と、ハードに迫る後半で全く別の曲のようだし、後半の展開の中にも小刻みなリズムの変化やフォーカスが突如ずれたようなアンサンブルのサイケデリックな変調があって、素直には進めない。
ギターの大胆なアドリヴでは、グリーンがその力量を思い切り発揮している。
オーソドックスなプレイの奔放さ、安定感、アドリヴのインスピレーションも鋭い。
前半のリード・ヴォーカリストはフィル・シャルマン、後半のリード・ヴォーカリストはデレク・シャルマン。
「Mister Class And Quality」(5:50)
オルガン、ギター、ベースらによるリラックスした、しかしポリフォニックなアンサンブル。
オルゴールの多重録音による室内楽のような、軽妙なイントロダクションだ。
そして、すぅっと 1 つのリフへとまとまってゆく手際よさ。
跳ねるように勢いのいいドラム・ビートとともに、リフの主導はヴァイオリンに移り、デレク・シャルマンによるお得意のひねくれたメロディ・ラインの歌唱が始まる。
オルガンがシンコペーションによる裏拍アクセントのオブリガートを放つ。
間奏は、オルガンとギターの珍妙なやりとり、オルガンの三連による転がるような調子のまま、2 コーラス目へ。
再び、オルガンとギターのやりとり、三連フレーズ反復を経て、リズムはシャフルに変化。
エコーでにじむギターとキーボードがスペイシーな呼応を繰り返し、高まるテンションとともに、2 拍子のピアノによるヘヴィなストロークが飛び込んでくる。
オルガン、ピアノらによる強烈な演奏を軽妙なオルガンが受け止め、数珠つなぎアンサンブルを経て、ぐにゃぐにゃなキーボードによるソロ、そしてギターによるブルージーなアドリヴ。
奇妙なノリのよさとともにここまでのインストの展開は流れるように巧みである。
エレクトリック・ピアノ、ギターらによるジャズロック調のアドリヴ合戦は、やがて、クロス・フェードで戻ってくるヴァイオリンのリフに乗り越えられる。
そしてデレク・シャルマンのメイン・ヴォーカルの復活。
けたたましい演奏は軽妙なギター、オルガン、三連でたたみかけて一気にクライマックスへ。
シャフルで突き進む、軽妙でユーモラス、ノイジーで精緻な怪作ブギー。
ポップなブギーを対角線方向にぎゅっと押して歪ませたような作品である。
オブリガートでは、アクセントの位置を巧みに変化させて、「実はノりにくいノリ」でテンションを生んでいる。
デレク・シャルマンのヴォーカルは、パワフルにしてよどみないが、ハードロックというにはメロディ・ラインが作り物めいていて、不気味である。
ただし、全体に曲調やサウンドはソフトで軽妙であり、ラウンジ・ミュージック風だったり、ラジオ・ジングル風だったりする。
そのユーモラスなフレーズをやたらと複雑なアンサンブルでこなすところが特徴である。
三連フレーズが数珠つなぎのように楽器を渡り歩くかと思えば、圧倒的にヘヴィなアドリヴが飛び出すのだ。
途中で見せるスペイシーなエフェクトは新鮮。
「Three Friends」(3:00)
前曲から途切れなく、悠然たるメロトロン・ストリングスとオルガンに守り立てられて教会風のコーラスが高まる。
ギターだけは前曲のグルーヴのままにヘヴィでねじれたプレイを続けるが、コーラスとともに次第にメロディアスでしなやかな音へと変化する。
広々と響き渡るメロトロン、オルガンとうねるギターがリードする、厳かな響きの演奏である。
堅実に繰り広げられるアンサンブル、その営みを見下ろし祝福するようなオルガンの響き、そして名残を惜しむかのようなフェード・アウト。
厳かにして美しい感動の終曲。
キーボードによるこういったシンフォニックな盛り上げ方は、このグループの作品としては珍しい。
右側のジャケットはアメリカ盤であり第一作と同じ巨人のイラスト。
これは第三作がアメリカでのデビュー作だったためと思われる。
現行 CD は、こちらのアメリカ盤と同じです。
以前の米 COLUMBIA 盤と同様、ユニバーサル盤でも、最終曲とその前の曲の収録時間が正しくないようだ。
つまり、歌唱と歌詞から判断しても、本当の最終曲は CD カウンタ上の最後の曲の 2:26 辺りから始まると思う。
これはどういうことなのでしょう。
(2019.1 補足)
米 COLUMBIA 盤では、LP ラベル上の演奏時間が、「Mister Class And Quality」(3:23)、「Three Friends」(5:30)となっているので、この LP 製作時の曲の切れ目がそのまま CD になっているというのが正しい事情のようです。(LP 上の表記の曲時間と CD での曲の切れ目は合致している)
とはいえ、VERTIGO の LP には曲時間の表記がないために本来の意図は不明ですが、5 曲目の歌詞が CD では 6 曲目に現れるのはいかにも不自然です。
(VERTIGO 6360 070 / CK 31649 / UICY-9689)


| Derek Shulman | lead vocals, alto sax |
| Ray Shulman | bass, violin, guitar, percussion, vocals |
| Phil Shulman | sax, trumpet, mellophone, vocals |
| Kerry Minnear | keyboard, vibraphone, percussion, cello, moog, vocals |
| Gary Green | guitars, percussion |
| John Weathers | drums, percussion, xylophone |
73 年発表の四作目「Octopus」。
屈指の大傑作の一つ。
コーラス・ワークや第ニ作の延長にある眩惑的な演奏は前作を凌ぐ。
これは新ドラマー、ジョン・ウェザースの加入によって、リズム・キープを超えた緻密なプレイと過激なテンポの変化が可能になったためか。
前任者二人もかなりテクニシャンだったが A 面最終曲や B 面 1 曲目のような曲を聴くと、ドラムスもアンサンブルの一部を占める楽器なのだと再確認させられる。
明確な音は、ビル・ブルフォードとも共通する。
作品は、豊かな中世/クラシック色に加え、これまで以上にパワフルなロック色も強まる。
また同時に、対位的なアンサンブルと急激に場面転換する演奏も進化を続けている。
各作品の性格、見せ場がはっきりとしており、このグループの作品の中では取りつきやすい方だと思う。
35 分弱の作品にもかかわらず、内容はギッシリ詰まっており、まさに一皮むけてしまった傑作だ。
潜在的なプログレ病患者同定のためのリトマス紙的作品ともいえる。
Godley/Creme が好きな人にもオススメ。
VERTIGO レーベル。
「The Advent Of Panurge」(4:44)。
クラシカルなアカペラをギター、ベースが静かにオブリガートするオープニング。
ギターとミネアのオーヴァーダブ・コーラスがおだやかにこんがらがる。
得意の中世風のメロディがくるっと THE BEATLES 風に変化する不思議さ。
突如ヘヴィなオルガン、ピアノ、ギターによって演奏が動き出す。
ギターのベンディング一発に続き低音を効かせたジャジーなピアノ・ソロ。
ヘヴィなギター、オルガンがピアノと騒がしく反応しあう。
ハードでファンキーな調子が独特だ。
突如天から裁定を下すようなデレク・シャルマンのヴォーカルが降ってくる。
テーマはおなじ。
ピアノがリードする演奏は突如、トランペットの鮮やかなファンファーレとミネアの繰り返しヴォーカルで遮られる。
デレクの裁定に異議を申し立てるような調子である。
チャーチ・オルガンの柔らかな響き。
ころころ曲調が変わる。
ミネアのファルセットとギターのこちょこちょしたプレイが重なり合う。
ドラムスが戻りフリー風のピアノ伴奏で始まるは幻想的なヴォーカル・パフォーマンス。
複数の声が角度を変えつつ呟き話しかける。
ピアノの重苦しいオブリガート、ギターのつぶやき。
そしてオープニングのひそひそコーラス&ギター、ベースが再現。
幻惑的にしてあまやかなコーラス。
再びヘヴィなオルガンが飛び込みアヴァンギャルドなピアノが暴れる。
ハモンド・オルガンとギターが低音でもつれるようにかけあい。
シャルマンのソウルフルなパンチのあるヴォーカル。
最後はジャンと決めて終り。
中世風味とジャズ、ロックが大胆かつ細心に交ぜあわされた傑作。
テーマは再び巨人にまつわるラブレーの風刺小説より、パンタグルエルとパナージの邂逅である。
そして演奏は 1 曲目からかなりやりたい放題だ。
ジャジーにして強いビート感もあり、込み入ったアンサンブルから眩暈コーラス、ツイン・ヴォーカルも駆使する得意技総覧的のアヴァンギャルドな作品である。
リズム・キープに現われるドラムスにほっとするほど普通のノリがなく一定の曲調を保たずに次々と変化してゆく。
それでいて折れ曲がるような感じはなくきちんと流れている。
これでは 1 曲目でいきなり引く人もいるかもしれないな。
強いていうなら歌入りフリー・ジャズ。
「Raconteur, Troubadour」(4:05)。
チェロ、ヴァイオリン、エレクトリック・ピアノのアンサンブルが伴奏する中世音楽調のヴォーカル・パートでスタート。
バスドラ、タンバリンが巧みにアクセントする。
8 分の 5+6 のパターンである。
ヴォーカルがサビに入るとヴァイオリンがヴォーカルの旋律を引継ぐ。
サビは 8 分の 6 で最後だけ 8 分の 10。
ヴァイオリンのトリルからエレクトリック・ピアノ、マリンバ、ドラムスとめまぐるしく演奏が動き出す。
渦を巻くような曲調だ。
ピアノがテーマを奏でチェロがのほほんと変奏する。
吸い込まれるように音が消えると再びオープニング・シーケンスへ。
繰り返しが済むと再びスネアやマリンバも加わってぐるぐる回り出す。
今度はベースがテーマを弾いている。
エレクトリック・ピアノのリフレインを経て突如行進曲風のビートが現われる。
そしてチェロが悠然たる旋律を奏ではじめる。
オルガンやリコーダー、ヴァイオリンも重なりシンフォニックな流れができあがる。
湧き上がるスネアのロール。
そして鮮やかなトランペットのファンファーレだ。
ヴァイオリンがおなじ旋律を引継いで歌う。
ピアノの伴奏はちょっと妙。
ピアノが軽やかに一閃すると、みたびオープニング・シーケンスヘ。
終章である。
最後は壊れたレコードのように繰り返すエレクトリック・ピアノ。
寂しいのか明るいのか判然としない終りだ。
表題通り、トルバドールを連想させる中世民俗音楽風のテーマを過激なリズムと多彩な音色でひねくり回したクラシカル怪作。
弦楽器とヴォーカルがフィーチュアされたサウンドはいかにも中世風でありテーマもトラッド風のわりと地味な旋律である。
しかし、インスト部分は 8 分の 6 拍子で各パートがくるくる回るようにせわしない動きを見せるとても面白いもの。
どこかで必ずテーマが流れているのに注意。
中盤しらじらしい管絃によるシンフォニックな演奏への展開はまさにあっけにとられる大胆さ。
楽器はたくさん使われておりとても全部はわからない。
ヴォーカリストはデレク・シャルマンだろう。
バッハの管弦楽組曲の変態アレンジ版。
「A Cry For Everyone」(4:08)はヘヴィなギター・リフとソウルフルなヴォーカルで攻めるパンチの効いたハードロック。
こういう曲ではデレク・シャルマンのヴォーカルが映える。
開口一番叩きつけるようなギターが轟き、ヴォーカルはファンキーに迫る。
変拍子を交えパラグラフの切れ目が分かりにくいところがいかにもである。
間奏のギターやピアノのフレーズには後の作品にも現われる東洋風味というか珍妙な味わいがある。
テクニカルなベースがドライヴするギターとオルガンの追いかけっこも面白い。
セカンド・ヴァースを経た間奏に続く初登場のシンセサイザーは動物の鳴き声のようなものすごい音である。
ヴォーカルに続くギターとオルガンのかけあいはさらにエスカレート、めまぐるしい演奏が火蓋を切る。
ヘヴィでハード、しかしリズミカル。
ドラムスとギター、キーボードがファンク・バンドのようなみごとなノリを見せ、エレクトリックでノイジーな切り込む過激な演奏だ。
ラストのヴォーカル・パートを経て最後はもつれつように演奏が続きシンセサイザーがピリオドをうつ。
中華風の技巧的なハードロック。
ギター・リフ中心のビートの強い曲調や変則リズムは一作目や三作目のオープニング曲を思わせる。
しかし、間奏部分のギターとオルガンのかけ合いや、凝ったシンセサイザーの音など、一筋縄でいかないものばかり。
ヘヴィでファンキーかつ東洋風のメロディのおかげで、どこかコミカルという密度の高いハードロックの名品。
過剰にアンサンブルに凝ってはいるものの、JETHRO TULL に通じるイメージもあり、アメリカで受けたのがなんとなく理解できる。
「Knots」(4:12)。
のっけから得意のアカペラ四声カノン・コーラス。
受けるはサックス、チェロ、マリンバが繰り広げるコンクレート風の断片的な器楽。
これを交互に繰返し、やがて、ドラムスの決めをきっかけに、コーラスと器楽が重なりはじめる。
突如リズムが入り、ゆったりとしたギター・リフがリードするアンサンブルへ。
そして柔らかなコーラス。
断続的な演奏で始まっただけに、ここのメロディアスな全体演奏が心地よい。
リズムが止むとピアノ伴奏でマリンバ・ソロが始まる。
ピアノもマリンバも、かなり奇天烈な演奏だ。
はっきりいってちょっと変。
続いてヘヴィなピアノとギターが飛び込む。
かなり凶暴なギターと攻撃的なピアノの和音連打、そしてうねるオルガン。
一気に不穏なムードになり、次の展開に向けて緊張が高まる。
もっともこれだけ妙だと、何があっても大して驚かないだろう。
唐突にアカペラ・コーラス。
またもたたみかけるヘヴィなギターとピアノ、オルガン。
またもアカペラ井戸端会議コーラス。
ドラムスの決めが入り、再び断片的な器楽とコーラスが重なる。
ここの器楽はオルガンがメイン。
ゆったりしたリフが再現、メロディアスな全体演奏。
コーラスが動いてゆく。
自由に叩きまくるドラムスがすごい。
最後は、わりとまともに和音を響かせて、どこかへ飛び去ってゆく
超絶追いかけコーラスとミュージック・コンクレート風の器楽をメロディアスな主題でまとめたアヴァンギャルドな作品。
コーラスはやはりクラシカルもしくは教会風である。
このコーラスに影響されたグループは数知れない。
合いの手を入れる珍妙な器楽が、コーラスを模しているようでおもしろい。
1 曲目もそうだったが、規則的なリズムのパートが一層の安定感をもって聴こえる。
これ以上やるとバラバラになるという寸前で、一体感のあるメロディアスなトゥッティへとまとまるスリル。
間奏のマリンバとピアノのデュオは、子供の遊びか現代音楽か。
歌詞は D.レインに触発されたという言葉遊び。
「The Boys In The Band」(4:36)。
楽しそうな笑い声。
そしてコインが転がる。
コロコロコロ。
そして一気に始まる超絶変拍子アンサンブル。
あきれるくらいスピーディでスリリングなプレイである。
切れ味抜群。
オルガン、ギター、ムーグそしてハモリにサックス、ヴァイオリン、マリンバなどが入っているようだ。
受けるは軽妙なオルガンそして怪しげなピアノ。
再び鮮やかにユニゾンをかっ飛ばすと、今度はギターとオルガンでジャジーに受ける。
小気味よいドラミング。
ピアノやベースなど低音を強調したアンサンブルが続く。
そしてジャジーなギター・ソロ。
続いてサックスのリフに乗ってムーグのソロ。
バッキングが気持ちよい。
再び軽妙なオルガン、ワウ・ギターと不思議なピアノのコンビネーションによる受けのアンサンブル。
そしてみたび超絶アンサンブル。
微妙にパターンが変化している。
最後は繰り返しのままフェード・アウト。
これぞテクニカル集団 GENTLE GIANT の面目躍如の超絶技巧大傑作。
オープニングのスピーディなアンサンブルは P.F.M が憧れて真似したらしい。
確かによく似ている。
こういった、ヴァイオリンを活かしたスピーディなアンサンブルとジャズロック的な緻密さをもつ展開は、新境地といえるだろう。
爆発力と緻密さを同時に備えた完璧な演奏であり、一作目や三作目のオープニング曲を倍速にしたような感じもある。
ちなみにライヴ盤も同じ笑い声とコインで始まる。
インストゥルメンタル。
「Dog's Life」(3:13)。
アコースティック・ギターの重音フレーズによる愛らしいイントロダクション。二つのギターが重ねられているようだ。
メイン・ヴォーカル・パートは中世教会風であり、伴奏は、弦楽奏と手回しオルガン?の雅なアンサンブル。
再びアコースティック・ギターの重音フレーズ、そしてメイン・ヴォーカル。
弦楽と手回しオルガンの響きは、ヨーロッパの古い石畳の街並みをイメージさせるいい音だ。
三度アコースティック・ギターの重音フレーズから高音のサビとゆったりした弦楽のかけあい、そしてヴォーカルとジャジーなアコースティック・ギターのかけあい。
三度メイン・ヴォーカル、そして繰り返し。
四度アコースティック・ギターの重音フレーズ、そして展開部へ。
今度のヴォーカル・パートは、厳かだがどこかユーモア含みでありシャンソン風でもある。
ここの伴奏と間奏がおもしろい。
カエルの鳴き声か草笛のような管楽器(メロフォン?)がそれこそカエルのように気ままに吹き鳴らされる。
マリンバは柱時計のようにユーモラスに時を刻む。
弦楽奏のオブリガートをきっかけに、雅なメイン・ヴォーカル・パートに回帰。
アコースティック・ギターの重音フレーズを呼び覚まして、コーダ、弦楽奏と手回しオルガンで曲を回想しつつ去ってゆく。
キュートなアコースティック・ギターと弦楽奏、手回しオルガンによるバロック室内楽風の作品。
弦楽と手回しオルガンの響きが見知らぬ街への幻の郷愁を誘う。
中間部の管楽器のアンサンブルはカエルの合唱か。
器楽の構成は GRYPHON のようだ。
ヴォーカリストはフィル・シャルマンと思われる。
バロック・テイストとシャンソン風のポップ・テイストのブレンドが「Revolver」あたりの THE BEATLES のようだ。
ドラムレス。
「Think Of Me With Kindness」(3:33)。
暖かなピアノの響きに導かれるジェントルなバラード。
ミネア独特のソフトで上品な教会風の歌唱である。
サビを導くピアノの和音がポップス調でいい感じだ。
ささやくようなサビは絶品。
ベースはフレットレスか。
クラシカルですてきなバラードは、リズムを得てゆったりとした起伏を見せはじめる。
ピアノは控えめながらも抱きしめたくなるようなプレイ。
間奏は、歌メロを繰り返すトランペットとオルガンの響き。
これまた THE BEATLES を思い出す 60 年代の音だ。
唐突に始まる新たな展開は、オルガンがささやくように寄り添う無調風のハーモニーである。
初めのバラードのサビを導くピアノとこのハーモニーが奇妙な交錯を見せるが、気を取り直したようにサビが再現してゆく。
悠然たるオルガン、トランペットの響きに支えられるように、バラードは高まり、柔らかなピアノの響きとともに消えてゆく。
抱擁の暖かさとうっすらとした無常感が交わる慈愛のバラード。
気品あるヴォーカルが秘めた感傷とオルガン、管楽器のシンフォニックな広がりには思わず涙が出そう。
遠く P.F.M や MAXOPHONE などイタリアン・ロックへとこだまする音である。
あまやかなバラードにもかかわらず、実験的なヴォーカル・パートを突っ込んで、やや不気味な味つけをするところが興味深い。
クラシカルな香りとともに、ジャジーな味わいもほんのり漂わせており、いかにも 70 年代ブリティッシュ・ロックらしい。
そして、このグループのルーツを感じさせる音でもある。
ヴォーカリストはミネア。
「River」(5:52)。
ギターとオルガンによるひそやかなデュオが、一気にけたたましいヴァイオリンとワウ・ギターのデュオによる変則譜割テーマに上書きされるオープニング。
テーマは鋭く始まるがうねうねと語尾が長く続く得意のパターンである。
冒頭から何かが飛び去るような、吹きすさぶ風のような効果音が現れる。
長めのブレイク、そしてオルガン、エレクトリック・ピアノによるユーモラスな伴奏でややキーのずれたようなヴォーカルが歌い出す。
ここはデレク・シャルマンである。
イントロ部が奇妙なアクセントを持つだけに、ジャスト・タイムの 8 ビートがじつに気持ちよし。
伴奏のオルガンがふざけたコーラスのようでなんともユーモラスだ。
トーンを抑え、風が吹き込むような音のオルガンとギターによるひそやかなる間奏は冒頭のデュオの再現だ。
そしてまたも、ヴァイオリン & ワウ・ギター・デュオにのっとられる。
この変拍子デュオは拍子を切り換える役割を担っているようだ。
またも飛び交うノイズ(ムーグか、シンバル音の逆回転処理か)、そしてヴァイブがきらめくややおちついたテンポの演奏に導かれて、もう一人のヴォーカリストが歌い出す。こちらはフィル・シャルマンだろうか。ここからは 3 拍子だ。
ジャジーなエレクトリック・ピアノとメロディアスなファルセット気味のヴォイスが、雰囲気をファンタジックなソフト・サイケ風に和らげる。
オルガンのひそやかなるリフに、ヴァイブの響きと金属的なノイズ(変調したオルガン?)がからみつき、しつこく耳を刺激する。
三度、ヴァイオリン&ファズ・ギターによるデュオのテーマが登場。
今度のテーマは、途中でタムタムの連打を刻み込まれて大胆に断片化している。
次の主役はギター。
オーソドクスなブルーズロック/ハードロック・ギター・ソロである。
フレージングは明快でリズム感もいい。
ギターに引き寄せられるように、 ヴァイオリン&ファズ・ギター・デュオが破壊したリズムが 8 ビートの秩序へと形作られてゆく。
モーダルで複雑な器楽のうち、ギターだけは明快なロックらしいプレイをするところがこのグループの特徴の一つであり、アメリカで受けた一因と考えられる。
ピアノの打鍵も重なり、いい感じにタイトな演奏になる。
四度、エレクトリック・ピアノに導かれて、ヴァイオリン&ファズ・ギターによるデュオのテーマが登場。
そして再び、デレク・シャルマンによるマッチョなヴォーカル・パートへと回帰。
ゴワゴワとした低音はオルガンかシンセサイザーか。
最後に、もう一度ギターとオルガンのデュオからヴァイオリンとファズ・ギターのデュオのテーマを提示して終わり。
3 拍子と 4 拍子の性格をともに持つようにアクセントを配したテーマを狂言廻しにした、やや悪夢的な作品。
ヴォーカルのメロディ・ラインがモーダルで色彩感が希薄な一方、器楽テーマはけたたましいながらも朗々としており、必然的に後者の方が目立っている。
これは通常のロックではあまり見られない状況である。
さらに、電気的な効果を散りばめているので、全体として目が眩むような、サイケデリックなイメージがある。
ギター・ソロのパートの安定感が際立つが、どこか空々しく、あたかも普通のロックのパロディのような位置付けになっている。
トーンを調節したハモンド・オルガンの丹念なプレイなど、サウンド面の工夫も多彩である。
ヴォーカリストはデレク・シャルマンとフィル・シャルマン。
技巧的なドラムスの加入で音楽の幅が広がり、どの曲とも個性をしっかり発揮し、完成度も高い。
鋭くスピーディなフレーズやリフ、超絶アンサンブルなどテクニック指向の時代にも充分耐える作品だろう。
コーラスはもう完成の域に入っており、声も楽器として用いられている。
そしてハードネスと対を成す切ないまでのリリシズムも健在。
しかし同時に、ハード、ソフトと簡単にいえないくらいのアヴァンギャルドな作風も強調されている。
中途半端に浮き上がってしまったような主題を巡る傾いだような演奏は、単純な感情移入やノリを許さない。
また、クラシカルな曲からヘヴィな曲まで取り揃えてそれぞれ適役が歌うという、複数のヴォーカリストを持つ強みを存分に発揮している。
アレンジの鬼・技巧派集団の面目躍如たる大傑作。
ただしこれだけ濃いと好みを分けるかもしれない。
個人的にはハモンド・オルガン、ムーグの丹念な使い方が気に入っている。
右側のジャケットはアメリカ盤 LP のもの。
(VERTIGO 6360 080 / PHCR-4203)

| Derek Shulman | vocals, alto sax, soprano sax, recorder |
| Ray Shulman | bass guitar, violin, acoustic guitar, percussion, backing vocals |
| Kerry Minnear | keyboards, tuned percussion, recorder, vocals |
| Gary Green | 6 & 12 string guitars, mandolin, percussion, alto recorder |
| John Weathers | drums, percussion |
73 年発表の五作目「In A Glass House」。
前作完成後、シャルマン兄弟の長兄フィル・シャルマンが脱退。
メンバーを欠くという大事件にもかかわわらず、高度な音楽が維持されている。
さすが熟練のプロフェッショナルである。
大胆なリズム・チェンジを平然と乗り切る研ぎ澄まされた演奏は、すでに何かをイメージさせるのではなく、音そのものの存在を主張する。
それでいてポップでグルーヴィな衣をまとうのだから、もはやある意味グロテスクである。
トリッキーなプレイが次々と繰り広げられる中で目立つのは、モダンで多彩なキーボード(トーン調節したハモンド・オルガン、クラヴィネットなど)とルネッサンス音楽を思わせるリコーダーの音。
メロディアスなテーマ、クラシカルなアンサンブル、ファンク調のノリのいいロックの生む分かりやすい幻想性や情感は、ガラスの迷宮のような楽曲のなかへと抽象化し、刃の上で舞うが如き演奏のけれん味が最も強く印象に残る。
得意のバロック・アンサンブルとファンクなロックンロールは、ふと気づけば何の矛盾もなく一つになってしまっているのだ。
不気味な作品である。
プロデュースはグループ。
本作品から WWA 所属となる。
「Runaway」(7:15)。
ガラスを叩き割る音がいつのまにかビートを刻みはじめる面白いオープニング。
フェード・インで湧き上がるオルガン、そしてギターがリズミカルな 6 拍子のリフで口火を切り、たたきつけるようなパターンで解決する。
ヴォーカリストは抑え目のデレク・シャルマン、そして最初の小節でいきなり 8 分の 5 拍子も交ざってくる。
伴奏のギターの 三連アルペジオとのズレが奇妙だ。
主旋律は得意の平板な無調風だが、歌唱のおかげでいつになくレガートで軽やかである。
繰り返しの最後には 8 分の 5 拍子と 2 拍子の交錯もある。
ここまで、わずか 2 分の間にすさまじいリズムの変転を見せている。
間奏はリフを刻むエレクトリック・ピアノにムーグが一閃。
解決のキメから、さえずるようなリコーダー合奏へ。
ギターのリフが繰り返されて、演奏に安定感を取り戻す。
遠景にたなびくようにリバーヴを深くしたコーラス。
今度はオルガン、エレクトリック・ピアノ、ムーグらキーボードが、8 分の 6 拍子の呼応パターンを繰り返し重なりあう。
たくさんの小人が踊っているような奇妙にダンサブルな演奏であり、さきほどのギター・リフ同様、反復によって安定点を取り戻すような意図が感じられる。
ブレイクを経て、一転してミネアの賛美歌風のヴォーカルとリコーダーによるバロック・アンサンブル。
ここからは 4 拍子。
アンサンブルを打ち消すように、両チャネルからややメタリックなメイン・ギター・リフが飛び出す。
バロック・アンサンブル対ギターが繰り返され、突如ギターは新たにレガートなリフを提示する。
ここでも執拗に反復することで、独特の効果を上げている気がする。
8 ビートによる安定感が生まれてくる。
再び 8 分の 6 拍子に戻り、調子ッ外れなマリンバ・ソロ。
マレットを持つ手が絡まってしまうような込み入ったプレイである。
メタリックなメイン・ギター・リフ、幻想的なミネアのささやきを経て、メイン・ヴァースへと復帰。
リフを刻むエレクトリック・ピアノにムーグが重なり一閃、たたきつけるようなギターの演奏、そしてデレクのヴォーカルヘ。
メイン・パートを繰り返し、8 分の 5 拍子と 2 拍子の交錯を経て強引なエンディング。
軽妙かつみごとな安定感を見せるクロス・リズムの上で、リズミカルなプレイがパノラマのように流れてゆく力作。
デコボコしながらも終始動きはなめらかであり、そして構成はがっちりと緻密である。
リズミカルなリフからソロまでギター、キーボードが大活躍。
そして意外にも、全体のイメージは軽やかなのだ。
執拗な反復は、過激な変転の準備/助走のようにも聴こえて興味深い。
ギターに似た音はエレクトリック・ピアノかクラヴィネットか。
「An Inmates Lullaby」(4:39)。
前曲ラストのこだまのようなドラム連打が、定位を変えて意味ありげに打ち鳴らされる。
一転してヴァイブ、マリンバ、トライアングル、フロア・タムらによる、ひそやかなアンサンブルが始まる。
イコライザでにじむレイ・シャルマンのアカペラが、独特の無表情な節回しで入ってくる。
ハーモニー(こちらがミネアだろうか)が静かに追いかける。
童謡を思わせるハーモニーだ。
間奏は目のさめるようなヴィブラフォンによるオープニングのテーマ。
再びヴァース、厳かで密やかなハーモニーである。
ヴァイブに続いて、マリンバやフロア・タムの音が遠く近くに散りばめられる。
遠くで聴こえるのはオルガンとマリンバだろうか。
再び囃子歌か童謡のようなヴォーカル。
遠くでざわめくドラム・ロールやマリンバ。
規則的なビートのない奇妙な世界。
ヴァイブやハーモニーのヴォリュームが次第に上がり、コーラスは交錯しはじめる。
ざわめくマリンバ、ドラム・ロールに導かれて、エレクトリック・ピアノとオルガンによるファンタジックなリフレイン。
再びヴァイブによる鮮やかなオープニング・テーマからメイン・ヴォーカル・ハーモニーへ。
ヴァイブのテーマへタムの打撃音やマリンバが絡み、フェード・アウト。
アカペラ、対位的なヴォーカル・ハーモニー、各種パーカッションによるサウンド・コラージュ風の子守唄。
音の定位を変化させるたびに、世界の奥行きが伸び縮みし、フレーズの断片は無造作に散りばめられ、なんとも摩訶不思議な効果を生んでいる。
奇数偶数のポリリズムだと思うが、うまく数えられない。
この突き抜けなさ、どこにも到達しない感じ、コップからこぼれた音がそのまま床の上で静かに模様を成してゆくような感じは他では味わえない。
取りとめない印象は、子守り歌というよりも、子守唄を聴きながら眠りに落ちる寸前の意識の断片的な流れのシミュレーションのようにも思える。
PICCHIO DAL POZZO というイタリアのグループを思い出した。
「Way Of Life」(8:04)。
けたたましいギター・リフで突き進むアップテンポのテクニカル・ロックンロール。
ムーグやギターの切れ味鋭いフレージングはジャズロック風。
ベースのフレージングもきわめて大胆だ。
ヴォーカルに沿って、スキャットを思わせる巧みなプレイを見せるギター。
うねうねとのたうち、絡み合う演奏から、弾けるように飛び出すシンセサイザー(エフェクトされたギターか)がカッコいい。
リズムを刻々と変化させつつ、さまざまな楽器がフレーズをじゅづつなぎにして追いかけあう、忙しなくめまぐるしい間奏部。
演奏は、わずか 2 分でつむじ風のようにクルクルと世界を巻き取ってゆく。
2 分半頃からフェード・インして始まるのは、一転して雅なバロック・アンサンブル。
リコーダー、ヴァイオリンによる典雅な伴奏で、ミネアがエレガントに賛美歌を聴かせる。
こういうコントラストの付け方は、第一作から変わらない作風だ。
重厚なドラムスが加わりシンフォニックに高まるも、すぐにオルガン、ギターらが怪しく蠢き始め、その澱みからムーグが高らかに飛び出すのをきっかけに、あっという間にじゅづつなぎアンサンブル、そしてギターに導かれてメイン・テーマへと元気に突っ込む。
デレク・シャルマンのヴォーカルとギターが鮮やかなユニゾンで疾走し、ギター、オルガンらが得意の綱渡り/じゅずつなぎアンサンブルでめまぐるしいコール・レスポンスを繰り返す。
たたみかけるように鋭い 7 拍子と 8 拍子の応酬がシャフルになり、やがて、中間部でミネアが歌ったバロック・テーマを中心に据えてオルガンのリードする全体演奏で悠然と再現してゆく。
金管風のムーグが印象的だ。
リズムが去ると、オルガン、シンセサイザーらによるノイジーだが厳かな演奏が始まり、やがてノイズとなって消えてゆく。
スピード感あるジャズロックと優美なバロック・アンサンブルが交互に提示され、やがて一つにブレンドされてゆく大胆極まる大作。
前半のアンサンブルはかなり込み入っている。
それでも、ヴォーカル・ラインを軸にみごとなまでに一体となって走ってゆく。
猛スピードでカーブを曲がり続けるような演奏だ。
譜面を見るのがこわくなるような込み入った演奏を、次々とたたみかけてゆく。
そして、中間部のバロック・アンサンブルの配置の妙。
あたかもエア・ポケットのように、そこまでの流れを吸収している。
そして後半では、これらを強引にして精妙に融合してゆくのだからすごい。
エンディングは、ほとんど音響主義風のアヴァンギャルド・ミュージックなので、全体としては、何曲分かを一つにしてしまったような内容である。
トリッキーな展開をジャスト・ビートで支えるドラミングがみごと。
「Experience」(7:50)。
オルガン、ベース、アコースティック・ギターによるクラシカルなトリオがゆっくりとフェード・イン。
ミネアのモーダルなヴォーカルがトリオのテーマを受け、ベース、オルガンとともに対位的なアンサンブルを構成する。
ドラムスも加わると、ハモンド・オルガンのささやきとともに演奏が込みいってくる。
ワウ・ギターや加工されたキーボードの音が散りばめられた、浮ついた反復による間奏が続く。
3 拍子と 4 拍子の何気ない交錯。
昔のアメリカのアニメーションのサントラに近い。
再びメイン・ヴォーカルとそれに呼応するオープニングのテーマ。
今度の間奏は、ベースがテーマを提示してリードし、ワウ・ギターとエレクトリック・ヴァイオリンがカノン風の追いかけアンサンブルで伴奏する。
ポリリズミックだ。
オルガン、ベースによるリズミカルなリフを受けて、ミネアによるオルガン伴奏の賛美歌。
ベースのリフ(シンコペーションがカッコいい)による R&B 風のグルーヴと厳かな賛美歌調のコール・レスポンスの落差にぎょっとする。
しかし、ついにこのベースのリフがドラムスとギター・リフを呼び覚まし、ヘヴィなファンク・ロックへと突っ込むのだ。
デレク・シャルマンのソウルフルなヴォーカルが炸裂、クランチなギターのオブリガートもカッコいい。
続く間奏は、前と同じくひょうきんなのに抽象的で不気味なギターのリフレインである。
再び、ベース・リフとミネアの賛美歌を回顧する教会オルガンの呼応、反復。
ベース・リフは、またもキメの一発とともにヘヴィ・ロックを呼び覚まし、デレク・シャルマンの豪快なヴォーカルが放たれ、ハードなギターが牙をむく。
シュアーな 8 ビートとキメのドラムスの一撃がカッコいい。
これでおしまいかと思わせて、またもやオルガン伴奏によるミネアの賛美歌が挿入される。
最後は、8 分の 9 拍子によるオルガン、ギターらによるテーマを変奏し繰り返す込み入ったアンサンブルが続き、やがてフェード・アウト。
中世ルネッサンス風のポリリズム・アンサンブルとファンキーなハードロックが錯綜し、協奏する快作。
このごちゃごちゃさ加減、無理矢理なブレンド加減もまた魅力である。
賛美歌風のノーブルなヴォーカリストはミネアで、ハードロック担当のマッチョなだみ声がデレク・シャルマン。
圧巻は序章と終章の複合拍子ヴォーカル・パート。
ベースのリフが全体の狂言回し役か。
「A Reunion」(2:11)。
ミネアのソフトなヴォーカルをフィーチュアした小品。
オーヴァーダブされたヴァイオリン、エレクトリック・ピアノ、ベースによる室内楽風のおだやかなアンサンブル。
ミネアの歌うメロディに、グレゴリオ聖歌からシャンソンまで、ヨーロッパをイメージさせるあらゆる音楽が少しずつ顔をのぞかせる。
第三作の主題を再び取り上げたようなイメージもある。
いずれにせよ、第一作から必ずアルバム含まれている、あくまで控えめに佇むような佳品である。
「In A Glass House」(8:09)。
オープニングは、弾けるようなハーモニクスが印象的な、透明感あるアコースティック・ギター・デュオとヴァイオリンによる南欧風の華やかなアンサンブル。
こっちがオリジナルだが、ついつい AREA や P.F.M を思い出してしまう演奏だ。
ヴァイオリンの一人かけあい風のプレイを支えるドラムスのみごとなこと。
やがて、オーボエを思わせるムーグの 8 分の 6 拍子テーマ・リフレインに導かれて、デレク・シャルマンのメイン・ヴォーカルヘ。
これまた童謡のような愛らしい旋律だ。(声は野太いが)
けだるげなギターのテーマは、8 分の 7 拍子、8 分の 10 拍子、8 分の 12 拍子で 1 サイクル。(ライヴでは、このギター・リフから始まることが多いようだ)
間奏は、どことなく田舎くさいアコースティック・ギターとエレクトリック・ピアノだが、じつはヴォーカル・メロディの変奏になっている。
ソプラノ・サックスも加わってアコースティック・ギターに反応する。
この辺もイタリアン・ロック風だ。
再びオープニングのスピーディでなめらかなアンサンブルが復活。
尾を引くようなエレクトリック・ピアノの響きが美しい。
やがて、ジャジーなアルト・サックスとエレクトリック・ピアノのハーモニーをベースが追いかけ、ヴォーカルとかけあうビジーなアンサンブルへ。
ここのドラムスもカッコいいぞ。
テンポが落ちてメイン・ヴォーカルへ。
しかし 1 コーラスで、再び変拍子ギター・リフへ。
ここでは少しパターンを変えている。
再びアコースティック・ギター・アンサンブルにサックスも加わった、田舎風のメイン・ヴォーカル変奏。
ギターに対して、ヴァイオリンがフィドル風のオブリガート。
急転直下、曲を断ち切るようにヘヴィなギター・リフが刻まれて、デレク・シャルマンのソウルフルなヴォーカルが飛び込む。
これに応えるのは、クラシカルなアコースティック・ギター・アンサンブル伴奏によるミネアのもの静かなヴォーカル。
硬軟、動静対比する二人の応酬が続く。
とりなしはスティール・ギター(ドブロか)によるカントリー風の短いソロ、そしてベースがギター・リフを引き継ぎ、またもデレク・シャルマンのヴォーカルを経て、演奏はフェード・アウト。
アコースティックな音を活かした大陸風ジャズロック、牧歌的なトラッド・フォーク・ロックが少しづつ姿を変化させて、やがて強引なまでのファンキー・ハードロックへと展開する。
しかしさらにバロック賛美歌との応酬もある。
かなりイタリアン・ロックに近い不可逆変化型の作品であり、直線的に変化するのではなく、螺旋を描きながら複雑な変化を遂げてゆく。
不規則に変化するアンサンブルをあまりに正確に支えるドラムスに感嘆。
イタリアン・ロック、特に P.F.M がここから大きな影響を受けたことが分かる名品である。
ポーズの後、いくつかの曲の主要部分の断片がパッチワークされて、最後はガラスが砕ける音が余韻を残しつつ消えてゆく。
きわめてトリッキーな演奏を、クラシカルで安定した技巧とハードロックなパワーで難なく突っ走るリズム強化 GG 第ニ弾。
前作に比べると、ソウルフルでヘヴィな部分とクラシカルでロマンチックな部分のブレンドが巧妙かつ大胆であり、構成に工夫を凝らした密度の高い大作が並んでいる。
そして、リズムの変化を含む多彩なアレンジの妙が十分に発揮されている。
全体に洗練されたイメージを与えるアルバムだ。
前作に続き、一作目からのプログレッシヴなアプローチの完成形といえる新たな傑作である。
緻密にして軽妙かつダイナミック。
2001 年の ALUCARD からの CD は紙ジャケ、2 曲(圧巻の「Runaway」とデレク・シャルマン独り舞台でハードなアレンジの「In A Glass House」)のライヴ・テイクのボーナス・トラック入り。
(WWA 002 / alu-gg-02 / TRUCK CD 001)

| Derek Shulman | vocals, saxes |
| Ray Shulman | bass, violin, vocals |
| Kerry Minnear | keyboards, cello, vocals |
| Gary Green | guitars |
| John Weathers | drums, percussion, vocals |
74 年発表の六作目「The Power And The Glory」。
さまざまなリズム/ビートの採用、演奏の複雑化とポップ・テイストの折り合いを試みる好作品。
アヴァンギャルドな表現をバラードやリズミカルでなめらかな演奏へと馴染ませるスキルが冴えわたる。
その味わいは、ひとことで言えばコミカルにしてシリアスという奇妙なものである。
中世風の旋法、和声とモダンなポップスの組み合わせもある。
このスタイルは、次作の「Free Hand」で最高潮に達する。
サウンド面では、クラヴィネット含めエレクトリック・ピアノの多用が特徴的だ。
全体を通じた「軽さ」は、このキーボードの選択とも関連しそうだ。
アルバム・タイトルは、キリストを讃えるためのカトリックの言葉(栄唱)(グレアム・グリーンに同名の小説がある)より。
プロデュースはグループ。
KING CRIMSON の「Red」同様、安全に見えて実はプログレ病への感染力の強い作品。
80 年代以降のロック・ファンは、ここら辺りからが入りやすいと思います。
「Proclamation」(6:47)
潮騒のように歓声が湧きあがる。
軽妙なエレクトリック・ピアノのリフ、そしてむさ苦しいヴォーカルが 1 拍食って歌い出す。
ヴォーカルは 9+7 拍という切れ目で歌っているため伴奏と合うのである。
なんでこんなことをするのか分からん。(ちなみにライヴでは、キーボードが頭に一拍入れてテーマをずらしてヴォーカルとキーボードのテーマが合って聴こえるようにしている)
音質的には軽さとファンキーさが微妙に拮抗している。
エレクトリック・ピアノのリフレインは、シンコペーションでありスタッカートを交えて奇妙なアクセントをつけるが、オブリガート、間奏部の反復で姿勢を立て直して安定感を演出している。
繰り返しのヴァースでは、ようやくヴォーカルがエレクトリック・ピアノ伴奏に同期する。最初のヴァースは一種の目くらましだったようだ。
ここでベースも加わり、いい感じのグルーヴも生まれてくる。
裏拍の使い方がいい。
「Hail...」ではどエらいエコーとともにハーモニーも加わる。
さらに繰り返しのヴォーカル・パートでは、追いかけハーモニーが加わる。
安定したノリのいい演奏だ。
調子のいいエレクトリック・ピアノの伴奏に追いたてられるように「Hail....」コーラスが消えてゆく。(途中ですでに次のレガートなエレクトリック・ピアノのパターンを低音で先取りして 2 回示している)
やにわに始まるのは、エレクトリック・ピアノによる新たな(すでに少し示されていたが)パターンである。
レガートにして調子のいい、ややクラシカルなリフレインをオルガンがスピーディに追いかける。
続いて、オルガン主導のややジャジーな 10 拍子リフレインから、すぐさまハモンド・オルガンのパーカッシヴな 5 拍子リフレインに変化し、ピアノが華々しいパッセージで雪崩落ちるように追いかける。
繰り返しごとに高まる緊張、転調、そしてハーモニーが高まる荒々しくも厳かで歪なクライマックス、ギターもオルガンも唸りを上げて祝福(?)する。
厳かなオルガンの響き、繰り返される祈り、そして「Day by....」の繰り返しが吸い込まれるように消えてゆく。
「Day by」にクロス・フェードで重なるベース音、そしてエレクトリック・ピアノやギターの断片が散らばり始める。
次第に集まる音。断続音が間を狭めてゆき、しりとりのように次々とつながってゆく。
ドラムスがすべてをまとめて、一気にメイン・ヴォーカル・パートへと復帰し、軽妙だが安定したアンサンブルが走る。
しかし、今までのドラマをどう始末をつけるつもりだ。この妙に軽めの落ちついた演奏にハラが立たなくもない。
もつれるようなエレクトリック・ピアノのオブリガート、ひょうきんなリフレインによる間奏、やがて歓声が湧き起こり、何も分からなくなる。
キーボードを中心とした躍動的かつグルーヴィ、そして裏切りもあるポップ・チューン。
変拍子パターン、テンポの切り換え、器楽コラージュ、意表を突くアクセントをもつフレーズが絡み合う多旋律アンサンブルなど、きわめて個性的である。
中盤のリズムレスのパートにおける「クラシカルだが突き抜けないクライマックス」もこのグループならではの味である。
器楽のフレーズ一つ一つは意外にクラシカル(教会風)だったりジャジーだったりファンキーだったりするが、それらが組み上げられたアンサンブルはどこにもない、眩暈を起こさせるものだ。
この独特のノリも、基本はおそらく R&B なのだろう。
音程を極端に上下させる調子っ外れな歌メロが妙だが、男臭くソウルフルな唱法が有無をいわせぬ説得力を持たせる。
器楽の主役は、テクニカルかつ音色を工夫したキーボードおよび何気なくも超絶なリズム変化を乗り切るドラムスだろう。
リード・ヴォーカリストはデレク・シャルマン。
「So Sincere」(3:51)
サックス、ヴァイオリン、チェロ、アコースティック・ギターらが断続的なフレーズで追いかけあい、ユニゾンするオープニング。
HENRY COW か KRONOS QUARTET か、CD プレイヤーが壊れているのか、プレイヤーが壊れているのか、はっきりいって「変」である。
リード・ヴォイスは厳かなるケリー・ミネア。
ファルセットによる繊細な歌唱だが、旋律はモーダルであり、アブストラクトで不思議な響きを持つ。
伴奏は、序奏のまま。まったくリズムがわかりません。
2 コーラス目から、ピアノ、ギター、ドラムスが加わる。(ということは序盤の不規則に思えたアンサンブルにもリズムがあったということだ)
普通に 8 ビートを刻むドラムスのおかげでやや落ちついたアンサンブルとなるが、他の伴奏が変なのでポリリズミックな効果がある。
(ちなみにライヴではドラムスが先にテンポを決めて打ち始め、伴奏が追いすがるようになっている。それが普通なのだ。)
息つく間もなくギターがけたたましく叫び、テンポ・アップ、
ヴォーカリストはデレク・シャルマンに代わって、ギター、ベース、ピアノ、オルガンが数珠繋ぎで追いたてるリズミカルな演奏が走る。
ギターのパワーコードだけが序奏と同じ奇妙なパターンを憶えていて刻んでいる。
8 ビートではあるが、この数珠繋ぎはかなり難しそうだ。
そのギターの勝ち、ミネアによる一人ハーモニーに変わって冒頭と同じ変な伴奏(今度はドラムス付)で歌が続く。
再び、ギター、エレクトリック・ピアノ、ピアノ、オルガンが数珠繋ぎ(前回とはエレクトリック・ピアノとベースが役割を交代しているようだ)でけたたましく、転げ落ちるようなアンサンブルが炸裂、デレク・シャルマンが吼え、エレクトリック・ピアノが追いたて、オルガンが追いかけ、ドラムスが締める。
カウントのような奇妙な数珠繋ぎアンサンブルを経て、ギター・アドリヴへ。
ブルージーなギター・ソロ(周囲が変なので普通さが際立つ。素面で狂宴に紛れ込んだら意外にノリが合ったという感じ)の伴奏はオルガン、オブリガートでたたみかけるピアノがすさまじい。
三度ミネアのメイン・ヴォーカルから、数珠繋ぎアンサンブルとデレクのヴォーカルへ。
置いてきぼりを食らったサックス、ヴァイオリンがぼそぼそっとつぶやくと、扉を叩きつけるように唐突なエンディング。
全編ガシャガシャとした音でギクシャクと動く現代音楽風の傑作。
アクセントを妙な位置においたスカスカのアンサンブルと、驚異のコラージュ風「数珠繋ぎ」が主役である。
普通のポップスのつもりで聴いていると「ここに音が」という自然な予想をことごとく覆されるため、かなりストレスが溜まるし、唐突な変化も何が起こったのかがその場ではほとんど分からず、置いてきぼりになる。
もちろん、分かるように繰り返してくれるが、それにしてもなかなかついてゆけない。
4 分弱だが、実験色の濃さは前曲を超えている。
エンディングが全体を象徴する。
小節とリズムがずれているこういう作風は、やはりストラヴィンスキー辺りの影響なのでしょうか。
リード・ヴォーカリストはケリー・ミネアで、サビはデレク・シャルマン。
ライヴ盤でどのように再現しているかを確かめましょう。
「Aspirations」(4:40)
悩ましげに揺らぐシティ・ポップス風のエレクトリック・ピアノの音。
密やかな歌はケリー・ミネア。讃美歌、古楽風のヴォーカルと AOR 調のエレクトリック・ピアノの取り合わせが不思議なことにハマっている。
ただし、ファンキーにはならず、どこまでも憂鬱である。
3 コーラス目からは、静かにリズムが加わり、アコースティック・ギターが和音をかき鳴らす。
AOR だったはずだが、いつのまにか、くすんだ英国フォークの趣に変わっている。
深く心に食い込むようにかき鳴らされるギターの和音のせいだろうか。
間奏は、得意のアクセントをずらした、イン・テンポなのにそうは聴こえないアンサンブル。
間奏からサビまではこのアクセントのズレのおかげで若干緊張感が高まる。
サビのヴォーカルは、透明なまま無常感あふれる歌をささやく。
「Hopes, Dreams...」
繰り返しの後、最後は「Forever...」という一言が謎めいた調子で付け加えられて、ジャジーなエレクトリック・ピアノの演奏が消えてゆく。
ケリー・ミネアの繊細な歌唱によるジャジーなバラード。
厳かな響きのある神秘的な作風である。
憂鬱さあふれる幻想性は VERTIGO 時代と同じだが、エレクトリック・ピアノの使い方などジャズロック、フュージョンの台頭に影響を受けたらしき面もある。
比較的ストレートな作風(ただし間奏はあいかわらず)ではあるが、一つ一つの音を活かした丹念なアンサンブルがすばらしい。
音は和んでいるが、歌詞はかなり深刻だ。
リード・ヴォーカリストはケリー・ミネア。
「Funny Way」の時代に合わせたリニューアルという感もあり。
「Playing The Game」(6:46)
マリンバとシンセサイザーが訥々と刻む中華風のコール・レスポンスに、エフェクトされたベースが応じる軽妙なイントロダクション。
なんとなく 007 映画の香港辺りのイメージである。
ギターとリコーダーのユニゾンによるシンプルながらもオリエンタルなテーマが加わる。
ベース(シンセサイザーだろうか)の音が何とも不気味だ。
メイン・ヴォーカリストは。デレク・シャルマン。
メロディ・ラインは、他の曲ほどではないものの、高低の落差がわざとらしいが、きっちりと歌い込んでいる。
間奏は深みをのぞき込むようにドリーミーなタッチ、ざわめくシンセサイザーにギターが応じ、シンセサイザーが切なく歌い、ギターが荒々しく受けとめる。
再びテーマ。
オブリガートにさりげなく変化をつけている。
セカンド・ヴァースでは、ヴォーカルをマリンバが裏拍から支え、変な音のベースも積極的に絡んでくる。
リラックスした短い間奏、メイン・テーマの再現を経てフェード・アウト。
え、3 分もたたないうちに終わり?
一瞬のブレイク。
終わるはずもなく、やわらかなエレクトリック・ピアノの和音の響きとともに、ミネアがひそひそとささやき始める。
完全に別の曲である。
ベース、エレクトリック・ピアノらが物憂げに、しかし自由に、舞い踊る。
そして、ギターの和音、ホィッスル風のオルガン、エレクトリック・ピアノが穏かに語り合うようなアンサンブルを成してゆく。
ひらひらと舞うオルガン・ソロ。
ギターのコード・ストロークとエレクトリック・ピアノのアドリヴ。
リズムを意識させず、ジャジーな即興風である。
抑え目のヴォリュームでミステリアスに演奏が続く。
しかし、ドラムスが鋭い決めを連発、アクセントの強いリズムが復活する。
マリンバのアクセント。
中華風テーマとは裏腹な、なかなかハードなイメージの展開であり、ファンキーなビートとともに、荒々しいサウンドのオルガンによるソロが始まる。
ハモンド・オルガンのいい音が出ている。
最後のヴァース。
中華風のリフにぐにゃぐにゃベースが反応しつつ、きらきらとした鍵盤による優美な間奏を経て、ベースも巻き込んで最後まで中華風のテーマを繰り返しつつフェード・アウト。
YELLOW MAGIC ORCHESTRA のような中華風の軽妙なテーマ・アンサンブルが耳に残るポップなロック。
テーマを構成するマリンバらのアンサンブルは特徴的だが、そのほかは比較的普通の作風だと思う。
または、このグループの水準からするとそれほど凝っていない、といえばいいか。
歌メロのなじみやすさ含めポップス・ファン層を意識したアクセスしやすい作品といえるだろう。
もちろんソロ・パートの比重の高さや、中間部でちゃぶ台をひっくり返すような展開を見せるなど、それなりに仕掛けはあります。
メイン・ヴォーカリストはデレク・シャルマンで、中間部のヴォーカリストはケリー・ミネア。
「Cogs In Cogs」(3:07)
勢いあるハモンド・オルガンにスピーディなシンセサイザーが華麗に絡まるテクニカルなオープニング。
リフは得意の変拍子(8 分の 8 + 8 分の 7)である。
ベースの動きも敏捷だ。
一転激しいユニゾン(8 ビートのアクセントずらし)、アクセントの強いオルガンの 16 分の 9 拍子フレーズ、そして間髪入れずクラヴィネットの 7 拍子リフが応酬する。
そして、斜め上からパワフルなヴォーカル降臨だ。
ギターとオルガンがハードに攻め込む間奏。
決めとオルガン、シンセサイザーの短いかけ合い、そして序盤のオルガン、クラヴィネットがリードする演奏が繰り広げられる。
ハイハット連打が熱気をやや冷まし、それとともに 8 分の 6 拍子で複雑なカノン風のコーラスがうねうねと続いてゆく。
横を流れる不気味な音はメロトロン・フルートだろうか。
再びメイン・ヴァース、そしてオルガンとギターの挑発的なデュオによる間奏。
最後はオープニング・テーマがのスリリングに繰り返され、たたみ込むリズムとともにコーラスが激しく高ぶってピタッと終わり。
ブレスができずに窒息しそうになる超絶快速クロスリズム・チューン。
得意のユニゾンには、凄まじいパワーとともに、限りなくしなるような弾力がある。
クラヴィネット、オルガン、ギター、ヴォーカルの対位的な絡みは、怪奇なまでにこんがらがっている。
ウェザースの正確無比なドラミングがこういう曲では一層際立つ。
「The Boys In A Band」に比べるといくぶんエッジが和らいで軽やかだが、それでもすさまじいテクニックである。
本アルバムでは比較的「普通な」作風も見せるが、この作品では GG 技巧全開である。
ヴォーカリストはデレク・シャルマン。
パーカッシヴなハモンド・オルガンとデジタルな感触のクラヴィネット、そしてきらめくようなシンセサイザーが印象的。
「No Gods A Man」(4:27)
エレクトリック・ピアノ、ギター、ヴァイヴのアンサンブルが奏でるまろやかなテーマにアコースティック・ギターが生々しい音で応じ、ベースが蠢き始めるイントロダクション。
優しげなのにどこかヒヤっとさせらるイントロである。
とはいえ、前曲よりもぐっとフォーク・タッチの展開だ。
繰り返しからの展開は、バッキングから徐々に浮かびあがる位相系エフェクトをかけたギターのストローク、そしてクラヴィネットとチェンバロのささやき。
低音が響けば、謎めきながらもスリリング。
繰り返されるテーマには忙しないベース・ラインが加わっている。
メイン・ヴァースは、イントロのテーマに近いメロディ・ラインによる三声マドリガル、教会調のまま無理矢理ポップスをやっている感じ。
ギターとオルガンのオブリガート。
序奏は 3 拍子系だったが、B メロからは 4 拍子も交えて、4 分の 7、4 分の 4、4 分の 5 と変化する(やれやれ)。
ハーモニーの尾を捉えるような(拍の調節?)ギターやオルガンのオブリガート。
間奏は、クラヴィネットのユーモラスなフレーズで 3 拍子に戻すも、オルガン、チェンバロからギター、ベースへとわたる間に激しく 4 分の 7 などに変化する(もうついていけません)。
現代風でも中世風でもある、共通するのは一種の軽妙さ、コミカルな味わいだ。
三声マドリガルによるメイン・ヴァースの繰り返し(オブリガートはクラヴィネットに変化)から、二度目の間奏は粘っこいロック・ギター・ソロ。
普通のロック・ギターが非常に際立つというこのグループ独特の表現法である。
このムードの大胆な切りかえが独特だ。
イントロのギターのストロークが繰り返され、ハモンド・オルガンの音が華やかにせめぎあいながら高鳴り始めると、三度目のメイン・ヴァースへ。
今度はデレク・シャルマンのパンチのあるヴォイスの一人舞台であり、序奏と同じ 3 拍子でストレートに迫る。
オブリガートはイントロでも現れた「受け」のアコースティック・ギター、そしてイントロと同じギターのコード・ストロークを経てオルガンが高鳴る。
四度目のヴァース、そしてわりとあっさりと終わり。
多彩なキーボードをフィーチュアしたミドルテンポのジャジーなテーマによる超変拍子ポップス。
テーマとヴァースでの拍子の切り換えに加えて、間奏などでもほとんど小節ごとにリズム・チェンジが行われており、比較的なめらかなメロディに奇天烈なひっかかりがある。
さらに、ヴァースごとのオブリガートがすべて異なっている。(序奏を分解して散りばめている)
ギター、キーボードともに多重録音されているようだ。
アクセスしやすそうなのに捻じれと企みが感じられる曲調は本アルバムの特徴の一つである。
ヴォーカリストはデレク・シャルマン。
とても 4 分少しとは思えない内容だ。
屈指の難曲と思われます。
「The Face」(4:12)
鈴が鳴る。
そして、ヴァイオリンとギターの応酬によるスピーディなテーマ。
返しは、8 分の 5 拍子に切りかわったオルガンとギターのデュオ、さらにオクターブを変えたテーマの変奏(ここがメイン・ヴァースのバッキングとなる)。
忙しなくもユーモラスなイントロダクションである。
パンチのあるメイン・ヴォーカルのメロディが一番変である。
バッキングも間奏もほぼ序奏の繰り返し。
展開を促す 8 分の 5 拍子への切りかえが自然に感じられるから不思議だ。
間奏は、8 分の 6 拍子のシンコペーションによるギターのフレーズを経て、荒々しいヴァイオリン・ソロ、続いてハードなギター・ソロ。
小刻みなバッキングが演奏に強烈な弾力を生む。
再び 8 分の 6 拍子のシンコペーション・パターン(しなやかで厳しい調子があらためて P.F.M への影響大と感じる)を経て、メイン・ヴァースへ復帰。
序奏から 8 分の 6 拍子のシンコペーション・パターンへと発展して、鮮やかにエンディング。
ヴァイオリンをフィーチュアしたダイナミックでスピーディなテクニカル歌もの。
序奏で提示したアンサンブルのまま一気に突っ走る。
小刻みなフレージングとコール・レスポンスをたたみこみ息もつかせない。
そして、ソロの前のブリッジで思い切ってなめらかな変化をつけるがそれがまたカッコいい。
ヴォーカリストは上ずりっ放しデレク・シャルマン。
痛快な作品です。
「Valedictory」(3:21)
ドラムスがタム回しでピックアップする小気味のいいイントロダクション。
ハードロック調のメタリックなギター・リフが示されて、オルガンの華麗なグリッサンドが一閃、パワフルなヴァースが始まる。
伴奏はギター・リフと歪んだハモンド・オルガン。
重いグルーヴである。
歌メロは 1 曲目のものであり、変奏曲らしい。
間奏では、ハードロック調のギターとオルガンが軽やかにかみつき合う。
繰り返し部分の間奏では、8 分の 5 拍子のキーボード・オスティナート(途中から 8 分の 6 拍子のギターのオスティナートも重なる)を経て、ピアノとともに長調への転調もあり。
サビはやはり三声のマドリガル。
サビの高まりにオーヴァーラップするように、メイン・ヴァースの復活。
再び 8 分の 5 拍子のキーボード・オスティナートから華やかなピアノのオスティナートへと高まってゆき、弾け飛ぶように終わり。
アルバムを締める 1 曲目の変奏曲。
軽妙さを抑えるように、ややメタリックなサウンドでヘヴィにアレンジ。
タイトルは「告別」の意。
なぜ同じ曲を入れたのか。ネタ切れとは思えないので不思議。
ヴォーカルはデレク・シャルマン。
「The Power And The Glory」(2:52)。
ボーナス・トラック。
男臭いヴォーカルにもかかわらずキャッチーなメロディと歯切れよいバッキングが冴えるモダン・ポップ・チューン。
クラヴィネットが軽やかに鳴り、ヘヴィなオルガンとギターもタイミングよくヴォーカルを守り立てている。
器楽のにぎにぎしさと歌ものとしてのアクセスしやすさのバランスがいい。
XTC 辺りのニューウェーヴ系の「ねじれ」ポップスに通じる面もある。
このまま 80 年代を走ってほしかった。
ポップな聴きやすさとアヴァンギャルドなアイデアを同時に実現するという大胆極まりない作品である。
楽曲はややコンパクト化し、全体的な曲調は「軽妙」という言葉が似合う。
そして、初期のような叙情性や重苦しさは少なくなったと感じる。
楽曲ではメロディよりもリズムが重視され、リフを中心とする歯切れのよいものが多い。
とはいえ、いざリズムを追ってみようとするとやはり一筋縄でいかないことが分かる。
変則型ばかりなのだ。
それでいてこのノリのよさだから恐れ入る。
「Cogs In Cogs」のように、テクニックをそのままぶつけてくる作品に至っては、もう圧巻としかいいようがない。
一方、初期の特徴であったケリー・ミネアのヴォーカルに象徴されるリリカルな表情をもつ演奏と、クラシカルなアンサンブルは相対的に出番が抑えられているようだ。
さらに、音色が洗練され、アンサンブルも整理されて聴きやすくなっている。
機材や録音技術の進化のおかげもありそうだ。
キーボードの種類が増えたことにもよるのだろう。
ふと思ったが、デレク・シャルマンの声質およびメロディ・ラインがドナルド・フェイゲンによく似ている。
そういえば、この室内工芸的(無論 GG の場合ライヴもあるわけだし、それが凄まじかったのも有名だが)な音の作り方も共通している。
まあ思いつきです。
スピーディでリズミカルなのにもかかわらず、不気味にひねくれた感触もあるアルバムである。
(WWA 010 / S21-18468)

| Derek Shulman | vocals, saxes |
| Ray Shulman | bass, violin, vocals |
| Kerry Minnear | keyboards, cello, vocals |
| Gary Green | guitars |
| John Weathers | drums, percussion, vocals |
75 年発表の七作目「Free Hand」。
超技巧的にしてポップな GENTLE GIANT サウンドの集大成といえる作品。
躍動する変拍子、中世ルネサンス風のテーマ、ポリフォニックなコーラス、ジャズ・テイスト、現代音楽調のこんがらがったアンサンブルなど、いくつもの渦巻きが大きさを変えながらぐるぐると回り続けるように、得意技すべてが、ノリノリのファンキー・ロックと典雅なバラードの姿で立ち現れる。
そして、サウンドそのものも洗練されている。
おそらく、初めてこのグループを聴く方には、嵐のようなチャカポコ・フレーズと急転回する演奏が目眩を起こさせるだろう。
しかし、じっくり順を追って聴いてきたファンは、遂に突き抜けた楽曲に感動すら覚えるはずだ。
前作での試行錯誤は、本作品で開花した。
卓越した技巧と深い音楽観を楽曲にとけこませて、聴きやすさも手に入れた大傑作といえる。
時流とともにあるポップスにとって矛盾するような表現だが、遂にかれらはポップスの不易な面を抽出することに成功したのかもしれない。
一曲挙げろといわれれば「On Reflection」。
中世マドリガル風の雅とジャズ、R&B、ドゥワップまでが一体となった空前絶後の傑作。
心地よい頭痛がします。
プロデュースはグループ。
本作品から、CHRYSALIS レーベル所属となる。
ちなみに、フランク・ザッパは GG の大ファンだったそうだ。
「Just The Same」(5:34)大胆なクロス・リズムによるブンチャカブンチャカ・ロックの傑作。
4、3+3、3+4 が平然と交錯するアンサンブル、異常なブレイク、切れ目なしフレーズ、管楽器かシンセサイザーか分からないがピーとかプーとか変な音でいっぱい。
ファンキーでどこか愛らしいという不思議な作風である。
フレットレス・ベースの音を聴くといつも思うのですが、XTC はおそらくこのグループの本曲に相当影響されているのではないでしょうか。(雑談、実際アンディ・パートリッジは GG のファンらしい)
後半のシンセサイザーのソロは「変」過ぎ。
オープニングとエンディングのフィンガー・スナップがなんとも挑戦的でニクらしい。
しかし名作。
「On Reflection」(5:41)問答無用の大傑作。
みんなが真似したがる 四声 GG マドリガルの代表作でもある。
ミネアの賛美歌への切り替えのみごとなこと。
キーボード、マリンバによる演奏は、絡み合って解けなくなった知恵の輪のようだ。
美しいリコーダーのさえずりとヴァイオリンに支えられた一人輪唱を経て、終盤はなんとロックンロール調の本格カノン。
ギター、ハモンド・オルガン、ベース、エレクトリック・ピアノが追いかけあう。
「Free Hand」(6:14)
オゲレツなファンキーさ、パンチの効いたヘヴィさ、知的な軽妙さと三拍子揃った名曲。
感傷的なようで妙にアブストラクトなイントロダクション。
ピアノに重なるクラヴィネットの繊細な無神経さ。
一転、ヘヴィでファンキーなメイン・パート。
あいかわらず男臭さ満載のヴォーカルである。
クラヴィネットで軽く切り返すオブリガート。
ギターのコード・ワークもいい感じのノリを生む。
ジャジーで幻想的な間奏部。
デリケートながら不機嫌なイメージの和声進行と透明感あふれるサウンド。
3 拍子系と 2 拍子系が混迷を極める。(というか私が混乱している)
「Time To Kill」(5:08)ファンキーでリズミカル、そして切なくポップな佳曲。
奇妙なノイズ(オルガンだろうか)が入るオープニングや間奏に挑戦的な変拍子/ブレイク・パターンをはさむも、メイン・パートは珍しくメロディアスなテーマのおかげもあって、軽やかな聴き心地がある(もっとも 4 拍子と 5 拍子の呼応パターンなのだが)。
初期のアルバム・オープニングを思わせる作品だ。
前曲に続き、無理やりな硬軟/剛柔のコントラストを鮮やかに決めてゆく。
パワフルに、ダイナミックに突っ込みつつも、センチメンタルな多声ファルセット・ハーモニーで縁取ったりメロディアスに迫ったりと、粋なポップ・テイストを盛り込むセンスのよさを見せる。
それにしても、「思わず前を歩く人の背中に激突しそうな」大胆極まるオブリガートです。
「His Last Voyage」(6:27)
技巧的なアドリヴ風のアンサンブルによるクラシカルかつジャジーな傑作。
ベース、ヴァイブ、ギターによる気難しげなカノン調アンサンブルと、バロック調の典雅にしてセンチメンタルなメイン・ハーモニーが特徴だ。
中盤からのジャズロック調の演奏(アコースティック・ピアノが珍しい)とマドリガルの交錯、フィードバックで泣くブルージーなワウ・ギター・ソロとクラシカルなピアノ、オルガンのコンビネーション、巧みに重ねられるカノンのテーマ。
分裂気味のようでいて、やや投げやりにして感傷的な雰囲気は一貫している。
金管風のシンセサイザーが降り注ぐと、絶望の上におおいかぶさるようにバロック管弦楽曲が現れる。
終盤はアコースティック・ギターがうら悲しいハーモニーを支える。
もちろんリード・ヴォーカリストはケリー・ミネア。
とてつもなく丹念な演奏です。
物悲しく無常感のある余韻がいい。
最初期の「Nothing At All」辺りを思い出させるということは、音楽の基本的なバリエーションはすでに一作目で完成していたということなのか。
本アルバムの叙情面を代表する佳曲。
「Talybont」(2:43)
エレクトリック・ピアノ、ベース、ドラムス、ワウ・ギターによるカノンとリコーダーとチェンバロの雅なデュオが応答しあうクラシカル・チューン。
愛らしくほんのり幻想性もある円舞風の小品である。
ロックバンドによるクラシカルなアンサンブル表現という観点では、音楽的にダントツの水準にあると思う。
特に管楽器を模したようなエレキギターの表現がみごと。
インストゥルメンタルなのに、不思議なことに、シャルマンとミネアのヴォーカルが聴こえてくる。
いわばカラオケ GG。
奇妙なタイトルはウェールズにある地名らしい。
「Mobile」(5:05)
アコースティック・ギター、ヴァイオリンをフィーチュアしたトラッド風ブギー。
ギターとヴァイオリンによるカントリー/トラッド・テイストと童謡、そして労働歌風ファンキー・ロックの合体である。
ラフなようでいて、やっぱり緻密。
フィドルによるメイン・テーマのリードが気持ちいい。
間奏では 3 拍子も挟み込んで田舎のダンス。
「しりとり」もあり。
終盤のオルガン主導のアンサンブルは妙にデジタルであり、ものすごく変な感じ。
ヴァイオリンが入るとたいへん P.F.M に似ている。(お互い様か)
(CHR 1093 / CDL-57338)

| Derek Shulman | vocals, saxes |
| Ray Shulman | bass, violin |
| Kerry Minnear | keyboards |
| Gary Green | guitars |
| John Weathers | drums |
76 年発表の八作目「Interview」。
基本路線を保ったまま、音の輪郭の明確さとしなやかな味わいが増した傑作アルバム。
リズムに凝った軽妙なアンサンブルとヘヴィでパンチの効いたサウンドという看板に独特のコミカルな含みも交え、全体を "ポップ" なテイストでまとめあげている。
いわゆるハードロック色は後退し、目まぐるしくもなめらか、けたたましくもカラフルという、きわめて個性的なファンキーさが音楽の軸となっている。
かように "ポップ" 色を打ち出しても、実験的なスタンスはきちんと貫かれている。
大胆なクロス・リズム、モーダルなメロディ、現代音楽調といった特徴は維持しつつ、シンセサイザーの大幅な導入やレゲエなど分かりやすい挑戦も行う。
ツアーに明け暮れるバンドの内幕を暴くというコンセプトにしたがい、1 曲目はインタビュアーに「Where should we begin ?」と聴き返すところから一気に曲が始まる。
プロデュースはグループ。
「Interview」(6:54)
「In A Galss House」のガラスが割れる音を思い出させる独特のガチャガチャ感のある、パンチの効いたハード・チューン。
前作の作風をよりマイルドに口当たりしたよくしたような感じもある。
ギター、ベースとオルガンが抜群に歯切れいいスタッカートで快調に伴奏をリードし、ツイン・ヴォーカル、多彩なキーボードなどをフィーチュアする。
間奏部分とミネアのヴォーカル・パートを伴奏するコワれかけたピアノのパフォーマンスもすごいが、メイン間奏部の、抽象的なハープシコード、オルガンのアンサンブル、エフェクトされたベースとギターのデュオに、ひそひそ声のハーモニーが加わり、おもちゃのようなエレクトリック・ピアノも加わったアンサンブルにいたっては、大胆不敵としかいいようがない。
グルーヴを拒否したグルーヴがある。
歌詞内容は、インタビュアーへのバンドからの返答である。
「四作目で、やりたいことと世間との折り合いがついたのさ、それから後はそのまんま」、「みんなロックが見たいんだろ。俺たちを見たまま以上だなんて思わないでくれよ」、「誰かが去れば誰かが来て、同じを歌を歌うのさ」など、きわめてストレートに、リアルで辛らつな言葉が並ぶ。
終盤、メイン・ヴォーカルを支えるきらびやかなシンセサイザー・サウンドが新鮮。
「Give It Back」(5:09) 7 拍子と 5 拍子の呼応による変拍子レゲエ。
クラヴィネットの低音らしきリフをメインに、軽妙なヴォーカルを支えてギターのカッティングが丹念に裏を取る。
キラリと光るような音のアクセントはシンセサイザーが、ピアノの弦を弾く音か。
多彩な音が、「贅沢に」というよりは「無造作かつ丹念に」散りばめられている。
中間の展開部、ギターがリードするふんわりと浮き上がるようにメロディアスなアンサンブル、それを追いかけるマリンバ、ギターとマリンバの軽妙な追いかけあいなど、ユーモラスで温かみある演奏(ただし、リズムの小刻みな変化に加えて、音のすきまが多くリズムをキープするのは難しそう)が盛り込まれている。
ふるえるような音はミュージック・ソーだろうか。
よく聴くとオルガンもうっすら響いており、ミネアのキーボードが大活躍していることが分かる。
跳ねるようなリズムによる削ぎ落とされたアンサンブルを主人公とした作品である。
「Design」(4:58)
厳かで謎めいたアカペラ、コーラスがアヴァンギャルドな変化を遂げてゆく問題作。
序盤はミネアのデリケートなリード・ヴォイスにハーモニーが重なり、賛美歌風の四声となる。
中盤からは、即興風のアグレッシヴなパーカッション(一部キーボードもありそうだ)とともに得意の四声マドリガル(輪唱)。
古楽風味と不気味な現代音楽テイストが交じり合う。
終盤、アドホックな打撃を繰り広げるドラムスと四声ハーモニーの交錯に目が回って酔っ払いそうだ。
オープニングは、「自分たちの音楽をどう説明しますか」という質問に全員が勝手に話し始めるので何だかさっぱり分からないという、「マドリガル」をネタにしたモンティ・パイソンのようなギャグ。
ヴォーカル・ハーモニーと打楽器のみによる、不可思議なムードの作品である。
「Another Show」(3:29)
16 分の 5 拍子で転がるように突っ走る快速テクニカル・チューン。
ギター、オルガン、エレクトリック・ピアノらの金属的な音が耳に刺さる。
タイトすぎるスーパーなドラミングに注目。
熱気はあるが、テープを早回ししているような、機械的な印象が強い。
スピード感はあるが、いつもほどは曲が捻れていないせいだろう。
「Boys In The Band」の系譜にある作品である。
「Empty City」(4:23)
センチメンタルな弾き語りバラードとファンキー・ロックの合体。
東洋風のゆらぎのある美しいアコースティック・ギター・アンサンブル(グリーンとレイ・シャルマンだろう)、多声のマドリガルから R&B 調のファンキー/ヘヴィ・テイストも織り交ぜる。
このファンキー・パートはサックスが迸る。
マドリガルとともに、きらめくようなエレクトリック・ピアノなど、さまざまな音が丹念に織り込まれている。
一陣の風とともに表情をさっと変化させるアンサンブルの妙がある。
本アルバムの叙情面代表。
「Timing」(4:51)
やーれどっこいしょ的な労働歌のニュアンスのあるアッパーなパワー・ポップ・チューン。
ヴォーカルをパーカッシヴでヘヴィなハモンド・オルガン、メタリックなギターがドライヴし、管弦楽器が華やかにオブリガートで盛り上げる。
間奏部分では、ヴァイオリン、重量感あるピアノ、ギターらがポリリズミックなアンサンブル、ソロを繰り広げる。
自由に変化するうわものを支えようと、8 ビートを慎重に刻むドラムスが印象的。
「I Lost My Head」(6:57)
東洋風のメロディ、ハーモニーと軽やかなアンサンブルによる無国籍ソフト・ロックと得意の民謡風へヴィ・ロックの合体技。
透明感あるアコースティック・ギターのアンサンブルとキーボード、ケリー・ミネアのヴォーカルによる軽妙な中世風の演奏から、クラシカルなアンサンブルを経て、デレク・シャルマンがリードするファンキーなパワー・ロックへと進む。
要所で中華テイストが出るところが面白い。
前半はドラムレス、中盤は鼓笛隊風のスネアのみ。
弾けた演奏を巧妙にポップ・ミュージックに馴染ませるスキルがアップした傑作アルバム。
弾け方が足りない、抑制しすぎておとなしいといったイメージもあるかもしれないが、これは絶頂期の余裕である。
コーラス・ワークや変拍子を用いた大胆な構成、様々な楽器をパズルのようにはめ込んだ緻密なアンサンブルは、今回もすさまじい。
さらにすごいのは、これだけアンサンブルが精密化しながらも、メインのメロディや音色がポップに熟していることである。
端的にいえば、さまざまなスタイルへの挑戦とディテイルにこだわったポップ・ソング集なのだ。
パワフルで躍動的で知的で水も漏らさぬ緊密な演奏が最高のグルーヴを生んでいる。
必聴の傑作です。
(CHR 1115 / S21-18467)

| Derek Shulman | vocals, alt sax, descant recorder, bass, percussion |
| Ray Shulman | bass, violin, acoustic guitar, descant recorder, trumpet, vocals, percussion |
| Kerry Minnear | all keyboards, cello, vibes, tenor recorder, vocals, percussion |
| Gary Green | electric & acoustic & 12 string guitars, alto & descant recorders, vocals, percussion |
| John Weathers | drums, vibes, tambour, vocals, percussion |
77 年発表のライヴ・アルバム「Playing The Fool」。
76 年秋のヨーロッパ・ツアーにて収録。
楽曲のライヴ再現性がにわかには信じられない、テクニカル集団 GG のライヴを体感できる貴重な作品である。
メドレーやリコーダー・カルテットなど、スタジオ盤では味わえないライヴ盤独自のおもしろさにあふれている。
そして、アクロバチックな演奏を支えるのが意外やゲイリー・グリーンの堅実なギター・プレイであることや、ミネアのヴォーカル・パートが器楽やデレク・シャルマンのヴォーカルにおきかえられていることなど、さまざまな発見もある。
楽器の持ちかえを追いかけてみると、かなりいろいろと分かって興味深い。
とにかく、いくらでも楽しみの見つかる名ライヴ盤であり、必携であることは間違いない。
さて、表題からして、「人からどう見られているか」の自覚はある模様。
もっとも、「いやいや、あくまでご要望に応えて演じて "Playing" いるだけなんだよ」という皮肉っぽさとそれを支える自信を深読みすることもできる。
CD 二枚組。
「Just The Same」(6:08)
「Proclamation」(5:07)
「On Reflection」(6:24)
「Excerpts From Octopus」(15:35)
「Funny Ways」(8:35)
「Proclamation」1974 年ブリュッセルでのライヴ映像。
「The Runaway」(3:57)
「Experience」(5:33)
「So Sincere」(10:22)
「Free Hand」(7:40)
「Sweet Georgia Brown (Breakdown In Brussels)」(1:15)
「Peel The Paint / I Lost My Head (Medley)」(7:35)
(CTY 1133 / RTE00354)

| Gary Green | guitars, mandolin, recorders |
| Derek Shulman | vocals, saxes, recorder, bass |
| Kerry Minnear | keyboards, vibes, flute, cello, recorder |
| John Weathers | drums, percussion, vibes, vocals |
| Ray Shulman | vocals, bass, violin, viola, trumpet, recorder |
94 年発表の作品「Gentle Giant Live In Concert」。
78 年 5 月 1 日収録の TV 放送用スタジオ・ライヴ。
英国の TV への初出演であり、同時に、英国での最後のステージとなったらしい。
「The Missin Piece」からの作品が半分を占めるも、「Free Hand」から名品三曲、「Power And Glory」からも一曲収められている。
ギター・ソロの拡大やキーボードのサウンドなど、スタジオ盤との違いが聴きどころ。
非メロディアスなテーマとミドル・テンポというごまかしの利かない状況になっても、演奏は安定感抜群である。
特に、キーボードとギターは無茶苦茶うまいです。
最後の二曲では難しいままポップ化するという離れ業に唖然とします。
「The Missing Piece」もそんなに悪いアルバムではなかった、と再認識できる内容です。
「Two Weeks in Spain」(3:06)「The Missing Piece」より。
4 拍子なのにシンコペーションのせいで目まぐるしいリズム・チェンジに聴こえる。
しなやかなギターとオルガン、エレクトリック・ピアノがアグレッシヴな演奏を繰り広げる。
間奏部のオルゴールのような音(オルガンか)もおもしろい。
「Free Hand」(6:38)「Free Hand」より。
冒頭のベースとギターのやり取りはじめ、一貫して軽妙にしてしたたかで挑戦的。
ポリリズムの果て、誰が先頭になっても一糸乱れぬ旋回を続ける音楽的ブルー・インパルス。
後半のワウ・ギターとキーボードがせめぎあうジャジーなインプロがライヴらしさたっぷりでたいへんカッコいい。
多声のコーラスもあり。
前曲もそうだったがクラヴィネット系エレクトリック・ピアノが多用されている。
「On Reflection」(5:39)「Free Hand」より。
最初に挨拶と曲紹介の MC あり。(この間にミネアがチェロを構えて、レイ・シャルマンがリコーダーを用意し、ウェザースがヴァイヴのところに移動しているのだろう)
リコーダー、ヴィブラフォン、チェロのトリオによるクラシカルなテーマ演奏から始まって、四声(三声か?)マドリガルへとつながる。(マドリガルの間に元のポジションに戻っているのだろう)
しなやかなトゥッティを経て、奇妙な音色による軽妙なキーボード・ソロが繰り広げられる。(レイ・シャルマンはすかさずヴァイオリンを手にしている)
「Just the Same」(4:57)「Free Hand」より。
ファンキーでノリノリのクロス・リズム・チューン。
7 拍子のテーマ、6 拍子の B メロを、8 ビートのオブリガートが受け止める。
牧歌調の間奏部では、しなやかなギター、変態的なキーボード・オブリガート、ソロを堪能できる。
リプライズするエンディングもいい。
スタジオ盤ではフェード・アウトの楽曲をどのように終わらせるかワクワクするのも、ライヴ盤の楽しみの一つである。
「Playing the Game」(4:46)「The Power And The Glory」より。
レゾナンスを効かせたシンセサイザー・サウンドが際立つ。
独特の俗謡、民謡風のテーマ、リフはどこから来たものか。
中間部のギター・ソロの「真っ当さ」が目立つ。
「Memories of Old Days」(7:03)「The Missing Piece」より。
メランコリックな表情が貫くアコースティックなバラード。
序盤のアンサンブルは、P.F.M に酷似。
二つの達者なアコースティック・ギターは、レイ・シャルマンとゲイリー・グリーンだろう。
ほのかに哀愁あるトラッド風のテーマが新鮮。
野太く存在感あるヴォーカルのせいか JETHRO TULL のイメージも。
「Betcha Thought We Couldn't Do It」(2:26)「The Missing Piece」より。
爆風スランプ風のパンキッシュな快速ロックンロール。
ゲイリー・グリーンはこういう曲が好きそうだ。
「I'm Turning Around」(4:00)「The Missing Piece」より。
中後期 GENESIS の作風に通じるデリケートな歌ものシンフォニック・ロック。
オルガンをフィーチュア。
「For Nobody」(4:09)「The Missing Piece」より。
キレのいいハードロック。
ノリはいいが、シンコペーションによる独特のアクセントずらしのせいで、思わずつまづきそうになる。
ギターとオルガンがキレキレのやり取りを見せる。
勢いあまって弾け飛びそうな演奏である。
「Mountain Time」(3:07)「The Missing Piece」より。
リズミカルなファンキー・チューン。
舟歌のようなブルージーで垢抜けない労働歌系が得意だったが、ここでは素直に R&B に寄せている。
ピアノをフィーチュア。
(WINCD 066)

| Derek Shulman | vocals, saxes |
| Ray Shulman | guitar, bass, violin |
| Kerry Minnear | keyboards, vocals |
| Gary Green | guitars, vocals |
| John Weathers | drums |
98 年発表の作品「King Biscuit Flower Hour Presents Gentle Giant」。
75 年 1 月 18 日ニューヨーク、アカデミー・オブ・ミュージックでのライヴ録音。
当時、アメリカ人には、パンチが効いてグルーヴィだがどこかコワレた変態ハードロックとして気に入ってもらえていたに違いない。
クレジットにはないが、ミネアによるヴィブラフォン演奏、ウェザースによるパーカッション・ソロ、リコーダー・アンサンブルもあり。
2018 年に新装で出た「At The Academy Of Music, New York, 1975 King Biscuit Flower Hour」は、本 CD と同じ音源と思われます。
「Proclamation」(5:00)第六作「The Power And The Glory」(本ライヴの時点で新作)より。
ファンキーなブギーが矢継ぎ早に現れるアブストラクトな変拍子パターンとテンポ・チェンジのせいでどんどん変容してゆく。ロックが壊れてゆくイメージである。
「Funny Ways」(7:57)第一作「Gentle Giant」より。60 年代的な感傷を引きずった「Eleanor Rigby」風の作品。
オリジナルのリード・ヴォーカルはミネアだが、ここではデレク・シャルマンが歌っている。ヴァイオリンが活躍。展開部では管楽器とオルガンが勇壮に高鳴り、ミネアによるヴァイヴのソロがある。
「The Runaway」(3:53)第五作「In A Glass House」より。
「Experience」(5:55)第五作より。ポリリズムの嵐が吹き荒れる難曲。
「So Sincere」(8:53)第六作より。これまた変態的に複雑なアンサンブルとハーモニーによる難曲。ヴォーカルはデレク・シャルマン。インストゥルメンタル・パートを拡張したヴァージョン。
「Knots」(7:01)第四作「Octopus」より。Knots はレインの「結ぼれ」のこと。得意のマドリガルと超絶アコースティック・ギター・デュオ(ゲイリー・グリーンとレイ・シャルマン)をフィーチュア。
「The Advent Of Panurge」(5:53)第四作より。全員リコーダーあり。
(70710-88035-2)

| Derek Shulman | vocals, saxes |
| Ray Shulman | guitar, bass, violin |
| Kerry Minnear | keyboards, vocals |
| Gary Green | guitars, vocals |
| John Weathers | drums |
2000 年発表の作品「Totally Out Of The Woods」。
HUX レコードによる BBC 音源の発掘盤。
卓越した演奏技術はスタジオ・ライヴでも発揮され、すべての楽曲が爆発的なスリルとともに再現されている。
目玉は初出の「City Hermit」。
オルガンをフィーチュアしたハードでトリッキーなプログレ作品であり、第一作に入り損ねたらしい。
Strange Fruit による同名の単一 CD 作品の補完版である。
CD 二枚組。
「City Hermits」(4:45)初出作品。70 年 8 月 17 日「Sounds Of The 70's」放送音源。
「Isn't It Quiet And Cold ?」(4:23)第一作「Gentle Giant」より。70 年 8 月 17 日「Sounds Of The 70's」放送音源。
「DJ's Presentation」(0:26)詳細不明のモノローグ。
「The Advent Of Panurge」(5:24)第四作「Octopus」より。73 年 8 月 28 日「Sounds Of The 70's」放送音源。リコーダー・アンサンブルによる「アルプス一万尺」あり。
「Way Of Life」(5:44)第五作「In A Glass House」より。73 年 8 月 28 日「Sounds Of The 70's」放送音源。
「The Runaway」(6:36)第五作「In A Glass House」より。73 年 8 月 28 日「Sounds Of The 70's」放送音源。
「Excerpt From Octopus」(2:09+3:54+0:53+5:36)第四作「Octopus」より。73 年 12 月 4 日「Sounds Of The 70's」放送音源。
「Knots-The Boys In The Band-Organ Bridge-The Advent Of Panurge」
「Way Of Life」(5:45)第五作「In A Glass House」より。73 年 12 月 4 日「Sounds Of The 70's」放送音源。
「Proclamation」(6:00)第六作「The Power And The Glory」より。74 年 12 月 17 日「Sounds Of The 70's」放送音源。
「Experience」(5:31)第五作「In A Glass House」より。74 年 12 月 17 日「Sounds Of The 70's」放送音源。
「Aspirations」(4:56)第六作「The Power And The Glory」より。74 年 12 月 17 日「Sounds Of The 70's」放送音源。
「Cogs In Congs」(2:55)第六作「The Power And The Glory」より。74 年 12 月 17 日「Sounds Of The 70's」放送音源。
「Free Hand - Live arrangement demo」(0:51)75 年宅録。
「Just The Same」(5:58)第七作「Free Hand」より。75 年 13 月 10 日「Sounds Of The 70's」放送音源。
「Free Hand」(6:03)第七作「Free Hand」より。75 年 13 月 10 日「Sounds Of The 70's」放送音源。
「On Reflection」(5:42)第七作「Free Hand」より。75 年 13 月 10 日「Sounds Of The 70's」放送音源。
(HUX 018)

| Derek Shulman | vocals, saxes |
| Ray Shulman | guitar, bass, violin |
| Phil Shulman | sax, trumpet, recorder, lead vocals |
| Kerry Minnear | keyboards, vocals |
| Gary Green | guitars, vocals |
| Martin Smith | drums, percussion |
2009 年発表の作品「King Alfred's College Winchester 1971」。
SIMON DUPREE AND THE BIG SOUND 解体後、ケリー・ミネア、ゲイリー・グリーンを加えた編成による最初期のライヴ・アルバム。(スリーヴには最初のライヴ録音と書かれている)録音状態は海賊版レベル。
「Giant」第一作より。
「Hometown Special」
「City Hermit」
「Funny Ways」第一作より。
「Plain Truth」第二作より。第一作の選曲から漏れた模様。
「Alucard」第一作より。
「Isn't It Queit And Cold」第一作より。レイ・シャルマンのヴァイオリンとケリー・ミネアのチェロをフィーチュア。リード・ヴォーカルはフィル。残念ながら途中で切れる。
「Why Not」第一作より。ゲイリー・グリーンのブルーズ・ギターが全開。
「The Queen」第一作より。
「Peel Off The Paint」第三作の作品と題名は似ているが別物。グリーンのギター・アドリヴをフィーチュアしたパッチワーク。
(ALU GG 07)
初めて聴いたのが七作目の「Free Hand」。
僕はどちらかといえばハードで重い演奏が好みなので、最初に聴いたアルバムがこの作品だったことはかなりアンラッキーな出発だったと思う。
ファンキーさともちょっと異なる、軽妙なリズムと飄々としたメロディが、最初は全然肌に合わず、一二回聴いておしまいになる運命は間違いないと感じた。
けれども、全体にどこか正体をつかみきれないじれったさと深読みさせてくれそうな底無しの暗さがちらちらと現れてきて、結局はアルバムを買い続けて、反芻するように聴き込むことになった。
二つ目のアルバムは四作目「Octopus」。
ハードさという意味では僕のテイストかなと思ったが、やはり第一印象ではズシッとハートに響かず、ぼんやりとした感触だけが残った。
しかし、この作品を何度も繰り返し聴くうちに、何かが見えてきた。
それは独特のリズムであったり、フレーズににじむダークなユーモアのようなものだったり、アカペラやリコーダー等を使っためまぐるしい演奏であったり、実にさまざまな要素であったが、それらが結びついたのか、ある日突然音楽が「入って」きた。
こうなるとのめり込むのは我ながらお馴染みの行動パターンである。
あっという間にアルバムは揃い、すっかりフェイバリットになってしまった。
今でも汲めども尽きぬ泉のように、聴き返す度に新鮮な驚きを与えてくれるアルバムは、他のいくつかのお気に入りとともにしっかりローテーションの一角を占めている。
なぜのめり込んだのかということについて、言葉で表現するのは難しい。
聴き続けていくうちに言葉が見つかるかもしれないが、今いえるのは「これはとんでもなくプログレッシヴだ」という僕の基準をある日突然クリアしたということのみ。
おそらくキーワードは「ポップ」と「暗さ」と「ヨーロッパ」。
豊かなアイデアと知識を緻密な計画で組み立てた音楽であることは間違いないと思うが、一点僕の経験からいえることは、彼らの「ノリ」に耳が慣れるまでにはそれなりに時間が要るということだ。
独特の「間」や「決め」が実はとんでもないテクニックに裏付けられていることが分かるに連れて、どんどん面白くなっていったというのが僕の実際だったかもしれない。
このバンドについては、すべてのアルバムがいろいろな音楽が混ぜこぜになった摩訶不思議な味わい(莫大な情報量を削らずにそのまま音にしているというべきか)をもっており、明快な感想をもちにくくしているせいで、アルバムの人気投票をやったら投票の意味がなくなるくらい票が割れそうな気がする。
ある人にとってベストが、同時に他の人のワーストであることも十分考えられる。
それくらいアルバム毎、曲毎にめまぐるしく色々な顔を見せるし、また見ようと思わなければ見えない部分の沢山あるアーティストである。
とにかく「凝る」ことに誇りを持っている職人気質全開の変人集団であることは間違いない。
これは誉めてます。
サウンドを一ことでいい切れればこんなに字は書かないんだが、あえて誤解を恐れずまとめるなら、ファンキーなハードロックにジャズ、バロック・アンサンブル、中世教会音楽風のコーラスを突っ込んだアヴァンギャルドなポップスでしょうか。
彼らのプログレッシヴなアプローチは、クラシックやジャズを大胆に取り込むことの他に、複雑なリズム・パターン、アクセントずらしそして多彩な楽器のアンサンブルなどがあるが、それらがあからさまでないだけに他のグループに比べると格段に分かり難い。
本当の名手のプレイがファイン・プレイに見えない、というのに似ているかもしれない。
既存の音楽を大胆にアレンジし直して解釈し、これ以上タガを外すと大変なことになってしまいそうなギリギリところで演奏が行われているにも関わらず、それを全く表情に出さず、キャッチーなハードロックとして悠々かつ飄々と演ってしまうところが凄いし、「粋」である。
大層な組曲もなければ、音楽以外の精神性云々といったようなプログレッシヴ・ロック・グループにありがちなメタ・フィジカルな尾ひれもない。
そして緻密なスコアによる幻惑的な演奏に加えて、ライヴでは凄まじい即興もあったそうだからもうこれは大変な人たちだ。
サウンドとアプローチは異なるが、KING CRIMSON と同じく発表後 20 年以上経っているにも関わらず全く古くならないロックである。
できることなら再結成して来日してもらいたい。
また、このグループは P.F.M や BANCO といったビッグ・ネーム含めたイタリアのグループに多大な影響を与えているそうだ。
そのせいか、本家のサウンドのイメージまでがブリティッシュ風味を越えて大陸的な薫りを帯びてきているのも面白い。
また、多くのアメリカのプログレッシヴ・ロック・グループが、影響を受けていることも知られている。
九枚目にライブアルバムを出した後は、ポピュラリティを得ようと路線を転じたものの、結局成功に至らず 81 年に解散しているということだが、これだけたくさんの質の高いアルバムを聴いてしまうととても信じられない。
また、本国イギリスではさほど人気がなかったというのも驚きだ。
英国以外からは決して現れないサウンドなのに、これも不思議なことだ。
