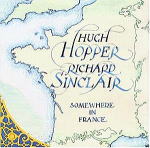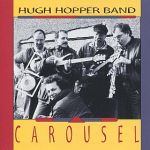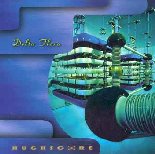Hugh Hopper
1984
| Hugh Hopper | bass, percussion, mellophone, loops, piano, sax |
| John Marshall | drums on 2,3,4,5,6,7 |
| Pye Hastings | guitar on 2 |
| Lol Coxhill | soprano sax on 2,7 |
| Gary Windo | bass clarinet on 3, tenor sax on 2,4,7 |
| Malcolm Griffiths | trombone on 2,3,4,7 |
| Nick Evans | trombone on 2,3,4,7 |
72 年発表の初ソロ作「1984」。SOFT MACHINE の「6」より前に発表されている。
SOFT MACHINE での仕事を「6」を最後に終えるホッパーが、自分のやりたいことに向けて独自に動き始めたということだろう。
主題はタイトルから明らかな通り、オーウェルのディストピア小説「1984」。
曲名は原作に登場する行政管理機構を示しており、非人間的な組織というイメージを大胆な音響で描いている。
思わず、このおぞましき管理体制社会を眺める目で SOFT MACHINE の状況をとらえていたのかもしれない、とコワいことも考えてしまう。
全曲インストゥルメンタル。
プロデュースもホッパー。
アルバム・オープニングは、後にも繰り返し録音される恐るべき名作「Miniluv(愛情省)」(14:38)。ほとんど彼のベースの多重録音からなるサウンド・エフェクト的な実験作である。
ハーモニクスやグリッサンドはおろか極端な高音部でのプレイからピッキング・ポルタメント(というよりノコギリ音)、ブリッジ部分でのノイズなども交えた断片的なフレーズが重なり呼応し不気味な風景を描いてゆく。
とりとめなさと緊張が両立し、やがて帰ってこられない旅に出てしまったような気分になる。
メロフォンとクレジットされた管楽器もホッパーによる。
個人的には全く古びることのない音のように感じます。
また、ビル・フリゼールの作品と同じヴァイブレーションを感じます。
2 曲目「Minipax I(平和省)」(3:17)
軽妙なパイ・ヘイスティングスのコード・ストロークに支えられ、管楽器がメロディアスに歌う。
メロディには脱力感とやや下品なニュアンスもあるような。
フリージャズ調の絶叫サックス(コックスヒルだろうか)が間の抜けたトロンボーンやベースのリフと響きあいかなりズッコケた雰囲気である。
活気は確かにあるのだが不自然でありテーマはやはり不気味。
3 曲目「Minipax II」(3:09)
スタッカートのフレーズを吹き続けるバスクラリネット、ドローン風のベース、そしてやたらとハイテンションのトロンボーン二管のアドリヴ。
さらに、紙をクシャクシャさせる音、クシの歯を弾く音がずっと続いている。
自動演奏機械を見るようであり、こちらの思いは決して伝わらないような暗い気持になる。
取りつくしまがない。
4 曲目「Minitrue(真理省)」(1:24)
シリアスなジャズロック小品。
ホッパーはピアノのみ。
マーシャルが力強くリズムを叩き出しブラスが力強くうねる。
不安定なイメージを強めるピアノの残響。
5 曲目「Miniplenty(豊富省)」(17:03)
エレクトリックなノイズやうめき声がつくる音塊を、パーカッションの軽快な音が削り取り輪郭をつけてゆくようなイメージのアヴァンギャルド巨編。
サステインするエレクトリックなリフレインと切れ味の鋭いパーカッションのコントラストが鮮やかである。
パーカッションがリバーヴを残すという逆説的な展開になると軽快なリズムにあわせてファズ・ベースがエンジン音のように次第に頭をもたげ電気の粒を飛び散らせつつ動き始める。
機械のようなノイズとファズ・ベースの驀進にパーカッションが応える。
そしてテープによる軽快な演奏の挿入。
地獄の洞窟で巨大で醜い怪物がうめき声をあげつつテレビを観ているようなイメージが浮かぶ。
ベースは挿入された演奏に反応して次第に激しく動き出す。
ノイズそしてパーカッションとベースのインタラクションさらにはサウンド・コラージュまで、前衛手法をつぎ込んだ大作である。
6 曲目「Minitrue reprize」(3:08)
前曲から切れ目なく始まる。
ノイジーなサックスのオーヴァーダブが圧するとベースがゆったりと秩序をもたらす。
ベースとは思えないクリーンな高音が湧き上がるサックスの海を吹き抜ける。
サックスもホッパーによる。
7 曲目「Miniluv reprize」(5:02)
ボーナス・トラック。
長いブレイクに続いて始まるのは 1 曲目のフル・バンド・ヴァージョン。
メロディアスなトロンボーンそして敏捷なベース、ドラムス。
激しく切り込むのはヘイスティングスのギターか。
リードはトロンボーンであり不協和音を使ったベースも目立つ。
再びワウ・ギターが轟く。
ギターは頻繁にエレクトリックな音で切り込みトロンボーンにアクセントを付ける。
そして絶叫するサックスの登場だ。
混沌とする演奏しかし前進は続く。
ファンク、フリー・ジャズのニュアンスたっぷりのジャズロックであり、マイルス・デイヴィスを思わせるミドル・テンポの迫力ある演奏である。テーマはホッパーらしいインダストリアル調のざらざらした手触りである。
実験色の濃い作品を中心に現代的で鋭利なジャズロックまで不協和と不安感が全篇を貫く。
ホッパーのアヴァンギャルドな感覚がはっきりと分かる作品である。
素材はラフながらも組み合わされた音の印象は緻密できめが細かい。
普遍的な作品といえるだろう。
CARAVAN のパイ・ヘイスティングスのゲスト参加が珍しい。
なお日本版CD は 5 曲のアウトテイクのボーナスがつく。
(CUNEIFORM Rune 104)
Hopper Tunity Box
| Hugh Hopper | bass, guitar, recorder, soprano sax, percussion |
| Elton Dean | alto sax, saxello |
| Mark Charig | cornet, tenor horn |
| Frank Roberts | electric piano |
| Dave Stewart | organ, pianet, oscillators |
| Mike Travis | drums |
| Richard Brunton | guitar |
| Gary Windo | bass clarinet, saxes |
| Nigel Morris | drums |
77 年の発表の作品「Hopper Tunity Box」 。
内容は、ISOTOPE の朋友ナイジェル・モリス、フランク・ロバーツ、旧知エルトン・ディーン、デイヴ・スチュアートらをゲストに迎え、サイケデリックな発散をやや抑えた(ソロイストのエゴを制御した)アヴァンギャルドなジャズロック。
SOFT MACHINE 時代の作風をより濃縮したイメージである。
変則リズムと不協和音と無調旋律を駆使したインダストリアル・ロックに近い作風であり、雄弁なるディストーション・ベースを駆使したノイジーなプレイとふれれば痺れそうなサウンド・メイキングなどなどどこまでもアグレッシヴでキナ臭い。
デイヴ・スチュアートも気合の入ったプレイを見せている。
全体にアヴァンギャルドに尖りながらもジャズとロックの基本的な疾走感とスリルを堅持した作品ばかりである。
さすがホッパーだ。
一部作品は、ISOTOPE からの離脱を考えて用意したものだそうだ。
プロデュースはマイク・デューンとホッパー。
オープニング「Hopper Tunity Box」(3:34)
歪みきったベースが鬱々と響く。
金切り声を上げる管楽器のような音はオルガン(ホッパーのリコーダーも重なっているような気がする)だろうか。ベースとの対位的なデュオにバスクラリネットが加わるも、ノイズが吹き荒れて、キナ臭い展開となる。
バスクラによる「Facelift」のリフも飛び出す。
「Miniluv」(3:32)
轟音ベースがアグレッシヴに突進する、ホッパーの名刺代わりの代表作。
インダストリアルなノイズの嵐をギャリー・ウィンドのフリージャズ・サックスが力強く切り裂く。
3 曲目「Gnat Prong」(7:55)は、プログレ・ファンにはたまらない名曲。
ゴージャズなテーマとデイヴ・スチュアートによる迫真のオルガン・ソロなど躍動感とファンタジー、クロスフェードを経た後半のクラシカルな厳かさが一体となっている。
スペイシーかつスリリングであり、おおげさにいうとトリオの NATIONAL HEALTH をシンフォニックにしたような感じ。
マイク・トラヴィスの攻め込むようなドラミングもカッコいい。
4 曲目「The Lonely Sea And The Sky」(6:31)
マイルス、コルトレーン直系の「ジャズ」なジャズロック。
初期の WEATHER REPORT とも相通じる作風である。
エレクトリック・ピアノとサックスによる優雅なテーマなどホッパーの作風としては異色かもしれない。
もっとも、オブリガートのテープ処理や、ブリッジ部での、ノイジーでデンジャラスなムードはこの人らしい演出だ。
クレジットによれば、イントロや間奏のメローなギターはホッパーの演奏。
中盤のディーンのソロ、終盤のチャリグのソロもよく歌っている。
幕引きはマイルス・ディヴィスの作品そのもの。
5 曲目「Crumble」(3:55)
ギターとエレクトリック・ピアノがリードするファンキーかつ上品な英国風ジャズロック。
ソロは、ロバーツのエレクトリック・ピアノ。
メイン・ストリームでも通用しそうなキャッチーな作風は、SOFT MACHINE では見られなかった。
こういう曲も作れるんですね。
マイク・トラヴィスという人はジャズ畑だと思う(GILGAMESH に参加)が、なかなかけれんのあるカッコいいドラミングを見せる。
6 曲目「Lonely Woman」(3:20)
オーネット・コールマンの作品。
ブラスのユニゾンによるブルージーで無常感あふれるテーマがずるずると続き、一つの紐がときほぐれてゆくように音が散らばってゆく。
オリジナルは知らないが、リズムレスでブラスとベースのエフェクトで演るというアイデアは、ホッパー独自のものではないだろうか。
即興も交えるが、和声/音階がモダン・ジャズ調なため、さほどアヴァンギャルドな感じはない。
7 曲目「Mobile Mobile」(5:00)
再びデイヴ・スチュアートを交えたキーボード・トリオ。
ファズ・ベースが牙をむくノイジーなインダストリアル調の演奏である。
テーマはあるが即興風。
序盤は、各自のプレイが交錯し、全体としてはのっそりと動き始めるイメージだが、ノイズを巻き込みつつ次第に一体感が強まる。
後半の疾走がたまらなくカッコいい。
せわしないドラム・ビートは、まるでキーボード主体の ISOTOPE。
8 曲目「Spanish Knee」(3:48)
ブラスが力強い、ベースラインも明確なジャズロック。
エンディングのサックスは、ほとんどコルトレーンである。
タイトルは「Spanish Key」のパロディ?
9 曲目「Oyster Perpetual」(3:10)
ホッパーのギター、ベースの多重録音による作品。
「1984」風の世界だが、リラックスしている。
(3012842)
76 年発表の「Cruel But Fair」。
ディーン、ティペット、そしてアメリカ人ドラマー、ジョー・ギャリバンとのセッション作。
仕掛け人はホッパーらしい。
内容は、元 SOFT MACHINE の二人とフリー・ジャズメンのティペット、ギャリバンらが熱くぶつかり合うアヴァンギャルドなジャズロック。
SOFT MACHINE なら「5」の世界である。
ただし、オルガンの代わりという言葉では足りない巨大な存在感を見せつけるピアノの音がある。
爆発力と繊細な歌心を併せ持つディーン、明晰で豊かな音色を活かしてソロでも伴奏でも激烈な演奏を聴かせるティペット、両雄相譲らずのパフォーマンスが見ものだ。
ギャリバンによるアドホックな電子音のインサートも健闘するが SOFT MACHINE のような電気の魔術の域には至らない。
ホッパーはベースにファズを使用しておらず、普通のトーンで勝負。
どちらかというといわゆるフリーの器楽の力比べのようなニュアンスはなく、火傷しそうな熱気を伴いつつもあくまで明確な知性に支えられた奥深い審美センスを感じさせる。
英国ジャズの特徴なのかもしれない。
一音一音の響きに張り詰めた緊張感と厳かな情念がある。
米国のインプロヴァイザーを迎え撃つには英国勢の超絶個性の発揮がもう一息というシーンが多いものの、サックスのロマンチシズムとピアノの奇天烈パワーを核にした強烈な即興集団としては十分な演奏だと思う。
プロデュースはフローデ・ホーン。オリジナル LP はノルウェイで発表された。
いわゆる「フリー・ジャズ」にはあまり詳しくないが、字義通りなら、各器楽の自由闊達な即興演奏が繰り広げられる 1 曲目「Seven Drones」(8:30)および 2 曲目「Jannakota」(4:36)は、間違いなく美しいフリー・ジャズだろう。
サックスとピアノ、ドラムスの演奏はまさに爆発という表現がふさわしい。
ヒートアップした和音の連打を見せるティペットに、キース・エマーソンの姿がだぶる。
フリー・ミュージックからのアプローチだろうとクラシック・ピアノからのアプローチだろうと、ハイ・テンションの名手にかかれば、等しく音楽的な興奮をもたらすということだろう。
サックスの要所でのロマンティック極まる仕切りも絶妙である。
2 曲目は、モコモコしたプリミティヴな電子ノイズと身悶えるサックスによる対話風インプロヴィゼーションである。
3 曲目「Echoes」(8:43)は、ベースによる静かなイントロを経て、メランコリックなエレクトリック・ピアノ伴奏に寄り添われたディーンのサックスが官能的なメロディを歌い上げてゆく名品。
緊張感と繊細な美感のバランスが絶妙であり、本アルバム中で最も高い完成度を持つと思う。
初期 WEATHER REPORT の名曲「Orange Lady」を髣髴させる。
個人的にお気に入りの一曲です。
4 曲目「Square Enough Fire」(9:23)は、2 曲目にエレクトリック・ピアノとエフェクトされたベースが参加した形になる。
混沌とした空間に次第に秩序が築かれていくミニマル・ミュージック風の展開は、SOFT MACHINE そのものといっていいだろう。
中盤からの展開のきっかけとなりその後の駆動力となるのは、ドラムス、ベースの生み出すしなやかなリズムである。
エレクトリック・ピアノ、サックスはほどよく抑制しつつも鋭く緊張感あるプレイを放つ。
浮遊しつつもドライヴ感もある好演だ。
続く 5、6 曲目は比較的小品であり、発展前の断片または試行といってもいいかもしれない。
5 曲目「Rocky Recluse」(2:24)は、本アルバムでは珍しくエコーとエフェクトをかけたベースとアコースティック・ピアノの訥々とした対話である。
対話が熱を帯びるとともにシンセサイザーの電子音も参入して、未来の遁走曲のような展開となる。
6 曲目「Bjorn Free」(2:18)
透明感あるピアノがざわめきつつサックスの気高く伸びやかな朗唱を支える。
ニューエイジ・ミュージック風のニュアンスもある、ロマンティックにして先鋭的な小品である。
爽やかな夕暮れの風にまぎれる哀愁のイメージ。
ぜひ発展させてほしかった。
7 曲目「Soul Fate」(5:38)
前のめりのドラムス・ビートとピアノの即興的な伴奏が幾重にもリズムを沸き立たせ、サックスがメロディアスにパワフルに歌い上げる。
この奇妙なカリプソのようなアンバランスが面白い。
長閑で開放的なのに、息詰まるような緊張感もある。
即興の呼応の果て、テンションはどんどん上がる。
まるで秘教の儀式のクライマックスに向かうようだ。
サックスが去るとピアノは低音から高音までを駆け巡る狂おしいソロを経て、リズミカルに和音を刻む。
ピアノも立去るとドラムスだけが残って奇妙な世界の余韻を受け持つ。
(FIDARDO 4 / OW 31373)
77 年に収録、85 年に発表された第二作「Mercy Dash」。
メンバーは前作と同じである。
日本語盤の帯にはライヴ録音とあるものの、真偽は不明。
内容は、サックス、ピアノ主導の破壊的、幻想的なフリー・ジャズであり、現代音楽風の険しく厳格な表情や光沢あるモノクロのイメージの作品である。
音の数は増えたと思うが、硬軟絶妙の流れをもっていた即興の集中度合い、多彩さという点では前作にやや譲ると思う。
しかし、明快にして力強い瞬間やリリカルな光明が鮮やかに差し込む瞬間はあり、そのコントラストの鮮やかさはすばらしく、ときとして、シンフォニックな響きすら感じられるところもある。
第一曲で出現する「Calyx」のテーマの力だろうか。
ジャズロックというよりはアヴァンギャルド・ジャズというべき内容であり、ティペットとドラマーはこの方向を目指していたように思う。
前作同様、フリージャズに傾倒した SOFT MACHINE の「5」のファンにはお薦めしたい。
最終曲に代表される、難解さを越えた感動がある。
本作では演奏面でのホッパーの存在感は今一つ。
1 曲目「Intro / Calyx」(13:58)オープニングからシンセサイザーのノイズが渦巻く、パワフルなフリー演奏。
3 分過ぎアルト・サックスにより「Calyx」のテーマが提示され、その後は、さらにサックス、ピアノのリードで爆発的なインプロが続いてゆく。
テーマにティペットのピアノが忍び寄る瞬間の痺れるカッコよさが吹き飛ばされるほど、この後続する即興合戦がすさまじい。
10 分付近の嵐のようなティペットのプレイを耳にするとこれがどこかにたどりつくとは到底思えない。
しかし、誰もまとめようとしていないのにちゃんとまとまる。それもまたすごいことだ。
その最終的なまとめ役としてサックスが絶叫する「Calyx」のテーマが再び現れる。
2 曲目「Waffle Dust」(2:54)シンセサイザー・パーカッションのノイジーな連打にピアノのざわめきとサックスの調べが重なる断章。
シンフォニックな余韻あり。
3 曲目「Brass Wind Bells」(9:19)
「1,2,2,2」という奇妙なカウントの後、ピアノとベースが重なるパワフルかつ高密度の変拍子リフが示され、緊迫感が一気に高まる。
リフは低音域で押し上げるような力をもち、序章をスリリングに彩る。
その音の奔流にサックスは悲鳴のようなロングトーンを重ねてゆく。(編集によるオーヴァーダブか、サックス自体もコーラスのように重なり合っている)
ピアノは鍵盤パーカッションに近いアタックの音列も放つ。
サックスがリフに同調するのをきっかけに、ピアノも含めて一気に集団即興へと突入。
前作と同様の、狂おしいまでにパワフルなピアノ、サックス中心の即興演奏である。
息苦しくなるほどに音が詰め込まれる。
区切りに現れるサックスの詠唱、間断なきピアノによる煮えたぎるような激情の放射。
不意を突くように、ピアノ、ベースの変拍子リフが復活、サックスもメロディアスに迫って、煮えたぎった即興演奏をタイトな全体演奏へとまとめ上げる。
鮮烈だ。
強引な変拍子リフ、テーマと爆発的な即興パートによる挑戦的な作品である。
攻撃性という観点からロック・ファンにもアクセスできそうな音だ。
強烈なドラム・ビートが加わったらさらに凄まじかったのでは。
4 曲目「Anguishy」(3:02)
ざわめくピアノ、ドラムスと朗々たるサックスのコンビネーション。
情熱的な調べを荒々しい打撃音が支える。
前曲と同じ形式の演奏からクライマックスを取り出したような、荒々しくもロマンティックな表情である。
身悶えるような「苦悩」を表現しているのだろうか。
ピアノのプレイは、ギターの激しいコード・ストロークのようなニュアンスがある。
ピアノの変拍子リフレインから発展しそうだったが、そのままフェード・アウト。
前曲のクライマックスの変奏のような佳品。
5 曲目「Waffling Again/Punkom」(8:00)
ピアノによる近現代クラシック風の美しいリフレインの騒めきを二本のサックスが朗々と貫く。
KING CRIMSON の「Lizard」辺りの雰囲気に近い。(コルネットが加われば完璧だろう)
水面に幾何学的な文様を描いては広めてゆくようなピアノのリフレインに応じて、サックスはうつむくような表情を見せながらも次々と新しいフレーズと歌を生み出してゆく。
繊細なナノマシーンたちがじゃれ合うような異形のファンタジーの趣である。
シンバル、タムの乱れ打ちが加わる辺りでは、すでに、舞い上がりそのまま浮遊してゆく不思議な空気ができあがっている。
音は激しいが、ピアノとサックスによる絶妙の絡みがふんわりとした酩酊感を生む。
終章、ピアノの間断ないざわめきは曙を迎える海辺の潮騒のイメージであり、淡々と悠然たる自然の営みのたくましさを連想させる。(ロバート・フリップのコード・ストロークのニュアンスにも通じる)
幻想的なイメージとともに近代クラシックに似た感動を呼び覚ます傑作。
(CP 2001 / 3012802)
Monster Band
| Hugh Hopper | all instruments on 1-5, bass on 6-9 |
| Elton Dean | saxello on 6-9 |
| Mike Travis | drums on 6-9 |
| Jean-Pierre Carolfi | keyboards on 6-9 |
| Jean-Pierre Weiller | bass on 6-9 |
79 年の発表のアルバム「Monster Band」。
前半 5 曲が一人多重録音、後半 4 曲がバンド形式による 74 年のフランスでのライヴ録音である。
前半の内容は、ファズ・ベースやエレクトロニクスを中心としたノイジーかつ挑戦的なもの。
ミニマルな表現手法と過激な音響による威圧感のある作風であり、改めて SOFT MACHINE の先鋭性、前衛性を担った人らしいと思う。
後半は、ワウ・ワウやファズを用いたベース、エレクトリック・ピアノにディーンのサックスが力強く挑む、危険な香りのインプロヴィゼーション。
スクエアなリズムとリフの上で、思うさま暴れる演奏であり、SOFT MACHINE をよりブルージーにへヴィに再現した感じである。
録音の悪さが、却って鬼気迫る様子をよく伝えている。
ディーンの語法は完全に SOFT MACHINE である。
4 曲だけというのが惜しい。
ベーシストのジャンピエール・ウェイユは、カンタベリー一派の 70 年代フランスでの録音に多く携わっている。
「Golden Section」
「Sliding Dogs」ISOTOPE でも演奏していた作品。フルートも聴こえる。
「Churchy」
「Lily Kong」
「12-8 Theme」
「Sliding Dogs」
「Lily Kong」
「Nozzles Tecalemit」
「Get Together」
(3012782)
Somewhere in France
| Hugh Hopper | bass, fuzz bass, keyboards, gong |
| Richard Sinclair | voice, fretless bass, guitar, bongos |
| guest: |
|---|
| Serge Bringolf | drums on 3,4, percussion on 6 |
| Helene, Jacky, Pascale | voices on 7 |
83 年発表のアルバム「Somewhere in France」。
旧友リチャード・シンクレアとのコラボレーション。
内容は、ベルベットのようなシンクレアのテナー・ヴォイスをフィーチュアした王道カンタベリーな歌ものが主である。
ホッパーは、作詞・作曲およびキーボードやベースをプレイし、シンクレアを支えている。
宅録に近いような製作にもかかわらず、楽想はきわめて豊かだ。
不運にも一線を退くことを余儀なくされるも、無聊を託つことない二人らしく、メロディ、ハーモニー、上質なユーモアのセンスはいささかも衰えていない。
シンクレア作の 3 曲目、4 曲目は HATFIELDS の再来のような佳曲。
ドラムスを担当するセルジュ・ブランゴルフはフランス ZEUHL 系ジャズロック・グループ STRAVE のリーダー。
「Long Lingers Autumn Time」(5:00)ホッパー作。
「Potted History」(3:02)ホッパー作。
「Keep On Caring」(6:03)得意のブクブク・ヴォイス。佳曲。シンクレア作。
「Cruising The Eastern Sky」(4:25)シンクレア作。
「Oldest Story Ever Told」(2:19)ホッパー作。
「Video Shows」(5:19)シンクレア作。
「Solidarity」(4:55)ホッパー作。
「Only The Brave / Colin-A-Dell」(3:44)ホッパー作。
(VP133CD)
Meccano Pelorus
| Hugh Hopper | bass |
| Patrice Meyer | guitar |
| Dionys Breukers | keyboards |
| Pieter Bast | drums |
| Frank Van Der Kooij | tenor & soprano sax |
| Hans Van Der Zee | guitar on 5,6 |
| Kees Van Veldhuizen | alto & soprano sax on 5,6 |
91 年の発表のアルバム「Meccano Pelorus」。
SOFT MACHINE に憧れたオランダのミュージシャンに招かれて結成された、HUGH HOPPER BAND 名義による 89 年と 87 年のライヴ録音。
内容は、知的にしてフィジカルなスリルもあり、そして何よりファンタジックなエレクトリック・ジャズロック。
ホッパーは、作曲およびベーシストとして演奏に貢献する。
変拍子のリフはもちろん、大胆なフレージングを見せているが、ファズは用いていない。
他のメンバーでは、驚異のオルタネート・フィンガー・ピッキングで繊細なニュアンスを表現する巧者パトリス・メイヤー(アルバムでの演奏は前任者と分け合う)、端正なフレーズを奏でるサキソフォニストが印象深い。
ディーン風のサックスや THE BEATLES などのくすぐりもあり。
「Miniluv」も収録。
全編インストゥルメンタル。
録音はややチープ。
「Wanglosaxon」(10:13)ホッパー作。サックス、ギターのソロをフィーチュアした比較的オーソドックスな内容。
自然発生的にスタート、サックス主体のモダン・ジャズ調テーマから、ベースのリフをエンジンに、サックス、ギターとソロがわたる。
ブラス・セクションを模すシンセサイザーのデジタルっぽい音は、この時代ならではのもの。
89 年のツアーから。
「Spanish Knee」(6:15)ソロ第二作の作品。
ホッパー作。
思い切りのいいテーマ、サスペンスフルな展開がカッコいいホッパーらしい作品。89 年のツアーから。
タイトルはもちろんマイルス・デイヴィスのパロディ。
「Meccano Pelorus」(9:14)ホッパー作。
ギターとベースのアドリヴ風のやりとりから発展するスペイシーな作品。
キーボードがメロトロン風の音や大胆な効果音を挿入するせいか、プログレ色強し。
後半は、サックスとベースのインタープレイ。
終盤のユニゾン・ラインがいかにも。
89 年のツアーから。
冒頭のベース・ソロは、ラヴェルの「ボレロ」のテーマでしょうか。
「Miniluv」(6:30)ホッパー作。
ホールズワースばりのギターをフィーチュアし、元曲の面影はなし。
跳躍アルペジオはフィンガーピッキングの独壇場、と思っていましたが、最近の人はピッキングでも難なくやるからなあ。
89 年のツアーから。
「Seven For Lee」(10:31)エルトン・ディーン作。
SOFT HEAD の「Rogue Element」収録の作品。
7 拍子のリフが特徴。
87 年のツアーから。
「Springtime 85」(8:20)ヴェルトヒューツェン作。
ギター・シンセサイザーが加わる後半からが、カッコいい。
87 年のツアーから。
(WAYSIDE WMAS 6)
Alive!
| Hugh Hopper | bass |
| Frank Van Der Kooy | saxes |
| Kees Van Veldhuizen | saxes |
| Dionys Breukers | keyboards |
| Hans Van Der Zee | guitar |
| Pieter Bast | drums |
| Andre Maes | drums on 6,7 |
93 年の発表のアルバム「Alive!」。
HUGH HOPPER BAND 名義の作品。87 年のオランダでのライヴ録音(6、7 曲目のみ、85 年録音)
「Meccano Pelorus」と同時期のツアーでの録音と思われる。
内容は、フュージョン寄りのジャズロック。
モダン・ジャズのパロディのような表現(ホッパーも実直にランニング・ベースを決めている)にぼうっとなっていると、ファズベースが唸りをあげて変拍子のリフを刻んでいるのに気づき、我に返る。
わりとのんびりしたテーマが多く、アドリヴも洒脱に緩め。
最初期 WR や RTF と同質の官能的かつ神秘的な風景もある。
(ホッパーがヴィトウスになり、サキソフォニストがショーターとなる)
最終曲は ISOTOPE でも演奏した作品。
「Glider」(11:22)
「Forget The Dots」(6:34)
「Turfschip Enterprise」(8:43)
「Double Booked」(11:45)
「Nomali」(9:56)
「Lullaby Letterbomb」(5:10)
「Hanging Around For You」(2:55)
「Just In Time」(5:36)
「Golden Section」(5:36)
(VP150CD)
Carousel
| Hugh Hopper | bass |
| Patrice Meyer | guitar |
| Frank Van Der Kooy | sax |
| Dionys Breukers | keyboards |
| Kim Weemhoff | drums |
| Robert Jarvis | trombone on 5,7 |
95 年の発表のアルバム「Carousel」。
HUGH HOPPER BAND 名義の作品であり、93 年のライヴ録音(トラック 2,3,4)と 94 年のスタジオ録音で構成される。この編成でのスタジオ録音は本作品のみだと思う。
内容は、明快なトーンによるメロディアスな表現ながらヒネリの効いたジャズロック。
エレガントで時に神秘的なソロ含め、演奏には常にファンタジーとエスプリというかシニシズムというかワサビの効いたユーモアがあり、どこをとってもメインストリーム・フュージョンとは異なる肌合いである。
(個人的には EARTHWORKS の作風に近いと思う。
つまりこの共通性が「カンタベリー」ということ?)
ヘヴィ・ディストーションを用いたベースにリードされるインプロヴィゼーションの鋭利さは KING CRIMSON を思わせる。
ギタリスト、メイヤーによるタイトル・チューン(新時代のカンタベリー・テイストを代表するほんのりカリビアンな名作)は圧巻のパフォーマンス。
スタジオでのインプロヴィゼーション 2 曲に「Sliding Dogs」も入ったお得な内容だ。
(CUNEIFORM RUNE 67)
Caveman Hughscore
| Hugh Hopper | fuzz bass, bass, double speed bass, wah feedback bass, cats |
| Elaine di Falco | piano, Fender Rhodes, accordion, vocals |
| Fred Chalenor | bass, double speed bass, Fender Rhodes |
| Henry Franzoni | drums, voice |
| guest: |
|---|
| Jen Harrison | French horn |
95 年発表の作品。
ヒュー・ホッパーがアメリカ人ベーシスト、フレッド・シャルノー率いる「Caveman Shoestore」なるユニットにホッパーが参加して製作、発表された。
内容は、ギターレス、ツイン・ベースがリードするユニークな編成による、メランコリックでアヴァンギャルド、無表情な中にクールネスと攻撃性をきらめかせる現代的なジャズロックである。
ホッパーのファズ・ベースは凶暴性や神秘性など多彩な表現という意味ですでにギターの域に達しており、リズムのみならずメロディ、アドリヴとしても十分機能している。
(ホッパーがバッキングするときには、シャルノーが超絶的な速弾きで前面に出る)
また、ディ・ファルコのけだるい低血圧ヴォーカルとアコーディオンにも存在感あり。
アヴァンギャルドな和声やリズムによる尖った感じを巧みに和らげているのはこのヴォーカルであり、一方、独特のペーソスはアコーディオンが放っている。
また、ガレージ調のヌケのいいドラムスやリフ中心のドライヴ感ある演奏は、ジャム・バンドの 5 年先をいっていたともいえる。
全体に、固めで弾力のある鋭い音とゲストのフレンチホルンのような柔らかい音との組み合わせがよくできていると思う。
エコーの深いローズ・ピアノの音はもはやジャズロックの要素としてすっかりおなじみだが、ここでも十分に活かされている。
すでにジャズだ、ロックだというこだわりからは遠く離れたホッパー氏、独自のオルタナティヴ・ミュージックを目指す若者たち相手に、感性でも演奏技術でも堂々と渡り合う。
このあたりがやはり只者ではない。
そして、その若者たちがとりあえず辿りついた音がカンタベリー・サウンドと似通っているのだから驚きである。
乾いたユーモアとシリアスネス、転がるようなメロディに象徴される親しみやすさが同居するこのサウンドには、確かにカンタベリーがこだましている。
ニューヨークのアヴァン・ロック・シーンに現れた先祖返り達にとって、ホッパーは現人神のような存在に違いない。
ディ・ファルコの個性的なヴォーカルと輪郭のはっきりした音響、そしてシリアスかつ明快なメロディが生み出すユニークなサウンド。
やはりコンテンポラリーなジャズロックというべきだろう。
どちらかといえば、SOFT MACHINE よりも歌姫(声質も歌唱法もまるで違うが)を獲得した HENRY COW に近いかも。
独特のクールネスもまたよし。
「Dedicated To You, But You Weren't Listening」のカヴァーあり。
「A Rabbit Or A Lemon」(6:34)
「More Than Nothing」(7:00)5 分過ぎあたりのソロはギターのようなベース。
「Maja Raja」(1:14)
「Dee Dum」(4:34)
「Scooter Trash」(3:20)
「Dust My Mindv」(3:12)
「Splinter Cat/Edorian」(2:32)
「A Small Seed」(5:32)
「Dedicated To You, But You Weren't Listening」(1:14)
「Virtual Cats」(3:23)
「Oregon Transplant」(2:37)
「Freak Control」(2:19)
「Extra Lungv」(3:42)
「Sasquatch Elevator」(1:13)
「Panic」(7:15)
(TK95CD093)
Highspotparadox
| Hugh Hopper | bass, sampler |
| Elaine di Falco | Fender Rhodes, accordion, synthesizer, vocals |
| Fred Chalenor | bass |
| Will Dowd | drums, percussion |
| Jen Harrison | french horn |
| Craig Flory | tenor sax, clerinet, bass clarinet |
| Wayne Horvitz | ring modulated keyboard |
96 年の作品「Highspotparadox」。
「HUGHSCORE」名義の一作目。
ユニットのメンバーはヒュー・ホッパーに加えてフレッド・シャルノー、エレイン・ディ・ファルコの三人であり、他はゲスト。
内容は、往年のエネルギッシュなインタープレイやソロではなく、より抑制された感覚で自発的に発展しつつなおかつクールなキナ臭さを漂わすというきわめて現代的なジャズロック。
ニューウェーヴを経た後のロックの薄っぺらさや進化しなかったジャズの残骸を活かして、アカデミズムの助けも借り、まあまあ洒落た意匠にまとめている。
無国籍なメロディ・ラインやストレンジな反復といったファクターは現代音楽的であると同時にカンタベリーの名残にも聴こえる。
結果として、ラウンジ風のソフトでなめらかな歌ものと HENRY COW 風の尖った演奏が、さほど過剰反応も見せずに並立している。
もちろん抑制にはかえって深刻さを強調する効果もあるが、そういったものを孕みつつもアヴァンギャルドな音楽がきわめてナチュラルに(極端にいえば「聴きやすく」)届いている。
これは昨今のレアグルーヴに耳が慣れたおかげだけではないだろう。
おそらく、遥か昔から斬新な音楽に取り組み続けたミュージシャンたちの発する息遣いや体臭のようなものなのだ。
SOFT MACHINE のぶっちぎりの先鋭性に舌を巻かざるを得ない。
オープニングは、もはやホッパーのテーマ・ソングといっていい「Miniluv」。
ディファルコ嬢のけだるいヴォーカルとアコーディオンが演奏にソフトな手触りを付与するも、聴き終えるとやはり不条理な世界へ取り残されたような心持ちになる。
ギターを思わせるエフェクト・ベースのリード・プレイにさらに磨きがかかっているからコワい。
6 曲目では本家の音源もコラージュされている。
そしてなんと、最終曲は悩殺タンゴ。
緊張感はあるものの、いわゆるアヴァンギャルド・ミュージックのように過剰に暴れることはなく、ときとしてメロディアスで穏やかな印象すら与える逸品である。
最近の作品にしては、録音がデッドなところが唯一残念。
プロデュースはウェイン・ホービッツ。
「Miniluv」()
「Against The Wheel」()
「Baby Brother」()
「High Spot Paradox」()
「Otis Trout」()
「Here They Come」()
「Lullaby」()
「Upgrade」()
「Bald Eagle At Carnation」()
「Once Upon A Babysitter」()
「4 1/2」()
「Last Word Tango」()
(T/K 109-2)
Delta Flora
| Hugh Hopper | bass, fuzz bass |
| Elaine di Falco | accordion, Rhodes, Vox organ, Wurlitzer, synthesizer, voice |
| Fred Chalenor | bass, guitar |
| Tucker Martin | drums, percussion |
| guest: |
|---|
| Chrystelle Blanc-Lanaute | flute | Jon Hyde | pedal steel |
| Elton Dean | alto sax | Dave Carter | trumpet |
| Robert Jarvis | trombone | Craig Flory | tenor sax |
HUGHSCORE の第二弾「Delta Flora」は 99 年の作品。
ドラムスのタッカー・マーティンを加えてフル・バンド編成となり、活動基盤が整ったようだ。
インダストリアル・ミュージックに通じる薄暗くメカニカルなサウンドを背景に昨今のプログレ復権に大きく寄与したノスタルジックなサウンド・サンプリング(実際ヴィンテージ・キーボードを駆使している)と個性的なメロディ・ラインが浮かび上がり、耽美でアヴァンギャルドな展開の中に真っ直ぐ未来を志向するベクトルがある。
思い切って言えば 90 年代 SOFT MACHINE なのだ。
ディ・ファルコのアルト・ヴォイスは、クールに暴れるアンサンブルを象徴するように底力を垣間見せつつ冴え冴えと存在を主張する。
オルガンがメロトロンを思わせ、ローズ・ピアノの音色はどこまでも哀し気だ。
あるべき場所に音をしっかりあらしめる管楽器のサポートも充実している。
この訥々とした現代のジャズロックを二世代下のメンバーとともにリードするのが大ベテランだから恐れ入る。
まさにマイルス・デイヴィスに匹敵するセンスとパワーである。
「Facelift」の再録もあり。
中盤は得意の音響派アヴァンギャルドの様相を呈すも、8 曲目の大作「Based On」でガッチリと雰囲気を作っている。
エルトン・ディーンも元気。
1 曲目「Was A Friend」は、ロバート・ワイアット作詞であり、彼の最新作「Shleep」にも収録されている。
シューベルトの歌曲「辻音楽師」をクールにアレンジしたような名曲だ。
「Was A Friend」(7:05)ホッパー/ワイアット作。
「Facelift」(8:25)大胆な音響処理を施すものの原型はしっかりとどめるカヴァー。ホッパー作。
「November」(5:49)夢想的なバラード。
ディファルコ作。
「Ramifications」(5:37)ごつごつしたインダストリアル・サウンドによるストリート系ジャズロック。魔術的。
ホッパー作。
「Robohop」(6:28)「1984」に通じる厳めしく険しい音響作品。ただしそこはかない哀感もある。
ホッパー/ディファルコ/シャルノー作。
「Remind Me」(6:18)ディーンとホッパーのデュオをフィーチュアしたムーディなバラード。ホッパー/ディファルコ作。
「Spacelift」(2:29)
ホッパー作。
「Based On」(9:29)悪夢に捲かれて迷宮を彷徨うようなモダン・ジャズロック。牙を剥くインストゥルメンタル。傑作。
ホッパー作。
「Tokitae」(6:42)幻想的な変拍子ミニマル・ミュージック。ディファルコ作。ホッパーの作風に影響を受けたのだろうか。
(CUNEIFORM Rune 110)
 close
close