
| Pekka Pohjola | bass, piano, violins, final organ on 5 |
| Risto Pensola | clarinet |
| Pekka Poyry | soprano sax, flute |
| Reino Laine | drums |
| Jukka Gustavson | organ, piano on 4 |
フィンランドのニューエイジ・ミュージシャン「 Pekka Pohjola」。 70 年 18 歳で WIGWAM にベーシストとして参加、さまざまなユニットやソロ・アーティストの道を歩む。 作風は、クラシック、ジャズ、ポップ・ミュージックをブレンドした独特の音と親しみやすいメロディが特徴。 マイク・オールドフィールドと同じく、マルチ・プレイヤーにして希代の作曲家。 2008 年現在、天国にて活動中(らしい)。

| Pekka Pohjola | bass, piano, violins, final organ on 5 |
| Risto Pensola | clarinet |
| Pekka Poyry | soprano sax, flute |
| Reino Laine | drums |
| Jukka Gustavson | organ, piano on 4 |
72 年 WIGWAM 在籍中の第一作「Pihkasilma Kaarnakorva(ResinEye BarkEar)」。
ユッカ・グスタフソンやペッカ・ポイリら旧知の仲間も参加した本作は、WIGWAM のインストゥルメンタル部分を進化/拡大させたジャズロック・インストゥルメンタル・アルバムである。
ギターレスのアコースティック・サウンドを軸にカンタベリー・ジャズロックにも一脈通じる精緻でユーモラスな曲調が主。
ペッカは、すべての作品で溌剌たるプレイを見せている。
楽曲は、スピーディで若々しいジャズロックにヒヤっとするような厳格な表情とクラシカルな展開、また純ジャズの 4 ビートなどを盛り込んだ密度の高いもの。
知的でていねいなアンサンブルに軽やかなドライヴ感があるのは、管楽器やベースの明快で人なつこいフレージングのおかげだろう。
クラリネット、ソプラノ・サックスら管楽器のテーマが非常に魅力的であり、特に木管の暖かみある響きがいい。
また、ベースのテクニックは、メインストリーム・ジャズのプレイヤーとしても十分通用するみごとなものだ。
2 曲目のヴァイオリンや 5 曲目の「ゴリヴォーグのケークウォーク」のようなピアノのように、マルチ・プレイヤーぶりも遺憾なく発揮されている。
全体に、ジャズとクラシックをブレンドした新しいロックというイメージもあり、フレッシュな勢いのよさに好感が持てる作品といえます。
全曲ペッカ・ポーヨラの作品。
プロデュースはマンス・グランドシュトロム。
「Metsonpelia(Carpercaillie Games)」(10:38)サックス、クラリネットの明快なテーマから、ソロをフィーチュアしつつ、ひたすら突進する即興風の名曲。
受けにまわるピアノもいい感じだ。
中盤には、ベース・ソロを大きくフィーチュア。
丹念なシンバル・ワークと弾けるようなスネア打ちがカッコいいドラムスは、今でも十分ウケそうなスタイル。
「Virtojen Kiharat(Curls Of Streams)」(5:32)オルガン、ピアノをフィーチュアしたブルージーなテーマ部。
ジャジーなビートを効かせたりリリカルで暖かみのある管楽器のアンサンブルをはさむなど、アクセントの付け方がみごと。
ソフトな管楽器のリードする演奏は、クラブ・ジャズとしても通用しそうだ。
後半は、クラシカルなアンサンブルも巧みに織り込み、メロディアスな演奏へと変化する。
そして、なんとフィドルとジャジーなオルガン・ソロが交互に現れる。
最後もクラシカルなアンサンブル。
ジャズとクラシックの素養をたっぷり見せつける、才気煥発の名品。
やりすぎなくらい、いろいろ入ってます。
「Armoton Idylli(Merciless Idyll)」(3:49)クラリネットとサックスによるリズミカルでユーモラスなアンサンブル。
繰り返しでは、チェンバロ、ピアノも加わり、管楽器との応酬を見せる。
ドラムス、ピアノによる小刻みなビートが心地よい。
品のいい SAMLA。
「Nipistys(Pinch)」(3:31)ヴァイオリンとクラリネットのユニゾンによるクラシカルで精緻なテーマから、ピアノ、ヴァイオリン、サックスらがソロをとりあう。
細かく連打し続けるドラムスが、緊張を持続する。
サックス・ソロの背後で、ベースが華麗なプレイを見せる。
クラシックとジャズのブレンドである。
「Valittaja(Complainer)」(9:29)
サティを思わせるユーモラスにしてテクニカルなピアノ・ソロは、ひょうきんなアンサンブルへと変化する。
前曲のグスタフソンよりも、こちらのペッカの方がピアノはうまい。
そして、オルガン、ピアノ伴奏によるワウ・ベース・ソロ。
次第に加熱する演奏は、クライマックスを経て静かに去り、厳かなオルガン・ソロが幕を引く。
ややソロが長いが、予想不能の曲展開がおもしろい。
(LRLP 71 / LRCD 71)

| Pekka Pohjola | bass, piano, electric piano |
| Tomi Parkkonen | drums, percussion |
| Eero Koivistoinen | soprano & tenor sax |
| Pekka Poyry | soprano & alto sax |
| Paroni Paakkunainen | alto & baritone sax, piccolo |
| Bertil Lofgren | trumpet |
| Coste Apetrea | guitar |
74 年 WIGWAM 在籍中の第二作「Harakka Bialoipokku」。
内容は、管楽器セクションと自身のピアノを大きく取り上げた個性的なジャズロック。
二作目にしてすでにオリジナリティ全開であり、アルバムとしての完成度もアップした。
何より、オープニングのピアノ・ソロ小品がうれしいようで哀しいようななんともいえないあのペッカ節を完全に確立していてビックリである。
前作がアイデアを奔放につめ込み演奏を楽しむようなジャズロック・アルバムであったのに対して、本作はきちんと整理された展開のあるヴァラエティに富む楽曲で作曲者としての力を発揮した作品となっている。
管楽器やキーボードらによる明快なテーマと弦楽やギターによるアクセントなどアレンジはぐっと洗練され、次作と同レベルの完成度といえる。
演奏面では、今回もベースにとどまらずピアニストとしても非凡な才能を見せている。
作曲家としても演奏家としても一流なのだ。
スリーヴには、生まれたばかりのカササギ「Bialoipokku」が森の暮らしの味気なさを通じてちょっぴり成長するという奇妙な物語が綴られている。
曲名から考えても、おそらくそのストーリーをモチーフにしたトータル性のあるアルバムなのだろう。
(ただし本人はこの物語は後付であり、楽曲と関係ないといっているらしい)
ポジティヴでリズミカルな曲のうまさはすでに実証済みだが、3 曲目の挽歌のような作品でも、実に巧みな曲想をもっている。
SAMLA の名手コステ・アペトリアがゲスト参加した 6 曲目は、チック・コリアとアル・ディメオラのデュオを思わせる完成されたエレクトリック・ジャズ。
全曲インストゥルメンタル。
プロデュースはマンス・グランドシュトロム。
スウェーデン録音。
英 VIRGIN からも「B The Magpie」として発表された。
イロ・コイヴィストイネンは、フィンランド・ジャズ界の大物。
パロニ・パークナイネンは、サイケ・ジャズの第一人者。
ペッカ・ポイリは、夭折の天才管楽器奏者。
「Alku」(2:11)ソロ・ピアノ。
「Ensimmainen Aamu」(5:31)ほのかなペーソスのある独特のテーマをさりげない変拍子でドライヴするジャズロック。童謡のような親しみやすさがキーである。
「Huono Saa / Se Tanssii」(6:49)管楽器セクション(弦楽にも聴こえるが)をフィーチュア。第一部は再びピアノが導く挽歌。厳かで沈痛ながらも穏やかであり、サイケデリックな味わいも。
第二部は、素朴なリズムでバグパイプを思わせるにぎにぎしい管楽器が踊るフォークダンス・ミュージック。
ベースにあるリズミカルな民族音楽など、マイク・オールドフィールドと共通する資質を感じる。
「... Ja Nakee Unta」(4:33)ビートの強いピアノと管楽器をフィーチュアした朴訥で逞しい田園詩調ジャズロック。
長閑なようでいて、どこか狂的なものをはらむ。
「Hereillakin Uni Jatkuu」(5:42)ファンキーさを強調した変拍子ジャズロック。テクニカルなアンサンブルによる、ユーモラスなのに緊張感がある演奏だ。コイヴィストイネンのパンチのあるサックス・ソロ相手に一歩も引かないベースがおみごと。
「Sekoilu Seestyy」(4:17)にじむエレクトリック・ピアノとベース、ブルーズ・フィーリングがあふれ出るギターによるロマンティックで悩ましいデュオ。
きわめて FOCUS 的。
後半のソロ・ベースは、ミロスラフ・ヴィトウス、スタンリー・クラークをクラシックに寄せたような卓越したもの。
「Elama Jatkuu」(7:47)エネルギッシュでキャッチーな管楽器ロック。このゴキゲンでやんちゃな感じ、ジャズロックではなく、ロックといいたい。
ポイリのアルト・ソロ、パークナイネンのパワフルなバリトン・ソロをフィーチュア。
(LRLP 118 / LRCD 118)

| Pekka Pohjola | bass |
| Reino Laine | drums, percussion |
| Paroni Paakkunainen | flute, soprano & alto & melody sax, maestro woodwind sound system, percussion |
| Olli Ahvenlahti | electric piano, grand piano, moog satellite, string synthersizer, organ |
| Nono Soderberg | guitars |
75 年発表の作品「Uni Sono」。
ペッカの作品で見かける奏者が集ったグループ「UNI SONO」による唯一作。
内容は、ファンタジックでさりげなくテクニカルなユーロ・フュージョン。
主導は管楽器奏者のパロニ・パークナイネンらしいので、当然ながらペッカのソロ作品ほどは彼の個性が前面には出ておらず、相対的にメイン・ストリーム( WEATHER REPORT など)に近接するサウンドではある。
ただし、ファンク、ラテン色は希薄、というか輪郭のはっきりした幾何学的なパターンによって変質させられている。
このエレクトリック・ジャズは、北欧モダン・ジャズの猛者たちがサイケデリック・ムーヴメントやプログレなどロックからの流れを受けて生み出したオリジナルなもののようだ。
ストリングスやエレクトリック・ピアノを活かしたファンタジックでメローな作風と、挑戦的な変拍子とポリリズムがドライヴするアンサンブルを拮抗させるなど音楽的なチャレンジ精神は旺盛だ。
パークナイネンの管楽器のつややかな表情がみごと。
そして、ギタリストのアドリヴがクリス・スペディング(フォルガー・クリーゲルか?)そっくり。
ペッカは曲を提供せずプレイヤーに徹している。(ベースではエフェクトで目立とうとしている模様)
Hi Hat レーベル。
「TVL」(6:22)9 拍子のベース・リフの上でサックスとエレクトリック・ピアノとギターのテーマが華やぎ、たゆとうファンタジックな序盤、スピーディでキレのある 4 ビートでマイルス・ディヴィス、NUCLEUS 風のサイケなアドリヴの応酬の始まる中盤(ギターがクリス・スペディング風、ベースはワウワウで演奏をリード)、テーマへと回帰して、エレクトリック・ピアノがざわめきサックスがささやく。
かわいらしい WEATHER REPORT というイメージのサイケデリックなジャズロック。
ライノ・レイン作。
「Chorea Urbana」(8:37)
ギターのカッティングやふてぶてしいサックスなど R&B 色の強い 8 ビート作品。
アーバンなイメージ、AOR 風でもあるが、やや汗臭い。
エンディングでは再びペッカのワウベースをフィーチュア。
パロニ・パークナイネン作。
「Boulevard Blues」(6:50)
ギターとストリングス系シンセサイザーで描くスローでロマンティックな作品。
エレクトリック・ピアノのアドリヴも優雅。
なんというか王道っぽさ満点。CM で使えそう。
オリ・アーベンラーチ作。
「Jedi And Rekku」(11:27)ピアノの重量感ある音が特徴的な変拍子ジャズロック。
ポリ・リズミックな独特のグルーヴ。
バラードのパートの説得力もみごと。
後半は RETURN TO FOREVER ばりのリフとギターがドライヴするスリリングな演奏、かと思いきやわりとマッタリしてテクニカル民謡化。
パロニ・パークナイネン作。
「Iltatahti」(9:38)謎めいたオルガンが高鳴り、リズム・セクションが執拗に変拍子を刻み、サックスらがアドホックなアドリヴで交錯する。
リズム主導のアブストラクトなジャズロック。
パロニ・パークナイネン作
(HILP 106 / ROK047)
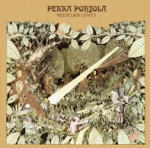
| Geroge Wadenius | guitar on 1,5, percussion on 5 |
| Wlodek Gulgowski | synthesizer on 1,5, grand piano on 5 |
| Vesa Aaltonen | drums on 1,5 |
| Pekka Pohjola | bass, grand piano on 1,2,6, cembaro on 2,6, string synth on 2,5, keyboards on 3,4, synth bass |
| Mike Oldfiled | acoustic guitar on 2, electric guitar on 2,3,4,5, mandolin on 6, whitsle on 5, percussion on 5 |
| Sally Oldfield | vocals on 2,6 |
| Pierre Moerlen | percussion on 4, bell on 5 |
76 年発表の第三作「Keesojen Lehto」。
内容は、明快なテーマを躍動するリズムと多彩な音のアンサンブルで支え、クラシック、ジャズ、ロックをユニークな形で結合したオリジナリティあるものである。
天才ミュージシャンの内部で培われてきた音楽は、密かな温もりとユーモアと子供っぽい残忍さやはしゃぎまわるような無限の運動性を持って光り輝いている。
そしてその光は、暖かく純朴で限りない広がりをもちながら、闇の深さもしっかりと際立たせる。
優れた作曲家であると同時にパワフルなプレイヤーであるだけに、ジャズロック/フュージョンに近いダイナミズムが強く感じられるが、楽曲そのものは普通のジャズロック/フュージョンではない、もっと個性的なものだ。
おそらく、生命感あふれるニュー・エイジ・ミュージックというのが、最も適切な表現だろう。
また、英 VIRGIN レーベルのサポートを得てマイク/サリーのオールドフィールド姉弟とピエール・モエルランがゲスト参加して、このユニークなサウンドを支えている。
マイク・オールドフィールドの生き生きしたプレイは、あたかも眷属の誕生を祝福するようだ。
また。ギタリストのゲオルグ・ヴァデニウスは MADE IN SWEDEN のメンバー。
全曲インストゥルメンタル。
英 VIRGIN からは、「Mathematician's Air Display」として発表された。
邦題は「数学家の空中広告」。
ここのジャケットはフィンランドの LOVE RECORD のもの。
1 曲目「Oivallettu Matkalyhty(The Sighted Light)」(5:03)。
エコーの効いたベース(高音部と思われる)による鼓動が、いかにも北欧フュージョンを思わせる波乱含みのオープニング。
ジャズ・タッチの丹念なシンバル・ワークがカッコいい。
ピアノとベースの低音がビートを刻み、ワウ・ギターのロングトーンが切なく歌う。
一転、テーマはシンセサイザーの変調音がオルガンのように渦巻くなかを、重いピアノの和音とギターで刻まれる。
再び、ギターのテーマ、そして鮮やか過ぎるベースのオブリガート。
ピアノのリードでテーマが展開される。
ギターは、素朴な音の素朴なプレイ。
再び、ピアノのリードで、力強くビートの効いた変拍子の演奏が続く。
ギターが細やかなフレーズで応える。
勢いよく立ち上がるようにスタッカートで跳ねる演奏がカッコいい。
仕切り直しは、ずしっと重いピアノのビートが演奏をリード。
そのビートの上でテーマ変奏が、ゆったりと提示される。
シンセサイザーのノイズが一閃し、ピアノと人力テクノ風のハンマー・ビートが突き進む。
再び、テーマ変奏、そしてスペイシーにして強圧的なテーマが再現。
タム回しも鮮やかだ。
最後はメロディアスなギターのテーマから、軽やかにエンディング。
弾けるようなビートを強調したジャズロック。
WIGWAM での作品や前作までの世界に近い。
シンプルなテーマを、ややサイケデリックな音響を用いた一体感あるアンサンブルで、きっちりと浮かび上がらせる。
ピアノを主に、低音に強勢をおく演奏は、いかにもベーシストらしいセンスである。
ナチュラル・ディストーションを効かせたメロディアスなギターもいい。
CARAVAN などカンタベリー系に通じる雰囲気あり。
2 曲目「Kadet Suoristavat Veden(Hands Calming The Water)」(4:40)。
序盤は、バロック風のチェンバロ独奏。
前曲の強烈なビート感をぬぐい去る物哀しいテーマが、丹念に綴られる。
豊かに響く低音部には、ピアノも重なっているようだ。
そしてチェンバロ、ピアノは伴奏へ周り、コンプレッサーで震えるような音になったアコースティック・ギターが、静かにテーマを奏で始める。
せせらぎのように流れ、ギターを支えるストリングス・シンセサイザーの響き。
ギターは、トラッド調の哀感を強めつつ切々と歌い上げる。
そして静かに音を残して去るチェンバロ。
ギターが止むと、深い霧に包まれるようにエコーがたゆたい、ピアノとともに透き通るようなヴォカリーズが湧きあがる。
夢のように美しくたおやかなヴォカリーズだ。
ストリングスとともに、ヴァイオリンを思わせるエレキギターがささやき始める。
やがてヴォカリーズとストリングス、エレキギター、すべてが重なりあい力強い流れとなってゆく。
哀しくも美しい思い出をかみ締めるようなチェンバー・アンサンブル。
典雅なバロック室内楽とトラッド・フォークを、哀感ある旋律で結びつけた、ファンタジックなニューエイジ・ミュージックである。
前半の胸が裂けそうな悲哀から、後半の儚くも心安らぐ幻想世界への展開がすばらしい。
序奏のチェンバロのテーマは「ペール・ギュント」の翻案だろうか。
メイン・パートのギターのテーマは、チェンバロのテーマをひねりつつ、かなり癖のあるメロディに仕立てている。
リズムもやや変則的だ。
オールドフィールド姉弟が参加したトリオによる演奏。
終盤の粘っこいギターが、いかにもオールドフィールドらしい。
3 曲目「Matemaatikon Lentonaytos(Mathematical Air Display)」(7:18)
あまりに印象的なピアノのテーマは、現代音楽にローカルなユーモア・センスを織り込んだような、きわめて個性的なもの。
このテーマを巡って、行進曲風の演奏が続いてゆく序盤。
2 コーラス目からはギターが加わって、ピアノを追い越し、主導権をつかんでゆく。
受けに回るベースは、控えめながらも、テクニカルなプレイをしっかり決めている。
躍動するテーマとそれに応ずる繊細なアンサンブルが、起伏をつけながら、次第に音が豊かになってゆく。
テーマはすっかりギターのものになり、転調を繰り返しながら進む。
ここで、連なって湧きあがる泡のような第二主題が、キーボードによって示される。
繰り返されるたびに厚みを増してゆくアンサンブル。
第二主題に寄り添い、自由なプレイを見せるギター。
きらめきながら、どんどん高まってゆく演奏と舞い踊るギター。
ビッグ・バンドとオーケストラが合体したような演奏だ。
そして、最後に再び、ギターによる第一主題、そして、そのままキーボードへと主題は引き継がれる。
最高潮を経てストリングス、ギターの余韻を感じつつ、ベースによるスピーディなアドリヴがひそひそと続いてゆく。
次第に遠ざかる演奏、リダルダンドして、そうっとおしまい。
あまりに印象的なテーマをもつ代表作。
民族音楽風の主題や、巨大なバグパイプを思わせるアンサンブル、反復を主とした展開など、マイク・オールドフィールド調が強すぎるきらいもあるが、テーマを彩るリッチでオプティミスティックな音作りは、ペッカのものだ。
ジャズのビッグ・バンドとシンフォニック・オーケストラを混ぜてしまったようなアレンジが、おもしろい。
目立たないところで我関せず風にベースのアドリヴを入れるのも、なんとなくユーモラスなニュアンスが感じられる。
粘っこいギターは、マイク・オールドフィールド。
ドラムスは、ピエール・モエルラン。
4 曲目「Paantaivuttelun Seuraukset - Osa1. Sulamaan jatetty kipu(The Consequences Of Indecisions-Time Heals All Wounds)」(4:30)
モダン・クラシック調のピアノ・ソロ。
ロマンティックながらもストイックであり、残酷なまでに利己的な美意識が感じられる。
美しくも険しく、緊張感のある演奏だ。
続いてベースが加わり、ピアノと干渉しあう。
ピアノに比べると、ベースの音は人の声のように暖かみがある。
やがて、二つの楽器は、運命的な出会いであったかのように静かなハーモニーをなす。
そして、ゆっくりと階段を下りるように手をとりながら、スケールを降りてゆく。
ブレイク。
そして、ピアノの和音を伴奏に、ベースがリードをとり哀しげなメロディを歌い始める。
クラシック調のピアノとジャジーなベースのソロというユニークな世界である。
ベースは機敏な動きを見せるも、素朴で品のある演奏であり、密やかな温もりが感じられる。
再びブレイク。
打ち鳴らされるシンバル、そしてストリングスとともにエレクトリック・ギターが降臨、泣き叫ぶように高鳴る。
情熱に任せて細く鋭く鳴くギターと地を揺るがすベース。
ストリングスとともに吸い込まれるようなエンディングを迎える。
ピアノ、ベースをフィーチュアしたロマンティックな作品。
クラシカルで厳格なイメージを与えるピアノに対し、ベースはジャズ的な自由闊達さと瑞々しさを強調する。
一種の象徴ともいえる演奏だ。
密やかながらもきちんと律せられた空気を貫くのは、意外にも、ジャズで鍛えられた逞しさである。
終盤のギター、ストリングスのシンフォニックな演奏には、厳かながらもすっきりした開放感もある。
5 曲目「Paantaivuttelun Seuraukset - Osa2.Nykiva keskustelu tuntemattoman kanssa(The Consequences Of Indecisions-Comfort With A Stranger)」(11:21)
二部作の後半であり、前曲のエンディングから間隙なく始まる。
ピアノは一転ジャジーな和声によるプレイへと変化した。
ピアノの主題をギターが引継ぎ、ドラムスのピック・アップとともにダイナミックな演奏が始まる。
ジャスト・ビートのドラムスによるリズム・キープの上で、変拍子の主題をギター、ピアノ、マリンバ、シンセサイザーが軽やかに奏でてゆく。
シンセサイザーとギターのユニゾンが軽やかに駆け上がり、メロディアスなギターとエレガントなプレイで演奏が高まり、ゆったりと落ちつく。
マリンバとシンセサイザーによるコール・レスポンス風のアンサンブルに対して、ギターが力強く応える。
繰り返しでは、ギターの応答に、ムーグ・シンセサイザーが重なる。
続いて、ベースによるシンコペーション・リフの上で、ギターとムーグが軽妙なやりとりへ。
やがて、ファズ・ギターとつややかなムーグの呼応から、ムーグによる華やかなソロへ。
スピーディな指捌きが目に浮かぶ。
ブレイク。
再び、ベースがファンキーなリフを提示、今度はギターが果敢に立ち向かってゆく。
奔放なワウ・ギターに、ファズ・ギターとピアノが応じる。
ジャジーなアドリヴ大会だ。
そして、一気に飛び出すは、オールドフィールドのファズ・ギターによる超絶ソロ。
この人、実はロックギターらしくない速弾きが非常にうまい。
再びブレイク。
そして、再びマリンバ、シンセサイザーによるコールレスポンス風のアンサンブルから、ギターによる応答が繰り返される。
変拍子の主題を、ギター、ピアノ、マリンバ、シンセサイザーが軽やかに奏でてゆく。
メロディアスなシンセサイザーが演奏をなめらかにリードし、ピアノが和音を響かせる。
続いて、抑えた伴奏をしたがえて、万を辞すようなベース・ソロ。
伴奏はハイハットとピアノ。
ギターも加わるが、主役は完全にベースである。
不協和音を示すベースにピアノも応酬する。
ギターのリードでようやくメインの変拍子アンサンブルが復活し、シンセサイザーが三度軽やかに演奏をリードし、シンフォニックな余韻を残して終わる。
凝ったテーマをソロをつないだ快活なジャズロック。
リズムはかなり変則的だが、サウンドの印象がメインストリーム・フュージョンに近いことと、シンセサイザーによるメロディアスな決めのおかげで聴きやすい。
1 曲目に近い作風ながらも、今度はソロをたっぷりフィーチュアしている。
全体に自由な雰囲気のプレイが続き、なんとも気持ちよい開放感がある。
メインのトゥッティは技巧的にしてシンフォニックな広がりがあり、プログレ・ファン向け。
リズム・セクションが音数よりも引き締まったビート感のキープを重視しているところが、この独特のはじけるような曲調を支えていると思う。
演奏は、1 曲目のメンバーにオールドフィールド、モエルランが合流したゴージャスな陣容による。
6 曲目「Varjojen Varaslahto(False Start)」(1:50)。
ホィッスルの一閃とともに勢いよく始まる演奏は、快速フォーク・ダンスである。
マンドリンとチェンバロ、ピアノが、小気味よいメロディを刻み疾走する。
大胆な転調や素っ頓狂な奇声は、ほとんど無声映画のオーケストラである。
中盤にさしかかると、演奏はやや傾いできてバランスが危うくなり、今にもひっくり返りそうである。
ところが、いきなりメロディアスなソプラノのヴォカリーズが入って、演奏を無理やり立て直すのだ。
嬌声とともに再びコミカルな快速フォーク・ダンスが復活し、元気いっぱい突っ走るもドン、ピーでおしまい。
北欧のフォーク・ソング調なのだろうか、ユーモラスでエネルギッシュな小品。
コミカルな快速アンサンブルとホイッスル、奇声はまちがいなく SAMLA のセンスに通じる。
運動会のかけっこの音楽みたいです。
クラシック、ジャズ・フュージョンなど既成のパターンをうまく使いながら、美しいものを希求する鋭利な感性を巧みに音におきかえたような作品。
かわいらしいが野心的である。
ジャズロック/フュージョン調の演奏は耳に馴染みやすいが、流してゆくうちにドキっとするような和音やメロディに遭遇する。
テーマとヴァリエーション、ハーモニー、繰り返しなど、音楽の骨格をよく知った上で、主題に的を絞ってさまざまな工夫が加えられている。
細部への凝り捲くりではなく、テーマをいかに浮かび上がらせるかに集中しているようだ。
しかも、そのでき上がりが自然で小粋なところがすごい。
3 曲目は一つの成果だろう。
個人的には、フォーク・ダンスのような親しみやすいメロディをひょいと裏返すと真っ暗な深淵になっているような、不条理な連想が浮かんでしまう。
明確で腰のすわったピアノの音と、小人がせっせと働いてるようなベースのプレイもユニークである。
ちょっと普通ではない、奇妙なものが好きな方には、お薦め。
ギタリストに関しては、二匹目ドジョウを狙った VIRGIN の気持も分からないではないが、オールドフィールドよりもアンソニー・フィリップスあたりを抜擢していただきたかった気もする。
(LRLP 219 / LRCD 219)

| Pekka Pohjola | bass |
| Vesa Aaltonen | drums |
| Olli Ahvenlahti | keyboards |
| Seppo Tyni | guitars |
79 年発表の「The Group」。
新グループ「THE GROUP」名義の作品。
当時のメインストリームであるフュージョン・サウンドと、ペッカ流の愛くるしいメロディがいいポイントにて出会った佳作である。
サウンドはあくまで爽快で手ざわりがよく、演奏そのものはきわめてテクニカルで精緻、そして小気味がいい。
ゆったりリラックスしながらも、必要十分な音がしっかり連携した緊張感とシャキッっとした歯切れよさがあるのだ。
特にギタリストは、端正にしてエモーショナルなプレイが光る逸材だ。
ドラムスも音数に頼らない切れがある。
もちろん、ベースは、自由自在なペースで歌いまくり、決めどころでは鮮やかな快走を見せる。
全体に、ひとさまに聴いてもらうならこれくらいは当たり前でしょ、という表情がニクらしくもみごとである。
自己満足専門のシンフォニック・ロック・バンドは、爪の垢を煎じて飲んでください。
「Urban Tango」の原点はここ。
全曲インストゥルメンタル。
作曲は、ペッカとオーヴェンラティ。
プロデュースは、グループとトム・ヴオリ。
バンドとしてのペッカ・サウンドを聴きたいときには、本作が最もお薦めでしょう。
しかしながら、個人的には、これがいいとなると他のフュージョンもかなりほめなくてはならない。(苦笑)
「Thai」(5:15)ほんのり東洋風のテーマを巡る本作の明快なるイントロダクション。しなやかなギターが心地よい。
「Ripple Marks」(10:00)メローな展開に変拍子のテーマがアクセントする大作。
豊かな音色のピアノ伴奏で、華麗なるギター・ソロからベース・ソロへと進む。
ギターがフュージョン然とせずロック・スピリットあふれるプレイなのが好感大。
「Berenice's Hair」(5:20)当時の流行のニューエイジ・ミュージック風味もあるフュージョン。リラックスしているようで不思議なテンションがある。
「Gado-Gado」(6:50)ややハードなタッチのジャズロック。それでもテーマの愛らしさは変わらず。
「Annapurna」(11:36)メインストリームで流行ったフュージョン的な音使いながら、不思議な浮遊感と重厚さがある傑作。
終盤に鮮やかな "リード・ベース" もあり。
ペッカ氏は音で世界を描ける稀有の人物なのでしょう。
終盤のシンセサイザーもいい音だ。
(DIGLP 1 / WARNER 8573-87580-2)

| Pekka Pohjola | piano, bass | Vesa Aaltonen | drums |
| Eero Koivistoinen | sax | Junnu Aaltonen | sax |
| Teemu Salminen | sax | Pekka Poyry | sax |
| Olli Ahvenlahti | electric piano, bass | Seppo Tyni | guitar |
| Esko Rosnell | percussion | Tom Bildo | tuba,trombone |
| Aale Lindgren | oboe | Markku Johansson | trumpet |
79 年発表の第四作「Visitation」。
バンドとしての一体感はさらに発展、ホーン・セクションやオーケストラの導入によって厚みと迫力が増した好作品である。
全体的に、前作のナイーヴなファンタジーという趣よりも、ロック、ジャズ的なダイナミックさが顕著になっている。
音楽は、切れ味鋭いジャズロックからシンフォニックな作品、そしてユーモラスなトラッド調まで幅広い。
あの人懐こいメロディは全編に散りばめられている。
ベース、ピアノのプレイから作曲まで、何でもこいの絶好調である。
THE GROUP のメンバーが、全員参加。
本作までは、シンセサイザーは用いずに生の管絃のサポートを得ている。
全編インストゥルメンタル。
「Strange Awakening」(5:09)
謎めいたテーマを優美なワルツのリズムが支える代表作。
きらめくピアノによる提示から管楽器による変奏まで、一貫してこのテーマを反復する。
流れるように優雅な管楽器セクションは、レーベル・メイトのイイロ・コイヴィストイネン、ヤンヌ・オールトネン、ティム・サルミネン、そして名手ペッカ・ポイリ。
ポイリはソプラノ・ソロもフィーチュアする。
終盤では、テーマ演奏の裏で、闊達なベース・ソロも披露する。
わりと粘っこい演奏を、テーマのよさで、すっきりとした口当たりに仕上げている。
「Vapour Trails」(4:41)
ギターがリードするハード・フュージョン・ナンバー。
名手セッポ・タイニの流麗かつ暖かみあるフュージョン・ギターと、ポイリの西海岸風のサックス(デヴィッド・サンボーン辺りか)がじつに爽やかだ。
ここでも、後半に鮮やかなサックス・ソロがある。
リズム・セクションも、かなり技巧的な感じである。
ベース、ドラムスともに手数が多く、軽やかというよりは適度な重みがあり、キレもいい。
全体を通した重くコシのある調子は、音を詰め込んだメイン・リフのせいだろう。
THE GROUP の実力を見せつける作品といえそうです。
「Image Of A Passing Smile」(5:36)
木管とチェロが朗々と歌うクラシカルなパートから、ルーラルでにぎやかな演奏へ変化する作品。
テーマを演奏する木管とチェロの音色が哀愁を帯びているにもかかわらず、演奏そのものには交響曲調の不思議なパワーがある。
THE GROUP 組の演奏は、他の曲同様どこまでもしなやかで、タフなうねりをもっている。
後半、ハンドクラップも巻き込んだリズミカルなお祭り風の演奏に変化した後は、ギターとサックスを活かしたジャジーでユーモラスな演奏が続く。
この間奏部分の後半では、フランジしたベースがテクニカルなプレイを何気なく披露している。
シンフォニックな作風といえるでしょう。
「Dancing In The Dark」(5:35)
パーカッションを活かしたユーモラスだがパワフルにグラインドするビートの上で、西海岸フュージョン風の管楽器セクションが爽やかに舞うジャズロック。
WIGWAM に通じるユーモア感覚は、ファンキーというのともまた違う、独特の児戯めいた作風である。
その影響は主流ジャズ風の管楽器セクションや管楽器ソロにも現れ、ジャジーなフレーズからふらふらっと逸脱し始める。
他の曲同様に演奏にあふれるパワーの源は、後半でソロを披露するベースと遠慮なくハードロック風に迫るギターである。
普通ならギターが決めそうなオブリガートをベースがカッコよく決めている。
中盤のトランペットのソロが新鮮。
「The Sighting」(3:30)
「Try To Remember」(7:08)
フュージョンやクラシック風の演奏に、管弦楽にて厚みをつけた傑作。
緻密なアンサンブルを張り巡らせた作品もリラックスしてプレイに徹したような作品も、それぞれに味わいがある。
そしてどの曲にも共通するのは、優しくて簡単に口ずさめるのにも関わらずどこかひやりとする怖さをもった、童謡のような旋律である。
アルバム全体にうっすらと漂う幻想的なムードは、このテーマに因るところ大である。
もちろんナチュラルな音色によるベース・プレイの気持ちよさも格別。
フュージョン風の曲でもパッションよりもファンタジックな優しさを感じさせるところがうれしい。
(DIGLP 4 / 220222)

| Pekka Pohjola | bass |
| Ippe Kätkä | drums |
| Pekka Tyni | keyboards |
| Seppo Tyni | guitars |
80 年発表の「Kätkävaaran Lohikäärme」。
メンバーを若干変更した「PEKKA POHJOLA GROUP」の作品。
内容は、世間のノリとはあまり関係のない、ペッカらしさ全開のジャズロック。
メロディ・ラインがほのかにユーモラスなのであまり意識に上らないが、このリズムとフレーズのキレはただごとではない。
スタジオ盤だがライヴ盤に近い性格のアルバムであり、昔のジャズの録音のようにワンテイクで済ませたような勢いがある。
効果を緻密に計算したような作曲ではあるが、基本的には、プレイヤーが伸び伸びと楽しげに演奏している感がある。
3 曲目「Sampoliini」はメインストリームのフュージョンを茶化して「倍速/倍密で軽くまとめて見ました」といわんばかりの痛快作。
4 曲目「Inke Jamä」は傑作。(Inke はこの頃の奥様の名前のようだ)
ミステリアスなタッチのスリリングな演奏を意外にホンワカと楽しめる稀有なジャズロック・アルバムである。
ペッカによるのかどうか分からないが、ドラムスのアレンジが凝っている。
「Kätkävaaran Lohikäärme」(14:33)ミニマルでマジカルな作品。
エキゾティックな第一テーマ、ドラムスが地鳴る第二テーマが独特。
中盤でアグレッシヴなギター・ソロを大きくフィーチュア。
謎めいた感じととりつくしまがない感じが、SOFT MACHINE 的。
「Tehdasmusiikkia」(7:34)ラウンジ・ジャズのような、お囃子のような、でもへヴィ・ロックでもあるペッカらしい作品。
パリの高級ブティックの大きなショウ・ウィンドウを叩き壊して粉々にするような、ガツンと荒々しい音でアクセントする技が冴える。伸びやかなギターを映えさせるアレンジのみごとさ。
「Sampoliini」(12:08)セポ・タイニ作曲。ベースが大活躍。このベースと渡り合うには、このギターでないと。
「Inke Ja Mä」(9:53)ふくよかでどこか哀しげなテーマがいい名曲。終盤、緊迫感が高まり、謎めいた表情で去る。
(DIGLP 12 / 4509-96415-2)

| Pekka Pohjola | bass, keyboards |
| Peter Lerche | guitar, mandolin (solo on 3) |
| T.T. Oksala | Roland synth guitar(solo on 1) |
| Leevi Leppänan | drums |
| Jussi Liski | keyboards |
| guest: | |
|---|---|
| Kassu Halonen | vocals on 4 |
| Esa Kaartamo | vocals on 5 |
82 年発表のアルバム「Urban Tango」。
自身のレーベル立ち上げ後、初の作品。
メンバーも一新している。
フュージョン、ニューエイジなど 80 年代メイン・ストリームのポピュラー音楽を意識させるも、よく聴けば、やはりそのどちらでもないスリルとユーモアをもつ不思議の音楽である。
時として、ハードロックのようなパワーを感じさせる演奏すらある。
一番近いのは、ジャズのビッグバンドだろうか。
ロックとジャズとクラシックの素養が結びつき、独自の洗練を経て、生み出された音なのだろう。
平易なテーマ、明快なリズム、クリアーな音色によるちょっと見にはシンプルな曲想が、聴く毎に深みを増してゆく。
ゆったりとしたシンセサイザー・オーケストレーションとしなやかなリズムはひたすら心地いい。
そしてギターや管楽器風のシンセサイザーによる歌は、きらきらとしながらもどこまでも優しくおどけている。
やはりこの人は小人を飼っていて、その魔法で曲を編みだしているにちがいない。
歩み続ける力はロック、精密に織り上げられたアンサンブルはジャズ、親しみやすいメロディはクラシックから授かった、天才からのすてきな贈り物といえるアルバムだ。
いわゆるジャズロック的なサウンドからは一歩踏み出でてすでに孤高の境地を見せつけている。
それにしても、フィンランドでもタンゴは流行したのだろうか。
クレジットによれば、本作から生の管絃に代わってシンセサイザーが用いられているようだ。
(もっとも、どうしても生のサックスやストリングス類に聴こえるが...)
4 曲目とボーナス・トラックをのぞきインストゥルメンタル。
ヴォーカルは英語。
パット・メセニー・グループのファンの方へもお薦め。
「Imppu's Tango」(9:22)サックス風のユーモラスなテーマと力強いリズムが特徴の「タンゴ」。
ギターを軸とした演奏が、なかなかヘヴィでカッコいい。
マンドリン(まさかこれがギター・シンセサイザー?)が効果的。
「New Impressionist」(15:20)
リズミカルなギターとシンセサイザーによるテーマを、オーケストラ/ビッグ・バンド風の演奏が取り巻くファンタジックな大作。
明るくユーモラスでいて、どこか暗がりのようなうす寒さをもつところが、ペッカらしい。
アンサンブルに隠れているが、すさまじいベース速弾きもあり。
キャッチーなアンサンブル/シーケンスが次々と現れる。
ギターの音など、マイク・オールドフィールドが垣間見えるところも、いまだ若干あり。
6 分 20 秒あたりで、一度クライマックス。
その後の歌うようなベース・ソロがカッコいい。
かなり流行ったフランジャー系のエフェクトを用いたフレットレス。
終盤はテーマが再現し、ビッグ・バンド風に盛り上がる。
「Heavy Jazz」(10:46)どうしてもサックスに聴こえるテーマとレスポンスするヘヴィなギター、ベース、弦楽器。
繰り返しでは役者が交代、ギターがテーマで管楽器がレスポンスし、やがてユニゾンのメロディアスな流れとなってゆく。
テーマはジャジーでほんのりユーモラス。
ギターやリズムなど、かなりヘヴィな音が用いられている。
管絃も唸りを上げて高鳴る。
「生」オーケストラ・ヒットも決まってます。
中盤のメローなギター・ソロ(まさかこれがマンドリン?)から、ややハードなエレキギターのソロへ。
タイトル通りのヘヴィなビッグ・バンド・ジャズ。
ギターがフィーチュアされている。
「Urban Caravan」(11:46)けだるいギターとソウルフルなヴォーカルが印象的な歌ものビッグ・バンド。
メイン・ヴォーカルに続くギター・ソロの後半が、ギター・シンセサイザーのような気がします。
やはりギターを軸に、ビッグ・バンド風に大いに盛り上がる。
リズミカルにたたみかける演奏とメロディアスなヴォーカルが、心地よいコントラストをなす。
7 分半あたりからの演奏は、流行のハードポップのパロディのよう。
「Silent Decade」(4:13)ボーナス・トラック。
アコースティック・ギター、ピアノ、ストリングスらの伴奏によるメランコリックなバラード。
弦楽器が美しい。
やはりクレジットは、意図的なお遊び(もしくは皮肉)のような気がするのですけど....
(PELP 1 / PELPCD1)
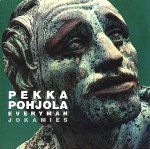
| Pekka Pohjola | bass, synthesizer |
| Peter Lerche | guitars |
| Jussi Liski | piano, synthesizer |
| Keimo Hirvonen | drums |
| Timo Versajoki | synthesizers |
| guest: | |
|---|---|
| T.T. Oksala | synthesizer programming |
| Kassu Halonen | vocals on 10 |
| The Chamber Choir Of Suomen Laulu | on 6, 10 |
83 年発表の「Every Man(Jokamies)」。
テレビ番組の中世劇用サウンド・トラックとして製作されたようだ。そのため、クラシカルで重厚な曲想が基調になっている。
中心となるのはキーボード主体の荘厳で厚みのあるインストゥルメンタルだが、それだけにとどまらず、上品なロマンチシズムが魅力のブルーズ・ロックや躍動的なジャズロックも交えて楽しませてくれる。
そして、チャーチ・オルガン風のシンセサイザーが轟々と高鳴る厳かな作品にも、ヒューマンな暖かみとごくパーソナルな哀感、オプティミスティックな軽やかさがごくナチュラルに織り込まれている。
法悦と無常の旅立ちに際しても決して微笑を忘れない、そういう感じである。
これこそがペッカの作風であり、魅力だ。
世に数いる「やたらと手の動くだけのキーボーディスト」たちがこういう音楽を手本にできるのはいつの日か。
コラールと最終曲以外は、全編インストゥルメンタル。
「Velka(Debt)」(0:45)
「Velkavanki(Goal)」(3:11)
「Blues Vernerille(Blues For Verneri)」(3:45) エリック・クラプトン風の名曲。
「Kuolema ?(Death ?)」(5:14)厳かなキーボード・オーケストレーション。悲劇的な重さから次第に開放されて、人知を越えた 抽象的な世界に入ってゆく。
「Toivo(Hope)」(2:32)希望だが、死に比べると、はるかにか細い。どちらかというと、故人の思い出を湛える感じである。
「Koraali(Coral)」(3:16)送り出される感じです。
「Kuristus(Strangling)」(5:00)重苦しいキーボード・サウンドながらもペッカらしさ全開の佳作。
「Umpikuja(No Way Out)」(7:23)スリリングなキーボード・アンサンブルを主役にしたジャズロック・チューン。「リード・ベース」も活躍。クラシカルな厳しさとグルーヴの巧妙なバランス。傑作。
「Rankkaus-Vapautus(Relief)」(2:50)
「Agnus Dei」(3:28)絶唱と聖歌が交錯する劇的なエンディング。
(PELP 2 / PELPCD2)

| Pekka Pohjola | bass, keyboards |
| Seppo Tyni | guitars |
| Keimo Hirvonen | drums |
| Jussi Liski | piano, synthesizer |
| Timo Versajoki | keyboards |
85 年発表の「Space Waltz」。
内容は、明快にしてクラシカル、そして躍動感あふれるフュージョン・インストゥルメンタル。
いかにも 80 年代らしい音色のデジタル・シンセサイザーを駆使し、明快なテーマを巡って、悠々と音を綴ってゆく名曲揃いのアルバムである。
巷間にぎわす「フュージョン」と共通するサウンドながら、その印象が決定的に異なるのは、子供のようにピュアで研ぎ澄まされた視線と音の清潔感、そしてユーモアで包まれたブルージーな重みがあるせいだろう。
本作の作風は、「Keesojen Lehto」から綿々と続く少年の潔癖さを持つと同時に、現在の作風の原点にもなっているようだ。
充実したキーボード・サウンドに加えて、ギタリストとして元 THE GROUP の名手セッポ・タイニが復帰して、みごとなプレイを披露している。
全曲インストゥルメンタル。
「American Carousel」(6:17)
明るくユーモラスな調子の名曲。
金管楽器をイメージさせる華やかなシンセサイザーのテーマと粘っこいギターをフィーチュア。
溌剌としたメジャー・コードのテーマを受けて、いきなり半音下がったフレーズが歌い出すという意外な展開だが、それすらもごく自然に聞こえる。
子供が駄々をこねているようなギターを、ゆりかごのようなベース・ラインが支えている。
半音進行のフレーズは、WIGWAM 時代からの得意技。
「Cat Boulevard」(3:45) WIGWAM の「P.K.'s Supermarket」の翻案である、ひねくれた感じの作品。
クラヴィネットのようにややパーカッシヴなエレピ、管楽器調およびメタリックなタッチのシンセサイザーらによる、どことなく謎めいたスローな 8 ビートのキーボード・アンサンブル。
3 拍子によるギターのブリッジが意表を突く。
ベース・ラインもよく聞える。
「Space Waltz」(8:08)
ギターとキーボードが抜群のコンビネーションを見せるリズミカルな名品。
ユーモラスでチャイルディッシュな「遊園地」スタイルのワルツである。
1 拍だけ余分なテーマのせいで奇妙な揺れがある。
中盤からの愛らしくも多彩なサウンドによるシンセサイザーのソロがすばらしい。
暖かみや素直な叙情性よりも諧謔味が強いところが違いますが、軽やかな運動性と親しみやすさという点で CAMEL や FOCUS に通じる作品です。
「Risto」(13:40)
あまりに優しげなテーマから、コーラス系エフェクトをうまく使ったヘヴィなリフ、アコースティック/エレクトリックな泣きのソロまで、ギターの魅力が大いに発揮された大作。
ギターに応じるメランコリックなベースのオブリガート、ソロもカッコいい。
「Changing Waters」(6:05) ストリングス系キーボード、ピアノを中心とした重厚な作品。前作「Everyman」に通じる作風である。終盤に向け、救済の光が見えてくる。
確かに光を受けてきらきらと変化する水の流れのようなイメージが浮かぶ。
往く川の流れは絶えずして云々、みたいな人生観的含みもあるんでしょうか。
和音のせいか、クラシカルな重厚さの間にジャズ・タッチも見える。
(PELP 3 / PELPCD3)

| Pekka Pohjola | bass | ||
| Seppo Tyni | guitars | ||
| Timo Versajoki | keyboards | ||
| Jussi Liski | keyboards | ||
| Keimo Hirvonen | drums | ||
| guest: | |||
|---|---|---|---|
| Lisa Pohjola | piano on 3 | Jaakko Ilves | violin |
| Jaako Vuornos | violin | Mikko Pohjola | viola |
| Heljä El-Herraoui | cello | Pentti Lahti | alto sax |
| Simo Salminen | trumpet |
86 年発表の作品「Flight Of The Angel」。
内容は、バンドに弦楽、サックス、トランペットらの小オーケストラを加えた編成によるキュートなインストゥルメンタル・ミュージック。
シンプルなのに味のあるメロディを溌剌としたリズムにのせて送り出しているが、これまでの作品同様、そこに独特の「長調の挽歌」と形容したらいいような独特の調子がある。
デジタルな人力、
この感じこそがペッカの作風といえそうだ。
どちらかといえば、曲作りよりも演奏そのものに力の入った作品になっていると思う。
名手セッポ・タイニやドラマーに負うところも大きそうだ。
1 曲目のジャズ・ロックンロールの開放的な感じは、JUKKA TOLONEN のソロ作にも通じるものである。
全編インストゥルメンタル。
ポーヨラという名字のメンバーが二人クレジットされているところから想像するに、一家総出のアルバム製作なのだろう。
「How About Today」(5:35)粘っこいギターがカッコいいブギー調のジャズロック。快調。
「Flight Of The Angel」(6:25)シンプルで愛らしいテーマを巡る美しい作品。
ゆったりとした動きを基調にテーマに対してキーボードやギター、弦楽奏のさまざまな旋律が立体的に交差してうねりを成す。
純潔で溌剌としながらもほのかに哀しげでありミステリアス。トラッド・ミュージックの特性をうまく織り込んでいる。
「Il Carillion」(6:46)ピアノ独奏。
「Pressure」(10:36)単純な音形をテーマをデジタル・タッチのビートで支えて独特の緊張感を生む。
ロックのようでクラシカル。強いて類似をいえばやはりマイク・オールドフィールド。
後半のハードなギター・ソロが際立つ。
「Beauty And The Beast」(10:54)ベースによるテーマが印象的な稀代の名品。
憂愁や官能や希望といった人間の営みに必ず現れる「状態」を音で現すことのできた数少ない音楽作品の一つである。
ペッカの本質がほぼ完全にフュージョン・ミュージックやニューエイジ・ミュージックに仮託されて認識できる形で外に出てきているといってもいい。
ブラス・セクションをフィーチュア。
(PELP 4 / PELPCD4)

| Pekka Pohjola | bass, electric drum fill & bass synthesizer on 4, 1st piano theme on 6 |
| Seppo Kantonen | keyboards |
| Markku Kanerva | guitars |
| Ansi Nykänen | drums on 4,5,6,7 |
| Markku Ounaskari | drums on 1,2 |
| Jukka Pohjola | 1st violin, violin solo on 6 |
| Susanne Helasvuo | 2nd violin |
| Teemu Kupiainen | viola |
| Matti Pohjola | cello |
| Teemu Salminen | clarinet on 2,4, flute on 4 |
92 年発表の作品「Changing Waters」。
内容は、薄暗い夢をなぞるように内省的で繊細、なおかつ透明感のあるフリー・ミュージック。
手折れそうなデリカシーと現代的な苦悩とほのかなユーモア、フォーク的な憂愁と逞しさが一つになってクラシカルな表象を取って現れた作品である。
編成は、前作同様バンドと管弦(メンバーはペッカ以外全員交代)。
ただし、金管がないためか、力強さよりも女性的なしなやかさが感じられる。
アコースティックな音への傾倒、初期作品の愛らしさへの回帰なども特徴。
ジャズロック的な面はほぼなくなり、いよいよ独自のクラシック・ミュージックの創生へと向かっている印象である。
また、余人のうかがい知らぬ苦悩を抱えているようにも思います。
全編インストゥルメンタル。
タイトル曲は「Space Waltz」にも収録された作品。
「Benjamin (Introduction)」(7:48)ピアノ、ベースが静かにリードする厳かな作品。
安っぽいヒーリング・ミュージック、ニューエイジっぽさは微塵もなく、ブルージーなジャズを感じる。
「Waltz For Ilkka (Ilkan Valssi)」(4:38)得意の「ネジの外れた挽歌」というべきワルツ。哀愁がナンセンスへと昇華する。ギターがいい。終盤の慈しみに酔う。愛らしすぎるエピローグ。
「Innocent Questions」(6:06)調を外れて抽象的な文様を描くアコースティック・ギター、ピアノ。次元の壁の向こうへ消えたり戻ったり、戻れば悲しい調べになる。不安の予兆のような第二楽章。
「Fanatic Answers」(10:02)追いすがる不安を振り切るようにギターのリードで力強く歩むシンフォニック・チューン。白黒映画のインサートのようなメロトロン、弦楽。
「Changing Waters」(6:29)ピアノの呪文がバンドを召還し、暗黒の伽藍をともに鐘を打ち鳴らしながら進む、暗鬱と純情が交ざりあった傑作。
「Waltz For Outi (Outin Valssi)」(7:11)「ネジの外れた挽歌」というべきワルツ第二番。どこかで耳にした曲がモチーフに現れる。 ヨーロッパ映画のように、ウィーンの公園のメリーゴーラウンドのように、洒落たタッチも。
「Benjamin」(9:16)
(PELPCD5)

| Pekka Pohjola | bass, keyboards on 5 | ||
| Seppo Kantonen | piano, keyboards | ||
| Markku Kanerva | guitars | ||
| Anssi Nykänen | drums, percussion on 7 | ||
| Mongo Aaltonen | percussion on 2,8 | ||
| Jari Valo | violin on 8 | Jukka Pohjola | violin on 8 |
| Teemu Kupiainen | viola on 8 | Olli Kilpio | viola on 8 |
| Timo Alanen | cello on 8 | Matti Pohjola | cello on 8 |
97 年発表の作品「Pewit」。
内容は、シンプルなテーマをクラシカルなアンサンブルが守り立てる、優しく暖かいニューエイジ・ミュージック。
ジャズ、クラシック、ロックといったさまざまな音楽的体験に基づいて、作曲者が熟成に熟成を重ねてできてきた、カラフルな絵巻物のような音楽である。
ジャンル分けは空しく、ひたすらにユニークな音を味わい素直に耳を傾けるのが一番である。
最終曲のみ、リズムを強調したシリアスな現代音楽になっていて他の作品と一線を画す。。
80 年代の作品と比べるとロック、フュージョン的な躍動感は引っ込み、反復とその展開を主に、溌剌としながらも落ちつきと均衡を目指しているような作風である。
安定したミドル・テンポが主であり、リズム、ビートにロックっぽいグルーヴが少ない。(あえてオールド・ポップス調で迫るところはある)
白の魔女のまじないのようなフレーズを真っ直ぐなビートでアクセントをつけながら延々と遠くへ運んでゆくような演奏であり、どちらかといえば、室内楽的な表現である。
もっと正確にいうと、60 年代あたりのクラシックをアレンジに取り入れたポップスに通じる表現だと思う。
独特のヒヤリとするようなタッチはほとんどないが、明朗なようでどこかに憂い、ペーソスをたたえた表情は健在であり、やはりそこが魅力だ。
あたかも、永遠に続く森の神々の春の祭典を彩る気まぐれな妖精たちのオーケストラのようである。
アコースティック・ピアノの存在感大。全曲インストゥルメンタル。
「Rita」(11:23)タイトルはジャケットアートを描いた女性の名前。
「Melkein」(13:47)
「Pewit」(6:17)
「Suuri Kallion Ritari Intro」(3:41)
「Suuri Kallion Ritari」(2:37)
「Toy Rock Intro」(00:40)
「Toy Rock」(4:17)
「Ordinary Music」(19:20)
(PELPCD8)
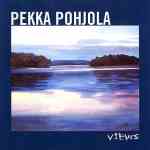
| Pekka Pohjola | bass, keyboards | Seppo Kantonen | piano, keyboards | Markku Kanerva | guitars on 2 |
| Mika Kallio | drums on 3,4,5 | Rhino Laine | drums on 3 | Anssi Nykänen | drums on 2, fills on 3,5 |
| Tapio "Mongo" Aaltonen | percussion | Jukka Perko | alto sax on 3,4,5, solo on 3 | Penti Lahti | alto & baritone sax on 3,5 |
| Manuel Dunkel | tenor sax on 3,5 | Tapani Rinne | soprano sax on 1 | Teemu Salminen | flute on 2,4 |
| Teemu Matsson | trumpet on 2,3,4,5 | Verneri Pohjola | trumpet on 2,3,4,5 | Markku Veijonsuo | trombone on 2,3,4,5 |
| Ilmari Pohjola | trombone on 2,3,4,5 | Jari Valo | 1st violin | Jukka Pohjola | 2nd violin |
| Teemu Kupiainen | viola | Timo Alanen | cello on 2,3,4,5 | Tomas Djupsjöbacka | cello on 1 |
| Laura Hynninen | harp on 1,2 | Sami Saari | vocals on 2 | Kim Lönnholm | vocals on 2 |
| Pemo Ojala | vocals on 2 |
2001 年発表の作品「Views」。最終作。
クラシックでありジャズでありロックである心温まる管弦楽調フリーミュージック集である。
喜怒哀楽なんていう言葉では容易にあらわし切れない人の心持の、ふらふらとした微妙なバランスに寄り添える音というか、音そのものが自律する生き物のように思えてくる。
それは一種の魔法である。
「Grand Wazoo」のファンにはお薦め。
洒落の効いた 2 曲目以外はインストゥルメンタル。
誰にも生み出せない音を残して旅立った。ザッパ先生が涅槃で待つ、はず。
「Waves」(6:56)管弦楽作品。ハープとソプラノ・サックスをフィーチュア。
「The Red Porche」(5:00)コミカルな歌ものロックなのに抜群の安定感があり、クラシカルなアレンジが冴える。歌詞はブコウスキの「赤いポルシェ」より。デヴィッド・ボウイのような一流のデカダンス、諧謔のある英国ロック風の作品。
アルバムアートを手がけるリタさんに捧ぐ作品らしい。別々に収録したトラックをまとめた苦労のためか、珍しくミキシング・エンジニアにも謝辞がある。
「Metropolitan」(14:05)ザッパ風の開放感と郷愁のあるビッグ・バンド・ジャズロック。胸元に刃を差し込まれたようにヒヤッとするシリアスな場面の切換えが独特だ。いつの間にかロマンティックなピアノ・コンボへ。
「Views」(7:34)非常に美しく愛らしい管弦、バンドの合奏曲。中盤の慈しむようなベース・ソロが印象的。
「Us」(11:32)ユーモラスで気難しく、開放的で内省的でなおかつ逸脱調という、ザッパ先生と同じ道を歩んだペッカ流ビッグバンド・ジャズロック。
嗚呼、この「やさしさ」と「変さ」哉。シンセサイザーとベースのやり取りは、遥か深宇宙との通信か。
(PELPCD 12)
