
| Darryl Way | violin, viola, keyboards |
| Dek Messecar | bass, vocals |
| John Etheridge | guitar |
| Ian Mosley | drums |
| guest: | |
|---|---|
| Ian McDonald | tambourines, piano on 6 |
イギリスのプログレッシヴ・ロック・グループ「WOLF」。 73 年、CURVED AIR 脱退後のダリル・ウェイらによって結成。 ヴァイオリンをフィーチュアしたサウンドで、三枚のアルバムを残す。 グループ解散後、ウェイは CURVED AIR に復帰、その後ソロ活動へ。 ジョン・エサリッジは、後期の SOFT MACHINE でプレイするテクニシャン。 イアン・モズレイは、オランダの TRACE を経て MARILLION へ。 デック・メセカーは、CARAVAN に参加。 オリジナル・アルバムの他には、アンソロジー(London PS 644 / King GP-1008)と、アルバム未収曲を含むシングル(Deram DM 378/395/401)三枚。

| Darryl Way | violin, viola, keyboards |
| Dek Messecar | bass, vocals |
| John Etheridge | guitar |
| Ian Mosley | drums |
| guest: | |
|---|---|
| Ian McDonald | tambourines, piano on 6 |
73 年発表の第一作「Canis-Lupus」。
ブルーズ調からアコースティックなナンバーまで、ヴァイオリンとギターをフィーチュアした多彩な曲調を貫くのは、ふんわりとしたファンタジー性だろう。
大まかにいって、前半はエサリッジのギターが冴える一方で、ヴァイオリンはアンサンブルの一員に収まっており、後半でようやく艶やかなヴァイオリンが最高潮に達するようだ。
ややおとなしめのヴォーカルが歌うナンバーでは、エサリッジの華麗なギター・プレイと堅実なアンサンブルが聴きもの。
軽快なオブリガートからエモーショナルなアコースティック・ギターまで、ジャジーな香りも漂わせつつテクニシャン振りを発揮している。
もちろん、絶妙の色艶をもつヴァイオリンも、渋めの演奏に華やかさと豊かな情感を加えている。
リズム・セクションやギターのダイナミックさと、ヴァイオリンやヴォーカルの繊細さが一体となって、比較的シンプルな曲想を、豊かで想像力を刺激するものに仕立てているようだ。
やはり英国風の音である。
プロデュースはイアン・マクドナルド。
1 曲目「The Void」(4:37)エレピが小さな音でリフレイン、ベース、ギターのグリッサンド、そしてドラムスと次々入って、ピアノがコードを叩くと一気に盛り上る。
しかし、続くヴォーカルは無表情を装う。
ギターのオブリガートは、ディレイ効果で実ににぎやかだ。
ハイハットを鋭く刻むドラムスもカッコいい。
一転テンポが落ち、ピアノの鮮やかなグリッサンドが一閃。
そして、サビはピアノのおだやかな伴奏によるファンタジックなムードである。
ヴォーカルは、起伏の少ない不思議なメロディを歌う。
ピアノとギターがユニゾンする悩ましい間奏。
ヴォーカルを追いかけるコーラス。
再びピアノのコードとともに、激しく細かいリズムが戻りメイン・ヴァースへ。
そしてギターのオブリガート。
演奏は次第に熱気を帯びるが、ヴォーカルは空ろな表情のまま。
フェード・アウト。
空ろなヴォーカルと躍動感あるリズム、シャープなギターがコントラストする不思議な雰囲気のナンバー。
リズム・セクションには、ジャズロック的な精密があるのだが、ギターとヴォーカルがふわふわと夢見がち。
それでも、細かく刻むリズムに合わせたようなギターのオブリガートは鮮烈だ。
中間部は、ピアノが静かに流れてさらに夢見心地。
ぼんやりした曲調だけに、ドラムスのフィルがとても気持ちいい。
ウェイはピアノに専念。
ウェイの作品。
2 曲目「Isolation Waltz」(4:41)ヘヴィで眠たげに下降するベース・ライン。
ブルージーだ。
リズムが入り歌い出すヴォーカルもブルー。
そしてギターとヴァイオリンは後拍ノリのヘヴィな上昇リフをユニゾンで繰り返す。
行きつ戻りつを繰り返して、遂に、スケールを駆け上がると、一気に華麗なヴァイオリン・ソロだ。
目の醒めるような音。
伴奏はかなりハードだが、ヴァイオリンの抜けのよい音が、演奏に飛ぶような軽快さを加えてゆく。
重いリズムと熱っぽいヴァイオリンのリフレインの対比。
次第に白熱するアンサンブルは、ユニゾンのクライマックスを経て、再びヴォーカル・パートへ。
引き摺るようなブルージーな演奏が、最後はビシッと決めて終わる。
ヘヴィなリフでドライヴするブルージーなロックンロール。
ブルーズなのに、泥臭さよりもメランコリックな若さがあるところが、英国のセンスである。
中間部をリードするヴァイオリンは、目の醒めるような鮮やかな音なのだが、こういう重たい曲の中ではやや居心地が悪そうだ。
フィドルというには、どっしりとした風格がありすぎるのかもしれない。
それにしても 4 拍子なのになぜワルツなんだろう?
ウェイ/メセカーの作品。
3 曲目「Go Down」(4:44)リリカルなギターとエレピのイントロから、優しげなヴォーカルが歌い出す。
なんと可愛いメロディだろう。
高音に伸びるところが、とてもフォークっぽい。
エレピに導かれて、鮮やかなアコースティック・ギターのソロが始まる。
高音を美しく響かせ、ビジーなパッセージでスリリングに盛り上げるソロである。
バックのコード・カッティングはオーヴァー・ダビング?。
ドラムスの軽やかなロールから、再びフォーク調のヴォーカル・パートへ。
エレピの伴奏も夢見るような穏やかさだ。
エレピのグリッサンドから、再びアコースティック・ギター・ソロへ。
最後はトレモロを響かせて終る。
胸キュンの青春フォーク・ソング。
頼りなげなヴォーカルがドリーミーな甘い曲調にピッタリだ。
サビがなんとも切ない。
一方、間奏のアコースティック・ギター・ソロは、メロディアスなプレイにもかかわらず、甘ったるい調子に一気に緊張感をもたらす。
グリッサンドしながらの速弾きやトレモロなど、ジャンゴ・ラインハルト直系のハイテク・ジプシー・ギターである。
バッキングがエレピのせいか、すっかりジャズ風の演奏となる。
これも一つのジャズとフォークの邂逅である。
ウェイ/メセカーの作品。
4 曲目「Wolf」(4:09)シンセサイザーによる高らかなファンファーレのようなメロディが、やや神経質に繰返されるオープニング。
少しミステリアスな空気である。
ギターもハモる。
そして始まるヴォーカルは、またも沈み込み気味。
ファルセットも使う歌メロはやや 60 年代ビートポップ風。
ブルージーなムードから、小気味いいドラム・パターンと歯切れよいギターのコード・カッティングによって、次第に緊張感が高まってゆく。
THE BEATLES 風でもある。
そして飛び出すヴァイオリン。
スリリングなメロディからメジャーに転調、軽やかなフレージングを見せつける。
ギターのパワー・コードが鳴らされ、オープニングのシンセサイザーが叫ぶと、再びヴォーカル・パートへ。
シンセサイザー、ギターとともにゆっくり上昇するアンサンブル。
再び鮮やかなヴァイオリンの決めのリフレイン、そしてギターが華麗な速弾きで突っ走る。
フェード・アウト。
シンセサイザーが使われるミステリアスでややヘヴィなナンバー。
切なく甘目で翳のある歌メロは、正に英国伝統もの。
次第に演奏がエキサイトして満を持してヴァイオリンが出てくる。
みごとな演出だ。
最後のギター・ソロは、我慢の限界を越えたような凄まじい勢いで迫る。
ソロはともかく、もう少しヴァイオリンとギターの絡みがあってもよかったのではないだろうか。
オープニングのタメの効いたロールなどドラムスのプレイは実に多彩。
ウェイ/メセカーの作品。
5 曲目「Cadanza」(4:52)いきなり、ヴァイオリンがぶっ飛ばしシンセサイザーが叫ぶオープニング。
文字通りヴァイオリンのカデンツァである。
ヴァイオリンはパガニーニ風の華麗なフレーズをスピーディに繰り返し、螺旋を描くように音程を上下する。
リズムが入ってチェンバロ、ギターのハードな演奏を経て、エサリッジの超絶ギター・ソロ。
華麗に舞い踊るジャジーなソロである。
ギター・ソロのバックでは、決めを連発し、再びドラムスが走り出す。
続いて、ドラムレス、ギターによる鮮やかなコード・カッティングのソロ。
再びシンセサイザーが金切り声を上げ、アンサンブルが走る。
そして決めの連発からベース・ソロ。
激しくアクセントするドラムス。
ピアノとともにリズムが戻り、シンバルを打ち鳴らすとドラム・ソロだ。
足技も駆使したマシンのようなプレイである。
リズムと演奏が戻り、悲鳴を上げるシンセサイザーとギターが激しく交錯して終り。
ヴァイオリン、ギター、ベース、ドラムスの順でハイテク・ソロを回すインストゥルメンタル。
カデンツァという名前の通り、ど派手なソロの連発である。
ヴァイオリンは、そもそも音が派手なため、ソロになってもあまり大きくは印象は変わらないが、ギターは壮絶の一言。
普通のジャズ・ギターを加速したような力一杯のプレイだ。
そしてドラムスのプレイも凄まじい。
重くて速いのだ。
ぶっ飛んだシンセサイザーによる「つなぎ」やギターのコード・カッティング、チェンバロのプレイ等、薬味も効いている。
ウェイ/モズレイの作品。
6 曲目「Chanson Sans Paroles」(6:29)ヴァイオリンをフィーチュアした曲。
穏やかなテーマに緊張感ある細かいパッセージを交えて、巧みに盛り上げてゆく。
全体にはクラシカルだが、メロディはほんのりフォーク調。
中盤はヴァイオリン、リズムともに一旦消えて、深い空間を感じさせる不思議な演奏になる。
ジャズ調である。
すべてが遠ざかり、ベースと余韻の美しいピアノ、ヴァイオリンがふわふわと漂っている。
ギターのゆったりしたソロも聴こえてくる。
ピアノとともにギターの音量が次第に上がり、ドラムスもリズムを刻みはじめる。
ベースの連打とヴァイオリンのリフ。
エキサイトするアンサンブル。
クレシェンドまたクレシェンド。
ギターは狂おしく暴れ、ピアノがざわめく。
クライマックスを経て、再び、オープニングの穏やかなヴァイオリンのテーマが再現。
細かいパッセージを繰り返し、次第に高まりふっと消える。
幻想的なインストゥルメンタル・ナンバー。
ヴァイオリンをフィーチュアしたロマンチックかつ牧歌的なアンサンブルから、浮遊感ある即興空間を経て、再びアンサンブルへと戻る。
中間部では、混沌とした宇宙にて次第に音がまとまり、やがて、何もかもが巨大な球体のように一つになって驀進する。
壮絶な演奏だ。
昼寝をして悪夢を見たような内容である。
前後のヴァイオリン・パートは、トラッド風。
ピアノはマクドナルド。
ウェイ/エサリッジの作品。
最終曲「McDonald's Lament」(7:06)
なんとプロデューサーのイアン・マクドナルドに捧げられた、哀愁の佳曲。
にじんだエレピと、波のように寄せては返すシンバルの響きの中、ヴァイオリンが哀しげな表情で歌い続ける。
ジャジーなギターの伴奏。
ドラムスは、マイケル・ジャイルスのように抑制された正確なプレイで、安定したリズムを供給する。
ヴァイオリンはギター、ドラムスとともに高まっては沈み込む。
最後は、ドリーミーなギターの響きとともに、ヴァイオリンが静かに歌う。
シンバルが潮騒のようにざわめく。
暖かみのある和音の響き。
ヴァイオリン(ヴィオラだろうか)を中心とした深い情感を湛えたロマンチックなインストゥルメンタル。
ヴァイオリンのメロディは、胸をかきむしるように古い思いを呼び覚ます。
ジャジーで控えめなバッキングも冴え、ヴァイオインを巧みに引き立てる。
ロマンチックだがベタベタした感じはなく、知的でありヨーロッパ風のエレガンスがある。
エモーショナルにして素朴さと抑制のあるサウンドは、アルバムを象徴する。
さほど美音ではないのだが、いい知れぬ余韻を残すところは、やはり名手なのでしょう。
グループの作品。
テクニシャン揃いでありながら、非常に叙情的でファンタジックな音の作品になっている。
したがって、安定感は抜群、余裕の感じられる演奏だ。
その安定したブリティッシュ・ロックらしい演奏に、ロマンチックなヴァイオリンとテクニカルでエモーショナルなギターが独特の色をつけている。
スパニッシュなテイストのアコースティック・ギター・プレイがフィーチュアされる 3 曲目や、即興風の 4 曲目など、エサリッジが本領を発揮、鮮烈な演奏を披露する。
そして、やはり最大の聴きものは、ヴァイオリンをフィーチュアした曲だろう。
太く柔らかな音色のヴァイオリンは、朗々とメロディを歌って存在感がある。
他のメンバーも引き締った演奏で受けて立っている。
特に、5 曲目は、基本的にはテクニックのお披露目ではあるものの、スピーディな展開に思わず圧倒されてしまう。
また 3、6 曲目は曲の構成もよく考えられており、じっくり味わって楽しめる。
メセカーの頼りなげなヴォーカルに、どうしてもイアン・マクドナルドを思い出してしまうのも、自然なことなのだろう。
プログレッシヴ・ロックというよりも、クールネスとロマンチシズムのバランスの取れたブリティッシュ・ロックというべきである。
また、正確なタイムとパワーをもちながら、ジャズ的でないドラムスのスタイルもおもしろい。
(POCD 1840)
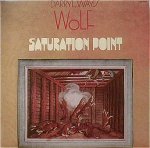
| Darryl Way | violin, keyboards |
| Dek Messecar | bass, vocals |
| John Etheridge | guitar |
| Ian Mosley | drums |
74 年発表の第二作「Saturation Point」。
前作の叙情路線からやや方向を変え、重量感あふれるリズム・セクションの上でヴァイオリンとギターがせめぎあう、ハードなロック・インストゥルメンタルが中心のアルバムになった。
ヘヴィではないが研ぎ澄まされおり、ロックンロールの小気味よさと切れ味をもった演奏である。
ヴォーカル・ナンバーは 2 曲目のみ。
ヴァイオリンとギターは、メロディよりもシャープなリフとスピーディーなアドリヴを主体とした演奏であり、たたみかけるようなドライヴ感が生まれている。
特に、1 曲目そして 4 曲目、5 曲目に、そのスタイルが顕著だ。
ゆったりしたテンポでヴァイオリンとギターが語り合う、ロマンティックな 3 曲目のバラードが一層映えるのも、他の作品の勢いのよさがあるからだろう。
タイトル・ナンバーはギターがフィーチュアされ、唯一ジャズロック・テイストのある作品。
ウェイはおそらくキーボードに専念。
メローだがジャズロックらしい緊迫感がある作品だ。
また「Toy Symphony」は、オーバーダブされたクラシカルなヴァイオリンが大活躍する、ボレロ風のシンフォニックなナンバー。
アルバム中最大の聴きものだろう。
エサリッジはラテン風のアコースティック・ギターや超絶速弾きを披露。
これだけ技巧的だと、5 曲目のようなペンタトニックのハードロック風アドリヴは、かえって妙に聴こえてしまうから面白い。
奔放さを前面に出したプレイ主体である。
また、ウェイのヴァイオリンは、ハードなサウンドに不釣り合いなくらい、クラシック/バロック調の音色でアクセントをつけ、これまた、安定した技巧でエサリッジと渡り合っている。
この二人の絡みはやはりスリリングだ。
そして、モズレイのドラムスは、ロックンロール調のシンプルな 8 ビート主体にも関わらず、正確なタイム感とずっしりした重みをアンサンブルにもたらしている。
全体にストレートな演奏にも関わらず、独特の緊張感が保たれるのは、この巧みなドラミングによるのではないだろうか。
特に、最終曲でのドラムスとヴァイオリンによる躍動感ある演奏はすばらしい。
傑作。
プロデュースはショーン・デイヴィス。
「The Ache(エイク)」(4:48)ヴァイオリンとギターがクラシカルなユニゾンで突っ走る快速ロック・インストゥルメンタル。
ウェイのヴァイオリンがカデンツァ風に爆発する冒頭(YES 風でもある)から、いきなりハイ・テンションのまま、演奏が続いてゆく。
ジャズロックではなくてハードロック。
これは、リズムが一直線でありうねりがないため。
ギターはポルタメントとトレモロのようなオルタネート・ピッキングを組み合わせた超絶速弾きと、ワイルドなコード・カッティング。
モズレイのドラムスもシンプルな 8 ビートのパターンで真っ直ぐひた走る。
猛るような演奏だ。
ウェイ作。
「Two Sisters(二人の姉妹)」(4:20)
シャフル・ビートで飛翔するブルージーなハードロック。
イントロはブルージーで挑戦的な 8 分の 6 拍子だが、一気に 8 ビートで軽快に走り出す。
ヴォーカル・ハーモニーにはウエスト・コースト風の爽やかさもあるが、ヴァイオリンはブルージーなプレイで、普通のバンドならギターがとるようなソロを披露する。
3 連のフレーズがスリリング。
世慣れしすぎた B 級アイドルの作品のような、けだるさもあり。
本アルバム唯一のヴォーカル・ナンバーである。
ウェイ作。
「Slow Rag(スロー・ラグ)」(5:17)
アコースティック・ギターとヴァイオリンによる苦悩するようなテーマが印象的なロマンティック・バラード。
エレアコ・ギターのアルペジオとドラムスが刻むやや沈んだ調子の 8 分の 6 拍子で、アコースティック・ギターとヴァイオリンがユニゾンしつつ語り合い、やがて熱気が高まってくる。
アコースティック・ギターのソロは彫りの深いシングルトーンのプレイに得意のトレモロも交え、みごとな説得力あり。
ややジャジーな表情を見せる瞬間もある。
訥々と哀しみを語りかけるギターと、憂鬱に沈みながらも朗々たる筆致のヴァイオリンとの対比。
ドラムスは、珍しく細かい技を次々と繰り出して、的確に行間を満たしている。
エレクトリック・ピアノもウェイだろうか。
エサリッジ作。
「Market Overture(マーケット・オーヴァーチュア)」(3:37)
FOCUS や TRACE を思わせるクラシカルなテーマによるインストゥルメンタル。
テーマは、二つのギターをオーヴァーダブしたハーモニーによる、ハイドンのシンフォニーのようなおだやかなもの。
ギター・ソロはブルーズ・ロックらしいペンタトニック・スケール系ながらも、独特の高速オルタネート・ピッキングをフル回転させた超絶プレイの連発。
オクターヴを交えたコード処理も鮮やか。
この曲でも、シンプルなテーマの間隙を縫うドラムスのプレイに耳がいく。
後半は、俗謡風のテーマを活かした調子っ外れのコミカルなヴァイオリン、ギターのデュオが繰り広げられる。
パーカッションもユーモラスだ。
ウェイは、ここでもエレクトリック・ピアノをプレイしている模様。
ウェイ作。
「Game Of X(X のゲーム)」(5:47)
ヴァイオリンのリフが緊張感を高める、ワイルドなハードロック・インストゥルメンタル。
MAHAVISHNU ORCHESTRA をソウルとガレージで味付けした感じである。
弛緩と緊張を繰り返しつつ、螺旋を描くように高まってゆく。
シンプルなリフの反復を軸に細かな変化をつけて曲を展開してゆく。
ギターとヴァイオリン、テーマとリズムといったコンビネーションを巧みに生かしている。
だらしのないスキャットも含め、不良っぽい、ワルっぽい素振りがカッコいい。
終盤。堰を切ったようにギター・ソロが飛び出す。
いかにも我慢の限界を越えたといった感じでおもしろい。
ギター・ソロをオブリガートするヴァイオリンがあたかもブラス・セクションのようにアッパーに盛り上げるのもいい。
エサリッジ作。
「Saturation Point(飽和点)」(6:45)
粘っこいギターをフィーチュアしたジャズロック・インストゥルメンタル。
ミドル・テンポでリフ主体のバッキングに支えられて、前半はアコースティック・ギター、後半エレキギターが自由なプレイを放っている。
ジャズ風の含みのある和音とオープニング、エンディングのリラックスしたハーモニーによるテーマ演奏が印象的。
このテーマには、FOCUS を思わせるジャズ、クラシックのブレンド感覚あり。
その後は、強靭なリフの上でジャジーなギター・プレイが続いてゆく。
バスドラを巧みに使ったテクニカルなドラミングにも注目。
バッキングはクリアーな音色のエレクトリック・ピアノ。
ウェイ作。
「Toy Symphony(おもちゃのシンフォニー)」(7:13)
再び、ヴァイオリンとギターそしてファズ・ベースが一体となって疾走するスリリングなインストゥルメンタル。
今度はヴァイオリンが主役であり、マーチング・スネアからティンパニ風まで、あまりに多彩なドラムスとともに華麗なプレイを見せる。
こんなに正確無比なシャフル・ビートってあり?
ヴァイオリンはみずみずしい音色にほのかな哀感を漂わせつつ気品ある流れるようなソロを放つ。
オーヴァー・ダビングされた二つのヴァイオリンが超絶的なドラミングに煽られるように華麗なデュオで舞い踊る。
終盤のギターとヴァイオリンが大見得を切る双頭アンサンブルもカッコいい。
バンドらしいヘヴィでアタックの強い音と透明感あるクラシカルなヴァイオリンの音の対比が鮮やかな勇壮で高潔なるシンフォニック・チューンだ。
ウェイ作。
(LAX 1037 / UICY-9063)

| Darryl Way | violin, keyboards |
| Dek Messecar | bass, vocals |
| John Etheridge | guitar |
| Ian Mosley | drums |
| John Hodkinson | vocals |
74 年発表の第三作「Night Music」。
IF のジョン・ホジキンソンを迎え、ヴォーカル・パートの充実を図った。
楽曲はウェイ主導であり、歌ものでポップ・テイストを打ち出しつつも各メンバーの多彩なアイデア、技巧、サウンド効果も盛り込んでおり、結果、実験精神旺盛な内容になっている。
どちらかといえば、全体的なアンサンブルとサウンド面に力を入れており、ヴァイオリンのプレイそのものはわりと抑え目だ。
ただし、メロディアスなヴォーカルを支えるはずの器楽がすぐに羽目を外して暴走気味に盛り上がり、はち切れそうになるところが、このグループの特徴である。
そういったセンスと爆発力を兼ね備えた演奏を誇るだけに、1 曲目や 3 曲目のようなスケールの力作が、もう一つくらい B 面にあってもよかったと思う。(B 面 3 曲目が惜しい!)
残念ながら最終作となる。
なぜか忘れられているプログレの名作といっていい。
個人的には、テクニカルなメセカーのベースとイアン・モズレイの音数の多い、スティックを垂直に振り下ろしているようなドラミングが好きです。
「The Envoy(エンヴォイ)」(6:28)ロマンとドライヴ感あふれる傑作。
ハードロックとフォーキーなリリシズムの合体という WISHBONE ASH 的な、おそらくこのグループの音楽性を最もよく表現した内容といえる。
ドラムス、ベース、ギター、ヴァイオリン、ヴォーカル、すべてが抑制の効いたベストのプレイでかみ合って楽曲を作り上げている。
けたたましいギターとトラッド的なニュアンスもあるヴァイオリンのインタープレイから爆発的なトゥッティへと突っ込むところで胸がすく。
メセカーのテクニカルなロック・ベースもいい。
ウェイ、エサリッジの作品。
「Black September(黒い九月)」(4:48)
物騒なタイトルのわりには、伸びやかな歌唱が冴えるメロディアスな歌もの。
ただし、インストゥルメンタルは高密度でハイテンション。
後半、エレクトリック・ピアノが現れてからのジャジーな展開もいい。
破裂しそうに超テクニカルなギター・プレイをさりげなく突っ込んでくる。
AOR タッチも若干あるか。
ウェイ、ホジキンソンの作品。
「Flat 2/55(Flat 2/55)」(6:52)エサリッジのギターを大きくフィーチュアしたジャズロック調の作品。
ギターはジャズを基調とする超絶的な技巧と歌心がみごとにバランスしたプレイ。
刻み込むように攻撃的な姿勢とメロディアスで悠然とした姿勢が調和している。
インストゥルメンタル。エサリッジの作品。
「Anteros(アンティロス)」(4:21)
シンセサイザー含めエレクトリックなサウンド効果を多用したアップテンポの歌もの。
オペラティックな歌唱をフィーチュアし、キーボードのオブリガートにヴァイオリン、ギターがピリっとスパイスを効かせる。
サウンドとヴォーカルは派手だが基調はフォーク・ソングである。
ウェイの作品。
「We're Watching You(ウィア・ウォッチング・ユー)」(5:10)
シンセサイザーの特異なサウンドと技巧的な器楽を散りばめたメランコリックなバラード。
英国フォーク風の翳りとシティ・ポップス調が一つになっているというか、どちらにも寄らず、やや不安定な印象。
多彩なシンセサイザーとエレクトリック・ピアノが多く使われている。
間奏のスパニッシュなアコースティック・ギター、終盤のシンセサイザー、ベース・ラインがカッコいい。
ウェイの作品。
「Steal The World(スティール・ザ・ワールド)」(4:18)
7 拍子、5 拍子を切りかえながら突っ走るしなやかな快速テクニカル・ロック。
技巧的なリズム・チェンジと優美に歌うヴァイオリンのコントラストもみごと。
ヴァイオリンとギターの細かいパッセージによるユニゾンやドラムス・フィルもスリリング。
ジャズでもクラシックでもない独自の音楽がある。
ウェイ、ホジキンソンの作品。
「Comrade Of The Nine(九人の仲間)」(2:43)
ホジキンソンの黒っぽいヴォーカル・スタイルがストレートに活きたブリティッシュ・ソウル。
リズミカルにしてパンチもキレもある演奏が、いかにもこのグループらしい。
埋め草っぽいようで痛快な聴き応えあり。
ウェイの作品。
(DERAM LAX 1038)

| Darryl Way | electric violin |
| Francis Monkman | synthesizers |
| Ian Mosley | drums, percussion on 4 |
| Bruno Schrecker | cello on 2 |
78 年発表の作品「Concerto For Electric Violin」。
ダリル・ウェイのソロ作品第一作。
内容は、エレクトリック・ヴァイオリンとシンセサイザーの擬似オーケストラによるヴァイオリン協奏曲である。
知的でファンタジックな英国クラシック・タッチであり、色彩豊かなサウンドを活かした、バランスのいい演奏になっている。
ウェイのヴァイオリンはロマンチシズムを押し出した素直なプレイだが、驚くのは、モンクマンのシンセサイザーのアレンジ、プレイが思いのほか繊細な表情をきわめていること。
管楽器系のサウンドが特に美しい。
CURVED AIR 時代とはえらい違いである。
したがって、この手のアプローチにありがちな粗悪な感じはまったくなく、クラシカルで落ちついた響きが全編にあふれている。
ただし、地味である。
これは、口ずさめるような、印象に深く刻まれるようなメロディがないせいだろうか。
もっとシンセサイザーとヴァイオリンが呼吸よく反応しあうとおもしろかったかもしれない。
小品である第三楽章が意外に名曲。
「1st Movement: Allegro Moderato」(9:37)
「2nd Movement: Slow」(10:51)伴奏するピチカートはチェロでしょうか。
「3rd Movement: Scherzo」(3:56)
「4th Movement: Finale (Gigue)」(11:31)
(EDCD 514)
