
| Rick Eddy | keyboards, acoustic guitar |
| Tim Drumheller | keyboards |
| guest: | |
|---|---|
| Michael Manring | bass |
| Scott McGill | guitar |
| Vic Stevens | drums, percussion |
| Akihisa Tsuboy | violin |
アメリカのプログレッシヴ・ロック・ユニット「A TRIGGERING MYTH」。 89 年結成。作品は六枚。 アコースティック・ピアノとシンセサイザーを中心とした演奏で、クラシック、ジャズ、ポップス、ニュー・エイジなどさまざまなジャンルからの中間地点に屹立する個性派。 冷徹で研ぎ澄まされたタッチが特徴。

| Rick Eddy | keyboards, acoustic guitar |
| Tim Drumheller | keyboards |
| guest: | |
|---|---|
| Michael Manring | bass |
| Scott McGill | guitar |
| Vic Stevens | drums, percussion |
| Akihisa Tsuboy | violin |
2006 年発表の第六作「The Remedy Of Abstraction」。
内容は、一気にテクニカル・フュージョン色を強めたエレクトリック・チェンバー・ミュージック。
前作に続いてスコット・マッギル、ヴィク・スティーブンスのサポートを得ており、さらにマイケル・マンリングも参加、それがそのまま作風につながっている。
キーボードを中心としたアンサンブルは時にカンタベリーや現代音楽調のアヴァンギャルドな表現で煙に巻き、時に思い切りジャジーなインプロでしなやかな表情を見せる。
エレクトリック・キーボードによる独特の冷徹で無機的なフレージングは健在であり、かわらず魅力的である。
さらに、表情が曇るように自然なメランコリーの翳が差す辺りも、今までにはなかった芸風である。
ただし、やや情に流されすぎというか、持ち味である独特の険しさ、狷介さとストレートなジャズ/フュージョン風の演奏とがまとめ切れていない印象も若干ある。
個人的な意見として、マンリングのベースのスタイルがアンサンブルのバランスをやや損なっていると思う。
ベース本来の低音部の進行とビートの確実化は、むしろアコースティック・ピアノによる方が効果的になっている。
また、ヴァイオリンはアンサンブルの補強としてはうまく機能しているが、その存在感が強まり過ぎると全体を陳腐なイージー・リスニング調にしてしまい、このグループの作品本来の魅力である緊張感を削いでしまう。
一方、アコースティック・ギターやエレキギターは、キーボード・サウンドとうまく対立、調和して演奏を立体的に引き立てている。
ぜひとも、従来のキーボード主体のポリフォニックなアンサンブルによるスリリングで知的なサウンドを継続して極めてほしい。
「Now That My House Has Been Burned Down, I Have A Beautiful View Of The Moon」(5:11)
「The Remedy Of Abstraction」(7:53)
「Her Softening Sorrow」(8:12)
「Not Even Wrong」(7:59)
「Rudyard's Raging Natural」(2:32)
「Shakespeare's Strippers」(4:55)
「The Eisenhour Slumber」(4:33)
「When Emily Dickinson Learned To Lunge」(8:09)
「The Last Resort」(2:34)
(LE 1044)

| Rick Eddy | keyboards, guitar, percussion |
| Tim Drumheller | keyboards, percussion |
| guest: | |
|---|---|
| Steve Williams | electric guitar on 2,3,4, bass, percussion |
| James Newton | keyboards on 1,4 |
90 年発表の第一作「A Triggering Myth」。
内容は、クリアーなキーボード・サウンドによる整然としたインストゥルメンタル・ミュージック。
メロディよりも幾何学的な音の配置と運動に重きを置いた音楽である。
フレーズは多彩であり、叙景的なところもあるが、テーマと位置付けられるような旋律はほとんどない。
つまり、普通の意味での「歌」はなく、その点で現代音楽的である。
また、張り詰めたような緊張感はあるが、いわゆるチェンバー・ロックのような凶暴な攻め一辺倒の演奏や暴力的な運動性はない。
同様な編成、アプローチということでは RASCAL REPORTERS が思い浮かぶが、かのグループほど、カンタベリー、レコメンというキーワードは当てはまらない。
ミニマルなリフ(しかし、そのリフそのものの存在感もあまり強くない)に支えられて、ジャズ・フュージョン、近代クラシック、AOR、フォークなどを揺れ動くような演奏が繰り広げられる。
アコースティック・ピアノの音に象徴されるように、独特の量感と透明感があるサウンドだが、安定することを静かに拒んで漂い続けるようなところがある。
それでも、エレクトロニック、シンセサイザー・ミュージックのような茫洋としたところはまったくない。
アヴァンギャルドな音楽特有の暗さを孕みながらも、キーボードのプレイにはジャジーなグルーヴがあり、ときにシンフォニックな広がりをもつアンサンブルへと発展することもある。
リズムについても、一人打ち込みよりは遥かに躍動感があり、デュオとは思えぬほど演奏はスリリングだ。
ただし、オーケストラを擬したようなキーボード・アンサンブルであるにもかかわらず、シンフォニック・ロックというにはあまりにクールであり、閉塞的である。
デジタルで緻密な構成とバンドとしての肉体的でダイナミックな呼吸が、きわどいところでバランスされている。
デュオという形態を活かした音といってもいい。
現代音楽的なニュアンスの中に、ほのかなエキゾチズムや神秘的な深みもある、変幻自在の演奏といっていいだろう。
要するに、一言では到底いい表せない無比のオリジナリティをもった作品ということだ。
曲名に漂う乾いたユーモアもよし。
「Living Out Loud!」(5:52)ピアノとオルガン、ストリングス系シンセサイザーによる変拍子パターンを駆使したシンフォニックな作品。
リズムを強調しつつも流れるような演奏だが、それにもかかわらず、情感よりも理知を優先したような趣であり、常に冴え冴えと冷え切っている。
マイク・オールドフィールドのファンではありそうだ。(宅録系アーティストでオールドフィールドに影響されなかった人はいないと思う)
ビートを強調した執拗なピアノのリフレインとシンセサイザーが次々と散りばめるスペイシーなフレーズ。
ドラムス、ティンパニが駆使された、勇壮なアンサンブルも現れる。
「The Delicate Balance Of Coincidence」(6:27)物語風に展開するシンフォニック・ロック大作。
シンセサイザー・デュオによる弦楽オーケストラ風の演奏から、1 曲目と同じピアノとストリングス系シンセサイザーのデュオを経て、シリアスなアンサンブルでクライマックスに達する。
序盤は、無機性が弱まり、ファンタジックで叙景的な、共感性のある演奏である。
中盤、一気に激した、緊迫感あふれる演奏となり、ギターやチェロ(コントラバス?)が唸りを上げる。
終盤は、ピアノと管楽器系のシンセサイザーによる厳かなデュオ。
激するアンサンブルをリードするギターとフルート、オーボエを思わせるシンセサイザーの音が印象的。
「Swimming With Sharks」(8:45)ファンタジックなニューエイジ、ミニマル・ミュージックを重厚なアンサンブルが塗り変える二部作風の作品。
シンセサイザー・デュオによるクラシカルなアンサンブルで始まり、半透明のヴェールのようなストリングス・シンセサイザーがゆっくり音を包んでゆく。
フランジ系エフェクトのベースが心地よい。
エレクトリック・ピアノは緩やかな世界の区切りのようにアクセントをつける。
序盤は、うっすらとした夢想世界だ。
中盤は、神経症的なピアノの低音オスティナートと管楽器シンセサイザーがリード。
テクニカルなピアノが緊張を生む。
謎めいたシンセサイザーのうねりに巻き込まれた果てに、唸り声のようなエフェクトを経て、管楽器シンセサイザーがリードする奇妙にゆがんだマーチがフェード・インする。
不協和音とスネアロールの感じは、フランスの TIEMKO を思わせる。
高音で不気味にさえずるシンセサイザーと手風琴のようなオルガンのざわめき。
突如重苦しいストリングスが低音から湧き上がり、厳かな調子で世界のネジを巻き直し始める。
タイトルからすると、マーチの前の唸り声はサメ?
「The Biology Of Doubt」(6:02)サックス風のシンセサイザーをフィーチュアしたスタイリッシュなジャズロック風の作品。
シンセサイザーのテーマやベースのスラップなどはジャジーだが、変拍子やピアノの強圧的リフレインが曲を捻じ曲げてゆく。
ウィンド・シンセサイザー・ソロ、エレクトリック・ピアノ・ソロをはさみ、時限爆弾のように時を刻む弦楽器のピチカート(?)とともに、管楽器/ストリングス・シンセサイザーがアドホックに舞い踊る。
印象派のような近代クラシックのいめーじを蓄えつつ、打楽器、ピアノ系の音が戻り、ポリリズミックな演奏へ。
明確なリズムもあり、フュージョンとクラシックの中間に位置する作品だと思う。
HAPPY THE MAN にも通じる作風だ。
「When Suddenly I Am Old And Start To Wear Purple」(1:43)
アコースティック・ギターとシンセサイザー・フルートの軽やかなデュオ。
ポジティヴでリズミカルな演奏に JETHRO TULL を思い浮かべては変?
「The Thin Edge」(5:54)近代クラシック調の独奏ピアノと管弦シンセサイザーによるダークな協奏曲。
重厚荘厳にして暗く偏執的なピアノ演奏が中盤まで演奏をリードし、終盤からスケールの大きな管弦楽が加わり、モノローグが入る。
「The Eye In The Looking」(4:40)印象派の作品を思わせるほのかにエキゾティックな作品。
後期 GONG のような鍵盤打楽器、パーカッション系シンセサイザーのミニマルな演奏に管弦楽を重ねて重厚さを演出し、サックス系の音(これまたデェディエ・マレルブ風だったりする)でジャジーに変化をつける。
管弦は西アジアをイメージさせる音であり、民族楽器風のパーカッション類も現れる。
「We Think About Our Thinking」(1:59)民謡風の素朴なピアノの調べを秘めやかな管弦楽が彩る、慈愛と郷愁あふれる小品。
(LE 1003)
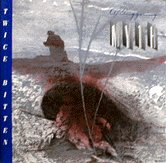
| Rick Eddy | keyboards, acoustic & electric guitar, trumpet, percussion |
| Tim Drumheller | keyboards, recorder, percussion |
| guest: | |
|---|---|
| Steve Williams | electric guitar, bass, percussion |
| Dave Yahe | electric & acoustic basses |
| Moe Vfushateel | drums |
| Eric Oritt | classical guitar |
93 年発表の第二作「Twice Bitten」。
内容は、ピアノ、シンセサイザーなどキーボードを多用し、リズムを強調したチェンバー・ミュージック。
トランペットと本格的なドラムスの使用によって、線の細さがなくなり、チェンバー・ロックらしい暗いパワーが備わった。
ただし、ジャズとクラシックの中間を揺れるような作風は変わらないし、変拍子を多用して押し引きを繰り広げる、一筋縄ではいかなそうなところも同じだ。
管楽器とハモンド・オルガンの音がアクセントとして目立っている。
リズムレスのアコースティック・アンサンブルでは、前作同様室内楽調の静けさとジャジーなおだやかさがある。
しかし、一度ドラムスが入ると、ロック的な重みや緊張感が顕著になる。
フリー・ジャズに迫る激しい展開や、変拍子のユニゾンでたたみかけるなど、ヘヴィ・プログレ的な場面もある。
そして、ピアノがリードするシーンでは、前作同様、クラシックとジャズをブレンドしたような、パット・メセニー・グループ風の幻想美がある。
ピアニストの演奏のうまい下手はあまり分からないが、表現を構成する音はきちんと出せていると思う。
ジャズ、クラシック、さらにはフォーク風の穏やかな旋律にエキゾチックなスパイスを効かせた、多彩な音楽性をもつ現代音楽。
縦糸と横糸の色合いを計算し尽くして、複雑に織られたタペストリのようなアンサンブルが、無限の輝きを見せる。
そして一曲中での多様な変化にもかかわらず、それぞれの曲の性格は明確であり聴きやすさもある。
それぞれが個性を放つ美しい作品である。
20 分にわたる「Myths(Parts I-VII)」が、くっきりとした稠密さとスケールの大きなドラマ展開で圧巻。
また、攻めに徹した「Suddenly South」は、シリアスな雰囲気に典型的プログレッシヴ・ロック風の展開も交えた面白い作品だ。
近現代クラシック然とした作品とフュージョン風の作品、ミニマリズムというよりもマイク・オールドフィールドに直接影響されたような展開などがあまり交じり合わずにそのまま出ているところが、素直さという点で強み、二番煎じ臭という点で弱みにもなっている。
ただし、こういった志向の「あいまいさ」に独特の魅力があるのも確かだと思う。思えばプログレはその曖昧さ、多義性の権化である。
「The Perils of Passion」(5:34)HAPPY THE MAN をよりニューエイジ・ミュージックに寄せて、同時に無機性も強めたような作品。主役はピアノ。攻めの圧迫感と引きのファンタジー風味がともに強い。
「Myths(Parts I-VII)」(21:30)一貫してドラマティックに展開するチェンバー・ロック作品。
「Twice Bitten」(1:27)シンセサイザーとピアノのデュオ。まろやかな音色のシンセサイザーがいい。生真面目な GILGAMESH。
「Falling Over Fear」(6:05)粘っこいエレクトリック・ギターをフィーチュアしたフュージョン風の作品。ただし、後半ではフュージョンに留まらずチェンバー・ロック的な展開へと突っ込み帰らず。
「Holding Up Half the Sky」(3:40)アコースティック・ギター、木管風のシンセサイザーなどによる牧歌的な世界。
「The English Lesson」(4:44)シンセサイザーによるウィンド・アンサンブル。クラシカルな演奏からサイケデリックな非調和世界へ。
「Suddenly South」(7:00)変拍子テクニカル・ロック。傑作。
「P.S.」(3:02)ナイト・ミュージック風のピアノ演奏。
ピアノのリードで繰り広げられる、緊張感のある室内楽風のインストゥルメンタル。
ジャズとクラシックの中間をさまようアンサンブルは、時に険しい表情をたたえ、精神の水面をゆっくりと波立てる。
(LE 1019)
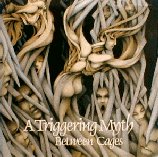
| Rick Eddy | keyboards, all guitars, assorted sundry instruments, titles, poetry |
| Tim Drumheller | keyboards, programming, assorted sundry instruments,production |
| guest: | |
|---|---|
| Moe Vfushateel | drums |
| James Newton | percussion |
| John McNamara | guitar |
| Mark Cella | drums |
95 年発表の第三作「Between Cages」。
後半に 20 分超のタイトル組曲を配置する構成は、前作とほぼ同じ、また、サウンドも前作の延長上である。
内容は、ピアノ、キーボードを中心とし、変拍子を多用するインストゥルメンタル・ミュージック。
ジャズや室内楽のエッセンス、スタイルを取り入れて、独特の冷ややかでシビアな世界を構築している。
本作品は、適切な製作のおかげか、従来からある固有の険しさ、冷徹さが際立つとともに、フレーズに素朴な叙情性や子供っぽい愛らしさが感じられる。
反対に、ロックの構成要素であるブルーズ・フィーリングや感傷からは、さらに距離ができた。
また、ジャズやクラシックの旋律、和声などの様式にも寄りかかり過ぎていない。
強いていえば、エチュードがエチュードのまま複雑怪奇になったようなイメージである。
きわめてユニークな音楽であるのは間違いない。
モザイクのようなアンサンブルは、不思議なほど圧迫感、緊張感をもたず、かといってゆったり弛緩しているわけでもない。
抽象的な模様がパタパタと形を変えてゆくようなアンサンブルであり、その中に叙情的といっていいような暖かみある瞬間がくっきりと浮かび上がる。
スイスの SFF の初期作品との共通性は、ライナーに謳われている通りである。
このスタイルにダイナミックな強度を加えると、BIRDSONGS に迫るだろう。
楽曲でとりわけ目を引くのは、AREA のデメトリオ・ストラトスに捧げられた作品。
リック・エディは、AREA に大きな影響を受けたと語っている。
そして、タイトル・トラックの大作。これは、豊かな世界観を提示する稀に見る傑作。
地味な作風ではありますが、シンフォニック・ロック・ファンにもアヴァンギャルド・ミュージック・ファンにもお薦めです。
シリアスにして透明感ある 1 曲目「Habile」(4:27)、ジャジーなタッチも見せる 2 曲目「Deftly Dodging」(5:18)、そして、パーカッション系のシンセサイザーとクロスオーヴァー風のムーグのペンディング、そして重厚なピアノが耳に残るアヴァン・ロックの 3 曲目「Squdge」(10:11)。
曲ごとの表情はさまざま、多彩である。
共通するのは、精妙に構築されたものに共通する冷徹な美感である。
4 曲目「Il Voce」(6:13)では、AREA に捧ぐというクレジット通り、AREAの作品からヒントを得たと思われる中近東風の主題をメインに配している。
ハモンド・オルガンやヘヴィなギターなど珍しく「ロックな熱さ」を取り入れている。
こういう作風が原点の一つであるというのは、ここまでのサウンドからするとかなり意外な感じだ。
もっとも、AREA の作風は、ATM らしく構築された世界の中の素材として活かされている。
先達に敬意を表したオマージュという位置付けになると思う。
5 曲目「Midiots, Vidiots And the Digitally Delayed」(3:27)
パーカッションとシンセサイザーをフィーチュアし、ややインダストリアルな電子音楽風にまとめた小品。
無機的な作風がイメージされるグループだが、こういうデジタルなテクスチャは意外にこのグループらしくない。
6 曲目、タイトル組曲「Between Cages」(21:51)。
7 つのパートからなる大作である。
ピアノとシンセサイザーによるシリアスなデュオから幕を開け、次第に演奏は躍動感を強め、同時にメロディアスに変化してゆく。
フルートを思わせるシンセサイザーとアコースティック・ピアノのコンビネーションには、カンタベリー風の美感もある。
ギター登場後は、ピアノとのアンサンブルにて、ソロを巧みに絡ませながら上品に緊張感を維持してゆく。
やはりカンタベリーという言葉が思い浮かぶ演奏だ。
ボトムは変拍子。「企み」のある演奏である。
5 分半過ぎ付近からの、ロックなドライヴ感をダイレクトに吐き出す演奏がなかなかカッコいい。
PEKKA POHJOLA の作品を思い出した。
オーケストラを思わせるアンサンブルは、ポジティヴなテーマをさまざまに繰り返し、ゆったりと飛翔するような演奏を続けてゆく。
ピアノのリフレインが独特の険しい表情をアンサンブルに取り戻し始めるが、演奏はそれすらも抱えながら悠然と続いてゆく。
15 分あたりからの、メロディアスなギター、ソプラノ・サックスを思わせるキーボードも、クールにして血の通った好プレイだ。
終盤は、幻想的なブリッジを経て、挑戦的な演奏が時を刻みなおすうちに、シャープなギターらによるアンサンブルが鋭く幕を引く。
幻想的なイントロから、鋭角的なアンサンブル、軽快な疾走パートを経て、シンセサイザーによるオーケストラでクライマックスを迎える超大作。
ピアノとシンセサイザーによるアンサンブルは、遥か未来の室内楽のような不思議な味わいをもつ。
聴きどころは中盤。シンセサイザー・オーケストラからピアノ、ギターも絡んだ美しくも込み入った演奏が続くところだろう。
終盤のメロディアスなソロもカタルシス。
カンタベリー、HAPPY THE MAN といったキーワードが連想される内容だ。
アルバム前半では抽象的なイメージが高まるが、この大作には気品と透明感、自然な抑揚があり、いわゆるプログレ、シンフォニック・ロック・ファンには強く支持されそうだ。
傑作。
(LE 1022)

| Rick Eddy | keyboards, guitars, percussion |
| Tim Drumheller | keyboards, percussion |
| guest: | |
|---|---|
| Moe Vfushateel | drums, percussion |
| Alberto Piras | vocals |
| Alessandro Bonetti | violin |
98 年発表の第四作「The Sins Of Saviours」。
ゲストに DEUS EX MACHINA のヴォーカリスト、アルベルト・ピラスとヴァイオリニスト、アレッサンドロ・ボネッティを迎えた。
内容は、キーボードを中心としたクラシカルかつシリアスなインストゥルメンタル・ロック。
変拍子の上でピアノ、オルガン、シンセサイザーらがクリアーにして込み入ったアンサンブルを成す。
角のないまろやかなデジタル・シンセサイザーの音色が独特である。
メロディアスなフレーズやきわめて透明感のある音色があるにもかかわらず、スカーンと突き抜けるようなところがなく、どこまでもグネグネと渦を巻くような演奏である。
重量感がさほどではないため、全体のイメージは、凶暴というよりは「峻厳」かつ「狷介」というべきだろう。
クラシカルなアンサンブル、ストリングス系の音を活かしたダークなシンフォニック色、ジャジーな即興などさまざまな要素がある。
今回光るのはピラスのパワフルにしてゆったりとした歌唱。
この歌が全体のイメージにメロディアスな丸みを帯びさせている。
ときに、独特のクールネスはそのままに、より険しく現代音楽的な風合いも強まるが、この歌の存在がいい感じでバランスを取っている。
ヴァイオリンが 1 曲だけなのは残念だった。
前作で明らかな通り、ATM 自身がデメトリオ・ストラトスの影響を受けているため、この共演には相当力が入っただろう。
3 曲目はストラビンスキーを思わせる傑作。
「the awful truth」(7:52)ピアノ、ギター、ストリングス・シンセサイザーを活かした重厚不羈な変拍子シンフォニック・ロック。
オープニングとエンディングのアンサンブルがなんとも厳めしい。
遁走曲風の展開や呪文めいた反復など、ホィッスル系シンセサイザーなど愛らしい音が多いにもかかわらず神秘的なムードが一貫する。
やや東洋風味あり。
「bagliore」(5:11)ピラスのヴォーカルをフィーチュアした作品。
「過激な讃美歌」に聴こえるのは、バッキングがオルガン、ピアノ系のシンセサイザー・アンサンブルだからだろう。
「his maddenning certainty」(10:50)
多彩なキーボード・サウンドを駆使して波打つような反復とともに緊張の高まるチェンバー・ミュージック大作。
ピアノ、ドラムスによる変拍子パターンをシンセサイザーのロングトーンが貫き、オルガン系のシンセサイザーやエレクトリック・ピアノのアドリヴが吹き荒れる。
抽象的な響きの中にうっすらとユーモアとペーソスが漂い、カンタベリー系に聴こえなくもない作品である。
「not a river」(4:18)ピアノ、ヴァイオリンをフィーチュアした作品。ジャズ、カントリー、Windom hill などさまざまに揺れる。
「the (ag)nostic gospels」(4:10)ピアノ、オルガン系シンセサイザー、ベース、ドラムスによるポリフォニックなアンサンブル。
他旋律による複雑な反復、遁走に衝撃的なアクセントを交えて展開させてゆく。終盤のギターの参加でロックっぽさが強調される。傑作。
「stato di confusione avanzata」(5:13)
無調の現代音楽とフリージャズを交えた室内楽。エキゾティックなピラスのヴォーカルが圧倒的なダイナミズムで迫り、歪んだベースとともに室内楽を凶暴なロックへと逸脱させる。
強烈なシンセサイザーのブリッジを経て、凶暴なまま室内楽へと回帰する。
「the dust on mother's bible」(8:03)
ワイルドでグラマラスなリズムでかわいらしいキーボードがひらひらと舞う。
硬軟の大仰でドラマティックな落差。
「when faith transcends reason」(2:42)ヴォーカル・パフォーマンス。
「ken who?」(1:48)クライマックスのみ?
(LE 1030)

| Rick Eddy | keyboards |
| Tim Drumheller | keyboards |
| guest: | |
|---|---|
| Scott McGill | guitar |
| Vic Stevens | drums, percussion |
2002 年発表の第五作「Forgiving Eden」。
内容は、ピアノ、シンセサイザーなどキーボードを主とした緻密な変拍子インストゥルメンタル・ミュージック。
冒頭、モダンジャズ調のピアノにびっくりするが、その後は、室内楽と交響楽の中間くらいのニュアンスをもつ丹念なキーボード・アンサンブルに、リリカルなアコースティック・ギターや爆発力のある超絶ギターが絡んでゆく、独特の緊張感をはらんだ作風を披露してゆく。
キーボードが次々提示するテーマは意外にもメロディアスである。
そのテーマをひねくり回してゆくうちに、螺旋を描くようにして息詰まるように精密なアンサンブルが作り上げられてゆく。
キリキリと時計仕掛けがネジを巻いてゆくような緊迫感は本作でも基調になっている。
基本的に落ちつきと透明感を備えた音であり、アンサンブルには HAPPY THE MAN にも通じるファンタジックな余韻とともに、衒気というレベルではないアカデミックな気風を漂わせている。
ピアノとともに金管風のシンセサイザーが鳴り響き、ティンパニが轟くと、往年の EL&P のように本格的なキーボード・シンフォニック・ロックへと駆け上がってゆく。
それでいて、一度ミニマルで精密な変拍子パターンとともに走り出すと、したたかで狷介な素地がはっきりと見えてくる。
この勇壮さや叙情性と険しく厳しい表情の落差は本作品、あるいは本グループの特徴の一つだろう。
全体をリードし雰囲気を統率しているのはピアノであり、したがって意外なほどにサウンドはアコースティックである。
今回はレーベル・メイトであるマッギル、スティーヴンスの助力を得ている。
特にマッギルのエレクトリック・ギターは、演奏の枠組みを崩壊させそうな勢いで強烈な存在感を示している。
効果音以外は全曲インストゥルメンタル。
楽曲のクレジットは記載がなく、全八部から構成される組曲と理解している。
他に類を見ないユニークな存在なのでぜひとも長く活動して多くの作品を発表してもらいたい。
(LE 1036)
