
| Santi Arisa | durms |
| Marti Brunet | guitar, synthesizer |
| Jordi Camp | bass |
| Manel Camp | piano, keyboards |
スペインのプログレッシヴ・ロック・グループ「FUSIOON」。 バルセロナ出身のグループ。 71 年シングル・デビュー。 70 年代に三枚のアルバムを残す。 ポピュラー音楽としてのロックを溶媒に民族音楽やクラシック、ジャズを積極的に取り込むアプローチを重ね、遂にはアヴァンギャルドな現代音楽にまで到達した。 マヌエル・キャンプはクラシック、ジャズの作曲家/鍵盤奏者として今も活躍。 ドラマー、サンティ・アリサはフュージョン・グループ PEGASUS を結成。

| Santi Arisa | durms |
| Marti Brunet | guitar, synthesizer |
| Jordi Camp | bass |
| Manel Camp | piano, keyboards |
72 年発表の第一作「Fusioon」。
オリジナル LP のタイトルは「La Danza Del Molinero」のようだ。
内容は、ポップスを素材にジャズやクラシックを大胆に取り込んだ、イージー・リスニング風アートロック。
カヴァー曲が主であり、アレンジの妙を味わうべき作品である。
作風は、聴きやすいテーマを選んでインスト化し、ストリングスやテンポの変化など豊富なアイデアを持ち込んで、一ひねり加える、といったもののようだ。
演奏は、クラシック風の本格的なピアノ、オルガンと場末のスナック風のジャジーなギターを中心に、自由でいかにも才気煥発といった様子である。
そして、スタジオ・ミュージシャンとしての経験があるのだろうか、どのスタイルのアンサンブルも一応堂に入っているところがすごい。
歪んだヘヴィな音色やダークな和声など、ハードロック風の音を用いながらも演奏に敏捷さがあり、予想を裏切る急激な変化が非常に面白い。
また、アンサンブルのリードは多彩なフレージングを誇るピアノのようだ。
クラシックからジャズ、現代音楽、ソロからアンサンブルと、軽やかに飛び回っている。
時としてストリングスとギターの組み合わせが、微笑ましいくらいデパートの店内放送調になってしまうところを見ると、やはりキーボードの存在あっての作品なのだろう。
奔放でユーモラス、それでいて緻密さも損なわないスタイルは、カンタベリーにも通じるかもしれない。
通常のバンド編成以外に、管弦楽およびサックスが使われている。
アレンジの研鑚のための習作というには完成度の高い作品だ。
1 曲目ではファリャの「粉屋の踊り」をオーケストラを交えたハードロック的アレンジで聴かせる。
また最終曲では、カザルスで有名なカタロニア民謡「鳥の歌」をヘヴィ・ロック調に過激にアレンジしている。
全曲インストゥルメンタル。
カタロアニア出身のメンバーによる作品らしく、いわゆるスパニッシュ、フラメンコなニュアンスのない作品となっている。
「Danza Del Molinero」(4:33)カヴァー。
ファリャ作曲。
「Ya Se Van Los Pastores」(5:16)カヴァー。
「Ses Porqueres」(3:13)カヴァー。
「Pavana Espanola」(3:01)カヴァー。
「Negra Sombra」(3:44)オリジナル。
「En El Puerto De Pajares」(4:13)カヴァー。
「Rima Infantil」(3:37)カヴァー。
「El Cant Del Ocells」(4:15)カヴァー。
カタロニア民謡。
鳥の歌。
(DIVUCSA 32-516)
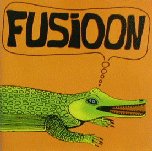
| Santi Arisa | percussion, durms |
| Jordi Camp | bass |
| Marti Brunet | guitar, synthesizer |
| Manel Camp | piano, organ |
74 年発表の第三作「Fusioon」。
内容は、精緻にして小気味よい運動性のあるアンサンブルによる、愛らしくも破天荒なプログレッシヴ・ロック。
変拍子を反復を駆使する現代音楽調はともすれば厳格で険しい印象を与えるが、ここではそこに可愛らしさとユーモアを持ち込んでバランスを取っている。
大胆なアレンジを駆使しながらも、まろやかなサウンドとユーモラスなタッチ、さらにメロディアスなテーマの使い方が巧みなために、結果としてイージー・リスニングなみにアクセスしやすくなっている。
全体を通したときの印象は、ある種のポップアートのような奇妙な味わいになる。
演奏は、オルガンを主にさまざまな音を放つキーボードがチャイルディッシュにして込み入ったフレーズを次々と放ち、ギターもそれに応じてギターも細やかなフレーズを刻み、それらの屋台骨を技巧的なリズム・セクションが支えるというもの。
目まぐるしい変転を破綻なく繰り広げる演奏にもかかわらず、ドライで突き放した感じがしないのは、変拍子パターンにしても EGG を思わせるとぼけた調子のあるところや、ギリギリのところで親しみやすいメロディや著名なクラシックの翻案を交えて耳を馴染ませる工夫をしているからだろう。
インストゥルメンタルだけではなくヴォーカル・ハーモニーもフィーチュアしている。
作曲は、ベースのジョルディ・キャンプとキーボーディストのマヌエル・キャンプ。
オリジナル LP のタイトルは「Concerto Grosso」のようだ。
クラシカルにしてアヴァンギャルドなところは、米国のカンタベリー・フォロワーに通じる。
収録時間のわりにはオナカいっぱいになる内容である。
1 曲目「Farsa Del Buen Vivir(生きる道化)」(3:08)
リズミカルなポップスに音程のずれた不安定なフレーズ、奇妙な電子音を散りばめた作品。
ヴォーカル・ハーモニーとシンセサイザーの電子音がうまく使われた切れ味よい演奏には、逸脱調のユーモアも漂う。
間奏のエレクトリック・ピアノなどにはジャジーなテイストあり。
しかしながら、べースとなるメロディ・ラインは、いかにもヨーロッパ調のクラシカルかつ暗めのもの。
軽妙さと微妙な歪みのバランスする様子は、GENTLEGIANT 的。
2 曲目「Contraste(対比)」(6:32)
変拍子テーマをメインにさまざまなソロ、プレイをつないでゆくめまぐるしいインストゥルメンタル。
小気味いいリズム・セクションによる細やかなビートの上で、オルガンをフィーチュアしたスピーディな 16 分の 9 拍子のテーマ、ヴォーカル・ハーモニーやキーボードによるテーマから、奔放なソロへと激しく動いてゆく。
オルガンによる変拍子テーマは、限りなく EGG 風。
オルガン、エレピ、シンセサイザーなど、キーボードがテーマからオブリガートまで主として演奏をリードし、テンポや音量/調子の変化も目まぐるしい。
途中 8 分の 6 拍子のキーボードと 8 ビートのリズムが交錯するポリリズミックな場面や、ドラムレスの場面もあり。
刺激的なノイズや即興風のプレイなど、奇妙なエア・ポケットと快調なリズムで走るアンサンブルがギクシャクと交錯しつつ進む。
アナログ・シンセサイザーのソロ、無調風のギターのプレイとエレピの絡みなどはかなり挑戦的であり、レコメン調ですらある。
本格的な現代クラシックの素養があるのだろう。
キツ目のリズム変化の応酬を丸みのある音で包んだジャズロック・インストゥルメンタル。
GENTLE GIANT やアメリカのカンタベリー・フォロワーのセンスに近い、なかなか挑戦的な内容である。
3 曲目「Tritons(海神)」(8:15)オルガンを軸にしたオムニバス風のクラシカルな組曲。
クールにしてエキサイティングなオルガンがリードするジャズロック風の演奏によるオープニング「1 Parte」。
シャープなドラム・ビートがドライヴするジャジーで熱気あるオルガン・ソロがカッコいい。
演奏のリードがベースへと移り、ギターのトリルとオルガンの不気味なざわめきに導かれて「Estampas」へ。
即興風の不安げなブリッジである。
ロマンティックなチャーチ・オルガン・ソロからオルガン、ギターによる「Variaciones Sobre Un Tema De Tchaikovsky」へ。
チャイコフスキーをモチーフにしたオルガンのテーマとギターのオブリガートによる愛らしいアンサンブルである。
オルガンの高らかな響きにムーグも加わり、一層盛り上がる。
可愛いらしい THE NICE か EL&P といった演奏で迫り、最後はオルガンによる勇ましい行進曲のテーマ演奏へ。
終章「Conclusion」は、スタッカートでたたみかけるオルガンのテーマからベートーベン風の短いピアノ・ソロを経て、ムーグとオルガンが唸りを上げるエネルギッシュな演奏へと発展。
エンディングではコラール風のハーモニーも加わる。
暖色系のオルガンの音とモチーフの軽やかな処理が魅力である。
全体としては EGG のイメージに近い。
4 曲目「Dialogos(対話)」(6:42)。
エレクトリックなノイズが渦巻き、パーカッション、マリンバが即興風ながらも呼応しあう奇妙なオープニング。
やがてギター、オルガン、ベースと順繰りに 3 拍子のリフレインが重なってゆき、コーラスが最後の仕上げをすると、一気にミステリアスなアンサンブルへと発展する。
8 分の 3 拍子と 16 分の 9 拍子が、アクセントのずれのせいで複合的に聴こえる。
泣き声のようなキーボードの音が独特の浮遊感を漂わせ、クラシカルなオルガンとともにリズムは 4 拍子へと移る。
そして始まるは、アフリカンなエキゾチズムを漂わせるコーラスとイタリアン・ポップス風のヴォーカルによる「対話」。
オルガンのオブリガートやムーグとベースのかけあいなど、珍妙にしてやや不気味である。
またもファルセットのコーラスとなめらかなヴォイスの呼応。
中間部では、再びオープニングのように、3 拍子のギター・リフの上で、エレピ、ムーグ、マリンバらの即興が交錯する。
テンポが上がり、次第に増す緊迫感。
再びポリリズミックな演奏になる。
キーボードの断片的なフレーズがもつれ合う中から、ムーグが鋭いフレーズで浮かび上がる。
3 拍子を変拍子に聴こえさせる挑戦的なアンサンブルだ。
最後はヴォカリーズとともに、静かにフェード・アウト。
アクセントずらしによる複合的なリズム、ノイズなどで味付けした、抽象的なイメージの現代音楽風ユーロ・ポップス。
アヴァンギャルドながらも停滞せず、タイトなアンサンブルによるジャズロック風のスリル、キーボードのクラシカル・テイストが活かされているところがみごと。
5 曲目「Concerto Grosso(壮大なる協奏曲)」(9:52)は、4 パートから成る大作。
各章がクラシック風のスタイルを取りながら、スリリングな演奏を繰り広げてゆく。
まずは、怪しげなピアノのリフレインから始まり、オルガンとギターによるテーマが提示される「Tema Y Variaciones(テーマと変奏)」。
テーマに続く GENTLE GIANT 風のスピーディな追いかけっこアンサンブルが面白い。
続いてメロディアスなギター・ソロ。
ジャジーである。
緊迫したボトムと妙にメロディアスなギターの不調和も、どこかユーモラス。
ピアノによる 8 分の 6 拍子のリフレインからアクセントの強い決めが続き、やがて声高く叫ぶコーラスへと進む。
呪術的なコーラスから始まり、一転してアコースティック・ギターの柔らかな調べとともに歌われる、幻想的な「Aria(アリア)」。
繊細なヴォーカル・コーラスと柔らかなヴァイオリン奏法ギターが美しい。
静かに爪弾かれるアコースティック・ギター。
間奏は、ドリーミーなピアノとヴァイオリン奏法ギターである。
続いて、ぐっと官能的なエレピ・ソロ。
湧き上がるコーラス。
唯一素直な情感の感じられる場面である。
そして、ユーモラスなムーグに導かれるバロック風の軽快な「Rondo(ロンド)」。
オルガンによるテーマがキュートだ。
ムーグとオルガンが交互にテーマを歌っては、ユニゾンする。
重々しいピアノとともに短調へと転調し、ミステリアスなオルガンとピアノのデュオが始まり、緊迫感が高まる。
再び「Tema Y Variaciones」の追いかけっこアンサンブルが出現。
スピーディなハイハットの刻みが緊張を煽ってゆく。
ユーモアも孕んだ演奏だ。
叫ぶコーラス。
そして「Final(フィナーレ)」は、ティンパニ風のドラム・ロールからアンサンブル全体で 5 度の和音を繰り返す一瞬の交響曲風エンディング。
落ちつきなく不安を煽るようなアンサンブルをうまく用いた、奇妙な味わいの作品。
めまぐるしい変化に目も眩むような内容である。
キーボードを中心とした現代音楽調の技巧派プログレッシヴ・ロック。
変拍子を多用する鋭いリズム・セクションの上で、キーボード主体のアンサンブルがめまぐるしい変化を遂げながら走り回るスタイルである。
ヘヴィではない。
なんというかきわめて巧妙なやり口である。
とらえどころがない、うねうねとした演奏だが、間違いなく切れ味はある。
晦渋な演奏から、一転分かり易過ぎるクラシックのモチーフを突きつけるなど、意表をついた大胆さもある。
喩えてみるならカンタベリーや GENTLE GIANT だろう。
技巧的でスピーディ、なおかつ計算し尽くされたようなアレンジにもかかわらず、血の通った暖かみとほんのり明るいユーモアがある。
テクニカルなプレイの連続の中では、3 曲目のチャイコフスキーの処理の生む愛らしさや 5 曲目中盤の素直なリリシズムが非常に印象的だ。
また、4 曲目のヴォーカルとコーラスに若干エキゾティックな旋律があるものの、いわゆるスパニッシュ・テイストはない。
ややこじんまりとした感じはあるが、総じて似たグループを探すのが難しいくらいユニークな音である。
リズム・セクションは一級品。
(DIVUCSA 32-517)

| Santi Arisa | percussion, durms |
| Jordi Camp | bass |
| Marti Brunet | guitar, synthesizer |
| Manel Camp | piano, organ |
75 年発表の第四作「Minorisa」。
内容は、ジャズロック的な演奏をベースに、様々なモチーフ、アイデアを散りばめた前衛音楽である。
巧妙なユーモアとテクニック、卓越した音楽的情報量は、SAMLA MAMAZ MANNA や PICCHIO DAL POZZO と同等、もしくはそれ以上である。
突然変異的に現れたスパニッシュ・プログレを代表する傑作です。
1 曲目「Ebusus」(18:50)
ユーモラスにしてアヴァンギャルドなリフレインへの固執、リズミカルな変拍子アンサンブル、ノイズ、メタリックでヒステリックなテーマ、急転直下の曲調変化、お経のようなハーモニー、さまざまな SE などが、独特のユーモアと現代生活の狂気を浮かび上がらせる組曲。
破天荒な展開は、ほとんど SAMLA MAMAZ MANNA の世界である。
もっとも、SAMLA が民謡の影響を強く感じさせたのに対し、こちらはほとんど風土を感じさせない。
どちらかといえば、汎西洋音楽的な現代音楽=アヴァンギャルド・ミュージックといったニュアンスである。
メロディアスな部分もあるが、カタロニア独自のものというよりは、いわゆるクラシックやポピュラー音楽の断片として認識できる。
そして、きわめて無法な展開を繰り広げるにもかかわらず、技巧的であることは歴然としている。
中盤のリズミカルな演奏の切れ味は抜群だ。
基本的には、カットアップやコラージュの技法を駆使しつつも、素朴な抒情味とユーモアの感じられる、優れた現代音楽である。
フレットレス・ベース、ややチープなシンセサイザー、多用されるメロトロンの音が印象的。
ポップかと問われれば、自信を持ってその通りといえるから不思議である。
2 曲目「Minorisa」(10:57)
ノイズに近い音を巧みに織りあわせたミステリアスな導入部を経て、クラシカルなアンサンブルが手を変え品を変え、続いてゆくパロディ風の作品。
ジャズロック調のリズムも交じえながら、さまざまなテーマによるクラシック調のアンサンブルをあくまで維持してゆく。
キーボードによる狂言回しもおもしろい。
1 曲目よりはフレーズやモチーフが長続きする分、動くモザイクのようだった前曲ほど落ちつかない印象はない。
その代わり、悪戯っぽさも分かりやすい。
「Minorisa」と唱えるコラールですら、厳粛というよりは、パロディのニュアンスが感じられる。
前作までの流れの上にある作風である。
ここでもメロトロンは大活躍。
教会の鐘の音が不思議な効果を上げる。
3 曲目「Llaves Del Subconsciente」(8:06)は二部構成の作品。
「I Parte: Mente」
メロトロン、シンセサイザーらが位相系エフェクト下で揺らぎながら、エレクトリック・ピアノ、ハーモニクスとともに感傷的なテーマを繰り返す序章。スキャットのハーモニーもエフェクト下で毛羽立ったノイズと化す。
迸るような電子ノイズの中、テーマが浮かび上がるも、ファズ・ギター、管楽器風のシンセサイザーが新たなテーマを刻み始める。
ノイジーで人工的な音使いによる哀歌。
「II Parte: Cerebro」
電子音による反復パターンが重なり合う挑戦的な印象の作品。
ドラムスのみはアコースティックな音で調子を整えている。
無神経かつ無表情な電子音群は、のたくり、踊り続ける。
強弱、緩急の係り結びも覚束ない。
フレーズが反復とともに以前のフレーズを飲み込んでゆくさまは、下等生物による捕食のイメージである。
ノイジーで無機的なエレクトロニック・ミュージックであり、情動を廃した実験音楽である。
あまり心地よくはないが、試みとしてはおもしろい。
しかし、エンディングがこれでは、アルバムの評価を拒否しているようなものである。
初期二作のクラシックを取り込んだジャズロック・スタイルから一歩前進した、真のアヴァンギャルド・ロック。
テクニカルなアンサンブルをフル回転させてリスナーを引きずりまわす 1 曲目、パロディ精神豊かな 2 曲目、そして真剣な実験音楽たる 3 曲目のエレクトロニクス・ミュージック。
真正面から攻め込んでくる前衛精神満載の作品である。
(ariola 74321511512)
