イタリアのプログレッシヴ・ロック・グループ「THE TRIP」。 67 年英国人メンバーによって結成。 作品は四枚。 第三作以降、ドラムスにフリオ・キリコを迎えてキーボード・トリオ編成となる。 サウンドは、八方破れの現代音楽風キーボード・ロック。出自のせいか、初期はかなり英国風。

| Billy Gray | guitars, vocals |
| Arvid "WEGG" Andersen | bass, vocals |
| Pino Sinnone | drums, percussion |
| Joe Vescovi | organ, vocals |
70 年発表の第一作「The Trip」。
内容は、コーラスやギターなどにまだまだサイケデリックな匂いが残るオルガン・ロック。
VERTIGO や HARVEST などのクラシカル・ロックに通じる世界である。
いわば、GRACIOUS をもっと大胆に、アヴァンギャルドにした感じだ。
70 年頃にこういう作品を発表し、その後独創的なアルバムで花開くというグループは数え切れないほどある。
72、73 年あたりというのは、英国プログレッシヴ・ロックが最も輝いていた時代であり、イタリアン・ロックも百花繚乱の時代を謳歌した。
このグループもその例にもれない。
ヴォーカルは、最終曲以外は、英語。
「Prologo」(8:05)
オルガンをフィーチュアした実験色濃い作品。
序盤は、オルガンのノイズが延々続き、不安を誘う。
ギター、リズムが加わってからは、大仰だがシンプルなリフがドライヴするマーチ風のハードロック。
ジャジーな演奏も交えるも、唐突なフェード・アウト。
思わせぶりなオープニングのわりには発展せずに終わってしまい、現代音楽調のアヴァンギャルドさを強調した倣岸不遜な姿勢のみが印象に残る。
「Incubi」(8:17)
ロックの形式解体、再配置を目指したような不可思議な作品。
冒頭から、ロマンティックなヴォーカル・ハーモニーとギターによる、つぎはぎのような演奏であり、
ジャジーなオルガンがリードする快調な演奏も、突然断ち切られる。
中盤は、不自然なブレイクを多用したクラシカルなアンサンブルだが、そこへ即興風のオルガンが飛び込んで脈絡を崩壊させる。
正調英国ロック的な、悠然たるヴォーカル・ハーモニーとオルガンによる演奏が落ちつきを見せるのは、ようやく終盤になってからである。
ギターだって普通にやれば十分カッコいい。
壊しすぎである。
悪夢的な脈絡のなさの原因は、間違いなくオルガン奏者である。
「Visioni Dell'Aldila」(8:46)
クラシカルなソロをふんだんに盛り込んだオムニバス風の作品。
オルガン、ドラムス(ティンパニ)、ベース、ギター、それぞれがクラシカルなテーマを奏でる。
そして、つなぎが本格的なヴォーカル・ハーモニーとブルージーなソロという、主客逆転的な発想である。
各パートは英国ロックだが、この強引で大胆、アートでタガの外れたセンスは、間違いなくイタリアン・ロックのものである。
コワれた GRACIOUS です。
トーン調節でオルガンの音に変化をつけている。
「Riflessioni」(5:45)
ようやくまともな曲が現れた。
もっとも、発想はロックの歴史を綴るというユニークなものである。
エモーショナルなヘヴィ・ロックからスロー・ブギーを経てロックンロールへ、そして再びヘヴィ・ロックへと旅をして帰ってくる。
ひょっとすると、ロックンロールで楽しくやっても結局はヘヴィな現実に戻らねばならんし、へたするともっと暗くブルーになるぞ、という世知も込めているのかもしれない。
ヘヴィな演奏と甘めのヴォーカル・ハーモニーのコンビネーションがいい。
普通に演奏したらうまいじゃないの。
そこにとどまっていられないのが性であり、やれやれだが、そのおかげで、こうして後世においても忘れ去られずにいるのかもしれない。
「Una Pietra Colorata」(2:25)
イタリア語で歌われるクラシカルなヘヴィ・チューン。
ハードロックというには、妙なジャズ、ラウンジ調あり。
まともな演奏を断片化した後再構成するというアプローチによる挑戦的な作品。
ヴォーカル・ハーモニー、ギター、オルガン、リズムのどれもが、同時期の英国の一流グループと遜色ないレベルにある。
これだけの素材なら、きわめてまともなビート・ロックができそうだが、どうしても通常の脈絡に我慢ができないようで、ぶち壊すことで独自性を打ち出している。
曲調、リズム、メロディ、楽器の変化が、頻繁にそして予期せぬタイミングでおこなわれ、次第に不快感とフラストレーションが募ってくる。
聴いている方はたまらないが、リスナーがちょうど楽曲と同調し始めるくらいのタイミングで容赦なく予測不能の方向へ展開するという試み、悪意満々のしかけとしておもしろい。
まともなメロディも少なく、インパクトのあるフレーズをパーカッシヴに叩きつけるやり方である。
頭にはくるが、間違いなくプログレッシヴ。
メインの作曲者であるキーボーディストは、現代音楽の教育を受けた人なのかもしれない。
ちょうど最後の曲くらいで堪忍袋が破裂します。
怖いものみたさの方や、よっぽどこの時期のイタリアものに惚れ込んでいる人向けです。
(RCA 74321-26542-2)

| William Gray | electric & acoustic guitars, vocals |
| Arvid "WEGG" Andersen | bass, lead vocals |
| Pino Sinnone | percussion |
| Joe Vescovi | hammond organ, piano, church organ, mellotron |
71 年発表の第二作「Caronte」。
内容は、荒々しいロマンの迸りを叩きつけるオルガン・ロック。
どぎついファズ・ギターと、クラシカルというにはあまりにワイルドなオルガンをフィーチュアしたノイジーなヘヴィ・ロックの嵐から、メロトロンが響き渡るセンチメンタルでロマンチックな歌ものまで、英国流へヴィ・ロックにクラシカルなイタリア風味を交えた曲調が主だ。
THE NICE 直系のサウンドながらも、モッズ/サイケというルーツにある本家と比べると格段にニューロック/アートロック・テイストが強い。
音楽的な安定感のある荒々しさと、キメ過ぎで不安定極まるふらつき感の違いといってもいい。
しかしながら、全体的なプレイのできは十分本家に匹敵する。
特に、爆発力あるノイジーなオルガンのプレイは、パーカッシヴなタッチを若干抑えてはいるもののまさにキース・エマーソン直流である。
全体に耳を聾するような轟音が渦巻くだけに、オルガンのクラシカルなフレーズが一際映える。
そして、すべてに共通するのは、暴発気味の若々しいエネルギーである。
時代の空気をたっぷり吸って、自由奔放にプレイしている姿が目に浮かぶ。
青春のイタリアン・ロックであり、とめどない芸術の奔流である。
ギターとヴォーカルの表現は英国ロックの流れを汲むが、それを尖がったセンスでプログレ方面に流れを捻じ曲げるのは、まちがいなくキーボードである。
凶暴な音ながらも楽曲の性格付けについてインテリジェンスをもってプレイしており、奔放とはいえやや平凡なプレイへ傾きがちなファズ・ギターとのバランスを取って楽曲を充実させている。
本作でギタリストが脱退したのも分かるような気がする。
1 曲目はもろに THE NICE。
4 曲目はジミ・ヘンドリックスに捧げられたナンバー。
オルガンをバックにギターがクラシカルなメロディでむせび泣く。
荘厳なチャーチ・オルガンのプレイも効果的だ。
タイトルはギリシャ神話の「三途の川の渡し守」のこと。ジャケット・アートはダンテの「神曲」の挿絵がモチーフ。さすがイタリア。
ヴォーカルは英語。
「Caronte I」(6:45)スピーディで攻撃的なハモンド・オルガンとブルージーなファズ・ギターによる轟音サイケ。オルガンのフレージングはエマーソンそのもの。インストゥルメンタル。
「Two Brothers」(8:15)ノイジーなオルガンと丹念なベース・ラインが取り巻くミステリアスでブルージーなバラードから、メタリックなリフを叩きつける DEEP PURPLE 風の快速ハードロックへ。ヴォーカルが英語なのでイギリスのバンドのよう。
「Little Janie」(4:00)ピアノ、メロトロン伴奏のクラシカルで愛らしいラヴ・ソング。オルガンのオブリガートもいい。
「L'Ultima Ora E Ode A J.Hendrix」(10:18)フォーキーでメランコリックなバラードをクラシカルなアンサンブルへと発展させたプログレらしい曲。オルガンはジャズ・タッチの間奏を経て、ギターとのクラシカルなアンサンブルに進む。チャーチ・オルガンもざわめく。
「Caronte II」(3:32)渦を巻いて咆哮するオルガン、ベタなタッチで怪しく迫るファズ・ギター、鐘のように打ち鳴らされるハイハットが導くオルガン・ハードロック。
(RCA ND74299)
72 年発表の第三作「Atlantide」。
ギタリストが脱退し、ドラマーもフリオ・キリコに交代。
リード楽器はキーボードのみとなり、ここでピアノ、ハモンド・オルガン、エレクトリック・ピアノなどを用いた THE NICE 型キーボード・ロックが完成する。
猛ダッシュと急転回を繰り返すハモンド・オルガンと、手数だけなら世界有数のドラムスによる独特のせわしなさ、スリルは EL&P をさらにどぎつくデフォルメしたようなイメージだ。
本家との違いは、エレクトリック・ピアノを多用するところ、そして、オルガンの音色に過剰な変化を盛り込むところ。
性急でアグレッシヴなプレイの応酬とともに、意表を突くミステリアスな場面演出も冴えている。
即興的なアンサンブルが続くようでいて、意外とドラマチックな流れがあるのだ。
ヴォーカル・パートが英語なためにシンプルなブルーズ・ロックに聴こえてしまう点や、メロディが珍妙であるなど、やや物足りない面もあるが、音をひずませたオルガンとドラムスによる爆発力あるプレイには、しばらく呼吸することを忘れるでしょう。
即興的なプレイにやや冗漫なところがあるのが残念。
なにより、コワれた感じが魅力。
BMG の CD は残念ながら見開き変形ジャケではありません。
「Atlantide」攻撃性と神秘性を兼ね備えたスケールの大きいインストゥルメンタル。傑作。PINK FLOYD と EL&P の合体技。
「Evoluzione」普通のハードロックがドラムスとエレクトリック・ピアノ、ハモンド・オルガンのおかげで異様な怪しさを生み出す。
こういうエレクトリック・ピアノのオブリガートはありそうでなかなかない。
「Leader」裏拍を強調するリズムと珍妙なヴォーカル・メロディによる奇妙にねじれた感じがブリティッシュ・ロック風の怪作。
押しつぶしたようなオルガン・サウンド。
雰囲気とは対照的に、オブリガートは鋭く旋回し、ドラム・フィルも俊敏だ。
「Energia」
初期 KING CRIMSON 風の 8 分の 6 拍子による切迫感あるインストゥルメンタル。
サイケでジャジーなハモンド・オルガンのプレイが冴える。
終盤、中華風のピアノはガーシュインか。
「Ora X」黒っぽいヴォーカルをフィーチュアしたやんちゃなブギー。
思わせぶりなリズムとダーティなピアノ。
フィルやタム回しに異常なまでの迫力がある。
ノイジーなオルガンと静かなピアノが交錯するエキセントリックな展開だ。
「Analisi」哀愁のソロ・ピアノ、チャーチ・オルガンをフィーチュアしたトラジックな歌もの。
オルガンが高鳴り、ドラムスがボレロのリズムを刻むと NEW TROLLS のよう。エンディングも力強いボレロ。
「Distruzione」
トーン・ジェネレータが渦を巻く古めかしいオープニングを経て、パワフルなドラムスのリードで曲が動き出す。
前半はハモンド・オルガンとドラムスが肩を並べて暴れまわる攻撃的インストゥルメンタル。
後半は完全にドラム・ソロ。
ロール攻めなところはカール・パーマーと共通するが、こちらはメトロノーム並み。
それでも正直なところやや冗漫。
「Il Vuoto」メロトロン・ストリングスとオルガンを多重録音した、厳かで美しく哀しい終曲。
(BMG 74321-26552-2)
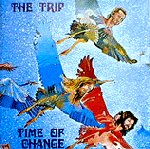
| Arvid "WEGG" Andersen | bass, vocals |
| Furio Chirico | drums, percussion |
| Joe Vescovi | keyboards, vocals |
73 年発表の第四作「Time Of Change」。最終作。
EL&P の向こうを張る、クラシカルかつジャジーにして過激な作品。
はちきれんばかりのエネルギーとテクニック、アイデアが、バランスした総決算的な内容だ。
旧 A 面を占める大作と小品 4 つから成る構成。
ヴェスコヴィのピアノとキリコのドラミングも堪能できる。
「Phapsodia」(20:02)
ガーシュインのミュージカルを見るような、軽やかでキュートな大作。
ジャジーなピアノ・プレイとミュージカル風のヴォーカル・パートなど、色とりどりの変化のある曲想を味わえる。
ヴォーカルがやや弱いようだが、後半のジャズ・クラブ風の演奏は実にユニーク。
プログレでガーシュインという着眼点がすごい。
即興的な展開にもかかわらず、破綻しないのも、イタリアン・ロックとしては珍しい。
キーボードを中心に演奏力は圧倒的。
「Formula Nova」(4:53)
モダン・ジャズのピアノ・トリオを爆発力のある演奏で破壊し、ぶッ飛ばす EL&P 的な過激さある作品。
ジャズをデフォルメして原色で塗りたくったアシッドなイメージは、強いていえば 60 年代のソウル・ジャズに近い。
8 ビートによるパワフルなジャズ・コンボに慣れると、今度はすさまじいムーグ・シンセサイザーのソロが待つ。
冒頭からハイテンションであり、そのまま最後まで押し切ってゆく。
ドラムスは、音が詰まり過ぎてかえって迫力を損なうのではと心配になるほど圧倒的。
ファズ・ベースもいいアイデアだ。
インストゥルメンタル。
「De Sensibus」(4:12)
ドラム・パーカッションのための作品。
いわゆるドラム・ソロではなく、神秘的なイメージを喚起する内容である。
あまりにメカニカルなロールやパーカッションのプレイにただただ唖然。
「Corale」(5:28)
チャーチ・オルガンやシンセサイザーの管弦楽、ヴォーカルをフィーチュアした作品。
正統的であるがゆえにかえって危なっかしく、そこがチャームポイントとなっている。
ベースは健闘するが、あまりに音色にデリカシーがなく、思わず失笑。
一方、シンセサイザーの多彩な音色やオルガンの演奏はみごと。
目指すはヴィヴァルディでしょうか。
同様なアプローチを英国のグループがやっても、こういうロマンチシズムは感じさせないだろう。
また危うさ加減は、PAR LINDH など近年のキーボード・ロックにも通じる。
やはりプレイヤーのルーツが同じということなのでしょう。
「Ad Libitum」(4:29)
ジャズ、クラシック、ブルースを行き交うピアノ・ソロ・ナンバー。
即興的でありながら自然な流れをもち聴きやすい。
ピアノの音の独特の存在感を思い知らされる。
このピアノ・ソロが最後の曲となったことは非常に示唆に富む。
音楽的な主導権を握ったキーボーディストが、これでもかといわんばかりにキーボード(特にピアノ)を駆使した作品。
ピアノのプレイは、クラシカルな本格派であり、そこへあえてジャジーな崩しも強調した表現を交える。
どの作品も分かりやすく、まとまりもあって、聴きやすいアルバムになっている。
音楽的な面白さという点では、やはりガーシュインをテーマにした最初の大作だろう。
さまざまなモチーフやフレーズが、タイトル通り奇想曲風に気まぐれに散りばめられており、即興としてのスリルとともに大河ドラマとしてのまとまりもある。
その他の各パートをフィーチュアした小曲もなかなかのでき映えだが、やはりこの大作が一番の聴きものだろう。
ひょっとすると本作は、すでにいわゆるプログレッシヴ・ロックは通過しており、クラシックとジャズの垣根を取っ払った一種のフリー・ミュージックに到達しているのかもしれない。
興味深いのは、アグレッシヴになればなるほどジャジーな演奏になり、情感を込めた演奏ではクラシカルなニュアンスが生まれること。
本作は、ロックとは何かを、改めて問うているのかもしれない。
EL&P とは異なる方向へと踏み出した、イタリアン・キーボード・ロックの傑作。
ヴォーカリストが英国人のためイタリア臭さはない。
キース・エマーソン好きには、お薦め。
(VM 008)
