
| Bill Pohl | guitars, bass pedals, vocals |
| John Livingston | drums |
| Matt Hembree | bass |
| Kurt Rongey | keyboards, vocals |
アメリカのプログレッシヴ・ロック・グループ「UNDERGROUND RAILROAD」。 96 年結成。 ギタリストのビル・ポール、キーボードのカート・ロンジを中心とするグループ。 ともにソロ活動で作品を発表してきた強者が、遂にグループで勝負に出たようだ。 2013 年 ギタリストのビル・ポールは、THINKING PLAGUE に加入したそうです。

| Bill Pohl | guitars, bass pedals, vocals |
| John Livingston | drums |
| Matt Hembree | bass |
| Kurt Rongey | keyboards, vocals |
2005 年発表のアルバム「The Origin Of Consciousness」。
ひさびさの第二作。
フェスティバル参加やソロ再発など、それなりに活動はしていた模様。
内容は、シリアスにしてキリリと冷気を帯びたテクニカル・シンフォニック・ロック。
音作りは、輪郭のはっきりしたきわめて現代的なものであり、いわゆる普通のメロディはどこにもないが、その音が生むアブストラクトな表情の裏側に、耽美で濃厚なロマンティシズムが垣間見える。
偏屈ながらも豊かな音楽の響きがあり、音数勝負といったレベルはすでに超えている。
衝撃的なシンセサイザーや全編で活躍する瑞々しくも鋭利なピアノ、技巧的なギターのリードでドライヴされるアンサンブルは、しなやかな骨格を備えつつも、おそろしいまでの切れ味がある。
スコアをベースにしたクラシック的な表現法であり、そういう意味で、きわめて技巧重視の構築的なロックといえるだろう。
キザというと語弊があるが、ストイックでスタイリッシュなイメージだ。
もう少しジャジーになれば TUNNELS ともいい勝負になる力があるが、そこはそれ、あえてロックのもつ小気味よさや過激さにこだわっているふしもある。
そこがユニークだ。
もっとも、ロックの特徴の一つであるルーズさはほとんどない。
クラシカルな表現が自然に収まっているのもそのせいだろう。
いわゆるテクニック志向のプログレ・メタル・グループですら、基本的にはロックンロールのグルーヴを根っこにもっていることを考えれば、このグループの独特の精密さはかなり特異である。
BRUFORD 直系の吹っ切れたフュージョン・ロックンロールのような楽曲でも、ノリよりはカミソリのような切れと厳密さを追い求める姿勢が感じられる。
暗黒ホールズワースなハイテク・ギタリスト、エマーソン/ポリーニ系超絶ピアニストなど、図抜けたタレントあっての内容だが、さらにすごいのは、そういった各人の芸を越えた地平にバンドとしての一体感があることだ。
また、往年の YES を思わせるみごとな余韻の引き方など、プログレにも精通しているところもおもしろい。
基本的な音楽センスが優れた人たちがスタイリッシュに迫るのだから、カッコよさの塊のような作品ができるわけである。
ヴォーカルのよさという基本的なポイントでも、他のテクニカル・シンフォニック・グループを大きく引き離している。
このヴォーカルが、怜悧でテクニカルな演奏にしっかりと潤いをもたせて、ロックとしての聴きやすさや入りやすさを保っている。(やはり ECHOLYN のリード・ヴォーカリストに似ていると思う)
サウンド・プロダクションもすばらしい。
個人的には今年度ベスト 5 入りは確実。まあ、あんまり明るくはないですが。ジャケットも怖いし。
「Julian Ur」(7:45)衝撃的にして技巧的、なおかつ相当に憂鬱な作品。抽象的なイメージが強い。
「Julian I」(2:38)無機的で凶暴なアヴァンギャルド・ヘヴィ・ロック。
変則的なリズムとガレージ風のヴォイス、モーダルなシンセサイザーがいびつに絡みあう。
調和や安定の対極にあり。
レコメン系に近い。
「Love Is A Vagabond King」(10:43)BRUFORD を思わせる快速シンフォニック・ジャズロック。
ただし、普通にジャズ/フュージョンらしく聴こえるのはテーマまでである。
中心となるギター・ソロはかなり変わっている。
ひょっとして難関フレーズの反復個人練習か? と思っていたら次第にロマンの花が咲き始める。
終盤は、現代音楽風のピアノがリード。
圧巻。
イェンス・ヨハンソンと比べるとドラマの作り方がうまいために、すさまじい変拍子の嵐にもかかわらず、耳に馴染みやすい。
エンディングの穏やかな表情もそれまでの展開あればこそである。
「Halo」(8:21)ピアノをフィーチュアしたアコースティックなタッチのバラード。
アコースティック・ギターとシンセサイザーによるクラシカルなアンサンブルが導く。
しかしながら、ピアノとギターが変拍子でこんがらがる間奏のすさまじいこと。
そこでの演奏は基本的に凶暴であり、無機的なエネルギーを放ちながら強烈にグラインドする。
SPOCK'S BEARD のように叙情的な表情を垣間見せるところもある。
その落差はすごい。
エンディングは美しいピアノ・ソロ。
「The Canal At Sunset」(4:18)アーシーにしてデリケートで若々しいアメリカン・ロック。
「普通の」オルタナティヴ・ロック調がカッコいい。
せつないヴォーカルにピアノが付き従う。
そういう点で ECHOLYN と共通しています。
「Metaphor」(2:57)べース、ピアノの低音が轟き、ギターがのたうつアヴァンギャルド・ロック。
インダストリアル調変拍子アンサンブルとメロディアスなヴォーカルのコンビネーション。
ギターは文脈に沿って超絶。
インテンシヴです。
「Creeper(The Doors Man. Pt 2)」(13:30)無調の込み入った、パワフルな演奏が微妙な表情の揺らぎを見せながら切実な物語を綴る。
もう一歩踏み込むと 5UU'S である。
中盤以降、渦を巻く変拍子の嵐に突入して超絶技巧が冴えるジャズロックへ。
リズム・セクションも大胆に活躍。
MARS VOLTA か PAIN OF SALVATION か。
音楽的な幅広さは本作随一。
「Julian II」(9:00)骨っぽく硬派な演奏と幻想神秘がコントラストする悪夢的なテクニカル・ロック。
珍しくオルガンが活躍。
激しく性急なリズム・チェンジなど、かなりアヴァンギャルド。
間違いなく、コンテンポラリーなサウンドで洗練された GENTLE GIANT です。
終盤リズムが入ってからは、すさまじい切れ味のジャズロックへ。
木で鼻をくくるとはこういうエンディングをいうのでしょうか。
(LDCD04)
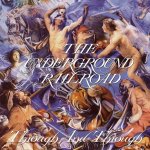
| Bill Pohl | guitars, guitar synthesizer, bass pedals, vocals |
| John Livingston | drums |
| Matt Hembree | bass |
| Kurt Rongey | keyboards, vocals |
2000 年発表のアルバム「Through And Through」。
4 年越しの作業を経て発表された第一作。
現代的な感覚のサウンドを使いながらも 70 年代プログレッシヴ・ロックの手法を活かした重厚な作品である。
アメリカンな爽やかさ、たくましさと神秘性が交わった作風は、新古典といって差し支えない高い完成度をもつ。
演奏は、エネルギッシュにして精密、硬質なパートと、幻想的でリリカルなパートを軽やかにゆき交う。
そして変拍子とともにギクシャクと逸脱してゆく感じが浮かび上がることもある。
大向こう受けする派手さこそないものの、テクニックは間違いなく超絶的。
ホールズワースを前衛的にしたような存在感あるギター・プレイとテクニカルなキーボード・プレイのコンビネーションは、BRUFORD、NATHAN MAHL の系譜にある。
また、無調のテーマは KING CRIMSON 的であり、リズムから逸脱したようなフレーズと深刻さと表裏一体の屈折したユーモア感覚はカンタベリー的ととらえることもできる。
そして、ライトだが複雑なヴォーカル・ハーモニーやダイナミックなリズムを重視したサウンドには、クレジット通り、ECHOLYN からの影響もあるようだ。
もっとも、ジャズ、ジャズロック、フュージョン・テイストをあからさまには感じさせない上に、精密すぎるプレイ、若々しいロマンティシズム、怪奇でシリアスな近現代音楽センスまでが自然に交錯するスタイルは、特定のグループの影響をそう易々とは云々できるものではない。
さて、音楽の背景に豊富な情報量を感じさせるなか、とりわけ特徴的なのは、スペイシーで神秘的な場面を活かした展開作りの巧みさである。
技巧を活かした、たたみかけるようなプレイの連続を売りにするグループは次々現れるが、これだけダイナミックにしてなおかつ繊細な語り口をもつグループは、そうは多くはない。
映像的なドラムレスのパートやスロー・テンポのシーンにおける際立った美しさ/幻想性は、U.K. や YES に十分匹敵する。
もちろん、アクティヴなパートでも、多彩なキーボードの音、超絶ギター、抜群のテンポ/リズム感覚を十分生かして、アンサンブルをしっかり練り上げている。
作曲センスとパフォーマンス力のバランスが取れているところは、ある意味、きわめてクラシカルであり正統的といえるだろう。
いかにも情報先進国のアメリカのミュージシャンらしく、アカデミックな姿勢に雑食性のセンスとタフネスがしっかりと備わっている。
2、3 曲目の巨大にしてダイナミックなインストゥルメンタル・パートから、ヴォーカルがピュアな若々しさを衒いなく見せる 4 曲目への流れは、かなり感動的だ。
要するに、技巧一辺倒ではなく、音楽としての基本がしっかりしており、とても聴きやすいということだ。
プログレ・メタルに対するオルタナティヴとして、凛と屹立するコンテンポラリー・プログレッシヴ・ロック。
7 拍子のリフがややわざとらしいくらいで、他に文句はありません。
最後を飾るタイトル・ナンバーは、ギター、キーボードがともに不思議なソロとアンサンブルを繰り広げる、幽玄かつアバンギャルドな超大作。
豊かで衝撃的な音楽。
グループ名は、奴隷の逃亡を援助した地下組織のことらしい。
このグループが気に入ったら、 BIRDSONGS OF THE MESOZOIC にトライする価値あり。
「May-Fly」(3:52)
「The Comprachicos Of The Mind」(10:28)瞑想的でありながらドラマのある傑作。
「In The Factory」(5:35)
「The Doorman」(10:05)
「Mars」(4:33)
「Through And Through」(20:13)チェンバー・ロック的な展開をもつ大作。
モダン・クラシック調のオープニング、エンディングに向けての展開がカッコいい。
(LE1033)
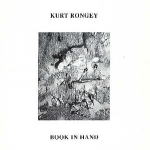
| Kurt Rongey | production, engineering, composition, performance, lyrics, design |
| Bill Pohl | guitar on 4 |
91 年発表のアルバム「Book In Hand」。
カート・ロンジのソロ第一作。
内容は、キーボード中心の陰影のあるシンフォニック・ロック。
深く冴え冴えとした音響とデリケートなメロディ、切れ味のいいキーボード・プレイが繊細にしてミステリアスな世界を提示している。
クラシックのバックグラウンドがあるらしく、明らかに現代音楽/音響的な表現(EGG の三作目など)があり、変則的なリズムのままフレーズが幾何学的な文様を成すところも多い。
しかし、そこへ切なくメランコリックなヴォーカルが加わると、シンフォニック・ロックなんていう怪しげなレッテルを貼るのを躊躇してしまいそうなくらい、立派なポップスとして響いてくる。
そこがすごい。
いかにも内省的な人柄が浮かび上がってきそうな、ひょっとしたらブライアン・ウィルソンやトッド・ラングレンが好きなのでは、などと妄想してしまいそうな音である。
実際、少しばかりネジの外れた感じもあり、たとえば、HAPPY THE MAN に通じるような調子もあるが、個人的にはキット・ワトキンスの作品よりも、こちらの方が音の感触が合う。
昔ならメロトロンを使ったようなところでストリングスがふわっと高まる。
そのストリングスが何ともいい。
一作品の共作とビル・ポールが一曲でギターを弾いている以外は、すべて一人でこなしている模様。
鋭角的なキーボード・ソロのタッチなど NATHAN MAHL の作品ともいい勝負だが、ヴォーカル込みでは完全にこちらの勝ち。
プロダクションこそ宅録風だが、静かに誠実に響いてくる美しい音楽である。
個性的なキーボード・ロック屈指の傑作。
こういうノスタルジックでメロディアスな表現と精緻な模様のような音配列が一つになった作風は、インディ/宅録系のアーティストに多いような気がする。ミュージシャンに必要な素地なのかもしれない。
製作レーベルは、「Long, Dark Music」というそうだが、この名前、自虐を越えた奇妙な自負が感じられないだろうか。
(LDCD1)

| Kurt Rongey | vocals, keyboards, programming |
| Bill Pohl | guitars |
2000 年発表のアルバム「That Was Propaganda」。
カート・ロンジのソロ第二作。
1991 年 8 月ソ連完全崩壊の端緒となったクーデターから着想したコンセプト・アルバムである。
政治、文明の転換点である事件に関わる随想を音楽で表現しようとする姿勢がクラシックの大家のようだ。(もっとも、職業的な音楽家というのは誰しもそうなのだろうが)
シンフォニックな作品からきわめて現代音楽的な前衛インスト作品まで、繊細な感性とセンスあふれる作編曲力に裏打ちされた傑作だ。
安易なロマンチシズムや甘さはないが、厳格で醒めた視線の裏に途方もない情熱が感じられる作風であり、それゆえに衝撃的なサウンドがコケオドシにならず、また絞り出すようなヴォーカルの切実さがより一層訴求力をもって迫ってくる。
いわゆる 70 年代ロック的なものが作者の原点にあるのかもしれないが、それ以上に、より本人のルーツに近いであろうアメリカン・ポピュラー・ミュージックや近現代クラシックの影響が現れていると思う。
また、無調性、変拍子による嵐のような展開もあるので、北米 RIO 系のファンにもお薦めしたい。
ヴォーカルがボブ・ドレーク似なので、もう少し音が荒々しいと 5UU'S に聞えそうだ。
前作に続いて力作です。カート本人によるコメントも参照してください。
冒頭の組曲「St.Petersburg」は、UNDERGROUND RAILROAD に直結する雄大なキーボード・シンフォニック・ロック。
ストリングス系の音とヴォーカルのセンシティヴな表情がいい。目まぐるしくもカラフルな展開とともにビル・ポールのギターもタイミングよく切り込んでおり、いかにもアメリカン・プログレらしい作品になっている。
緊張感ある和声が多用され、それらはそのまま他のシリアスな作品につながってゆく。
3 曲目「In The Know」は、キーボード・オーケストレーションを駆使した完全な現代曲作品。
4 曲目「Valutnaya」は、MAGMA、UNIVERS ZERO にも一脈通じそうな疾走型変拍子ロック。後半は ECHOLYN になって、それもカッコいいです。この作品も、UNDERGROUND RAILROAD にそのまま連なる作風だ。
5 曲目「Palach」は、重厚なクラシック作品。木管、弦楽、ピアノの音が美しい。
6 曲目「Kila」も同様のクラシカルな作品だが、人工的な電子音処理とアコースティック・ギターが加わっており、TANGERINE DREAM のようないわゆるシンセサイザー・ミュージック的なニュアンスもある。
8 曲目「The Interrogation」は、唯一ビル・ポールとの共作。KING CRIMSON 風ギター迷宮。
9 曲目「Desperation」は、パンキッシュなアジテーションと切り刻むようなキーボードが、メロトロンに吸いこまれるという過激な美学の感じられる作品。
(MMP 372)

| Bill Pohl | guitars, vocals |
| John Livingston | drums, percussion |
| Tom Main | keyboards on 2,3,5,6 |
92 年発表のアルバム「Solid Earth」。
ギタリスト、ビル・ポールのソロ作品。
内容は、ギター・プレイを中心にした耽美なるテクニカル・ロック。
少し聴けば爆発的なテクニックの持ち主であることがわかるが、本作品は、明らかに技巧を二の次にしてストーリー・テリングに重きを置いている。
無調や変拍子といったファクターを悪目立ちさせないエモーショナルなメロディ・ラインや攻め受けの流れのいい曲展開がある。
アルペジオや超速レガートなソロなどギターという楽器の特徴的な音を演出の一部として活かしながら、思いや物語をポップな味付けも付与しつつ語りかけている。
中性的な美声ヴォーカルも魅力的だ。
単に RUSH のファンなのかもしれないが、器楽の上に楽曲があるという、こういうバランス感覚はミュージシャンとして立派だ。
ホールズワースの技巧とスティーヴ・ハケットのような感性、イマジネーションを兼ね備えたギタリストといってもいい。
プロデュースはビル・ポール。
ノンクレジットだが達者なベースもポール本人のプレイなのだろう。
「The Fool pt.1」(2:51)
「Light Year」(7:13)
「Threshold Of Winter」(3:29)
「Bone Of Contention」(4:22)
「New Frontier」(4:26)
「The Incognizance」(8:35)GENESIS、KING CRIMSON、MAHAVISHNU ORCHESTRA の影響が感じられるサイケデリックなプログレッシヴ・ロック。
「Solid Earth」(6:52)アナーキーかつ抒情的な佳曲。そこだけならチャートインしそうなメイン・パートとプログレ感性の強すぎる間奏部のギャップがスゴイ。
「The Fool pt.2」(2:47)
(LDCD2)
