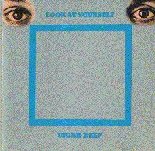URIAH HEEP
イギリスのハードロック・グループ「URIAH HEEP」。
66年 結成。
初期のサウンドはギター、オルガン、ヴォーカル・ハーモニーをフィーチュアした劇的なアレンジによる神秘幻想趣味が横溢するハードロック。
Very 'Eavy, Very 'Umble
| David Byron | lead vocal |
| Ken Hensley | organ, slide guitar, mellotron, piano, vocals |
| Mick Box | lead guitar, acoustic guitar, vocals |
| Paul Newton | bass, vocals |
| Ollie Olsson | drums,percussion |
| thanks to... |
|---|
| Alex Napier | drums on 1,2,3,6,7,8 |
| Colin Wood | keyboards on 3,8 |
70 年発表の第一作「Very 'Eavy, Very 'Umble」。
内容は、憂いある英国ロックにヘヴィかつメタリックなサウンドを合体させた新しいハードロックである。
ブルーズ・ロックとはニュアンスの異なるヘヴィなロックには、凶暴さや荒々しさにとどまらないセンチメンタリズムがあり、いわばインテリ調耽美主義ともいうべき新しさを感じさせる。
イギリス盤の不気味なジャケットにも挑戦的な姿勢がうかがえる。
音楽的な中心メンバーはボックス、バイロンのコンビであり、後に主導権を握るヘンズレイはいまだプレイヤーに徹している様子だ。
演奏面の特徴は、ファルセットを駆使するヴォーカルとスキャットによるハイトーンのハーモニー、徹底してけたたましいギター、マグマのように胎動し爆発するハモンド・オルガン。
これらのコンビネーションを攻撃的な場面やエモーショナルなバラードなどで巧みに使い分けた、じつにドラマティックな作風である。
リフやメロディ・ラインのセンスもいい。
クラシック、ジャズ、ブルーズ、R&B といったスタイルの吸収にとどまらず、それらをくすんだ独自の色でまとめているところがすごい。
いい形でサイケ、アート・ロック的なスタンスを残している面もある。
DEEP PURPLE よりも、ストレートなポップ・センスが洗練されていると思う。
英国ロックらしい屈折した美感をそのまま残した様式化以前のハードロックの傑作。
H を発音しない奇妙なタイトルは、グループ名になっている「デイヴィッド・コパーフィールドの登場人物」の口調の癖らしい。
VERTIGO レーベル。
プロデュースはジェリー・ブロン。
「Gypsy」(6:38)
ギター、オルガン、ハイトーンのコーラスが一体となって描く濃厚なロマン、そしてそれをハチャメチャにぶっ壊すことにいささかの躊躇いもないプログレッシヴなハードロック作品。
冒頭から変拍子による挑戦的なギター・リフを突きつける。
序盤は、コンプレッサでつぶされ凶暴な無機性で迫るリズム・ギターとシャープなナチュラル・ディストーション・トーンのギター、唸りを上げるオルガンらによるスピーディなインストゥ
ルメンタルである。
メイン・パートはずっしりと重い。
ヒステリックなファルセットが特徴的なハイトーン・ヴォイスが重厚な泣きのメロディをクールに抑えて表現する。
間奏部では爆発的なオルガン・アドリヴ。
アドリヴに続くフリーフォームの演奏は、サイケ時代の遺産なのだろう。
ボックス/バイロンの作品。
「Walking In Your Shadow」(4:31)
ZEPPELIN や FREE に近しいセンスを感じさせるリフ一発のスタイリッシュなハードロック。
シンプルなリフのヴァイヴレーションを再認識できる内容だ。
この曲の主役はオルガンではなく歯切れのいいリフを放つギター。(ヘンズレイもギターを演奏しているようだ)
ソロは、ペンタトニックによるオーソドックスなもの。
こまめなツイン・ギターの絡みもいい。
雄々しさと爽やかさのあるリード・ヴォーカルはニュートンか。
ニュートン/バイロンの作品。
「Come Away Melinda」(3:48)
メロトロンをフィーチュアしたアコースティック・ギター弾き語りの哀愁バラード。
イントロのフルート、伴奏/間奏部のストリングスなどメロトロンを多用している。
ささやくように密やかなヴァースを経て、コーラスでは一気にシンフォニックな高まりを見せる。
父と娘が亡き母親を語る内容であり、会話を表現するように、左右のスピーカにヴォーカルが交互に現れる。
沈痛な表情から伸びやかで厳かな歌唱まで、ヴォーカルの表現力に注目。
作曲は へラーマン/ミンコフ。
アメリカのフォーク・グループ THE WEAVERS による反戦歌のカヴァー。
「Lucy Blues」(5:08)
ピアノが印象的なシカゴ・スタイルのブルーズ・チューン。
ベース・ラインはどっしりと動き、翳を引きずりつつも艶っぽいヴォーカルが冴える。
間奏のオルガンも絶品。
ルーズさよりも引き締まった重みと渋みがあるところが、本場とは異なる英国らしさだろうか。
ギターはナチュラル・トーンによるオクターヴの控えめなソロで後半を支える。
後の作品では見られないだけに貴重なブルーズ・ロックである。
ここまで、A 面の 4 曲でこの編成の器用さがよく分かる。
ボックス/バイロンの作品。
「Dreammare」(4:40)
メタリックなサウンドが洗練された印象を与える HM の前身風ハードロック。
クラシカルなオルガン、絶叫型ギター、金属的なヴォーカル・ハーモニーが一体となって、引きずるような重さと稲光のような鋭さを合わせたパフォーマンスになっている。
ヴォーカルに突き刺さるギターのオブリガートや「lalalalala」というコーラスにソロ・ギターが狂おしく絡みつくところは、あたかも ZEPPELIN と PURPLE の合体のような強烈なイメージ。
ニュートンの作品。
このグループの特徴が活かされた佳曲である。
「Real Turned On」(3:38)
シャフルのギター・リフがドライヴする DEEP PURPLE 系ファンキー・チューン。
リフを刻むリズム・ギターと渋めのアドリヴで迫るリード・ギター。
間奏部の決めどころでは、二つがすっと一体となってツイン・リードを放つ。
シンプルだがギターのサウンドを活かしたハードロックらしい作品である。
エンディングのフィードバックなど、ライヴ風のアレンジもおもしろい。
ボックス/バイロン/ニュートンの作品。
「I'll Keep On Trying」(5:35)
このグループ固有のへヴィにして哀愁あるサウンドを核に急展開で意表をつくプログレッシヴなハードロック。
特に、中間部の叙情的でオプティミスティックなイメージのパートへの展開がキーとなる。
ハイトーンのスキャットとオルガンによる哀愁のサビ(このグループの基調をよく表現している)を印象付けるも、ヒステリックなギター・リフが主導するけたたましい演奏で雰囲気をひっくり返し、メインパートは、ヘヴィなギター・リフでオーソドックスに迫る。
先の予想のつかない展開だ。
けたたましいワウ・ギターの乱舞とともにいつしかへヴィ・ロックへと回帰し、あれよあれよという間に終末へ。
こうした無理矢理な急展開はイタリアン・ロックの得意技である。
1 曲目で訴えたこのグループの特徴を自らメタ視して翻弄したような作品である。
ボックス/バイロンの作品。
「Wake Up(Set Your Sight)」(6:26)
幻を追ううちに生の雄々しさが薄闇にとけてゆくようなロマンティックで劇的な作品。
ピアノとギターのビートで軽やかに走るジャジーでリズミカルなメイン・パートから、霧のかかった薄暗い世界をさまようバラードへと劇的に変化する。
ベースライン、ベースのオブリガートがカッコいい。
キーボーディストがコリン・ウッドであることから考えて古いレパートリーなのだろう。
メロトロンと爪弾くようなギターによる消え入りそうに神秘的な間奏部から穏やかなヴォーカル・パートへの展開には、喩えようのない哀愁があり、そこからプログレ王道の風格が浮かび上がる。
ハードロックという様式を得る直前のアートロックであり、CRESSIDA と同じ味わいの英国ロックらしい作品だ。
個人的には大好きな音です。
ボックス/バイロンの作品。
(VERTIGO 6360006 / VICP-2079)
Salisbury
| David Byron | lead vocal |
| Ken Hensley | organ, piano, electric & slide & acoustic guitar, harpsichord, vibes, vocals |
| Mick Box | lead guitar, acoustic guitar, vocals |
| Paul Newton | bass, vocals |
| Keith Baker | drums |
71 年発表の第二作「Salisbury」。
ドラマーは、元 BAKERLOO のキース・ベイカーに交代。
ケン・ヘンズレイが作曲に進出し(オルガンのプレイはややおとなしいように思う)、独自の様式的な叙情性を披露している。
16 分にわたるタイトル曲など管弦楽を駆使した独創的なアレンジはヘンズレイに負うところが大きそうだ。
他の楽曲も、キーボードの積極的な使用やヴォーカル表現の多彩さ、ジャズや現代音楽への接近などによって音楽的な広がりが出るとともに、それらを的確にまとめて盛り込んで曲想を正しく表現できていると思う。
バラエティに富むところもいい。
また、冒険的なアレンジやドラマティックな大作の提示と同時にキャッチーな曲作りという点にも重きをおいていそうだ。
一方、前作のような英国ロックの風土病のようなくすみや翳り、へそ曲がりなところは、洗練されるかオミットされてあまり見られなくなった。
それでも、いわゆるハードロックという完成した枠組みにはいまだあらず、古典的なロマンチシズムや荒々しい芸術性が挑戦的な姿勢のままで渦巻いている。
頭でっかちでもそこが魅力だろう。
全体のトーンの統一性は前作ほどではない(メンバーも安定しないまま突貫工事したにもかかわらず独特の色合いでまとまった前作が奇跡的というべきか)ものの、一つ一つの楽曲に安定感があり、多少の枝葉はあるが、曲想をきちんと表現した完成度がある。
それにしても注目すべきは、旧 B 面 2 曲目の超大作である。
これ 1 曲に力を注いだために他が手薄にとまではいわないが、この作品を世に出すための本アルバムだったことは間違いないだろう。
VERTIGO からの第二弾。プロデュースはジェリー・ブロン。
「Bird Of Prey」(4:13)
粘っこくもスピード感とキレのあるハードロック。ヴォーカルはファルセットのハイトーン。
誰も勢いを止めない。終盤のセクシーな R&B っぽい展開は意外。
ボックス/バイロン/ニュートンの作品。
「The Park」(5:40)
憂鬱で美麗なるスローバラード。ハープシコードのざわめきにファルセットがデリケートに震える。
少女マンガ的英国浪漫の世界。
ブリッジ風に挿入されたジャジーなアドリヴ風のパートが面白い。冷たくにじむヴァイヴも効果的。ヘンズレイの作品。
「Time To Live」(4:01)
ワウ・ワウ、コンプレッサでのたうつギター、火を吐くオルガン、イアン・ギラン風のパワー・ハイトーンから裏返るファルセット・ヴォイスが冴え渡るミドルテンポの堂々たるハードロック。
荒々しいパワーコードのリフを放つギターとオブリガートするオルガンが絶妙の均衡で吠えるところは火のように吠え、抑えるところはストイックに抑えを効かす。
気高く重厚な佳曲。
ボックス/バイロン/ヘンズレイの作品。
「Lady In Black」(4:43)
アコースティック・ギターのラフなストロークが似合うトラッド調のバラード。
不器用だが誠実な脚韻、武骨なリズム、薄暗いメロトロンの響きに包まれた、素朴でやるせない雰囲気がいい。
ヘンズレイの作品。
「High Priestess」(3:40)
ハーモニーを活かした軽快なロックンロール。
スティール・ギターの官能的なイントロやツイン・ギターのオブリガート、アドリヴはもう少し細身であれば、WISHBONE ASH と間違えるであろう。
こうなると、サイケデリックなファルセットのエコーとこもり気味で開放感がいまひとつサウンドに違和感があるが、これが個性である。
B 面 1 曲目なので気分一新か。ヘンズレイの作品。
「Salisbury」(16:17)
ブラス・セクションを大幅に導入した大作。
壮麗なイントロダクションに導かれ、メランコリックなヴォーカルとオルガンのリードによる哀愁のテーマを掲げつつ、ブラス・セクションの咆哮に支えられてビッグバンド・ジャズ風のドラマティックな展開を繰り広げる。
ハイ・テンションのブラス・ロックは直線的な第二テーマとともにクラシカルな高まりを見せるも、オルガンが主導権を握るとベース・ランニングとともに 4 ビートっぽいジャジーなムードに変転する。
4 ビート・ジャズにシャープな第二テーマが重なってアンサンブルは煮えたぎる。
ギターの出現をきっかけにオルガンが再び変転を促して、クラシカルな管楽器とともにエネルギーをため込んだ長い助走へと入ってゆく。
ヴォーカリストによる哀愁の歌唱が寄り添うと演奏は繰り返しごとに雄大なスケールへと広がり始める。
ワウワウギター・ソロの開始とともにロックなシャープネスと分厚い管楽器群のリードするアンサンブルが拮抗し、得意のファルセットのヴォカリーズも加わって、対比を成しつつこれでもかとドラマティックに盛り上がり続ける。
重厚華麗で壮大なハード・ロック絵巻。CRESSIDA などと同じく正統 VERTIGO オルガン・ロック路線。ボックス/バイロン/ヘンズレイの作品。
(VERTIGO 6360028 / VICP-2080)
Look At Yourself
| Ken Hensley | organ, piano, electric & acoustic guitar, vocals on 1 |
| Mick Box | lead guitar, acoustic guitar |
| David Byron | lead vocal |
| Paul Newton | bass |
| Ian Clarke | drums |
| guest: |
|---|
| Manfred Man | Moog on 3,4 |
| Loughty Amao (OSIBISA) | percussion on 1 |
| Teddy Osei (OSIBISA) | percussion on 1 |
| Mac Tontoh (OSIBISA) | percussion on 1 |
71 年発表の第三作「Look At Yourself」。
タイトル曲のヒットに伴って人気を決定付けた作品。
ドラムスは本作から元 CRESSIDA のイアン・クラークがつとめる。
ヘンズレイの作品が大半を占め、音楽的なリーダーシップは彼に移ったと見ていいだろう。
作風の基本は、ブルース色のないへヴィでメタリックなサウンドにオルガンがクラシック・テイストを持ち込むハイ・テンションのハードロックである。
ハードな曲調にも清々しさとメランコリーがあるところが独特だ。
オルガンを活かしたへヴィ・ロックとしてのクオリティは前作を凌ぐ。
オルガンと対比させたシンセサイザーによるアクセントもいい。
「対自核」という邦題はまったく理解不能だが、意味のない漢語に訳もなくカッコよさを感じてしまう辺りが日本人のアタマの悪さである。
ハードロックの名盤。
BRONZE レーベル。プロデュースはジェリー・ブロン。
1 曲目「Look At Yourself」直線的なブギー。
シャフルのリズムで進みへヴィでノリもいい。
クラシカルなオルガン、シンプルかつルーズなギター・リフ、シンプルなギター・ソロと、プリミティヴだが魅力的というロックの王道を行っている。
叩きっ放しのドラムスとオルガンの和音が次第にテンションを上げていき、クライマックスで爆発する。溜飲の下がるカッコよさだ。
2 曲目「I Wanna Be Free」
ヘヴィなギター・リフで幕を開け、遠く響くオルガンのバッキングで清々しいコーラスが意外なオープニング。
ヘヴィなリフを叩き付けてもヴォーカルのメロディ・ラインはどこか若々しくピュアである。
ギター・ソロもオーヴァーダブはあるがストレートでスカッとするようなソロだ。
ギターのギミックが冴えヴォーカルと絡むソロもシャープである。
鮮烈。
3 曲目「July Morning」
クラシカルなオルガンのアルペジオで始まりリズムとともにヘヴィなギターがヒステリックに食い込む。
オルガンが余韻を残して去ると静かなアンサンブルに沈んだヴォーカルが入る。
抑えた叙情が切ない。
ドラムスが叩きまわってヘヴィなギターとオルガンがバッキングで頭をもたげるがヴォーカルはクールである。
オルガンのソロは切なさをストレートに表現するすばらしい響き。
ハイトーンでシャウトするヴォーカルからギターの抑えたソロへと落ちるところもすばらしい。
オルガンとギターのユニゾン・リフレインも感情を抑えたところがあってクールである。
延々と続くエンディングも渦に巻き込まれるような錯覚を憶えてすばらしい効果をあげている。
クラシカルなリフレインに加えてムーグのソロもエンディングをエレクトリックなギミックで華麗に飾り幻想的な効果を出している。
全体にはヴォーカルの表現力が曲をリードしているといってよく終わった後も聞き手に何かを残してゆくナンバーだ。
名曲。
4 曲目「Tears In My Eyes」
素っ頓狂なギター・リフで始まるナンバー。
スピード感にあふれるナンバーだ。
早口ヴォーカルがカッコよい。
リフが退いてからのアコースティック・ギターの響きやオルガンの効果音のようなスペイシーな音色そしてスキャットは思いっきりスペース・ロックしている。
ギターとアコースティック・ギターの掛け合いからブレイクしてギター・ソロヘ突入すると喧しいギターの独壇場だ。
とにかく中間のスペース・ロックしているところがすばらしくカッコよい。
ギター・ソロはまあこんなもんでしょ。
ヘヴィネスやスピード感も素敵。
これは現代の HM に通じるものを感じる。
5 曲目「Shadows Of Grief」
ギターとオルガンの決めが三発入ってクラシカルでスピーディなオルガンとスキャットが始まる。
そのままヘヴィなリフに変ってヴォーカルは叫ぶ。
バッキングのオルガンは狂ったように弾きまくっている。
引きのオルガン・ソロはドラムスとの壮絶な掛け合いに発展しアンサンブルは前以上にスピードアップする。
ギターは走るアンサンブルに乗って華麗に三連を決めオルガンも一緒に走り出す。
疾走するアンサンブル。
決めの連続。
突如すべてが消えて静かで不気味なスキャットとオルガンの響きが満ちはじめ徐々にドラムス、ベース、ギターが戻ってくるとスキャットは壮絶なハイトーン・シャウトに変化してゆく。
ギターのノイズが唸りオルガンがクラシカルなソロを奏ではじめるとドラムスと共にハードなリフが戻ってヴォーカルが叫びアンサンブルが復活する。
オルガンが狂ったように和音を響かせるとあたりに轟音が湧き上がりドラムスは叩きまくりオルガンがスペイシーな SE のように空中に音をちりばめる。
最後は再びシャウトが天から降って来てシンバルが響き決めが入って余韻を残し去ってゆく。
リフとスピード命と見せかけて実は帰ってこないかと心配させるほどの凄い引きを備えたアナーキーな構成で迫る超大作ヘヴィ・メタリック・プログレッシヴ・ナンバー。
オルガンや三連のリフレインはバロック音楽風。
6 曲目「What Should Be Done」
ピアノ伴奏のバラード。
ワウ・ギターのバッキングもよいしコーラスも良し。
しかし何よりヴォーカルの存在感と枯れた感じがすばらしい。
トラッド・フォークの影響を感じる。
7 曲目「Love Machine」
オルガンの荘厳なオープニングはアグレッシヴなリフに変りリズムが入ってギターが食いつき一気に攻撃的なアンサンブルになる。
ヴォーカルも後乗りリズムで快調に飛ばす。
ギターのオブリガートも冴えまくる。
クリアでストレートなギター・ソロ。
あんまり素直でシンプルな乗りなんであきれるほどだが格好いいのだ、なぜか。
オルガンのアルペジオもファンキーである。
3連符のフレーズでブレーキがかかると轟音が轟きエンド。
シンプルでかっとんでいくナンバー。
「新しさ」から出発したグループによるさらなる「新しさ」を感じさせる傑作。
すべてのプレイがスケール・アップし曲のヴァラエティも一層広がりを見せる。
キャッチーにしてオリジナルな筋が一本通った名曲の連続にはもう唖然。
スピーディでハードなタイトル・ナンバーや間違いなくプログレッシヴ・ロックといえる「Shadow Of Grief」、ハードな展開の中にもメランコリックなメロディが美しいバラードの「July Morning」、純正バラードの「What Should Be Done」など珠玉の作品ばかりである。
もしかすると DEEP PURPLE というライバルあっての音楽レベル向上かもしれないがその結果はとてつもないものとなった。
セカンド・アルバムの方向をきっちりと進化させたという意味ではみごとな成功でありファースト・アルバムのもっていたどこへゆくのかわからない不気味な迫力も「Shadow Of Grief」のような作品にまだまだしっかり息づいている。
新しさとともに均整もとれた屈指の名盤。
(ILPS 9169 / VICP-2081)
Demons And Wizards
| Gary Thain | bass |
| Lee Kerslake | drums, percussion |
| Mick Box | guitars |
| Ken Hensley | keyboards, guitars, percussion |
| David Byron | vocals |
| guest: |
|---|
| Mike Clarke | vocals(1) |
72 年発表の第四作「Demons And Wizards」。
ベースとドラムスがそれぞれゲイリー・セインとリー・カースレイクに交代。
音楽的にはヘンズレイがリードしているようであり「Easy Living」のようなコマーシャル・ヒットも放つ。
前作で完成したクールで整合感のある個性的ハードロックを充実させると同時に主題としてややファンタジックな路線を打ち出しアコースティックなサウンドの取り込むなど積極的に新しいことに挑戦する雄姿がまぶしい。
セカンド・アルバムで頂点を極めたあとにも深化を続けた ZEPPELIN を思わせる。
ジャケットも幻想的なロジャー・ディーン風の作品となっておりここにもより一層サウンドをプログレッシヴな方向へと推し進めたいという意図が見えるように思う。
トータル性に加えて大作主義も新機軸のアイデアではないだろうか。
実際のサウンドは前作で顕著だった様式的ともいえるメロディ・ラインにヘヴィなギターとオルガンが絡むというパターンからややクラシカルでリリカルにそしてアコースティックに変化。
それでも独特の構築性とメタリックな軽快さをもったハードロックは健在。
ピアノやアコースティック・ギターがハードなサウンドとの対比で一層輝いている。
ただし詩的な色合いとともに、全体にいく分か軽さとウェットさが増している。
オープニングの「The Wizard」(3:01)はアコースティック・ギターがリスナーの度肝を抜いたであろうことは想像に難くない。
アメリカ風のアーシーな味わいもあるナンバーだ。
しかし続三曲「Traveller In Time」(3:24)、「Easy Living」(2:36)、「Poet's Justice」(4:14)は HEEP らしい芸風のハードロックである。
特に 4 曲目のファルセットのスキャットはバイロンの真骨頂だ。
続く「Circle Of Hands」(6:25)は教会風のオルガンとコーラスが宗教的な高揚感を呼びさますナンバー。
ロック的なパワーと迫力も備えておりクラシカルな音を巧みに用いてギターが生き生きと歌い上げている。
しかしながらメロディ・ラインは 1 曲目同様ややアメリカン・ロック風である。
スチール・ギターやピアノも用いたドラマチックな名曲だ。
「Rainbow Demon」(4:25)は中華風のオルガンによるオープニングが印象的なナンバー。
粘りつくようなヘヴィなリフが迫るミドルテンポのダークなハードロックだ。
タイトル通り呪術的なムードである。
そして「All My Life」(2:45)は一転してメタリックなギターがあおりたてる軽快なブギー・ナンバー。
サビのコーラス、ヴォーカルのシャウトはいかにもである。
ピアノの軽やかな伴奏が新鮮だ。
ヘンズレイ一色へ染まった B 面でのささやかな挑戦か。
終盤を飾る「Paradise」(5:06)と「The Spell」(7:35)はまたもアコースティック・ギターのストロークから始まる幻想組曲。
怜悧なヴァイブとフォーキーなヴォーカルに浮かび上がるほのかなジャズ・テイストが新鮮だ。
アコースティック・ギターの伴奏が鳴りつづけシンプルな繰り返しが続くうちに演奏は次第に重みを持ち始めクロス・フェードで一気にピアノのビートに導かれた快速ロックンロールへと変貌する。
左右のチャネルから交互に入るヴォーカルがカッコいい。
クラシカルなピアノ・ソロを経てコーラスとともにギターがメロディアスに歌い上げるシンフォニックなクライマックスへ進む。
こういう展開は今までにはなかった演出だ。
再びリリカルなピアノとともにヴォーカルが切々と歌い上げる。
ピアノとオルガンがテンポを上げ再び軽快なロックンロールの終章へと流れ込む。
ラフでイージーなロックもこういう位置におかれると不思議な味わいがある。
様々な新機軸と驚きをリスナーにぶつけており前作の延長を期待すると大きく裏切られることになるだろう。
とはいえ終曲のシンフォニックな高揚は大作を標榜したヘンズレイの思惑通りではなかったのだろうか。
全体に、アコースティック・ギターとピアノの多用、軽快な分かりやすいいわゆる「ロックンロール」、シンフォニックな音使いでテーマ性をもった楽曲をまとめること、この三点が新たな面として加わっているようだ。
同じ大作でも「Salisbury」や「Look At Yourself」で見られたようなジャズや現代音楽の注入というアヴァンギャルドなアプローチではなくいわゆるキーボード・オリエンテッドでクラシカルな「プログレ的」手法が用いられていることが興味深い。
時代の流れの反映でありスタイルの模索の結果ということなのだろう。
プログレ絶頂期でありなおかつ英国ロックにはや様式化の波がさざめいていたということか。
(ILPS 9193 / VICP-2082)
The Magician's Birthday
| Gary Thain | bass |
| Lee Kerslake | drums, percussion |
| Mick Box | guitars |
| Ken Hensley | keyboards, guitars, Moog synthesizer |
| David Byron | vocals |
| guest: |
|---|
| BJ Coile | steel guitar(7) |
72 年発表の第五作「The Magician's Birthday」。
完全に前作のコンセプト・トータル性路線を継承した作品。
サウンド的には前作で試みられた実験ともいうべき新たな試みがようやく楽曲へ定着した印象を与える。
出来不出来はあるもののまたもや新生 HEEP サウンドといえる音楽である。
いわゆるハードロックは 1 曲目のみになったといっていいだろう。
ハイトーンのヴォーカルもほとんどなくなった。
残りのナンバーはすべて何らかのチャンレンジが感じられ「Look At Yourself」の世界からは随分と距離ができたようだ。
ムーグの積極的な使用も本作からだ。
「Sunrise」は様式的なメロディとコーラスそしてヘヴィなギター、オルガンが怒涛のように押し寄せる正統HEEP節ハードロック・ナンバー。
ノイジーに唸りをあげるバッキングを従えた美しくもクールなコーラスが決まっている。
ドラムスのラウドな叩き方にも注目。
「Spider Woman」は DEEP PURPLE の向こうを張ろうかというロックンロール。
キャッチーなリフと弾むような軽快さは、「Look At Yourself」、「Easy Living」路線である。
「Blind Eye」はツイン・ギターのハーモニーによるテーマとアコースティック・ギターのコード・ストロークが印象的なナンバー。
前作辺りから見られるようになったタイプのヘヴィ・ロックとは一線を画す曲である。
軽めのシャフル・ビートにもかかわらず軽快というよりはヨーロッパ風のフォーク・タッチのメランコリーが漂う。
「Echoes In The Dark」前作同様ピアノを用いシンセの電子音が舞うなかにウェットな情感を込めたナンバー。
スライド・ギターの「泣き」が独特の哀感にあふれている。
シンセのギミックはやや唐突だが「泣き」一辺倒にしないための工夫・アクセントかもしれない。
シンセとコーラスそしてピアノが盛り上げてギターが切々とメロディを刻んでゆくドラマチックな作品。
オルガンも加わるサビの広がりは感動的だ。
「Rain」ピアノとヴィブラフォンで描かれるドリーミーなバラード。
歌メロは密やかな美しさをもちセンチメンタル。
バラードでのバイロンの表現力はシンプルなバッキングにもかかわらず堂に入ったもの。
今までにないタイプの作品だ。
「Sweet Lorraine」はけたたましいムーグとラウドなギターのイントロから始まる。
しかしヴォーカルが入ると意外にやや R&B 風味の強い普通のロック。
ワウ・ギターやオルガンなど様々にバッキングを工夫しているが、メロディは平凡。
アメリカでチャート・インしそうなロックンロールである。
ムーグの不可思議なソロのみが実験的。
「Tales」再び電子音が飛び交うものの、曲自体はアコースティック・ギターで歌われる落ちついたフォーク・ナンバー。
スチール・ギターのバッキングがカントリー風。
メロディは憂鬱な英国流。
ギターもノイジーではなくフォーク・ロック風にまとめている。
「The Magician's Birthday」久々にノイジーなギター・リフが繰り出されるハードロック・ナンバー。
メタリックなイントロからヴォーカルが決める。
コーラスも鮮やか。
しかしやはり中間部ではピアノが使われマウス・ハープがユーモラスに鳴る。
イコライザのかかったコーラスとヴォーカルの掛け合いは最早ポップといってもいいような展開である。
一転ヘヴィなアンサンブルが重々しく現れ、ギターの轟音で決めを連発しドラムスが走り出す。
ようやくかつての HEEP ワールドへ戻ったようだ。
ギターが暴れドラムスが烈しく叩きまくる。
ムーグやピアノの断片が時折降りかかるが頓着なくギターとドラムスが突っ走る。
痛快なまでのギター・ソロとドラムス。
ロングトーンを響かせて延々と続くギター・ソロ。
ベースのリフレインが湧き上りオルガン、ギターのコード・カッティングが始まるとヴォーカルが戻る。
様々なギミックを交えながらアンサンブルは淡々と進んでゆく。
ヴォーカルはファルセットを響かせ高く高く舞い上がる。
そしてフェード・アウト。
サウンド・コラージュの手法を存分に使ったプログレッシヴな作品。
ハードロックの断片を継ぎ接ぎしあたかもかつての自らのサウンドをパロディ化したような作品だ。
オープニング・ナンバーを聴いてホッとするのもつかの間やはりアコースティック・ギターやピアノを使ったナンバーが多いことにフラストするオールド・ファンも多いだろう。
しかし前作での試みをさらに積極的に反映してゆくスタンスはアグレッシヴではないだろうか。
残念ながらあまり感心しない作品も混在するのだが「Echoes In The Dark」のようにハードさの中に哀感を漂わせたナンバーや「Rain」のような正統バラードまで明らかに音楽の幅は広がっている。
そしてフォーク・ロック風のナンバーでは従来とは異なる落ちついた風情がある。
そして最後の大作。
前衛的な手法を用いてテーマをうまく描くと同時に自らのスタイルを素材化するという大胆極まりないアプローチの野心作である。
賛否両論呼ぶのは間違いない。
それでも、進むことを止めないグループはやはり魅力的です。
(ILPS 9213 / VICP-2083)
 close
close