

| Harald Bareth | bass, vocals |
| Uwe Karpa | guitar |
| Kono Konopik | drums |
| Matthias Ulmer | keyboards, vocals |
ドイツのシンフォニック・ロック・グループ「ANYONE'S DAUGHTER」。 75 年結成。 作品はライヴ・アルバム含め六枚。86 年活動休止。 プログレッシヴ・ロック・シーンが消えかかっていた 80 年代前半に秀作を発表して次代への架け橋となった。 2001 年復活、新譜発表。


| Harald Bareth | bass, vocals |
| Uwe Karpa | guitar |
| Kono Konopik | drums |
| Matthias Ulmer | keyboards, vocals |
79 年発表の第一作「Adonis」。
内容は、ファンタジックな曲想を安定した技巧と洗練されたサウンドで紡ぐ抒情的シンフォニック・ロック。
卓越した演奏力を生かして、甘く優しいメロディを精妙なアンサンブルで支える。
音楽的な源はハードロックのように思えるが、キーボードを軸にしてサウンドを進化、深化させ、力強くも繊細で奥深いロマンチシズムを描き切っている。
その象徴が、アルバムの軸となる A 面全部を使ったタイトル組曲「Adonis」。
演奏もサウンドもこれだけセンスがあれば、売れ線アリーナ・ロックに寄せることは十分可能だったと思うが、敢えてそうしなかったおかげでプログレッシヴロックの名盤として後世に語り継がれた作品になった。
ギタリストは英米ロックをよく吸収したかなりの凄腕。
ジャケットは左がオリジナル LP、右が再発 CD。
ヴォーカルは英語。
アドニスはギリシャ神話の美少年神、翻って男性同性愛の象徴としても名高い。
1 曲目「Adonis」4 つのパートからなる組曲。
メローなヴォーカル・ハーモニーを巧みな器楽で守り立てる、シンフォニック・ロック大作の名品である。
part 1. Come Away(7:49)ギターの弾き語りによるひそやかなオープニングから 7 拍子のタイトなアンサンブルへと流れ込むドラマチックな序章。
ジェントルな男声によるヴォーカル・パートは竪琴のようにきらびやかなアルペジオに支えられて進む。
間奏部はシンセサイザーとギターによる波打つようなアンサンブル。
バッキングのギターのコードプレイも多彩だ。
教会風のオルガンも高鳴る。
ハイハット・シンバルを細かく鳴らすドラミングはアンディ・ウォードのイメージ。
4 分辺りからのインストゥルメンタル・パートでは重厚なバッキングとともに吹きすさぶ風のようなシンセサイザーが寂寥感と哀愁を巧みに描き始める。
ヴォーカルを追うギターは細かな感情の揺れを巧みに表す。ベースとの呼応もカッコいい。
雷鳴、驟雨とともにフェード・アウト。
GENESIS 流のきらめくアンサンブルによる物語の導入部。
ドラマの始まりらしく、どこか波乱含みである。
アルペジオ主体のギターとシンセサイザーによる 7 拍子のリフや、ギター、シンセサイザーそれぞれのソロなど、おだやかな表情の中でもしっかりと訴えてくるものがある。
特に、交互に浮かび上がるギターとシンセサイザーのテーマの配置と、アルペジオとメロディアスなソロをタイミングよくきりかえるギターのプレイは絶妙だ。
ヴォーカルはソフトな美声型ではあるが、やや英語にクセがある。
part 2. The Disguise(3:29)ヘヴィな予兆とともにモノラル・シンセサイザーらしい電子音がうねるミステリアスなイントロ。
ハードなギターが飛び込むと一気にテンションが高まる。
テクニカルなムーグ・ソロとギターとのユニゾンがさらにスリルを生んで鳥肌ものだ。
ドラムスも緻密である。
ギターの 3 連フレーズが泣き叫び、シンセサイザーとのアンサンブルはユニゾン、かけあいと目まぐるしく変化する。
スピード感たっぷりの展開だ。
興奮を落ちつかせるようなギターのなめらかなフレーズに導かれてメイン・ヴォーカル・パートへ。
ポップで調子のいい歌唱、バッキングは小刻みなドラミングとギターとシンセサイザーの小気味いいユニゾンで緊張感をキープする。
エンディングは銅鑼の一撃。
スピーディかつテクニカルな展開パート。
ギター、シンセサイザーのソロとインタープレイがアップ・テンポでたたみかけるように次々と繰り出される。
前半のムーグ・ソロはキース・エマーソンの全盛期を思わせる。
ギターとキーボードのユニゾンは一転 CAMEL 調である。
3連を巧みに使って緊張を高め、8 ビートで落ちつかせるなどリズムの変化もたくみ。
part 3. Adonis(7:51)ドリーミーなエレクトリック・ピアノとヴォーカルによるバラード調のオープニング。
間奏のギターもエコー深くソフトな音色を用いた爪弾くようなプレイである。
ストリングス・シンセサイザーが星を掃くようにうっすらと背景を彩る。
切ないメロディを歌い上げるヴォーカルに寄り添うギターの伴奏。
ヴォーカルを引き継いでメロディを切々と歌い上げるギター。
降りしきる雪のように背景を埋めてゆくキーボード、しかし、ややヘヴィなギター・リフが静かに浮かび上がって新しい展開を予感させる。
ドラムスの復活とともに 11 拍子によるシンセサイザーのせわしないリフが提示される。
ここのリズムの変化はじつに自然だ。
ギター、シンセサイザーのネジを巻くようなユニゾンによるリフレイン。
この忙しない変拍子パターンをキープしたまま、重厚なアンサンブルが動き出す。
全体を貫くのは歓喜か狂乱か、舞い踊るムーグ・シンセサイザー・ソロ。
火花を散らすようにさまざまな音が激しく重なり合う。
情熱的かつ知的なアンサンブルはプログレッシヴ・ロックの醍醐味だ。
しだいにエネルギーをためこんでゆきつつ、混沌とするドラムス、シンセサイザー、オルガンの騒音。
そしてそれらを突き破るように、メロディアスなギターが歌い始める。
すでに終局の予感。
陶然たるギターの余韻をマーチング・ドラムスと電子音が引き継ぎ、やがてフェード・アウト。
バラードからスリリングなインストゥルメンタルへと進むクライマックス。
前半は、ストリングス・シンセサイザーによる乳白色のもやがかかったようなファンタジックなムードを堪能できる。
ギター・ソロで頂点を極め、巧妙にリズムの変化をつけながら場面転換、テクニカルな後半へとなだれ込む。
奇数拍子で緊迫感を出しつつも力強い和声で重厚に進むこの後半部は、このグループのポテンシャルをはっきりと伝えてくれる。
オーヴァー・ダブされたギター、シンセサイザーともに大活躍。
個人的には細かいプレイを積み重ねるタイプのドラムスが貢献度大と感じる。
part 4. The Epitaph(5:07)ピアノの和音が厳かに刻まれて、やがて優美にしておおらかなピアノ・ソロへと流れ込む。
終章らしいオープニングだ。
たおやかなヴォーカル・ハーモニー。
そして伴奏が加わり、シンフォニックなバラードへ。
間奏のギターはおだやかな眼差しで見つめるようなプレイ。
セカンド・ヴァースは端正なピアノの伴奏。
エコーをさらににじませるストリングスの響き、夢の階を刻むようなピアノ。
感情の高まりを抑えきれずにほとばしるギター。
情熱的なプレイに力強くドラムスとベースがアクセントをつけていく。
両チャネルから訴えかけてくるギターときらめくストリングス。
大きくリタルダンド、そして胸熱の余韻。
前章の熱気あふれるクライマックスを静かに回想する終曲。
情感の高まりが直截的に現れていて感動的だ。
全体を通してノーブルなメロディとヴォーカルがいい。
また、要所でスリリングなプレイで盛り上げてはいるものの、大筋はごくストレートという語り口が奏功し、仰々しさのないすがすがしさがある。
2 曲目「Blue House」(7:20)金管楽器と弦楽器がまじりあったような不思議な音色のシンセサイザーが高鳴る悠然としたオープニング。
渦を巻くようなシンセサイザーと音域広く和音を響かせるオルガン。
分厚い音からギターのアルペジオへとすっと落ち込む演出が憎い。
穏やかなアルペジオにのせて、再び、シンセサイザーが宇宙の歌を歌い始める。
絵に画いたような幻想、夢想、ファンタジーの趣。
HAPPY THE MAN をグッと素直にしたような雰囲気だ。
サスティンを利かせたギターのメロディも静かに寄り添ってくる。
CAMEL なら「Moonmadness」の世界である。
朗々と歌うギター、慎ましくも堅実なリズム・セクション。
静かに迫るストリングス、そしてドラムスの刻むリズムに応じながらギターは高らかに歌い上げる。
やがてシンセサイザーもギターに追いついて次第に主導権を取ってゆく。
いつしかすべては原点へと回帰、アルペジオとともに最初のテーマが思い出される。
万感胸に迫るファンタジックなシンフォニック・ロック・インストゥルメンタル。
シンセサイザーのテーマには耳にしたことのない精妙な美しさがあり、ギターはシンフォニック・ロックの切り札ともいえる伸びやかで情熱的なプレイである。
SEBASTIAN HARDIE を思わせる宇宙的な広がりと色彩のある名曲。
前の組曲の贅沢極まるエピローグとしても聴ける。
3 曲目「Sally」(4:20)レイ・チャールズ風のファンキーなピアノ、サックスをフィーチュアしたジャジーでリズミカルなポップ・チューン。
シンフォニックな味わいがメインの本アルバムでは異色といえる作風だ。
ソフトな歌メロはこのグループの持ち味らしい。
メインのリフとキャッチーなコーラスのアメリカンな「冴え」はさすがといえるだろう。
ごく短いギターのソロに意外な味わいあり。
4 曲目「Anyone's Daughter」(9:10)
悠然と広がるオルガンとシンセサイザーによる夢のユートピア的なイントロダクション。
ギターの点描が少しづつ感情のうねりを持ち始める。
湧き上がるリズム、高らかな昂揚。
ギターとキーボードの夢見るような旋律が幾重にも連なってゆく。
まず飛び出すのはジャジーなオルガン・ソロ。
ブルージーな大人の音だ。
ギターのグリッサンドとアルペジオ、小気味よいドラム・フィルが巧みに絡む。
快調そのものの演奏だ。
サーフロック風のギターが次第に前面に出始める。
そしてヴォーカル・パートへ。
スピーディなハーモニーでかけ合う軽快な演奏だ。
間奏はシャープなギター。
グループ名を連呼するヴォーカルをエレガントなキーボードが受け止める。
ヴァイオリンのスケルツォのように華麗なフレーズを繰り出すギターがクロスフェードする。
手数の多いリズム・セクションも巻き込んで、再びスリリングなアンサンブルへと展開する。
煽るようなドラムスと対照的にギターはどこまでもしなやかで悩まし気な風情である。
ギターのリードでテンポ・ダウン、そして優雅なアンサンブルが再開する。
ミドル・テンポで朗々と歌い続けるギターと高鳴るストリングス。
またも軽やかなドラム・ピックアップ、そしてヴォーカル・パートの再現。
間奏のシャープなギター・ソロはタイトな演奏に火を注ぎ、さらに熱く眼の眩むようなプレイで盛り上がる。
エンディングもギターとオルガンが華やかにリタルダンド、そしてドラムスのロールで大見得切って終り。
ソロをフィーチュアして自在なテンポのグルーヴを重視したルーズな作りがいい大作。
優美さとタイトなスリルを両極にする以外の緻密なシナリオはさておいて、まずは楽しみましょう的なスタンスが感じられる。
ブルージーなギター、ジャジーなオルガンそしてクラシカルなアンサンブルと、まるで打ち上げ花火のように惜しげなく大サービスである。
反応よいアンサンブルの力量がよく分かる。
ヴォーカル・パートの軽快な自己紹介ノリなど、ライヴのエンディングやアンコールを飾ったのではないか。
メロディ・センスと精巧なアンサンブルによって形作られた正統派シンフォニック・ロック。
「Adonis」第三楽章や「Blue House」に明らかなように、丹念にシナリオを練り上げ、音色も十分に活かしてドラマをつくってゆく手法がすばらしい効果をあげている。
そして、緻密さは細部に盛り込み全体としては起承転結の分かりやすいストレートな語り口にするセンスがスゴイ。
技巧が突出するようなことはなく、音楽には常に優美な歌心が感じられる。
もちろん技巧的でないわけではない。
キーボードやギターのプレイには胸のすくようなスリルと痛快さがある。
驚くべきはテクニカルなプレイの応酬にすら聴きやすいメロディがきちんと配されていることである。
キッチリまとまったアンサンブルとわかりやすく優美なメロディそして明晰な構成力は、CAMEL や SEBASTIAN HARDIE と同クラス、そして演奏力では U.K. に充分匹敵する(ライヴでは実際 U.K. のカヴァーもやっていたらしい。そういえば英語のヴォーカルはややジョン・ウェットン似)。
最高級のシンフォニック・ロックという賛辞がおおげさではない。
プログレッシヴ・ロック受難の 79 年に、ドイツでこんなにすばらしいアルバムが出ていたとは大きな驚きである。
。
(WMMS 025)

| Harald Bareth | bass, vocals |
| Uwe Karpa | guitar |
| Kono Konopik | drums |
| Matthias Ulmer | keyboards, vocals |
80 年発表の第二作「Anyone's Daughter」。
内容は、メロディアスかつリズミカルな陽性シンフォニック・ロック。
キーボードを多用した持ち前のシンフォニックなサウンドにコンテンポラリーなポップ・センスを加味してさらに聴きやすくなった。
キャッチーなテーマを中心にしたヴォーカル中心の作風となり、インストゥルメンタルによるめくるめく展開のカタルシスよりもシンプルなグルーヴに重きがおかれているようだ。
いわば「プログレ風味のアダルト・ロック」であり、この時代を生き残るには最善の道であったと思う。
ハイクオリティの 80 年代メイン・ストリームのハード・ポップと考えてもいい。
おもしろいのは、曲が単純になるに連れてかえって演奏のうまさが際立ってくること。
シンセサイザーやギターのソロの歌わせ方に技巧を越えてにじみ出る熱いロマンチシズムは前作といささかも変わらない。
一つ一つのシーンがとても丹念な作りになっていることに気づけば、このグループのセンスに唸らされるだろう。
メロディアスでポップなシンフォニック・サウンドという意味で、同時代の CAMEL や KAYAK、いや STYX に匹敵する内容だ。
多彩で優美なキーボード・サウンドとしなやか過ぎるギターに耳は釘付けである。
ヴォーカルは英語。
1 曲目「Swedish Nights」(4:52)
ミドル・テンポのソフトでメロディアスな歌もの。
ていねいな器楽と優美なヴォーカルのコンビネーションによる安定感ある作品だ。
冒頭のストリングスなど、全体のイメージはやはり CAMEL ですかね。
2 曲目「Thursday」(3:59)
快調なロックンロールにうっすらと品のある陰影を施した作品。
明朗さににじむこの悩ましげな、メランコリックなタッチはこのグループの特徴だと思う。
エレクトリック・ピアノによるほのかな AOR 調も悪くない。
ギターとキーボードの歌うようなやり取り、ていねいなドラミングもいい。
4 分弱とは思えぬ密度の高い演奏だ。
3 曲目「Sundance Of The Haute Provence」(3:39)
夜空の星を射るようなデジタル・シンセサイザー・ホイッスルの調べが印象的な慈愛のバラード。
エレクトリック・ピアノが暖かく優しくリズムを刻む。
ドラムレス。
4 曲目「Moria」(3:52)
ややエレポップ調のハードポップ・チューン。
泣きのメロディとキャッチーなサビをシーケンス風のデジタリーな伴奏で支えヘヴィなサウンドでメリハリを付ける。
コンパクトにドラマを入れ込んでおり、シングル向けの作品ではないだろうか。
はち切れそうにポップな曲調でも、シンセサイザー、ギターのソロはもったいないほどに冴えている。
オルガンの支えもよく効いている。
「モリア」は指輪物語でガンダルフがバルログに襲われて最大の窮地に陥った古の坑道のことだと思う。
5 曲目「Enlightment」(5:01)
重厚なピアノが晩鐘のように響き、ストリングスが厳かにざわめくトラジックなバラード。
ブルーズ・フィーリングを込めてむせび泣く、オーソドクシーを極めたギターの表現がみごと。
切々とした思いを訴える湿度のある曲調には英国ポンプロックと共通する味わいもあり。
6 曲目「Superman」(3:56)
メロディアスなハードポップ・チューン。
3 連シャフル独特の跳ねるようなビート感が生む華やぎが特徴か。
歌詞は意外にもきっぱりと決意を告げるような内容だ。
次曲のタイトルが歌詞に出てくるので、連作のようだ。
メロディ・ラインもギターの入り方も、ほんとうに CAMEL によく似ている。
7 曲目「Another Day Like Superman」(8:03)
ロマンティックなメイン・ヴォーカル・パートを前後に、間奏として華やかなソロを配した、劇的なシンフォニック・ロック。
このグループ独特の「上品なソロ・ピアノを思わせるアンサンブル」が活かされた傑作である。
インストゥルメンタル・パートはハードロック的なニュアンスも強く、やや古典的な表現ではあるが、安定した演奏とていねいなメイン・パートの雰囲気作りのおかげで、説得力ある内容となっている。
圧倒的なテクニックを見せつけるギターとシンセサイザーによるハイ・テンションなソロ合戦は痛快そのもの。
ギターは終盤にもメロディアスなプレイでドラマを締めくくる役を演じて存在感をアピールする。
凝ったドラムスにも注目。
CAMEL でいえば「Lady Fantasy」でしょう。(ギターのキレのよさはこちらに軍配が)
前作に近い作風の傑作。
8 曲目「Azimuth」(1:27)。
パーカッシヴなインストゥルメンタル小品。
フィル・コリンズを思わせる快速打撃と、目まぐるしいギター、キーボードが織り成すハイテンションのパフォーマンスである。
スティーヴ・ハケットの作風にも似る。
次曲への序章のようなニュアンスも。
9 曲目「Between The Rooms」(4:22)
エレクトリック・ヴァイオリンのようなシンセサイザーの音色が印象的な、ジャジーでやや AOR タッチの作品。
丹念なアルペジオが何気ない変拍子(15/16)を刻み、エレクトリック・ピアノが舞い、つややかなシンセサイザーがほのかなエキゾチズム(P.F.M の「Jetlag」でも聴いた音色だ)を漂わせつつ朗々と歌う。
ムーディな AOR 調の曲が、独特のリズムとシンセサイザーの音色のおかげで、眩く輝く未来のファンタジー・ロックへと昇華する。
さりげないエンディングがいい感じだ。
(INT 845.612)

| Harald Bareth | bass, vocals |
| Uwe Karpa | guitar |
| Matthias Ulmer | keyboards, vocals |
| Kono Konopik | drums |
81 年発表の第三作「Piktors Verwandlungen」。
ヘルマン・ヘッセの短編小説「ピクトルの変身」を朗読と演奏で表現したライヴ作品。
スタジオ・テイクと見まがうばかりの正確なテクニックに、ライヴ独特の迫力が加わった傑作アルバムである。
ライヴであるという事実を知らなければ、おそらく最後に観客の大歓声が聴こえるまでそうであるとは気がつかないだろう。
厳かなモノローグとドライヴ感にあふれた明快なシンフォニック・サウンドが絶妙のコンビネーションを見せ、やがて静かな感動を呼び覚ます。
ギターとキーボード(華麗なシンセサイザーに加えてハモンド・オルガンがうれしい)のかけあいには、ジャズロック的なスリルもたっぷりある。
文芸に主題を求めたトータルなロック・アルバムとして忘れられない名作である。
ちなみに、CAMEL の「Snow Goose」と異なるのは、テキストの力を朗読という形で直接借りていることと、管弦楽とは競演していないことである。
朗読はドイツ語。
「Piktor(ピクトル)」(2:14)
「Erstes Vorspiel(第一序曲)」(0:39)
「Erster Teil Der Erzählung(第一の章)」(2:23)
「Purpur(紫)」(2:55)
「Zweites Vorspiel(第二序曲)」(0:56)
「Zweiter Tell Der Erzählung(第ニの章)」(2:19)
「Der Baum(木)」(7:14)
「Dritter Teil Der Erzählung(第三の章)」(2:37)
「Sehnsucht(熱望)」(5:27)
「Vierter Teil Der Erzählung(第四の章)」(4:30)
「Piktoria, Viktoria(ピクトリア、ヴィクトリア)」(0:27)
「Fünfter Teil Der Erzählung(第五の章)」(0:43)
「Der Doppelstern(双子星)」(4:23)
(WMMS 033)

| Uwe Karpa | guitar, vocals |
| Peter Schmidt | drums |
| Harald Bareth | bass, vocals |
| Matthias Ulmer | keyboards, vocals |
82 年発表の第四作「In Blau」。
ドラマーがメンバー交代するも、輝かしいサウンドに大きな変化はない。
その内容は、テクニカルなギターとキーボードによるアンサンブルを中心とする 70 年代ロック・スピリットあふれるシンフォニック・ロックである。
キャッチーな AOR テイストのメロディ・ラインとこなれた変拍子によるスリリングなインストゥルメンタルをふんだんに用いて、暖かな郷愁ときらびやかな目新しさを同居させている。
悪名高き 80 年代初頭におけるこの優れた音楽センスは、当時の CAMEL と共通している。
うねる波のようなシンセサイザーときらめくギター、まろやかなヴォーカルが織り成す新時代対応シンフォニック・ロックの大傑作だ。
ヴォーカルはドイツ語。
この母国語の歌唱が深い味わいをもたらしている。
この時代らしいクリアーなサウンドへとシフトしながらも、キーボードとギターをバランスよく配置して丁寧かつ力強く音を綴ってゆくスタイルはまったく健在だ。
安定したトゥッティにセンスよいソロを交えたカラフルなパフォーマンスが続いてゆく。
ヴォーカリストはそこに豊かな情熱を加えてゆく。
演奏は、優しげな表情を見せながらも隅々にまでプロフェッショナルな仕込みが施され、丹念に構築されている。
凡百のアリーナロック、ハードポップとは明らかに一線画している。
特に、ドリーミーな世界をクラシカルな輪郭で切り取るアコースティック・ギターと甘さの中にスリリングなアクセントとして放たれるハモンド・オルガンのプレイがみごと。
全曲すばらしく甲乙は付けがたいが、なかでも白眉は終曲の大作「Tanz Und Tod」。
重厚でオーセンティックなシンフォニック・ロックをたっぷりと味わうことができる。
本アルバム、80 年代初頭にありながらも、胸を揺さぶるロマンティックな味わいとテクニカルなプレイによるカタルシスが奇跡的に調合された大傑作である。
「Sonnenzeichen - Feuerzeichen」(5:20)静々と湧き上がるオルガンとひそやかなヴォーカルから幕を開け、ゆったり広がるキーボードとアタックを消したギターによって悠然と演奏が進む。
そして思いを吹き上げるように迎えるクライマックス。
高まっては沈み込む。
熱く豊かな表現力を持つギターは、アンディ・ラティマーに酷似。
流れは最後には堂々たるギター・ソロへと注ぎ込む。
緩やかなクレシェンドが生み出すドリーミーにして無限の力強さをもつシンフォニック・ロック。
次第に心をとらえてゆく語り口がみごとだ。
このグループらしい夢想感とポジティヴなダイナミズムがバランスした傑作だ。
「Für Ein Kleines Mädchen」(5:20)竪琴を思わせる鮮やかなアコースティック・ギター・アンサンブルから華麗なシンセサイザーが描くファンタジーへと進むナンバー。
後半は、ほんのりラテン調でリズミカルに進む。
フュージョン・タッチのお気楽グルーヴではなく、知的な憂いとピュアな夢想感がある。
オープニングの 12 弦ギターとピアノによるデリケートなハーモニーは GENESIS を思わせるみごとな演奏だ。
「Nichts Für Mich」(6:45)前半は、フロア・タムによる太鼓ビートとフォーキーなメロディをもつヴォーカルのコンビネーション。
ジャーマン・ロック特有の素朴なタッチである。
ギターとシンセサイザーのユニゾンやベース、ハモンド・オルガンのプレイは目が醒めるほどテクニカル。
特に、ハモンド・オルガンは全編にわたってフィーチュアされる。
終盤のどっしりしたメロディアスなアンサンブルがみごとだ。
変拍子パターンから幻想的な場面までも交えたテクニカル・シンフォニック・ロックの傑作。
プログレ度満点。
CAMEL ファンは絶句。
「Nach Diesem Tag」(4:00)官能のほめきの感じられる柔らかなバラード。
ピッチを揺らがせるエレクトリック・ピアノのソフトな響きは、典型的な 70 年代後半 AOR 調。
コーラスに重なるギターには、優美さとともにロックらしい力強さがある。
「La La」(3:10)タイトルとおりのスキャットに導かれる、スリリングなインストゥルメンタル。
メロディ・ラインの濃い目のまろやかさとリズミカルで切れ味のいいリフ中心の演奏がみごとな調和を見せる。
コンパクト版の「Echoes」ですね。一瞬出てくるフルートの処理が印象的。
「Sonne」(4:30)竪琴のように深みのあるアコースティック・ギターの響きが特徴的な弾き語り。
ゾンネは「太陽」でしたっけ。
複数のギターが美しくも近寄りがたい気高さで絡み合い、時に凛とした表情を見せる。
後半のクラシカルなソロは、スティーヴ・ハケット的。
終盤ピアノやファズ・ギターも加わって、切ない響きが螺旋を描くように高まってゆく。
ドラムレスでのこの高揚感、GENESIS に負けません。
「Tanz Und Tod」復古調の優美なロマンチシズム、鋭角的でコンテンポラリーな芸術性をシームレスに結んだ傑作。
「a) Der Begleiter」(5:20)密やかな弾き語り。B.J.H を思わせる泣きの牧歌調である。
小気味のいいハモンド・オルガンに痺れる。後半はメロディアスなヴォーカルを軸に、ギター、キーボード、ドラムスが一体となって多彩な 7 拍子反復で追い込んでゆく。デジタル・シーケンス風のトゥッティとラフなタッチのギター・ソロが痛快な対比をなす。ジャジーな全体演奏からの最後のリタルダンドにはこの時代のユーロロック・テイスト(ハンガリーの EAST あたりか)が凝縮している。とても懐かしい。
「b) Yaqui」(3:30)気高い情熱がほとばしるクラシカルなピアノ独奏。本格的です。
「c) Tanz Und Tod」(6:15)密やかなモノローグを支えて、エレクトリック・ピアノとギターのアルペジオが綾をなす。
リズムとともに力を得、キレのいい 5 拍子のスタカートとともにギターが泣き叫ぶ。緊迫感ある終曲である。ドラムスの打ち鳴らされるブレイクを経て、第一楽章の 7 拍子アンサンブルが再現、ハモンド・オルガン、シンセサイザーが決然とリードを取って、重厚なドラマに幕を引く。
(INT 845.632)
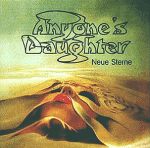
| Matthias Ulmer | keyboards, vocals |
| Uwe Karpa | guitar, vocals |
| Peter Schmidt | drums |
| Harald Bareth | bass, vocals |
83 年発表の第五作「Neue Sterne」。
これまでの作風をコンデンスしたコンパクトな楽曲に 80 年代初頭らしい産業ロック、アリーナロック・テイストやシーケンサーによるテクノ・テイストを盛り込んで開放感と享楽性を強調した佳作。
リズミカルでキャッチーなテーマやトゥッティに、軽やかな変拍子パターン、想像力を鼓舞するシンセサイザー・サウンド、古典的なハモンド・オルガン、レガートかつエッジも効かせるギター・プレイ、立体的で緻密なアンサンブルといったプログレらしい要素をぜいたくに散りばめている。
ジャジーな展開も鮮やかにこなしている。
さりげなくテクニカルなところや曲想の多彩さに気がつけば、センスのいいポップ化に唸らされるはずだ。
「Illja Illia Lela」は傑作。
(SPV 80532 CD)
