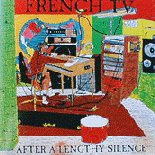FRENCH TV
アメリカのプログレッシヴ・ロック・グループ「FRENCH TV」。
84 年ケンタッキーにて結成。
作品は 2021 年現在で十四枚。
自主制作でガンバるプログレ好きの変なオジさんたちであり、戦費削減を謳うなど完全にオルタナティヴなスタンスを貫く現代 RIO。
グループ名は、フランス製のテレビの如く次々と色彩が変化するサウンド、という意味らしい。(壊れてるって)
最新作は
2021 年発表の 「14 All Our Failures Are Behind Us」。
I Forgive You For All My Unhappiness
| Mike Sary | basses | Jeff Gard | drums, percussion |
| Shawn Persinger | guitar | Steve Katsikas | keyboards, sax |
| Adam Huffer | sax | Hans Bodin | guitar synth |
| Roy Strattman | guitar | Warren Dale | sax, clarinet, melodica |
| Joee Conroy | guitar | Andrew Katsikas | vocals |
| Paolo Botta | keyboards | Chris Smith | guitar |
2010 年発表の第十作「I Forgive You For All My Unhappiness」。
内容は、加齢のもたらす根拠のない余裕なのかはたまたヤケッパチなのか、ユーモラスでもある明快なメロディ・ラインとジャズのスイング感、クラシカルなロマンチシズムをフルに活かし、鼓笛隊やオールディーズのようなルーツ・ミュージック・テイストも交えたノリのいいジャズロック。
往年の SAMLA の諧謔味とタフネスをそのままに、ジャジーにしてシンフォニックなロック=プログレを演じている。
ジャズっぽさを引き受ける管楽器群の活躍は見逃せないだろう。
また、作曲については、自発的に発展する即興演奏を素材として、そこからアレンジで組み上げていく手法を取っているようだ。
現代カンタベリーの傍流からも水を引いていると見ることも可能だが、スタイルが似る IN CAHOOTS と比べると、やはりユーモア感覚がアメリカンである。
そして、バカっぽいのにテクニカル。
リズムやテンポのチェンジをばんばん盛り込み、こんがらがるだけこんがらがっても、ちゃっかりと明快なテーマへと帰ってくる。
ただ、ちょっぴり発散気味なのは、予定調和をよしとしないのか気まぐれなのか。
この辺はザッパ先生の薫陶しからしむるところだろう。
粘っこいギター、鍵盤打楽器、元気なドラムス、爆発力あるハモンド・オルガン、パンチの効いたサックス、メロトロンにしか聴こえないストリングス系シンセサイザーなど、いい音もたくさんある。
ただし、アメリカ人特有というかありあまるエネルギーでテンションを落とさずにひた走るので、リスニングには想像力とともに体力も要求される。
もちろん、だからこそ、リリカルなシーンが一層生きるのではあるが。
日がな一日、エンドレスにプログレ、ジャズロックに酔いたい方にお薦め。
クレジットがないが、フルートも入っていると思う。
タイトルは「あたいが不幸せなのは全部あんたのせいだけど許したげる」ということか。
「Seven Rusty Nails」(7:00)
「Conversational Paradigms」(7:33)
「March Of The Cookie Cutters」(8:52)
「You Got To Run It Out, Dawson !」(9:15)チェンバー風のクラシカルなアンサンブルやフリーフォームの展開にも発展するも一貫してスリルを失わない名曲。
「With Grim Determination, Terrell Dons The Bow Tie」(6:41)目まぐるしく変化しつつも安定感ある、ジャム・バンド・テイストあふれる佳作。
「Mosquito Massacre」(5:55)
(PDR CD009)
French TV
| Mike Sary | bass |
| Artie Bratton | guitar |
| Stephen Roberts | keyboards, trumpet, vibes, drums |
| Fenner Castner | drums, percussion |
| Jeff Jones | sax on 3 |
| Jon Weiner | cello on 8 |
84 年発表の第一作「French TV」。
LP で発表され、2000 年に CD 化。
内容は、ユーモラスでコミカルかつシリアスな変拍子ロック。
チンドン屋風だったり室内楽風だったりザッパ風だったり 70 年代プログレの劣化コピー風だったりする。
それでいて、メロディアスでクラシカルなアンサンブルでは真っ当な力量を見せる。
カンタベリー・ジャズロックへの目配りもある模様。
一貫するのは多少の齟齬は気にせずアメリカンな無限エネルギーでひた走るところ。
屈折した音は喜怒哀楽の感情を自然に音に織り込めているからこそではないか。
自主制作らしいチープなサウンド、オレにもできるかもと思わせる宅録ノリが魅力。
リーダーであるベーシストは演奏面でも自己主張が強い。
全体を貫く独特の「逸脱感」はこの人の存在のなせる業では。
全編インストゥルメンタル。
「The Visit Revisited」(0:59)教会オルガン風のシンセサイザー独奏。タイトルがふざけている。
「Happy Armies Fight In Their Sleep」(3:48)80 年代初頭のフュージョンのパロディのような、カンタベリーの名残のような作品。
「Under Heaven Is A Great Disorder (And The Situation Is Excellent)」(3:31)チンドン屋系。
「The Artists's House」(3:21)メロディアスでロマンティックな作品。
「Spill」(10:44)
「Dream Of Peace」(4:13)カンタベリー調の傑作。
「No Charge」(5:12)骨折系変調子。ゲストのチェロも暴れる。
「Earth, I Wait」(7:47)
「The Visit」(5:52)
(No label / Pretentious Dinosaur Records CD005)
After A Lenghthy Silence
| Mike Sary | bass |
Fenner Castner | drums |
| Artie Bratton | guitar |
Tom Browing | guitar solo on 2,3,4,5 |
| Mark Miceli | little bent harmonized note on 2 |
Bill Fowler | keyboards on 3, piano on 5,6 |
| Bob Ramsey | keyboards on 4 |
Paul Nevitt | keyboards on 6 |
| Clancy Dixon | sax on 1,2,3,4,5, clarinet on 3,5 |
Bruce Krohmer | 1st sax solo on 5, bass clarinet on 5 |
| Rick Debow | flute on 5 |
Bob Douglas | vocals on 7 |
87 年発表の第二作「After A Lenghthy Silence」。
内容は、ユーモラスでメロディアスなテーマに変拍子を交えたインストゥルメンタル・ロック。
テクニカルながらも圧力は少なく、毒気のある軽妙さと、ユーモアと生真面目さの巧みな使い分けが特徴だろう。
技巧のキレそのものよりも、明快にしてヒネリのあるテーマを巡ってさまざまなフレーズやアンサンブルを積み上げてゆくスタイルであり、いわゆるジャズロックというよりは 70 年代のプログレッシヴ・ロックのインスト・パートに近いと思う。
ただし、重厚なテーマ性よりもユーモア優先であり、超絶テクニックお披露目にもさほど興味なしということで、往年の観念肥大型プログレや体育会系フュージョンのどちらからも、かなり距離がある。
前半はギター、サックス中心のタイトなロック寄りジャズロックであり、キーボードが加わった後半はそこへミステリアスな展開やシンフォニックな展開を交えている。
さすがに現代のグループらしく、70 年代プログレに憧れつつも、それ以降のさまざまな音楽のバック・グラウンドを作曲・演奏に活かしてはいるようだ。
しかし、なによりアカデミックな小難しさやマス・プロ的な冷ややかさよりも、ロッカーとして反骨精神がはっきりと見えるところがカッコいいのである。
結局、現代においてプログレ的イディオムを用いてオルタナティヴなマインドを貫き、なおかつ手強いアマチュアとしてのスタンスを維持する、ユニークなグループなのだろう。
影響元としては、フランク・ザッパを筆頭に、テクニックそのものを意識させずにユーモアたっぷりの表現でメロディアスに聴かせるところは SAMLA MAMMAZ MANNA 、一転してシリアスなシンフォニック調は、サックスの存在のせいもあって歌のない VAN DER GRAAF GENERATOR といった趣である。
細身ながらもつややかな音と敏捷な動きを見せるサックス、ソロを担当するギターはなかなかの腕前だ。
問題はこういう「狭間」の音は、フュージョン・ファンには「いま一つ」、シンフォニック・ロック愛好家には「変」、シリアスなニュー・ミュージック派には「新しくない」と評価され、メジャーなファン層からは見放されがちということ。
ジャンルにとらわれない貴方のような優れた耳の持ち主への贈り物とお考えください。
最終曲は、CD のみのボーナス・トラックであり NEKTAR の大作「A Tab In The Ocean」のカヴァー。
やや低音部が弱い録音やチープなキーボード、ドラムスの音など、自主制作特有のノリも含めてその根性を堪能すべし。
「One Of The Jones Boys」(3:14)
「You Fool! You Broke The Yolks!」(4:23)ここまでは軽いノリのギター/サックス・ジャズロック。
「Friendly Enzymes」(6:22)木管、キーボードをフィーチュアしたクラシカルかつスペイシーなアンサンブルの前半から変拍子ドッコイショ・ジャズロックを経て、まとめは再びクラシカルなアンサンブルへ。
「...And The Dead Dog Leaped Up And Flew Around The Room」(6:58)変拍子リフと無茶なソロ・ギターのアブストラクトな怪作。
KING CRIMSON に憧れたフランスあたりのバンドをさらに薄く引き伸ばした感じだが、独特の一貫した薄暗いトーンと即興的なスリルがあり悪くない。
「Go Like This」(12:53)終盤の熱い混沌が VdGG を思わせる。傑作。
「Vacilando」(9:27)
「A Tab In The Ocean」(15:09)ドイツのハードロック・グループ NEKTAR のシンフォニックな名作。
(MMP307)
Virtue In Futility
| Mike Sary | bass, bass pedal, tapes |
Ferner Castner | drums |
| Paul Nevitt | keyboards |
Dean Zigoris | guitars |
| Reid Jabn | WX7 wind synth, sax |
Gretchen Wilcox | violin |
| Jon Encifer | piano |
Bruce Krobmer | sax, clarinet |
| Richard Brooner | trumpet |
Howie Gano | scream, spastic keyboard solo |
| Bob Lamsey | keyboards |
Artie Bratton | guitars |
94 年発表の第三作「Virtue In Futility」。
内容は、YES、GENTLE GIANT を思わせる 70 年代プログレ王道的な演奏に、ジャズ/フュージョン・タッチやユーモラスでアヴァンギャルドな展開を盛り込んだ、技巧的なシンフォニック・ロック・インストゥルメンタル。
通常の 4 ピースにサックスやヴァイオリンのゲストを迎えた編成は、ほぼ前作と同じだが、クラシカルなアンサンブルや攻め立てるようなハモンド・オルガンなどが現れて、英国大物バンドの名作そのもののような世界を作り上げている。
「その筋」には大いに受けそうなサウンドだ。
演奏は、ギターを中心になかなかテクニカルだが、親しみやすいテーマを巡ってユニークなアンサンブルが繰り広げられる展開が主であり、やはり個人プレイ主導型ではない。
メカニックよりも、しっかりとした曲想とロックの基本であるシンプルなカッコよさに重心があるところも、前作と同じであり、こういうスタンスも往年の英国本流に通じている。
リリカルな場面の語り口の自然さに、特にそのうまみが現れている。
単に技巧的なだけなら、リラックスした YES や、今風の音を使った GENTLE GIANT といったイメージは浮かんでこないはずだ。
これにドギツク土臭いユーモアが加わると SAMLA であり、さらに演奏に切れが増せばフランク・ザッパのジャズロック作品にも迫る。
一方 4 曲目のようなインプロヴィゼーションでは、ジャズ的な逞しさと俊敏さもしっかりと見せている。
ライナーノーツや曲のタイトルのくだけ方とは完全に裏腹な、高品位の音楽に思わずニヤリだ。
SE 風のヴォイス以外は、インストゥルメンタル。
サウンド・プロダクションこそさほどお金はかかってなさそうだが、楽曲/演奏には風格すら感じさせる。
特にギタリストは相当な腕前。
最高傑作でしょう。
「Hey! Real Executives Jump From The 50th Floor!」(6:00)
凶暴な KING CRIMSON 風のギターで幕を開けるも、途中から一気に YES 風の懐かしくもカッコいいシンフォニック・ロックへ。
特にギターの手癖、クラシカルなピアノを披露するキーボードはかなり意図的。
テクニカルなギターのリードするジャズロックと YES がこんがらがる様子が面白い。
ニュー・エイジ・テイストまで見せるなど、パロディ精神旺盛。
CRIMSON、YES、EL&P までサービスする傑作である。
「Clanghonktweet」(6:39)
8 分の 6 拍子によるクラシカルな第一テーマと 4 分の 4 拍子による第二テーマをめまぐるしく駆け巡るフォーク・ダンス調のクラシカル・ロック。
ヴァイオリン、シンセ管楽器が使われる。
おもちゃみたいなピアノとヴァイオリンのピチカートなどユーモラスな表情がある。
緩やかなテンポでゆったりと歌うパートが美しい。
「The Family That Oonts Together, Groonts Together」(7:41)
マリンバのようなキーボードとつまづきそうな変則リズムが特徴的な作品。
凶暴なギターはザッパを真似るホールズワース。
ここでもトランペットをフィーチュアしたスロー・パートが活かされている。
どことなくヒゲダンスに似てます。
「I'm Whining For That Funky Baby Of Mine」(6:20)
IN CAHOOTS などカンタベリーの現在形に近いジャズロック。
即興演奏でありサックスの存在感大。
「Empate」(7:48)モダン CRIMSON 的なギターと場末エロティック系トランペット(ニニ・ロッソか?)というミスマッチが冴えるテクニカル・ナンバー。
ギターのアーミングによる奥行きあるバッキングがいい感じだ。
中盤からはまずギター・ソロで見せ、後半は分厚いシンセサイザーが高鳴る。
「Friends In High Places」(8:00)
ニュースや演説、爆音などを SE として散りばめ、パーカッションがアクセントをつけるミュージック・コンクレート作品。
政治色濃いプロテスト調のコラージュとともに打撃音を多用したサウンドも衝撃的。
「Slowly I Turn...Step By Step...Inch By Inch」(12:15)
シリアスで強圧的な大作。
ヘヴィな展開にもかかわらず、サウンドにドリーミーなフュージョン・タッチがあるところが HAPPY THE MAN を思わせる。
終了後ポーズを経てドラムンベースとオッサンたちが胴間声を張り上げるコーラスによる演奏が現れる。
なんじゃこりゃ。
(PDR CD001)
Intestinal Fortitude
| Mike Sary | bass, Chapman stick | Bob Douglas | drums, vocals |
| Tony Hall | guitars, back vocals on 2 | John Robinson | keyboards |
| Bob Fowler | keyboards on 2 | Jeff Mullen | drums on 2 |
| Dave Evans | back vocals on 2 | Jon Encifer II | back vocals on 2 |
| Sugarman Zigoris | guitar solo on 2 | Dave Stilley | baritone sax on 2 |
| guest: |
|---|
| Gregory Acker | sax, flute, sax, whistle | Gary Hicks | trumpet |
| Peter Rhee | violin |
95 年発表の第四作「Intestinal Fortitude」。
内容は、エネルギッシュで子どもっぽく、ちょっと狂気じみているがお茶目なジャズロック。
表現は幅広く、サーカスや運動会、ハイテンションの突っ走りや変拍子反復だけではなく、静謐なファンタジーや牧歌調も適宜盛り込んでいる。
プログレらしい「暗さ」ももちろんあり。
しかし、無闇にヘヴィではないところが、知的な印象を与える。
製作面での制限か、音響のメリハリはさほどでないが、ナチュラル・トーンのギターとチープなキーボード・サウンドも手伝って、全体にちょうどいい感じに軽やかになっている。
ジャケット裏に「このアルバムでダンスをすると寿命が縮まります」とある。
タイトルは「胆力、ど根性」の意。英米では根性が宿るのは「肝」ではなく「腸」なんですな。
インストゥルメンタル。
「Um Tut Sut」(8:57)
「No Raven Tonight」(9:00)アヴァンギャルドな歌もの。
Vdgg、あるいはピーター・ハミルの作風によく似ている。
特に序盤の展開。
「Perseids」(14:12) タイトルは「ペルセウス座流星群」のこと。パロディかと思わせるほどに真っ直ぐにシンフォニックな作品だ。
「Dispersion」
「Spiralling」
「Reign Of Ice」
「Black Day, White Light」(9:34)
「The Souls Of The Damned Live In Failed Works」(9:27)
「Pioneers Over 'C'」(14:43)Vdgg のカヴァー。
(PDR CD002)
Live:Yoo-Hoo!
| Mike Sary | bass |
| John Robinson | keyboards |
| Bob Douglas | drums, percussion |
| Dean Zigors | guitars, guitar synthesizer |
97 年発表の作品「Live:Yoo-Hoo!」。
95 年 11 月に収録された初のライヴ・アルバム。
翌年スタジオにて若干の追加修正を行って最終ミックスダウンしたとある(フルートのような音が聴こえるところがある)。
元々あまり製作に手がかかっていないのが特徴だったので、音質云々でなくヴァーサタイルな演奏を楽しむべしというリスナーとしての姿勢もすでに慣れっこである。
そんな中で、リズム・セクションがよく録音されているところはバンドのノリを楽しむための大きな強みだと思う。
内容は、変拍子を交えた巧みなアンサンブルで、ユーモアたっぷりに元気に駆け回る陽性レコメン・ジャズロック。
キャッチーなようでいて妙に屈折したメロディ・ラインや音符を殴り書きしては消しゴムでこすり捲くるような展開はライヴでも同じ、というかライヴではよけいにそういう感じがする。
SAMLA の狂的なガキっぽさを米国中西部のイナカものの垢抜けなさで置き換えたような芸風である。
管弦不在なのでスタジオ・ヴァージョンとはイメージが大きく異なる曲もあるが、最小限の音と細身に締まった演奏による再現も決して悪くない。
ぜひ、『図抜けた演奏力を誇るチンドン屋』という賛辞を捧げたい。
全曲インストゥルメンタル。(時おりの奇声とナレーションを別にすれば)
「Happy Armies Fight In Their Sleep」(5:45)第一作より。
「The Tingler」(6:16)鍵盤奏者の作品より。
「Clanghonktweet」(6:43)第三作より。
「Friendly Enzymes」(7:04)第二作より。
「The Souls Of The Damned Live In Failed Works」(9:52)第四作より。
「The Family That Oonts Together Groonts Together」(7:19)第三作より。
「And The Dead Dog Leapt Up And Flew Around The Room!」(7:45)第二作より。コレ、好きです。
「The Artist's House」(6:12)第一作より。
「Hey! Real Executives Jump From The 50th Floor!」(12:34)第三作より。個人的には代表曲。プログレですので。
(PDR CD003)
Violence Of Amateurs
| Mike Sary | bass, percussion |
Dean Zigoris | guitars, keyboards, percussion, g-synth, Ye-olde synth, noise, vocals |
| Bob Douglas | drums |
Brian Donohoe | drums, organic noise on 6 |
| Jon Encifer | keyboards |
John Robinson | keyboards, 1/4 Jack noise |
| Eugene Chadbourne | banjo on 1 |
Greg Acker | flute, sax, The Hawaiian nose flute, percussion |
| Steve Good | sax, clarinets |
Steve Aevil | tenor sax solo on 2 |
| Cathy Moeller | violin on 4 |
Chris Vincent | drums, vocals, percussion, popsicles |
| Kirk Davis | vocals, percussion, unbridled ehthusiasm | | |
99 年発表の第六作「Violence Of Amateurs」。
録音/サウンドがぐっとグレード・アップした作品。
いわゆるシンフォニック色は少なく、緩急/硬軟が激変するアンサンブルで元気にアグレッシヴに攻め立てる陽性シリアス・インスト・ロックである。
変拍子で強圧的に迫るパートとすっと脱力するパートの呼吸が絶妙。
しなやかでパワフルというイメージは存在感ある管楽器セクションのおかげだろう。
ただし、フリージャズの肉体性を誇示する素っ頓狂さというよりは、テクニカルなコミックバンド/チンドン屋というべきユーモアとペーソス、突き抜け感がある。
もしくは、町内の消防署辺りの吹奏楽バンドがロックをやっている感じか。
サスペンスフルな展開にすらも親しみやすさが常にあるということだろう。
どこかサーフロックっぽさがあるところも特徴。(モロなところもあり)
4 曲目「Mail Order Quarks」はミステリアスな名作。ヴァイオリンが印象的。
5 曲目「Tiger Tea」もユーモラスなフレーズと疾走感、そしてくるくると変わる曲調がたまらない。
オモチャ箱をひっくり返したような演奏と思ったら、最終曲はなんと SAMLA の大作「The Fate」のカヴァー。
今回も戦費削減を謳っております。
「The Kokonino Stomp」(4:42)
「The Secret Life Of Walter Riddle」(8:14)
「The Odessa Steps Sequence」(8:42)
「Mail Order Quarks」(10:27)
「Tiger Tea」(12:13)
「Joosan Lost/The Fate」(21:40)
(PDR CD004)
The Case Against Art
| Mike Sary | bass, percussion |
Warren Dale | keyboards, woodwinds, sax, recorder, clarinet |
| Chris Vincent | drums |
Chris Smith | guitar, violin, banjo, mandolin |
| Greg Acker | flute, sax |
Dean Zigoris | guitars |
| Cathy Moeller | violin |
Cliff Fortney | vocals, flute, recorder |
| Shawn Persinger | acoustic guitar |
Kirk Davis | percussion |
| Karen Hyer | soprano |
Steven Dale | trumpet, euphonium |
| Pam Thompson | tuba |
2001 年発表の第七作「The Case Against Art」。
内容は、相変わらずの自由闊達なジャズ・ロック・インストゥルメンタル。
オムニバス調の作風を活かした、ユーモラスで変幻自在、余裕シャクシャクの演奏である。
変拍子脱力ジャズロックから、奇天烈ハードロック、フルートとなめらかなシンセサイザーを活かした HAPPY THE MAN 風のファンタジック・フュージョン、YES を思わせる爽快にして込み入ったシンフォニック・ロックなど、全体にプログレ度はかなりアップ。
おもちゃ箱をひっくり返したような、という表現はよく目にするが、この作風は、ひっくり返ったおもちゃ箱から飛び出したおもちゃがそのままサルサを踊っているような感じである。
そして、フランク・ザッパのようにファンキーに盛り上がるバックでメロトロンが高鳴るなど、予想を覆す展開も多い。
また、今回は、透き通るような叙情性をもつ演奏での表現力にも驚かされる。
シリアスさとユーモアを矛盾なく併せ持つ稀有のグループなだけに、末永く活躍していただきたい。
一つ興味深いのは、ジャズやクラシックといった主流の音楽そのものへの直接的な依拠性があまり感じられないことだ。
アメリカのグループは、スウィング・ジャズ、ゴスペル、R&B、ファンク、モダン・クラシック、ブルーズ、フォーク、ブルーグラスといったルーツを感じさせることが多いが、このグループの作品にはそういう「体臭」がない。
ジャズロックというレッテルは、それが一番無難な範疇分けという程度のものに過ぎない。
間違いないのは、プログレ・ファンである、ということぐらいだ。("File under progressive rock!" というやつですな)
この点でも、HAPPY THE MAN と類似した音楽的体質をもっていると思う。
メンバーは、元 INFINITY のキーボーディストや 元 BOUD DEUN のギタリスト、そして HAPPY THE MAN のオリジナル・ヴォーカリストなど、さながら北米プログレ同窓会の趣が。
最終曲も、HTM のパロディのようでいて、濃い目のアンサンブルをくるくる変転する曲調で仕上げた傑作。
そして、毎度楽しみなスリーヴの内容ですが、今回も期待を裏切らずおバカさんです。
「That Thing On The Wall」テクニカルかつユーモアあふれる変拍子シンフォニック・フュージョン・チューン。
風格を感じさせるオープニング、そしてスタジオ・ライヴ風の録音。
「Visible Tissue Matter」フルートを使った叙情的なアンサンブルとヘヴィ・ジャズロックが一つになった大作。
「Partly The State」HTM の初期作品(Cuneiform レーベルからの発掘作「Beginnings」に収録)。ヴォーカル入り。GENTLE GIANT の影響大。
プログレ者のツボのど真ん中を射抜く。
「One Humiliating Incident After Another」
管絃楽器を交えた現代音楽風味、SAMLA 的な骨折ジャズロック、フォーク・テイストが入り混じる、オムニバス風の作品。
1 曲目をさらに豊かに緩やかにした感じ。
「Under The Big 'W'」
(PDR CD006)
Pardon Our French!
| Mike Sary | bass, keyboards | Jeff Gard | drums, percussion | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chris Smith | guitars, electric violin, viola, percussion, banjo, mandolin, cello |
| Warren Dale | keyboards, sax, clarinet, melodica, toys, accordion, flute, recorder, bass harmonica, percussion, saxello, celesta, marimba, vibes |
| guest: |
|---|
| Steven Dale | trumpet, flugelhorn | Denise Gilbert | spoken vocals |
| Howie Gano | piano, string synth | Stephanie Dale | piccolo |
| Will Stewart | trumpet | Pam Thompsom | tuba, euphonium, trombone |
| Natalie Nichole Gilbert | lead vocals |
| Richard Adrian Steiger | table, dymbek, riq, percussion |
2004 年発表の第八作「Pardon Our French!」。
内容は、管楽器、弦楽器、打楽器などなど多彩な音色をふんだんに使った、ややレコメン色もあるジャズロック。
安定した演奏力のある、真面目なコミック・バンドであり、たとえるならば律儀な SAMLA である。
シニカルでユーモラスなのに、まろやかではにかむようなデリカシーの感じられる、すてきな音楽だ。
アナログ・シンセサイザーの音があたかもプログレ王道を訴えるかのごとく効果的に散りばめられている。
圧巻は、3 曲目「The "Pardon Our French!" Medley」、フランス・プログレ・バンド総覧メドレーである。
いきなり ANGE で、PULSAR やら ATOLL も出てきます。
普通のアメリカ人はフランスのことなどほとんど知らないですが(Looney Tune のペペルピュをご覧なさい)プログレ好きは音楽を通して他の国のカルチャーを、きわめて限定的ではあるものの、正しく理解できるのである。
カレージ風の録音ももはや立派な特徴である。
1 曲目「Everything Works In Mexico」は、シンセサイザーとアコースティック・ギターのシリアスなラテン(チカーノ?)・タッチが印象的な作品。
2 曲目「Sekala Dan Niskala」は、マリンバやらギターやらが変拍子テーマを織り成すチェンバーロック風の作品だが、旋律がアラビア風なためあまり聴いたことのない雰囲気の作品になっている。
3 曲目「The "Pardon Our French!" Medley」。
ANGE「La bataille du sucre」(「Au-dela du delire」収録)、
PULSAR「Tired Answers」(「Halloween」収録)、
SHYLOCK「Laokcsetal」(「Ile De Fievre」収録)、
CARPE DIEM「Publiphobie」(「En Regardant Passer Le Temps」収録)、
SHYLOCK「Laokcsetal」(「Ile De Fievre」収録)、
ATOLL「Tunnel Pt. 2」(「Tertio」収録)、
CARPE DIEM「Publiphobie」(「En Regardant Passer Le Temps」収録)、
ETRON FOU LELOUBLAN「Yvette's Blouse」(「Batelages」収録)(ジャケットの表記はバンド名も曲名も綴りが間違ってるぞ)のメドレー。
4 曲目「Tears Of A Velvel Clown」は、サーカスをイメージしたようなトイ・ミュージック風のサウンドを使った作品。愛らしい音を使いながらけっこうシリアスな展開を繰り広げる。特に後半はなんだか思いつめた果てに転落していくような、カタストロフィックなイメージである。
オールドフィールドもあると思う。ウォーレン・デイルという人とは趣味が合いそうです。
5 曲目「When The Ruff Tuff Crempuffs Take Over」は、イメージ通りのバカ・レコメン・ジャズロック。クラシカルなキーボードが昔のプログレ風でいい。
(PDR CD007)
 close
close